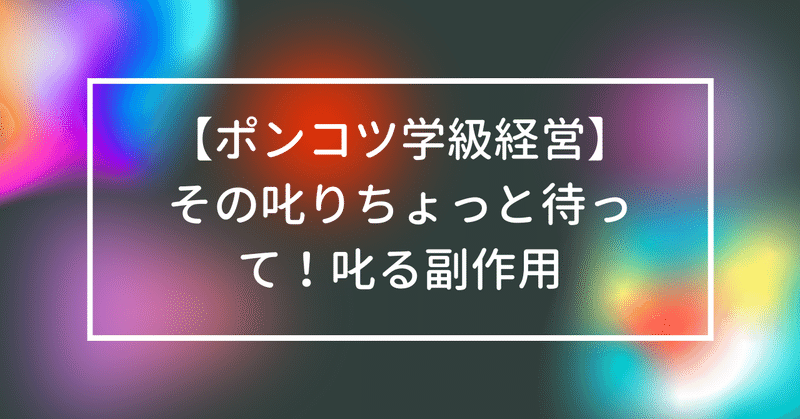
【ポンコツ学級経営】その叱りちょっと待って!叱る副作用
1.はじめに
久しぶり投稿です。
学級経営をしていると叱る場面というのがどうしても出てきてしまいます。
僕も教育の根幹は「アメとムチ」だと思ってます。
ただ、いつも子供を怒鳴っている先生をよく見かけます。
そんな現場を見ると、ついつい「それって大丈夫?」と思ってしまいます。
学級経営上欠かせないように思える「叱り」。
実は、「叱り」には副作用があるのです。
2.叱る4つの副作用
叱る副作用は以下の4つです。
1.弁別の原理
……条件によって、行動を変えて良いという学習につながる。
(怖い先生の言うことだけ聞けばいい……など)
2.派生の原理
……厳しく叱る人の周囲のものが嫌いになる。
3.反発の原理
……反抗心は蓄積します。
4.模倣の原理
……その対象に反発が向かわない場合、立場の弱い人へその矛先を向ける。
3.終わりに
教育書のベストセラー「ブラック学級づくり」の著者である中村健一先生は、
「怒鳴るのは月に1回が限界である」
と記してあります。
つまり、教師は「感情的に」「その場凌ぎ」で叱るのではなく、「策略をもって」叱らなければならないということです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
