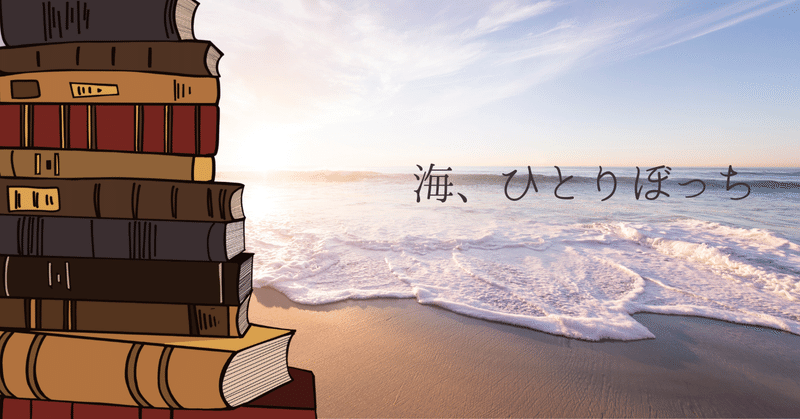
【短編小説】海、ひとりぼっち
海の夢を見ました。海というのは僕の同級生だった女の子の名前です。当時はみんな、彼女のことを海ちゃん、海ちゃん、と言ってかわいがっていましたが、海ちゃんは自分の名前が嫌いだったようです。僕も一度だけ海ちゃんのことを「海ちゃん」と呼んでみたことがあります。海ちゃんは僕を一瞥すると、すぐに何事もなかったかのようにして黒板の方を向いてしまいました。僕はそれから、海ちゃんのことを「斎藤さん」と呼ぶようになりました。斎藤、というのは海ちゃんの苗字です。海ちゃんのことを「斎藤さん」と呼ぶのはクラスで僕ひとりだけでした。
海ちゃんは僕に「斎藤さん」と呼ばれるのが好きだったようです。僕が「斎藤さん」と声をかけると、海ちゃんはいつも僕の方へと来てくれます。僕が海ちゃんを呼ぶのは、海ちゃんに本の返却をせかすときと決まっていました。僕は図書委員でした。休み時間になると図書室のカウンターで本の貸し出しなんかをします。海ちゃんはよくいろいろな本を借りていきましたが、返しにくることはあまりなかったのです。そんな海ちゃんに本を返すよう告げるのは僕の仕事の一つです。僕は海ちゃんに本を返すように言いました。海ちゃんは「分かった」と言って、たいてい次の日には本を返してくれます。
僕は海ちゃんに「斎藤さんは本が好きなの?」と聞いたことがあります。海ちゃんは「んー、」と柔らかい声を伸ばしてから、「大好き」と言いました。海ちゃんが大事な主語を省略して、しかも僕の問いからしばらく遠い場所から答えを投げたものですから、僕のおバカな心臓はどきりと跳ね上がるのでした。
海ちゃんは「将来は小説家になりたいな」と言いました。
僕は「すごく素敵だよ」と言いました。
どうやら、主語を省略する悪癖は僕の中にもあったようです。僕と海ちゃんはぎこちない会話を続けました。よく考えると、ぎこちなかったのは僕だけかもしれません。海ちゃんは水中を泳ぐ人魚のように、自由自在に僕との会話を楽しんでいたのですから。僕はこの時間が好きでした。でも、それは永遠のことではありません。寄せた波はいつか必ず返るのです。海ちゃんは嫌いな名前を呼ばれてすぐに、名残惜しそうに僕のところから離れていきました。
海ちゃんのことを考えるとき、僕はいつもあれは初恋だったのだろうかと考えます。僕の初めての恋はいつだったのだろうかと考えると、いつも海ちゃんの顔が思い浮かぶのです。だけど、いろいろな人に海ちゃんの話をすると、それは恋でもなんでもないというのです。
「それはあこがれだよ。俺も昔、かわいい子の名前が呼べなくて、高橋サン、なんてよんでいたよ」
世間では、好きなコは名前で呼ぶものだという風習が根付いているようでした。だけど僕も叶うのなら海ちゃんのことを海ちゃんって呼びたかった。僕が海ちゃんのことを「斎藤さん」と呼んだのは、海ちゃんがそれを望んだからなのです。
僕は一度だけ、海ちゃんに名前のことを尋ねたことがありました。それは冬のことでした。冬でも図書室はいつも通りです。海ちゃんはいつも通りたくさんの本を借りていこうとしていました。だけど海ちゃんはこの時も本を返しそびれていたのです。慌てた僕が間違えて「海ちゃん」と呼んだ時、海ちゃんはいつもの、あのすべてをあきらめてしまったかのような顔をせずに、呆れた顔をしたのです。僕はそれどころではなくて、はっと口元を抑えてから「斎藤さん」と言い直しました。
「なあに」
海ちゃんは笑っていました。
「先週借りていった、『よだかの星』の返却はまだ?」
「明日返す」
僕はほっとしました。海ちゃんは返却期限は平気で破るけれど、僕との約束は破りませんでした。海ちゃんが「明日返す」と言ったら明日返すし、来週返すといったら来週。一度、来月返すと言ったときには僕は交渉しました。さすがにそこまでは待てないと言いました。
海ちゃんが今日借りていったのは、名前に関する本です。僕は思わず、
「斎藤さんは、自分の名前が嫌いなの?」
と聞いていました。
海ちゃんはいつものように「んー」と間延びした声を挟んでから、
「大嫌い」
と言いました。
「どうして?」
僕はちょっとドキドキしながら、そんな問いかけを投げました。
「この名前、お父さんが昔好きだった歌手の名前なの。だからキライ」
そうなんだ、と僕は思いました。何と言ったらいいかわからなかったからです。僕は海ちゃんの名前が好きでした。海ちゃんの、いつも堂々とした振る舞いが僕の目には本当に美しく映っていたのです。陳腐な例えにはなりますが、本当の海のような美しさでした。僕はどうにでもなれと思いながら「僕は斎藤さんの名前、好きだよ」と言いました。
海ちゃんは、海ちゃんの嫌いな名前を好きだといった僕に対して「知ってる」と笑顔で言いました。
僕の心臓ははちゃめちゃになりそうでした。海ちゃんはにかっと笑ったまま「知ってる」と同じ言葉を繰り返しました。
「知ってたの?」
僕は思わず声を潜めました。海ちゃんは「うん」と元気に答えてくれました。
「君は、私が自分の名前を嫌いだって言ったら、私のことを海って呼ばないようにしてくれたよね」
僕の心臓は変に脈打っていました。僕は慎重に、まるでガラス細工を取り扱う職人のようにして、ゆっくりと首を縦に振りました。
「私は君のそういうところが好き」
そう言って、海ちゃんは図書室を出ていきました。
その日の休み時間、僕はずっと呆けていました。カウンターの向かいで本を借りたい生徒が「図書委員さん」と声をかけてくるまで、僕は海ちゃんの言葉を反芻していたのです。そういうところが好き、そういうところが好き、そういうところが……。
僕と海ちゃんは中学高校、同じところへ行きました。僕と海ちゃんが一緒のクラスになることはありませんでした。僕はずっと図書委員で、カウンターの向こうで本を読んでいました。僕の知っている海ちゃんなら、カウンター越しにたくさんの本を持ってやってきてくれるものだと思ったのです。けれども、海ちゃんが図書室のカウンターにやってくることは一度もありませんでした。
僕は時々、海ちゃんの夢を見ます。それは大学を卒業した今でも変わりません。海ちゃんはあのときと変わらない姿で僕に話しかけてきます。僕も変わらず「斎藤さん」と言って海ちゃんのことを呼ぶのです。いつしかそれは波の音に変わってゆくのです。今の海ちゃんは、僕が「斎藤さん」と声を張ってもきっと振り向かないでしょう。
最近になって、僕に友人の言葉が染みるのです。
「それはあこがれだよ」
彼の主旨とは違う解釈をすることになるとはいえ、ともかく僕は、海ちゃんに恋をしていたのです。けれども時の流れは僕の恋心を徐々に徐々に別のものへと変質させ、ついにはすっかりあのときめきを忘れてしまったのです。
僕は今日も海ちゃんの夢を見ました。海ちゃんは色の褪せた絵本を読んでいて、僕はカウンター越しにその様子をうかがっていました。砂浜の波のように、柔らかく半透明なカーテンが揺れています。僕は手元の本のページを捲ります。それは児童書のひとつで、次のページには美しい挿絵が描かれていました。海の絵です。とても素敵な海の絵です。大きな入道雲が天を貫こうと背伸びする空の下、どこまでも続く凪いだ海。海水に素足を晒す少女の姿が描かれていました。砂浜にはちいさな貝殻が一つ転がっていて、僕はこの絵の貝殻にえらく感情移入をしてしまいました。海ちゃんに置き去りにされた僕のような孤独を、この貝殻が背負っていたのが悪いのだと思います。
気づけば僕は泣いておりました。三十を過ぎた大の大人が夢を見て泣いたのです。
時計は朝の十時を告げています。静かに秒針が動いています。僕は静かに泣きました。気づけば僕は、夢の中でしか海ちゃんのことを思い出していないのです。僕はあの時、海ちゃんに置き去りにされたかのような気持ちでいたのですが、もしかしたら本当は違うのかもしれません。僕は泣きました。秒針は変わらず動いています。それを見た僕は、慌てて時計から電池を引っこ抜きました。
針は十時十五分三十二秒で止まりました。
僕はしばらくそのままでいました。カラスの声が聞こえてきます。遠くでサイレンが鳴りました。あれは救急車でしょう。今日も暑い日になります。冷房を付けて、水と塩をきちんと取らなければなりません。僕の部屋でも冷房がぶうんぶうんと言っています。たまらず窓を開けたのですが、あの日のような優しい夏はありませんでした。ただただ暴力的な熱に満ちた風が僕の頬を思いっきり張ったのです。僕は絶望を覚えながら窓を閉めました。室温の上昇を知った冷房がぶおおおんと叫んでいます。爽やかな風が僕を包みます。けれどもそれは潮風ではないのです。
隣の部屋からテレビの声が聞こえてきました。男性のアナウンサーが何かを言っています。
そしてほどなくして、僕の腹はぐうと鳴りました。
気の利いたことを書けるとよいのですが何も思いつきません!(頂いたサポートは創作関係のものに活用したいなと思っています)
