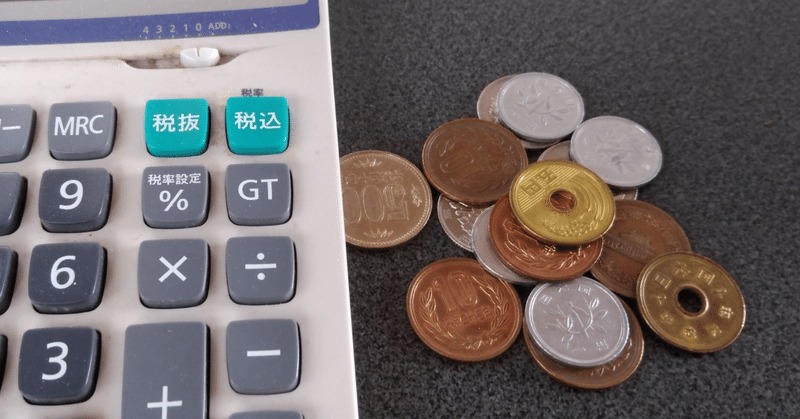- 運営しているクリエイター
#結婚

来賓スピーチを頼まれた結婚披露宴前夜に新郎から《釘刺し》電話「明日はくれぐれも《常識》をわきまえてくださいね」 (エッセイ・披露宴スピーチ前編)
娘から、彼女の結婚披露宴で私が問題発言(問題行動?)をやらかすのではないかと警戒されていたことを記事(↓)の末尾に書きました。 彼女はかねてから父親のことを《危険人物》視しており、中学・高校の頃から、 「将来、結婚したい相手ができても、お父さんには会わせない」 「お父さんは結婚式には呼ばない」 と断言していました ── しくしく。 一応、式には呼んでもらえたので、当時と比べて、 ➀ 彼女が《寛容》になった。 ➁ 私の《社会性が向上》した。 のいずれかでしょう。 私を《危険