
- 運営しているクリエイター
#学生
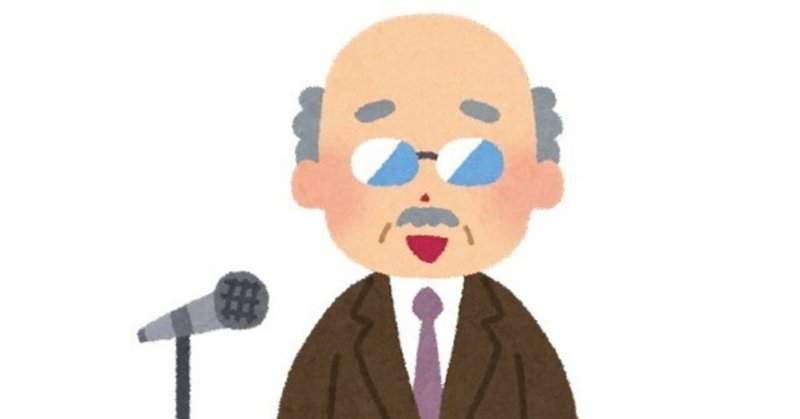
「彼は《眠れる獅子》と呼ばれていました ── そして、とうとう、眠ったまま卒業していきました」 (エッセイ・披露宴スピーチ後編)
私に結婚披露宴での来賓スピーチを依頼しておきながら、《危険人物》に頼んだことを後悔し始め、前夜遅くに電話をよこし、 「明日はくれぐれも《常識》をわきまえてくださいね」 と釘を刺してきた「往生際の悪い」新郎の話です。 披露宴当日、東京の会場に出かけました。 バブル景気が始まるのはその1年後ぐらいですが、一流ホテルの中規模のホールを会場とする、超豪華な披露宴でした。 新郎の所属した研究室教授A先生の主賓スピーチに始まり、新婦側の主賓、新郎の会社上司、友人、……と挨拶が続いてい






