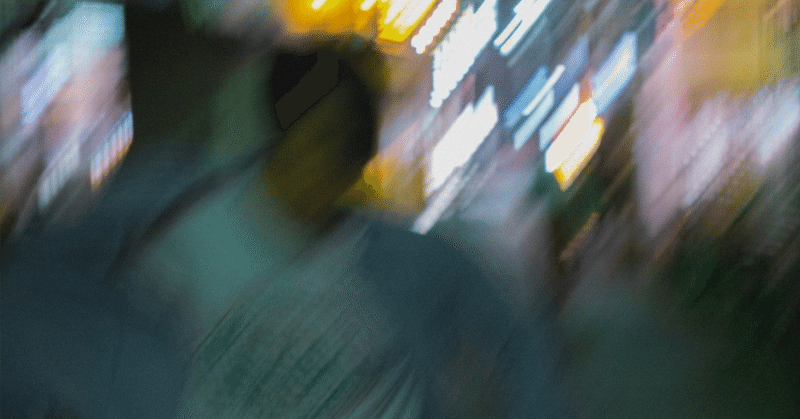
すべてと無とはじまりと終わりについての話(2)
昼休みが終わり、3時限目が始まった。
ぼくはユカリが少し怒っていたことを考えた。「まあそうだろうな。」とぼくは思った。
思い出してみればぼくは友達と飯を食って、麻雀をして飲んでいる間、彼女のことを考えもしなかったのだ。友達が「彼女に連絡しなくていいいのか?」とちょっと聞いてきて、大丈夫だよ。と答えた。それぐらいだ。
「可愛い娘なのに。明るくて気さくだし。頭もいい。」と友達は言った。まあね。とぼくは言った。ぼくは少し照れていたのだ。子供みたいだ。中学生の頃からそういう事についてはほとんど変わっていない。タフであろうとしていたのかもしれない。優しくあろうとすると、すべて嘘になってしまうような気がするんだ。とぼくは思った。
もちろんぼくはユカリのことが好きだった。そして立場が逆だったら、ぼくだって少しむっとするだろう。彼女の生活の事を最大限に尊重していたとしても。星はどう思うかな。と考えそうになってやめた。昨日からなんだか星のことを考えすぎる。「立場が逆だったら」。
そして人を好きになるということがどういう事なのかについて少し考えた。ほんとうに子供みたいだな。と思った。そんな事どうだっていいじゃないか。気の合う友達や仲間がいる。そいつらのことは好きだ。恋愛感情を持った女の子がいる。その娘が好きだ。今のところそれだけのことじゃないか。ぼくはモラトリアムに生きているんだ。現実が追ってきたら、その時考えればいい。でもいまはそれでいい。ただ優しくあろうとすればいい。人生について。世界について。宇宙について。
あとで連絡が取れたら謝ろう。と思って、また音楽を聞いて、小説を読むともなく読んだ。
二時を少し回っていたし、飽きてきたのでサークル棟に行って、出入りしているサークルに行ってみた。「世界民族研究会」という名前のサークルだった。これくらい胡散臭い名前の大学のサークルもそうあるまい。鍵はあいていた、これもちょっとした奇跡だ。
ドアを開けるといきなりマリファナの匂いがした。二つ年上のユキちゃんと呼ばれている男が、紙巻を吸いながら早く閉めろ。という動作をした。
ぼくはすぐドアを閉めて、鞄を置き、窓があいていたのでコートのジップを上げた。
「きのう、まわって、きたんだ。」とユキちゃんは言った。「上物だ。」といって吸いかけのいつもより心もと太く巻かれた紙巻を回してきた。ぼくはそれを受け取り、軽く吸い、肺に落とした。それからもう一度深く吸い。深く肺に落として、少し息を止めつつ返した。ゆっくり煙を吐き出した。たしかに悪くないものだった。軽い目眩を感じて、隣りに座った。向えにはケンと呼ばれている同い年の男がいて、マリファナの葉の部分を分け、花の部分を混ぜ、器用に丁寧に少しメンソールの煙草に混ぜて紙巻を巻いていた。紙巻をうまく巻けるという理由だけでそのサークルに出入りを許されているような男だった。脇にはマリファナが入ったビニール袋が置かれていた。
ユキちゃんはまたマリファナ煙草を回してきた。「だれか、みたか?」ぼくは受け取り深くゆっくり煙を肺に落とし答えた。「いや、今んとこ誰も見てない。」
ユキちゃんはケンの巻いた紙巻を黙ってもう一本取り、火を付けた。「アンラッキーなやつらだ。」「上物なのに。」ぼくは黙って受け取った紙巻を吸っていた。部屋が少し歪んで見えてきていた。体が少し重力から解放され浮いているような気がした。たしかに悪くない。
「おんがくをかけてくれ。」ユキちゃんが言った。けっこう決まっているようだ。傍らには水パイプがあった。多分はじめはそれで吸っていたのだろう。音楽をかけてくれ。ぼくはふんわりとした浮遊感の中立ち上がり、部屋のCDラジカセの電源を入れ、散らばっていたCDを眺めた。「どんなのがいい?」「きもちよくなれるやつ。」そんなのわかる訳ない。まあなんでもいいだろ。と思ってマッシヴ・アタックの「ブルー・ラインズ」をかけた。
「これはすきだ。」「ハマれる。」といってユキちゃんはぼくの紙巻がもう無いことを見て、自分の吸ってる紙巻を回してきた。そしてコーラを飲んだ。そしてしばらく焦点の合わない目で部屋を見ながら音楽を聞いて、自分の世界に入っていた。ぼくはそれを吸って、返そうとしたが、すでに彼は眼を閉じてトリップしていた。
ぼくもマリファナ煙草を吸いながらとろんとし始めていた。部屋はもう少しで回り始めそうだった。音楽もマリファナの酩酊のフィルターを通し聞こえていた。それはそのためにあるような音楽に聞こえた。
ケンはまだ紙巻を巻いていた。一定以上の数を巻き終わるまで彼はそれを吸うことを許されていない。
ユキちゃんが酩酊から覚める様子がないことを確認して、ぼくは立ち上がり、紙巻を三本とって千円札を置いた。ケンは黙ってそれを見ていた。鞄を取り、散らばっていたライターを取り、部屋を出て行った。
少しラリっていたせいで講義に行く気がなくなった。ぼくは校舎の今は使われていない棟に向かった。途中でコーラを買った。そこはぼくが見つけた場所だった。四階まで上がり、ロープをくぐって、窓を開けて外に出ると屋上に出られる。一応屋根があって、その脇にビニールのソファーとテーブルを持ってきて置いていた。そこを知っている人はぼくの他には四人しかいない。三人は他学科の、ぼくがこの大学で一番の友達たちだ、ぼくらは一つのチームだった。あとはユカリだ。
ぼくはソファーに横たわり、コートのジップを上まで上げ、ファー付きのフードを被ってマリファナ煙草に火をつけ、ゆっくりと煙を吸い込み、自分の世界に入っていこうとした。天気は回復傾向にあり、雲がながれて太陽の光が薄く射し込んでいた。ぼんやりとした光はマリファナの煙の前でちらちらと輝いて見えた。
少しあとで加藤がそこにやってきた。「ここにいたのか。」
「いるかと思って着たんだ。ガンジャをやってるのか?」
ぼくは黙って吸いかけのマリファナを渡した。彼はそれを受け取り、一服した。「なかなかいい。」と言ってぼくに返した。椅子を持ってきて腰掛けた。ぼくはまた一服して彼に渡した。「ユカリちゃんとケンカしたんだって?」受け取り彼は言った。「見てたやつがいたよ。」顔が広いのだ。
「それほどでもないさ。」ぼくはコーラを飲みながら言った。「なかなか難しいよ。授業は?」
「これから行くよ。話を聞いてお前がここにいるんじゃないかと思ってさ。」彼はマリファナを返しながら言った。
「女が怒ってる時は、悪くなくても謝って、甘いものを食べさせて、酒を飲んで、やればいいんだよ。」と加藤は言った。
ぼくは笑って言った。「そうかもしれない。シニカルだな、それで済むのはお前ぐらいだよ。」
「本当だぜ。でもやるときはきちんとやらなきゃいけない。女にはそれはわかるんだ。そして同じことを繰り返しちゃいけない。女はあらゆることに怒るし、されたことは何一つ忘れないんだから。そうだな、三回までだな。繰り返すたびにもっとちゃんとやらないといけないぜ。」と加藤は冗談ぽく言った。
「それを何回繰り返したんだ?」とぼくも冗談交じりに言った。
「覚えてないな。」と加藤は笑って言った。
マリファナはもう消えていた。ぼくはもう一本取り出し、「吸うか?」と尋ねた。
加藤は腕時計を見て、「いやもう授業が始まるな。出ないとまずいんだ。まったく面倒くさいよな。自分の好きなときに授業があればいいんだ。」
「じゃあおれも行くよ、一応授業はあるんだ。」とぼくは言った。加藤はぼくの目を見て「大丈夫か?」と言った。「大丈夫だ。それほどでもない。それに誰もおれのことなんて見てないさ。」とぼくは言った。
「そう言うやつほど、けっこう見られているもんだ。人ってそんなもんさ。」「お前はあまり自分のことをわかってないみたいだ。けっこう目立ってるよ。」と加藤は意外なほど真剣な顔で言った。「じゃあまあ行こうぜ。」
階段を降り、お互いの教室に行く前に加藤は言った「今日飲むか?」
「いや、お前の言うとおりユカリに謝らないとまずい。上手いこと行かなかったら連絡するよ。」とぼくは言った。彼は頷いた。「ところでナオと綿谷はどうしたんだろう?」
「あいつらは確か今日は重要な授業はないんじゃないかな。」「まあ飲むって言えば来るだろ。」とぼくは言った。そして別れた。
相変わらずクールで、優しいやつだ。弱いところを見せない。でもそれはあるんだろう。いや、ぼくは「それがある」ことを知っていた。奴が自分の気に食わない相手についてどれほど冷酷になれるかも知っていた。それが彼の弱さなのだろうか。
「そう言うやつほど、けっこう見られているもんだ。」ぼくは星のことを思った。星が自分を見ていることを思った。何故か考えないわけにはいかない。
「お前はあまり自分のことを分かっていないみたいだ。」その通りだ。星が自分についてどう思うのかも想像がつかない。ぼくはちょっと首を振った。振ったせいでマリファナの目眩がちょっとやってきた。
「考え方が飛躍しすぎる。」
教室は星のように遠くに思えた。
マリファナの軽い酩酊のせいで、芸術論の授業はいつもより少しシュールリアリスティックに聞こえた。
授業の趣旨はリアリズムに与えたモネにはじまる印象派芸術の影響についての話だったが、ダリがピカソに向かってシュールリアリズムについて語っているような気がした。ピカソはそれについてあまり興味はないようだった。それは宇宙を地上に表現するためのわりと一方的な討論のようだった。
酩酊が覚め始め、授業は写実派と印象派における光の認識と表現についての話に移っていた。それについて少し興味を惹かれたが、ぼくは酩酊の後と、昨日からのいろいろな思案が混じった疲れでうとうとしていた。そして授業が終わった。顔見知りの女の子を見つけて、ノートを見せてもらい、適当にメモした。
その後でユカリに電話をした。「何してる?」
「友達とお茶しながら待っていた。」「今終わったの?」とユカリは言った。
「ちょっとノートを取らしてもらっていた。今どこ?」とぼくは言った。
講堂からちょっと離れた学内でも比較的まともなカフェにいる。と彼女は言った。
「会えるかな?」ぼくは言った。彼女は少し黙っていた。
「女はあらゆることに怒り、それを忘れないんだ。」と加藤は言った。
「さっき行ったこと、わかった?」と然るべき時間がたった後ユカリは言った。これぐらいでいいかな。という風に。
「わかったと思う。」とぼくは言った。「悪かった。これから気をつけるようにするよ。」
「ご飯を食べよう。駅前で待ってる。」「髭を剃ってきてね。」と彼女は言った。「1時間ぐらいでいいでしょう?」
「わかった。何を食べたいか考えておいて。」ぼくは言った。
「遅れないでね。」と彼女は言った。
原付バイクで家に帰る途中、冬の短い昼が終わり、長い夜に月が登っていた。4分の3ぐらい欠けた月だった。
家に着き、シャワーを浴び、頭と体を洗い、髭を剃って顔を洗った。このうえマリファナをやったでしょう。なんて言われたら話が余計面倒になる。ユカリはぼくがマリファナをたまに吸う事を知っていたが、タイミングが悪い。加藤に言われるまでもない。
それから駅に向かって歩いた。大学よりは駅のほうが近い。曇っているので星ははっきりと見えなかった。
星が見えればいいのに。
ぼくはいまどこにいて、なにをしているのかわからない。今ここにいる。楽しいこともあるし悲しいこともある。
いまのところ楽しいことが多い。好きなやつらもいる、嫌いなやつらのほうが多いが、それはそいつらがぼくのことを嫌っているからだ、そもそもぼくがそいつらのことを嫌っていたわけではない、ぼくにはその理由がわからない。ちょっとした誤解のせいなのかもしれないけれど、今さらそれを解けるようには思えない。そして別に今のところそれに不自由はないから、別に解こうとも思わない。
星のようなものだ。何かの都合で、あるいはただそうであったためのために、近くに存在していた星のようなものだ。でもぼくはそこに何かの意味のようなものを感じる。星は近くにあるように見えて「とても」遠くにある。ぼくたちは近くにいるようにみえて「ちょっと」遠くにある。そこに運命的なものを感じるからだ。
ぼくにはチームがある、友だちもいる。仲間のような人達もいる。そしてユカリがいる。
それがたまたま近くに存在していただけのものだっていうのか? 始まりがいつかどこかにあって、いつかどこかで終りが来るのか?
ぼくにとっての世界は今のところそれで全てだ。それで無だ。
世界にあってそれが無に限りなく近いようなものという意味ではなく、全てであるなら、それは同時に無なのだ。どうしてそう思うのだろう?
全てでなければそれは無であり、そうであれば無は全てであるからだ。無茶苦茶な論理だ。でもそう感じた。全てでなければそれは結局無なのかもしれない。でもなぜそれで無が全てだと思うのだろう? かつて全てであったものが、無になったのなら、無は全てに限りなく近いものである。そう思うからだろうか。
星が見えればいいのに。
「考え方が飛躍しすぎる。」
駅に着き、ユカリに電話を入れた。いる場所はわかっていた。いつも待ち合わせをする、駅前の、チェーン店ではない、昔から(いつからあるかは知らない)のどこの学生街にあるような静かな喫茶店だ。それほど美味しいコーヒーを出すわけではないが、少なくとこも出来合いのものではなく、静かで落ち着ける場所だ。そのまま行っても良かったのだが、なんとなく電話を入れたほうがいい気がした。なにかが微妙なのだ、いつもと違うことが起こっているのだ。ユカリはいままでぼくがしてきたことに怒ったことはない。そしてぼくは特別なことをしたわけではない。「でも今は違う。」
「待った?」とぼくは聞いた。
「少しね。」とユカリは言った。別に機嫌が悪そうには聞こえなかった。「着いたの?」
「着いた。いつものところ? そこに行こうか?」とぼくは言った。
「ちょうどコーヒーを飲んだところだからいいよ。マックの前で待っていて。お腹が空いた。」とユカリは言った。
「わかった、じゃあ後で。」と言ってぼくは電話を切った。
10分ぐらいしてからユカリがやってきた。彼女はほっとしたような微笑を浮かべ、黙ってぼくにもたれかかり、「ちゃんと受業受けたの?」と聞いた。彼女の髪の匂いと香水と、懐かしく感じる体臭が混じって香り、ぼくは少し安心した。「ぼくはここにいるんだ。」
「受けたよ。あんまり良くわからなかったけど。光についての解釈の違いについては興味を惹かれた。」
「光?」とユカリは言った。
「芸術論の受業だよ。写実派と印象派の光の認識と表現の違いについての話。」
「何が違うの?」とユカリは聞いた。
「おれが聞きたいさ。」「多分それがはじめから自然に存在していたのか、それとも今自分が見ているものがそうなのか。そういうことじゃないかな。」とぼくは適当に言った。適当に言うべきじゃないかもしれない。でもぼくはうとうとしながら、昨日からの思案を含めてそう自分で考えをまとめたのだ。別に嘘じゃない。
「ふぅん。」とユカリは言った。
「何を食べる?」とぼくは聞いた。
「焼肉。」と彼女は言った。
「明日は大丈夫なの?」とぼくは聞いた。
「だって、明日はあんたと出かけるんでしょう?」とユカリは無邪気に笑いながら言った。「それにお肉を食べたい気分。」
「いいね。」とぼくは言った。加藤に連絡を入れようか迷ったが、放っておくことにした。ぼくらのチームには暗黙の了解っていうものがあるのだ。必要があるときには連絡を入れる。無いときはに入れない。
ぼくらはその街にあるチェーン店の焼肉屋に向かった。大衆向けで値段も手頃で、値段にある程度の付加価値をつけたような店だ。別に特に美味しい物を食べたいわけじゃない。とりあえず肉とよべるようなものと、酒があればいい。甘いものが抜けているが、まあ食べてきたのだろう。デザートに食べてもいい。
店には「サキソフォン・コロッサス」が流れていた、どうして焼肉屋に「サキソフォン・コロッサス」が流れていなければならないのだろう。和食屋にニルヴァーナの「ブリーチ」が流れているようなものだ。とぼくは感じたが、別にどうでもいい。「付加価値」にそれが必要だと判断したんだろう。経営方針なのだ。「サキソフォン・コロッサス」がどういう音楽なのかについて聞いても、だれも知らないし、どうしてこの音楽を流しているのか聞いても全く無駄というものだ。意味というものが失われている。大切な意味が。この地球の、日本の、東京という巨大都市の小さな学生街のチェーン店の焼肉屋で。
ユカリは食欲旺盛に肉を頼んで食べた。「ずっと前からお肉を食べたいと思っていたの。」ユカリは言った。「なんでだろうね?」「肉が不足してますよって言われている気がしていたんだ。」
「そういうことってたまにあるよ。おれは食が細い方だけどさ、それでも少しはあるよ。肉が食いたいとか、ラーメンが食いたいとか、スパゲッティが食べたいとか、ジャンク・フードが食べたいとか。」
「そういうのともちょっと違うんだよね。そういうのもわかるんだけどさ。」「もっときちんとした形で求めているって感じなのよね。」「肉、しからば無。みたいに。」「女の子だからじゃない?」とユカリは笑っていった。
「そうかも知れない。」ぼくは肉をつまみながらビールを飲んでいた。「可愛い娘だ。」と改めて思った。」音楽は「ウォーキン」に変わっていた。
ユカリは初めはビールを飲み、その後はウーロンハイを飲んで楽しそうに話していた、友達のことについて、講義について、あまり今の環境に満足していないことについて、自分の将来について。「それにはあんたも含まれているんだよ。」と彼女は嬉しそうに言った。
「どうしてそう思うの?」とぼくは聞いてみた。
「あんたは優しいから。」とユカリは言った。
「今まで会った人たちの中でいちばん優しい。あたしを守ってくれる。べつに強くなくてもいい。あたしがその分強くなるから。「優しくなければ生きていく資格がない。」そう信じられる。」
「でも強くなってくれればいい。そうすれば私は少し弱くいられる。」「あんたはもっと強くなれる。」
ユカリも満足したようだったし、場所を変えることにした。勘定はぼくが払い、あとからユカリは半分をぼくに渡した。優しい娘だ。ぼくのことをちゃんと考えてくれている、そして決して押し付けがましい態度を示さない。
近くにある馴染みのバーに行った。ぼくは相変わらずビールを注文し、ユカリは適当な注文をつけてカクテルを頼んでいた。
「ねえ、そのコート可愛いね。」とユカリは言った。
「そう?」バイクに乗るために一応ブランドショップのアウトレットで買った少し大きめのフード付きのオーバーコートで、上着の上に羽織るのにはちょうどいいぐらいだ。そしてポケットにマリファナ煙草が入ったままだったことを思い出した。着ていたものは下着を除いてそのままだったのだ。
その店で少しの間飲んだ。ユカリの機嫌はすっかり直っているみたいだ。「ずっとこうしていたいね。」とユカリは言った。それは終わりを示唆していた。「ずっとこうしていられればいいね。でもそうはいかないんだよね。」というふうに。
「そうだね。」とぼくは言った。「ずっとこうしていられるさ。」「おれがそうする、おれにはそれができる。君がいうように、おれはもっと強くなる。」
ユカリは言った「あんたはほんとうに優しい。」「でも。」
「でも?」ぼくは聞いた。彼女は黙っていた。
バーを出て一緒にぼくの部屋に帰り、途中で酒やら飲み物やらお菓子やらを買った。星は相変わらず見えなかった。でもぼくはその存在を感じた。そして星が自分の存在を感じていることを感じた。
ぼくらは酒や飲み物を飲み、セックスをした、そこにはいつもより親密なものがあった。別に加藤が言ったせいではない。ぼくはユカリを愛しく感じ、彼女もそれを理解し、応えていた。彼女の深い息づかいがそれを教えてくれた。星のことを考えた。ぼくらは星のように宇宙をたゆたっている存在なのだ。時には遠く、たまには近くにある。でもぼくらは近くに存在し、お互いを求めている。「それには意思があるんだ。」ただたゆたっているわけではないんだ。「ぼくは強くなれる。」
挿入するときにコンドームを探そうとしたが、彼女がそれを拒否した。「今日は大丈夫。」それでぼくは少し混乱した。彼女の生理周期のことを考えた。ぼくの記憶によれば、彼女の生理は正確だったし、今日はそれほど安全な日とは言えないはずだ。それに彼女は避妊については非常にデリケートだった。4分の3ほど欠けた月のことを思った。でもぼくはそれに応えた。彼女はそれを求めているし、ぼくも求めている。それにぼくはわりと避妊については自信がある。彼女の大きくはないが形のよい乳房を見つめ、ゆっくりと挿入した。それは暖かく湿って、ぼくを求めていた。ユカリは深く息を吐いた。そして深く抱き合った。
世界は正しく機能しているんだと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
