
チラシ制作の手順とポイント ~大切なのは材料集めとスケジュール管理~
こんにちは。Webディレクターの伊藤です。
これまでのキャリアで最も多く手がけた広告はチラシ。ということで、
今回はそんな私が、「チラシができるまで」についてお話したいと思います。
まずは必要な材料を集めよう!

「ビーヨン ヨンヨン コート ゴッパチ ハチマンブ」
なんだか呪文のようですが、なんだかわかりますか?
実はこれはチラシを作るのに必要な材料を表しています。
ビーヨンは「B4」のこと。紙のサイズを表します。
新聞折込をする場合はB3、B4などのB版が主流です。
なぜなら、新聞がB版だから。
ポスティングの場合も、B版の方が多い印象です。
ヨンヨンは「4色✖️4色」。両面フルカラーを表します。
ヨンゼロなら「4色✖️0色」。片面フルカラーですね。
チラシは使用する色の数によって費用が異なります。
現在は昔ほど大きな価格差はありませんが。
コートは「コート紙」のこと。紙の種類を表します。
コート紙は最もチラシに使われる紙で、
光沢感があり写真など色のノリが良いことが特徴です。
他に、光沢を抑えた高級感のある「マット紙」
コピー用紙と同じ、書き込みなどができる「上質紙」などがあります。
これについてはまた機会があれば触れてみたいと思っています。
ゴッパチは「58kg」のことで、紙の厚さを表します。
なぜ「厚さ」なのに「重さの単位」で表すのかは割愛しますが、
キロ数が大きくなればなるほど厚くなります。
厚い紙の方がペラペラの薄い紙よりも「高級感」「信頼感」が出ますね。
ハチマンブは「80,000部」。印刷する枚数を表します。
印刷業界では「枚」ではなく「部」で数えるんですね。
以上のように、
紙のサイズ
色の数
紙の種類
紙の厚さ
部数
この5つの要素が揃って初めてチラシを作ることができます。
印刷会社への見積もりを依頼するのに最低限必要な情報がこれです。
デザインを作ろう!
紙のサイズと色数が決まったらデザインに取りかかることができます。
デザインを他社に依頼する場合、どんなことを伝える必要があるでしょうか?
広告主の情報
広告の目的
掲載する商品やサービス・内容の情報
ターゲットや配布したいエリアの情報
商品画像などの素材
「こんなデザインがいい」などのイメージがあればその参考資料
キャッチコピーやデザインは基本的に制作会社が提案するものですが、提案に必要な「材料」の提供は必要です。最低限、1・2・3までは依頼前に内容をまとめておきましょう。
また以前の記事で紹介した通り、掲載する内容によっては景表法その他の規制がかかる場合がありますので、ここもクライアントと制作会社で共通認識を持っておくことが必要です。
完成前の「味見」は必須!

デザインが出来上がったら、いよいよ印刷工程に!
ここでは下記のようなチェック項目があります。
誤字脱字・リーガルチェック
誤字脱字はもちろん、言葉として意味が通るようになっているか?
景表法などの規制にかかる表現はないか?をチェックします。データチェック
チラシのデータはイラストレータというソフトで作られることが多いのですが、依頼する印刷会社・工場によって納品データの形式が異なります。
イラストレータのデータそのままというところもあれば、PDFというところも。データの形式を変換すると、文字化けや色抜けなど思わぬバグが発生することがありますので、データ変換時にもしっかりチェックします。リップデータチェック
印刷所では、入稿したデザインデータを印刷機で読み取り、出力できる形式である「リップデータ」に変換します。前段のPDF等への変換同様、この際にもバグが生じる可能性があるため、変換後のデータを戻してもらい、再度チェックをします。実際の印刷データに近づくため、元のデザインデータとは若干色味が変わったりする場合もあります。
このリップデータチェックで問題がなければ「下版(げはん)終了」!
印刷所の輪転機がグイングイン回り、チラシが印刷されます。
刷り上がったチラシは指定のサイズに裁断され、梱包され、
指定した納品先へを運ばれていきます。
作るだけでは完成しない

チラシは印刷して完成!ではなく、ユーザに届けて初めて意味があるもの
ですから、どう届けるか?を考えなければなりません。
代表的な配布方法は「新聞折込」と「ポスティング」。
まずはどちらにするか?はたまた両方使うか?も含めて検討します。
配布方法を決めたら次は「配布エリア・スケジュールの設計」です。
どこに何部、いつ配布するか?を設計します。
新聞折込の場合は、
スケジュール:「どの新聞の」「何月何日の」「朝刊or夕刊」
エリア:新聞ごとに定められた区分から配布エリアを選び、部数を指定
ポスティングの場合は
スケジュール:「何月何日〜何月何日の間に」
エリア:「市町村・町丁目」でエリアとそれぞれの配布部数を指定。
「戸建のみ配布」「集合のみ配布」「軒並み配布」のいずれかを指定。
※軒並み配布:戸建て・集合住宅どちらにも配布すること。
いずれの配布方法でも、エリアごとに配布できる部数には上限があります。
配布するエリアと上限内で配布部数を決めていきます。
その合計が、第一章で挙げた材料の一つである「部数」になります。
なので、まずは配布エリアを選定して部数を決定しないと、
見積もりは取れないということです。
配布エリアの選び方は様々ですが、
お店やイベントの広告であればその会場の近隣に配布する、
e-stat(政府統計の総合窓口)を活用してセグメントする、
などの方法があります。
スケジュール管理が大事!
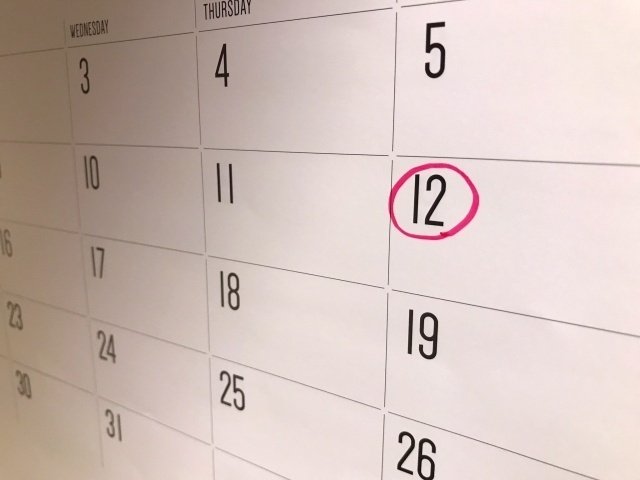
Webも同様ですが、チラシを作る際もスケジュール管理がとても大切です。
配布スケジュールが決まると、自ずと「納期」が決まります。
新聞折込でもポスティングでも、
配布日の3日前位までには拠点に納品する必要がありますので、
印刷工場から配布拠点までの輸送で1日、印刷に1日、デザインに1週間…
と逆算してスケジュールを組んでいきます。
印刷や配布の工程はスケジュールを縮めることが難しく、急ぎの場合は『デザイン』の部分に皺寄せがいってしまう形になります。デザイン期間を圧縮するとクオリティにも影響しますし、制作・印刷会社によっては特急料金などの区分を設けている場合もあります。
また納期を1日でも遅れれば、指定した日に配布ができないことはもちろん、スケジュールの変更により印刷会社や配布会社から追加料金を請求される場合もあります。
こうしたリスクを避け、納得のいくクオリティのチラシを制作するためには、クライアント・デザイナー・印刷会社・配布会社の各担当としっかりスケジュール・納期を共有し、いつまでに原稿の出稿・校了が必要なのか?
を明確にし、なるべく早めの相談と余裕をもったスケジュール確保を目指したいところです。
まとめ
長々とお付き合いいただきありがとうございます。
最後にもう一度、チラシを作る(印刷や配布のため)に必要な要素と、デザインのために必要な要素をまとめておきます。
紙のサイズ
色の数
紙の種類
紙の厚さ
部数
配布方法
配布エリア
配布スケジュール
広告主の情報
広告の目的
掲載する商品やサービス・内容の情報
ターゲットや配布したいエリアの情報
商品画像などの素材
「こんなデザインがいい」などのイメージがあればその参考資料
このように、チラシを作るためにはたくさんの要素が必要です。
どんな紙質で、どんなデザインで、どんな配布方法が良いのか?
プラスジャムはWebだけでなく様々な広告媒体をご提案可能ですので、
チラシ利用した広告展開をお考えの事業者様は、ぜひお気軽にご相談ください!
✙
プラスジャムはWeb制作会社です。
ウェブサイト制作、システム開発、Webマーケティングなど、さまざまな課題解決やアイデアを具現化するWebソリューションを提案・提供しています。

noteでプラスジャムを見つけてくださった方は、お時間あればコーポレートサイトや他の記事もご覧いただければ幸いです。
\コーポレートサイトはこちら/
\関連記事はこちら/
[今回の記事担当] ディレクター 伊藤
2024年入社。総合広告代理店出身のWEBディレクターです。
WEB以外のお話も投稿できたらと思ってます。
