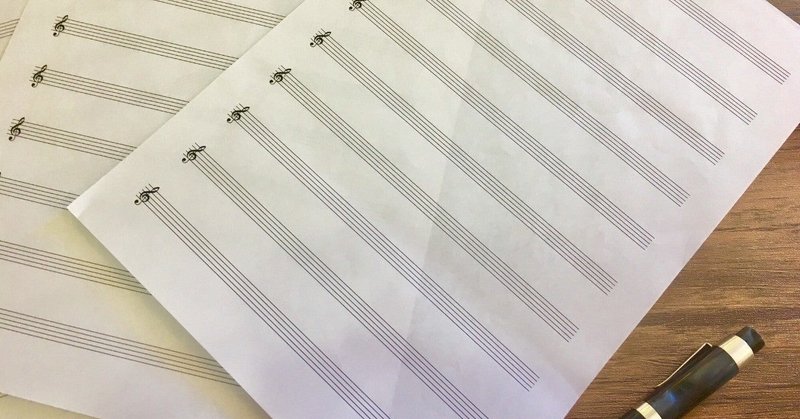
名前 | 五十嵐ファヨン
私は自分の名前を初見で正しく呼ばれたことがない。
在日二世の両親は、自分たちが通名を使用してきたことで何か背徳感でもあったのか、子供たちを本名で日本社会へ送り出した。いわゆる通名を使わせてはくれなかった。
韓国名は日本常用漢字でも表記可能だが、読み方はハングルのそれで、そのまま漢字を音読み、訓読みしたところで、どうやったって私の名前にたどり着けるわけがなかった。
ごく普通の公立小学校に入学した私は、自分が何か違うと気づくのにそう大して時間はかからなかった。
父は小学校入学前、私が人と「違う」ということをとても丁寧に説明した。
歴史を正しく知りなさい、ただ人間には罪はない。お前の名前で何かからかわれるようなことがあっても堂々としていなさい、と。
どのようにその歴史を説明されたのかは忘れたが、自分の存在に背徳感がないのは、あのときの父の話のおかげだと思う。
大人になってそのことを父に話したら、本人はすっかり忘れていたけれども。
名前が「違う」恐怖を最初に体験したのは小学二年生のときだ。
下ばかり向いている私をいつもからかっているガキ大将が、私を学級委員に仕立て上げた。私は初めて学校で号泣して先生に抗議した。
学級委員になることは、月曜の全校朝礼で任命状を渡されることを意味した。
黙って過ごしていれば、他の人と名前が違うことはバレない。けれど全校生徒の前でマイクを通して名前を呼ばれたら一巻の終わりだ。
先生は私が名前をただ呼ばれたくないだけということには気づかず、必死に私をなだめていた。
一方の私もただ自分の名前が人前で呼ばれるのが嫌なのだとは言えず、結局なだめられて家に帰った。
そしてそのまま迎えた任命式の日、私は全校生徒が大笑いするか、ざわざわするのか、なんにせよ地獄を見る覚悟で自分の名前が呼ばれるのを待った。
しかし、全校生徒の前で名前が呼ばれても、私の予想に反して誰も何も反応しなかった。あれほど拍子抜けしたのは、41歳になった今でも他に例がないほどだ。
私が小学生のとき憧れたのはザ・日本名だ。特に最後に「子」がつく名前が好きだった。
ちょうどクラスでかわいくて勉強もできて字もきれいな雪子ちゃんという子がいた。
雪子、なんて美しい名前だろう。
プリントの余白に雪子と何度も書いて、漢字と響きの美しさにため息をついていた。
今でもタイプしながら改めて「雪子」という文字を見ると、やはり美しいな、と思う。
とはいえ、別に改名できるわけでもなく、年が経つにつれて「違う名前」コンプレックスに諦めが加わった。4月のクラス替えで初めて出欠を取られる度に、新しい担任に自分の名前を訂正していった。
それは中学校に入っても一緒で、結局義務教育の9年の間、毎年――中学では教科によって教師が異なるから、もうそれはそれは何度も何度も――自分の名前を訂正することになった。
今考えれば外国人だのなんだのと噂になりまくっていたのだから、私の名前を知らない先生なんかいないはずで、わざとやっている先生もいただろうが、まあそれはどうでもよくて、とにかく数十人の前で自分の名前をひたすら訂正する作業は続いた。
人種差別の壁は厚い。嫌いだったら嫌いで、子供には罪がなくても腹が立つものらしい。
人に罪はない。
人種差別者にも。
あるのは環境の違いだということがうすうす、中学生の私にも理解でき始めていた。
ともかく始めこそ下を向いて自分の名前に恥じらいをもっていた私だったが、いつの間にか訂正するのは全く億劫ではなっていた。それどころか間違って呼ばれても返事するような、まあまあ無神経で特に繊細でもない女子高生が出来上がっていた。高校に入学すると、唯一仲が良かった幼馴染が秒速で学校に来なくなり、他の友達もなかなかできなかった。高校に入ったわけだから、勿論、イチから自分の名前を訂正する作業がはじまっていた。更に「外国人がいるって」という噂も広まったことで他クラスから私をわざわざ見に来る輩も現れ、青い目で金髪でもない自分に少々申し訳なさも感じつつ、結局その子たちへのケアも加わり、入学後最初の一週間はまあまあ忙しかった。
そして初めての音楽の授業が来た。
音楽の担当は眼鏡をかけた初老の男の先生で、髪はすでに白く、ちょっと禿げ上がっていた。
音楽室は校舎の一番東側にあって日当たりが良かった気がする。
勿論、最初の授業で出席が取られた。いつものように自分の名前を説明するセリフを頭で整理しながら自分が呼ばれるのを待った。このころには自分の名前について最短で説明を終え、相手に伝わる最良の方法を自分で確立していたから全くプレッシャーなどなく、この先生はどう間違えてくるのかな、と心配までする気配りができるほどだった。
自分が呼ばれる番が来て、確か先生はそのまま訓読みしたような覚えがある。そして私が訂正しようと口を開けた瞬間、
違うな。これは多分違う。
そう言って、私の名前を「正しく」発音した。
そのあとに私の顔を確認した先生は
ボクね、戦争行ってたの。韓国行ってた。だからね、ハングルわかるんだよ。
と言って、私の顔を見てニコリとした。
そしてそのまま出欠確認を続けた。
私は衝撃で声が出なかった。そして多分、衝撃を受けている自分にもびっくりしていた。
声が出なくて、そのまま授業が進み、何も頭に入らないまま授業は終わった。
当たり前だけれど、日本で、日本人から、自分の名前が正しく読まれたのは後にも先にもあのときだけだった。
授業が終わって一人でトイレに行って少し泣いた覚えもある。
そのあと、なかなか友達ができなくて一人で過ごす私を見つけては、先生は私を音楽準備室に呼び、コーヒーを入れてくれた。
初めて飲んだブラックコーヒーは苦くて全部飲めなかったけれど、ゆっくりちびちびと飲んでいれば、時間は潰せる。音楽準備室は吹奏楽部の楽器が所狭しと置いてあったので、私はティンパニーの横で小さくなって飲んでいた覚えがある。音楽準備室で先生は机に向かっていつも何かをやっていて、特に話しかけられることもなかった。でも、時間が潰せるし、誰にも気を使わなくていいので楽だった。コーヒーは相変わらずまずかったけれど。
幼少期から続けていたピアノのことも先生は知っていて、たまに私が黙ってグランドピアノを弾いていても、先生は話しかけてこなかったし、机から振り返ることもなかった。
卒業するとき、先生に呼ばれて楽譜を渡された。私の名前が書いてあった。
先生は私の曲を作ってくれていた。そして、その場で弾いてくれた。お礼は言ったと思うのだけれど、自分がどう反応したのかは覚えていない。嬉しかったけど恥ずかしかった。
私はイギリスの大学への入学が決まっていて、逃げるように日本を後にした。その楽譜は日本へ置いて行った。イギリスでもピアノは弾いていたが、その曲をもう一度思い出したとき、楽譜はもうなくなっていた。
卒業アルバムに載っている先生の住所を開いては電話番号を見て、連絡しようか、どうしようかと思い、そうしているうちにもう、20年も経ってしまった。
その間に自分の名前はどんどん意味がなくなって、まるで記号のようになってしまった。
あの曲はどんな曲だったんだろう。一音も思い出せない。
(了)
※このエッセイは、PLANETS Schoolで2020年5月に開催した「エッセイ添削講座」への応募作品です。
PLANETS Schoolとは、評論家・PLANETS編集長の宇野常寛がこれまで身につけてきた〈発信する〉ことについてのノウハウを共有する講座です。現在、7/9に開催する「レビュー添削講座」への応募作品の募集を6/26(金)まで行っています。ぜひ、チャレンジしてみてください!
※ご応募はPLANETS CLUB会員に限らせていただきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
