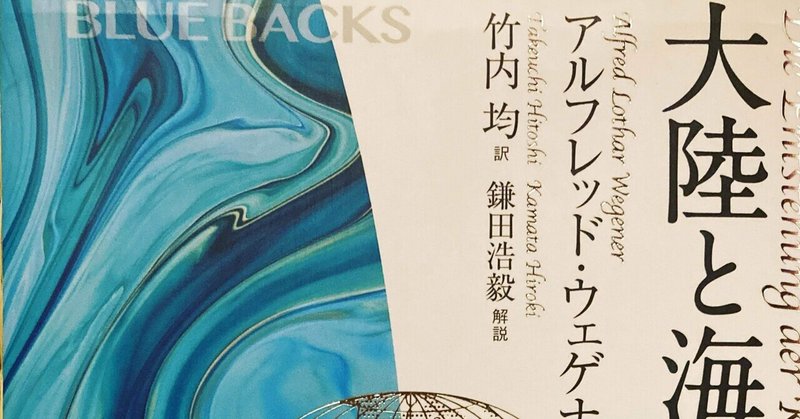
大陸と海洋の起源
"大陸移動の考えが最初に私の頭に浮かんだのは1910年のことである。その年に世界地図を眺めながら、大西洋の両側の大陸の海岸線の出入りに、私は深く印象づけられた。"1915年初版発刊の本書は大胆な仮説から30年後に"復活"地球科学の起爆剤となった古典的名著。
個人的には主宰する読書会の課題図書として手にとりました。
さて、そんな本書は地質学ではなく【気象学や地球物理学を専門としていた】著者が、アフリカと南アメリカでの動物の類似性に関する論文を読んだ時にその理由を『かって両大陸をつなぐ細長い陸地があったのではないか』(陸橋説)とする当時主要であり、常識的とされた学説に疑問を持ち【今は遠く離れている大陸は過去には一つだったのでは】また【大陸は海洋底に浮かぶ軽い物質では(=水平方向に動きうる)】との大胆な仮説(大陸移動説)を提唱、初版発刊後も反論を受けるたびに新しいデータと議論を加筆、亡くなるまでに刊行し続けた第四版『最終版』を翻訳したもので。
まず、現代感覚では『大陸移動説』こそが主要であり、常識的になっている私からすれば『陸橋説』の方が不思議であり、当時の著者が学会からは【これほど詳細な反論】もむなしく全面否定、変人扱い。【死後はすっかり忘れ去られてしまった】事実に愕然としてしまった。
また、そんな本書は大陸移動説自体は序文いわく『すべて第一章に書かれている』との通り最初に説明。後は【この説をめぐる議論・反論の歴史】が、測地学的、地球物理学的、地質学、古生物及び生物学、古気候学など様々な視点で書き続けられているのですが。詳細はわからなくても著者が【人生をかけて、この『大陸移動説』を世に出そう】と苦心していた事が【熱量高く伝わってきて】感動してしまった。
地球科学の古典的名著としてはもちろん、地道に研究に取り組んでいる全ての研究者の方にもオススメ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
