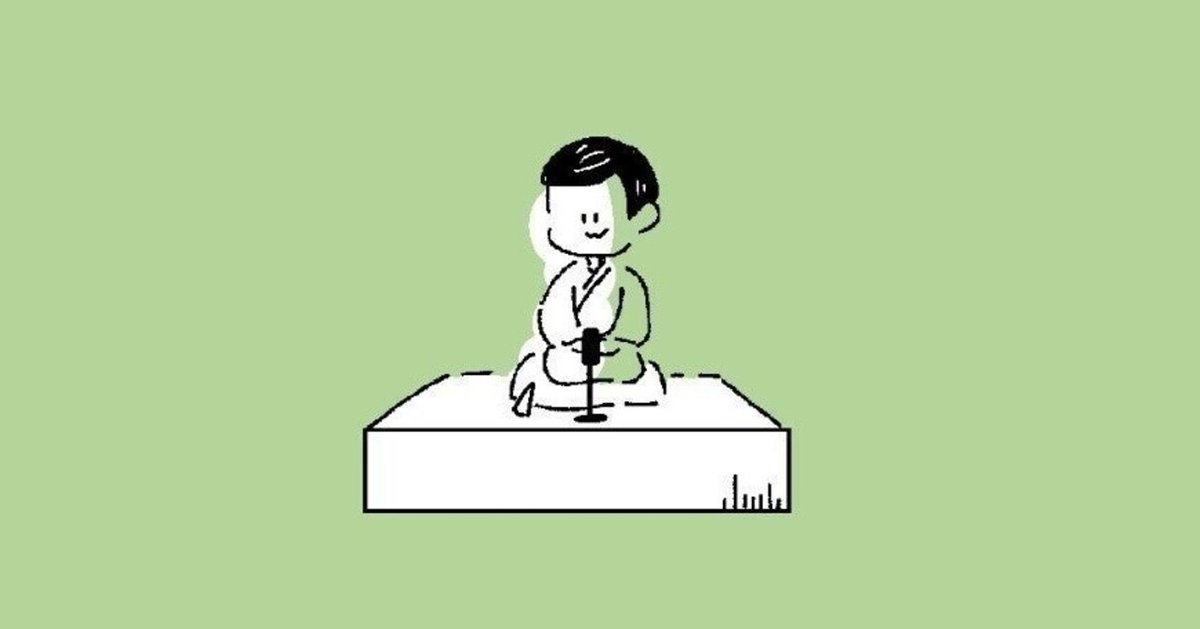
昔話に学ぶ《き》
今日も溜まったストックを完成させてみよう
『 ぶんぶく茶がま 』
これは群馬県に語り継がれる物語
群馬県館林市にある茂林寺で起こった物語
今でも分福茶釜が展示されており、
一般参拝客でも見学することができる
興味のある方は
是非に足を運んでみてくださいませ。
あらすじは以下…
むかしむかし、
群馬県に茂林寺というお寺がありました。
あるとき
その寺で千人法要を行うことになり、
大勢にお茶を振舞うための
茶釜が必要になりました。
そんなに大きな茶釜を
急には用意できないと
坊さんたちは悩んでいました。
すると、
守鶴という坊さんがふらりと出かけていき、
どこからか茶釜を手に持って帰ってきました。
その茶釜をみんなが気に入り、
法要で使うことにしました。
いざ守鶴の茶釜を使ってみると、
水を注ぎ足さなくても
湯が全くなくならないのです。
この不思議な茶釜は法要で大活躍し、
千人分のお茶を
これひとつで淹れることができました。
守鶴はこの茶釜を幸福を与える茶釜として
「分福茶釜(ぶんぶくちゃがま)」と名づけ、
分福茶釜のお茶を飲むと利益があるでしょう、
と言いました。
それからしばらく経ったある日、
守鶴がひとりで昼寝をしていました。
そこへ別の坊さんがやってきて
守鶴に声をかけようとしたところ、
守鶴の股の間から
大きな尻尾が生えているのが見えたのです。
実は、守鶴の正体は
数千年生き続けた古狸だったのです。
正体を知られては
もうこの寺にいることはできないと言い、
最後に、坊さんたちに実際に見てきたという
釈迦の説法と源平合戦を再現してみせました。
坊さんたちが感激している中、
守鶴は狸に姿を変えその場から去りました。
伝えることの重要性
ヒトには口があり、伝える言葉もある
思っていることも伝えなければ
何にも繋がらない。
数千年生き続けた古狸も
流石に火にかけられたり
タワシで洗われたりには
耐えられなかったのでしょう
茶釜もタヌキであったバージョンの話も
あったよね
坊さんの姿であっても
千人分のお茶を作るのも苦労しただろうに
案外出来た
たまたま出来た
いつか言おう
私はそもそも茶釜じゃありませぬ
私は坊さんでもありませぬ
私はタヌキです
と。
あるある。
周りの評価が
見積もりよりも高くなっちゃうこと
自分の知らないところで
勝手にハードルを上げられちゃうこと
無理してクリア出来れば万々歳なんだけど
そもそも身体を傷めてまでするべきか
色々なものを天秤にかけてみて
こりゃいかんな
そんな時には
伝える
これに尽きる
新人の時はよくミスった
よく分かってもないけれど
一丁前に返事は元気に「はい!」が正解だと
思い込んでしまってさ
曖昧な指示とか
ざっくりした説明で
そのまま何が分かってないのかすら
分からずとも仕事受けちゃって
〆切近付いて焦って無理して
結果、目標下回る出来で提出。
とりあえず提出されたけど
良くもなく悪くもなくの無難な結果に
特に何の評価もされることなく
また新しい業務を課せられる
一応さ
お金もらって働いているからさ
雇い主の目的にあった動きはすべきで
依頼を受けたら
100%依頼主の目指す内容を
理解した上で仕事に取り掛かる必要がある
それには
目的、内容、どのくらい、期日を
聞いておく
意思伝達、意思確認
これがものすごく大事となる
新人時代はさ
何が分からないのかすら分からない
今何してて、これが何になるのかすら
見えてないこと多々ある
不安や葛藤も多い
これは情報量が足りないからと
自分にとっての必要性が分かってないから
だと思うの。
新人職員もベテラン職員も
してもらって当たり前じゃなくて
歩み寄りが大事だよね
忙しいからで聞かない
相手に気を遣って聞けない
たったそれだけで
仕事をクリアすることから
グンと離れてしまう

一生懸命汗水たらして自転車漕いでもさ
目的地が全然違えば
一緒に歩き始めても
辿り着かない
前を行くものがズレてるのに
後ろの人が気付けば言えばいい
前の人が分からなければ
後ろの人に聞けばいい
単純なこと簡単なこと
だけどなかなか出来ない
でも
これが当たり前に出来れば
社会は優しくなると思うんだよなぁ、、、
サポートがなんなのかすら理解できていませんが、少しでも誰かのためになる記事を綴り続けられるよう、今後ともコツコツと頑張ります!
