
登山の日
語呂合わせで、日本山岳会が10月3日に記念日を制定。
現在は地球規模まで肥大化した経済が一人歩きをはじめてコントロールが困難になってきている時代だといわれる。ただ、まさにリベラルが標榜する理想に近づいているという見方もある。予測できない不安と混乱が経済に云々とか、人心の荒廃を招く危険がある。過去にはこうした不安と混乱を収めるため人類はこれを戦争で解決してきた。スクラップ&ビルドである。これもまた、人間の欲がなせる技である。
登山家の平林克敏は、ヒマラヤ登山中について、このように語る
[...]7千メートルぐらいの高所で吹雪に遭遇すると、細かい結晶のきらきらした粉雪がスポーターグラスの中や首筋の中に潜入してくる。風速が増すと呼吸を確保することすらできなくなってしまう。このままだと「あぶない」なんとか呼吸を確保しなければと、ピッケルで雪の斜面に頭だけ突っ込めるほどの穴を掘って顔を入れる。
呼吸が確保できると「ああ、助かった。これで生きてられる」と思う。
それから、その穴を少しずつ大きくして、自分の身体を蓑虫のようにまるめて入れるようにする。
風から身を護れるようになると、ようやく、ホッとする。
しかし、それもつかの間、30分もすると、その穴の中は、息も詰まるほど狭苦しく、丸めている足腰は痛いし、地獄のような場所に思えてくる。
[...]はじめ、吹雪から逃げられた瞬間は極楽のように思えた雪洞の中が、30分後には地獄のような場所になってしまうのである。
(「熱い心」より引用)
雪洞で、一晩すごした翌朝テントにいくとテントが天国になり、そのまた翌朝ベースキャンプにいくと、テントが地獄になる。ところが、このベースキャンプも地獄になるのである。カトマンズのホテルにいき、日本に返ってくると、日本に順応し、カトマンズのホテルが地獄にかわるという具合に、交互に天国と地獄を経験するようになる。

平林氏は、ここに人間の欲の根源をみてとり、日本だけで過ごす文明と脳の肥大による価値観にどっぷりとつかることに警鐘を鳴らす。さらに考えを推し進め、”3つのバブル”があるという、これまで幾度も経験した異様な投機「経済のバブル」、もう一つが「技術バブル」で度を越した技術革新の諸刃の剣を指摘し、「人の心のバブル」で倫理感を壊し、抑止力がなくなるという。
いったい地獄を経験するような精神的コストや物理的なコストなぜ山にいくのかという若き経営者の質問に平林氏はがっかりする。そこに、いうなれば頭だけで効率のみを考えている浅知恵を見抜く。氏は足るを知る、清貧の生活が理想としながらも、その美学だけでは、人間の行動は変わらないともいう。ではなにが、変える力があるかといえば、平林氏は熱き心だというのである。それは必ずしもすぐに経済的な活動に役に立つこととは限らない。蝶の生態であったり、ひいていうならばアムンゼンや植村直己や、堀江謙一の冒険心、熱き心、探究心のみが、文明を支え、世の中を変える力であるべきで、頭でっかちの肥大した知ではないと訴えるのである。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
平林氏のお説に反対する気はない。ただ私は、だからなんだ、といえば、それまでのことであると思う。畢竟熱き心を持てた側の立場のものいいだとさえ思うのである。畢竟熱き心があろうがなかろうが、なるようにしかならない力が働いて現在に至る。悪魔のような実験をしようが、効率だけを求めようが(つまりは楽な道を見出そうが)熱き心がそれにインパクトを与えようが与えまいが、畢竟なるようになる。こうしたことを、哲学では運命論者という。構造主義者なら、人間がそれぞれの欲動をそれぞれ好き勝手に働かせようが、ある状態に落ち着く構造をもっていると言い換えるであろう。
これに対し、サルトルなどは反駁し、人間には瞬間瞬間に無限の選び取りがあるといった。
ちょうど、ヒマラヤで雪洞→テント→ベースキャンプとたどるように。そのときそのときの瞬間で、心の状態が天国と地獄と変化するようなことである。たしかに地球規模で、人知が及ばないほどの影響力をもって科学や人間の営みが自然破壊をするまでになったことはいままでとは違った次元であるとは言えるのかもしれない。でも遅かれ早かれではないか。どうせ地球は永久に存在する星ではないことはわかっているのである。サルトルの無限の選び取りも構造主義者のものいいも、天国と地獄を辿っていく場面場面を切り取ってその瞬間になにかをいっているだけのことである。つまりは、雪洞を掘るときには、熱き心で堀ったのだと思う。その瞬間をとらえて感動を覚える。雪洞から抜け出しなんとかテントへ向かうのも熱き心であろう。同じくだ。熱き心の交感神経(地獄)と副交感神経(天国)を交互に味わっているに過ぎない。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
そういった、熱き心と安らぎという輪廻を回される存在をニーチェの超人のように超えることができないのであれば、絶対的な正しさというものは絶対的な力をもたないのである。
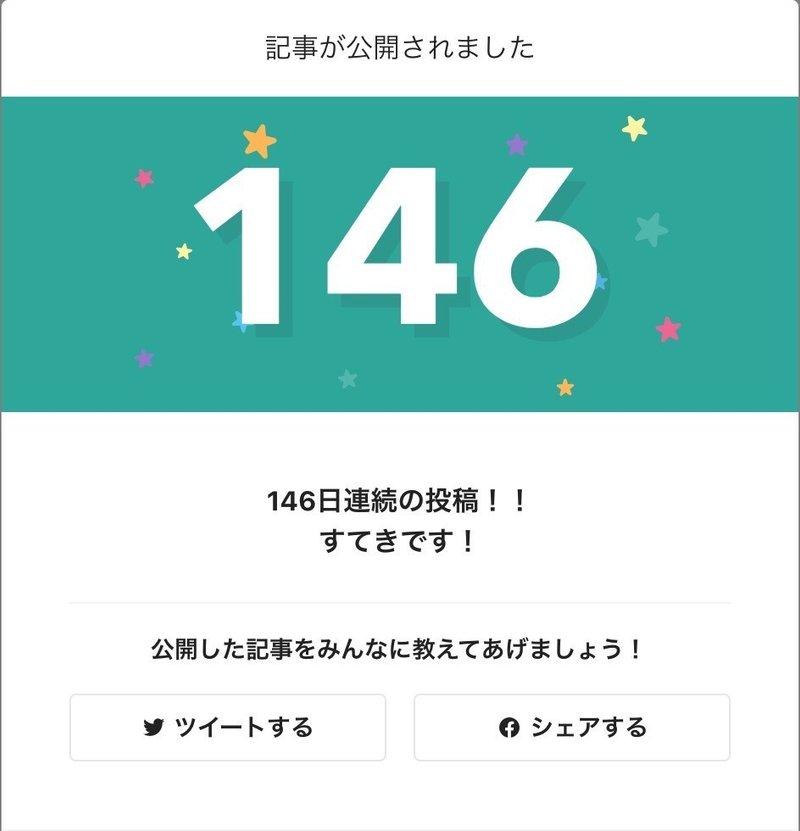
このnoteで147日連続という具合になる。
そこには、熱き心もあったし、惰性ももちろんあった。ただ目の前のことを淡々とこなすこと、それが大事であり、実は登山と同じことであるように思う。どんな心労があろうとも、続けようと思う。いまよりも高い場所がきっとあることを信じて山を登る気持ちだと思う。まだまだ平林氏のように高い山を制覇したわけではない。それでも。ただ目の前のことに一生懸命対応していく。順応していく。目指すものなんて何もない。そうすることが私にとって生きるということなのかもしれないし、そうではないのかもしれない。
求道者のように続けていければ、必ずやどこかにたどり着くことができるだろう。それは必ずしも期待するようなことになるとは限らない。でもそのたどり着く場所は自分が意図しない場所かもしれない。所詮は人間思いのとおりになんかならないのである。そして、それが山に登る理由に近いことになっているのではないかと思うのである。いまは答えなんかともかく一歩一歩楽しく生きていこうと思うのである。
------------------------------------------------
<来年の宿題>
・登山家の話をきく
------------------------------------------------
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
