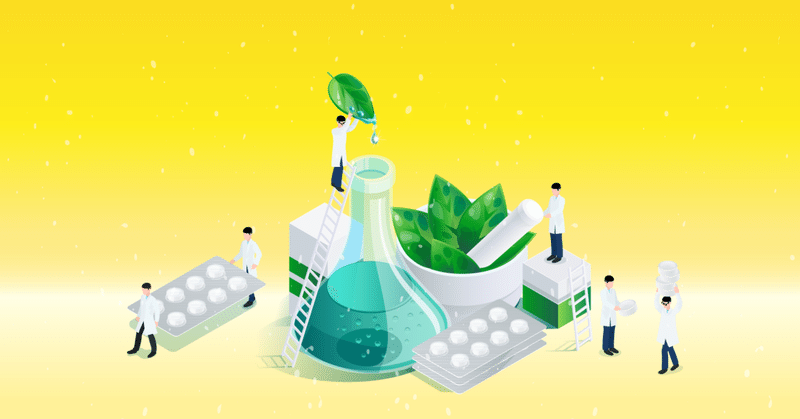
モルの日
北米の科学者が提唱したのが始まりで、10月23日am6:02〜pm6:02を
モルの日としている。
門外漢であるものの、化学に興味は持っている。小学生のときに、人口が増えたら地球は影響を受けるだろうという疑問だった。たとえば、50kgの人が1000人増えれば5トンである。人口増加は何億という単位なので、何十億トンも増えたならば地球の自転にもさすがに影響あるだろうと思っていたのだ。しかし、この問いの建て方は、中学生の理科で否定された。すなわち質量保存の法則である。何億何百億人人口が増えようが、地球上の物質を変換して人になったに過ぎず、地球の重さは変わらない。
もうすっかり忘れてしまったが、モルとは、原子をアボガドロ数だけ集めてくると計算しやすくなる単位の便法のことだ。単位変換しているにすぎない。物理の授業でディメンジョンチェック(単位)を揃える。それととても似ている。4.6gのNa(ナトリウム)は何個か・・・みたいな問題を考えてみる。1モル集めると23gになるので、1.2*10^23個になる。単位を合わせるだけで答えが出る。
![]()
もう一例、
砂糖に水を加えると ブドウ糖と果糖になる
C12H32O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6
なのだが、右辺のブドウ糖と果糖は、分子成分は同じであるので同じ式になるが結びつき方が違う。こういうのを異性体という。
これが、それぞれ何gずつできるかは、モルがわかればスマートに導きだせる。さらに
C6H1206 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
という感じに分解される。
二酸化炭素が砂糖からどのくらい(g)生まれるのかもわかる。
こういうのをとてつもなく面白いと思ったものだ。
モルは化学式においてとても便利な役目を果たすものであるが、
このアボガドロ数の決定には大きな意味が含まれていた。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
ポアンカレについて、いろいろとネットをみていて、ストックした記事を読み返した。
ジャン・ペランは、物質が分子からよりなることを実験によって明らかにしたことで、ノーベル物理学賞を1926年に受賞した。彼は陰極線( rayons cathodiques)の研究し、電子の発見への道を開いた人でもある。そんな彼の展覧会が、ポアンカレ工業大学で開かれたという記事である。
物質が不連続に存在していることについて、つまり分子と原子という状態で存在していることについて、ブラウン運動におけるアインシュタインの理論づけに必要な情報を彼は提供した。分子の動きをとらえる実験において、彼はアボガドロ数を決定づけたのである。
Grand expérimentateur, Perrin démontre une fois pour toutes la discontinuité de la matière, c’est-à-dire l’existence des atomes et des molécules, encore très controversée au début du 20e siècle. Il fournit la confirmation expérimentale de la théorie d’Einstein sur le mouvement brownien, le mouvement chaotique d’une particule dans un fluide. Ce phénomène permet d’étudier le mouvement, et donc l’existence, des molécules et cela amène Perrin à déterminer le nombre d’Avogadro (nombre de molécules par mole d'un gaz).
記事ではさらりと、アボガドロ数を決定づけたとしているが、
ちょっと時代の様子をみてみよう。
18世紀には、気体の諸性質を運動学的に理解しようとする試みがベルヌーイによってなされ、気体圧力と体積が反比例の関係で、圧力が粒子の速さの2乗に比例すると指摘した。1850年代には、気体のこうした諸性質を気体分子の熱運動から説明しようとする運動がはじまった。しかしながら、ベルヌーイはあまりにも当時としては考え方が新しすぎたために、マッハやオストワルドなどは否定的な見解を述べこの潮流に組する流れもたしかにあったのだ。実証主義者たちのこうした主張は、架空のモデルの上に成り立っている机上の空論という見解に終始していたのだ。さらにポアンカレが物理学の危機を唱え、直接みたもののみを頼りにしようといったので拍車がかかってしまい、物理学は動揺期に入った。そんな動揺期に、ペランはさっそうと登場してきたのである。
彼は、気体の粘性、ブラウン運動などさまざまな異なる現象から、
アボガドロ数の決定をして、まさに数えられるものとして、気体の運動法則を可視化したのである。
ポアンカレ工業大学の展示場は、CNRSの科学史家であるDenisGuthlebenによって設計され、数学者でありデザイナーであるConstanza Rojas-Molinaによって説明された一連のパネルが飾られペランのキャリアと取り組みのハイライトをたどることができる。
ペランはソルボンヌ大学で教鞭をとったときに、アンドレ・ジッドのような小説家にも教室をOPENにして招き入れた。
キュリー夫人が資金難だったときも、彼女の研究場からほど近い場所にセンターを作った。政府にもはたらきかけながら(というより科学研究国務次官として)国立科学研究所(CNRS)の建設した。ペランは生涯を通じて、科学の普及に努めたのである。彼が建てた建物の中で、”メゾンポアンカレ”(化学物理研究所)が2021年に開設を迎えるのである。
-----------------------------------------------
<来年の宿題>
・ポアンカレ「物理学の危機」
------------------------------------------------
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
