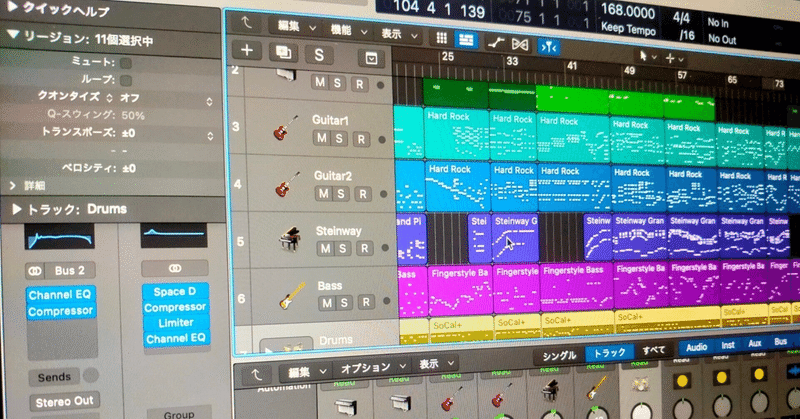
作曲におけるBtoBとは
僕自身前々から興味があったDTMに取り組みはじめ、音楽に対して関心が高まっている中、
最近、知人がニッチなボカロ曲を勧めてきた場面があった。
それらは再生リストにまとめられており、ほとんど聴いたことのない楽曲ばかりであった。僕自身そこまでボカロ曲を掘り起こしたりしているタイプでは無いのだが、そのプレイリストの楽曲は数100再生がほとんどだったため、ボカロがある程度好きな人でも知らない楽曲が多かったであろう。
そんな場面に出会って自分は、
「どこへ行っても人気商売は辛い…。」
と感じた。
楽曲のクオリティは決して悪いわけではない。
流行のアニソンみたいにきれいなストリングスも入ったアレンジされた素晴らしい楽曲もあった。2010年代初期であれば流行っていそうな楽曲もあった。
しかし、再生数は行かない。せっかくの傑作もこれでは有象無象とともに流れていくのか…。と。
一定まで時代が進むと、ボーカロイドや新たな表現による先行利益は無くなり、どれだけ技術力・知識を伸ばしても、他も同じようにこれでもかと吸収した技術や知識を使って曲を作る。
まず、人気商売としてやっていくならば、プロとして既に一線で活躍している天才達と勝負することになるであろうし、よほどの天才でない限りは、常にその時代その時代の流行をキャッチアップして、潜在的に求められる音楽を迅速にリリースしていく必要があるだろう。
また、「人間は「耳」で曲を聴いていない。」とも言う。
我々は、
「アーティストの背景や容姿が魅力的だから。」
「友人も聴いているし人気だから。」
「この楽曲のサムネやMVが魅力的。」
という理由で曲を聴いていないだろうか?
音楽の道では技術や知識だけでは、やっていけないのだろうと感じる…。
音楽は、絵やイラストと違って一瞬で目で見て鑑賞することが出来ない。
音楽は時間芸術である。SNSを通じてシェアされて人の目にとまるイラストと違って、そう簡単に人に感じてもらえるものではない。
どんなに良い音楽でも、再生ボタンを押してもらうか、再生ボタンを押さずとも自然に人の耳に流れる状況でない限り、その傑作は他人の耳で感じて貰うことができない。
つまり、再生ボタンを押さずとも自然に人の耳に流れる状況をいかに作るか。
それはつまり、「きっかけ作り」が重要であるということである。
そしてそれは、アーティストとファンというBtoC(ビジネスtoコンシューマー)の関係ではなくBtoB(ビジネスtoビジネス)で楽曲を提供すれば、その必然性を担保できて良いのではないかという結論に至ったのである。
では、そのBtoBでの楽曲提供先の例って一体なんだろうと考えてみる。
ゲームBGM・劇伴
最初に思いついたのは、ゲーム音楽や劇伴である。
ゲーム音楽はゲームという媒体を通じて人々を引き寄せ、BGMやテーマソングを通じて楽曲をほぼ必然的に人々の耳に聴かせることができる。
ただ、そこには、世界観にマッチするようなサウンドを作り上げなければならないという課題がある。
引き出しの多さや、類似の楽曲を探し出せる情報収集力、それを再現性のあるものにできる知識量が必要である。
それに成功することができれば、雰囲気を作り出せるミックスの能力、楽器や音源、モノによってはモードなどの音楽理論の知識を集約させることができるなど、ポートフォリオとしてあらゆる能力の証明になるだろう。
映像用BGM
映像用BGMは、テレビ番組・広告・YouTubeなどが考えられるが、最近ではゲーム配信などの個人による生配信にて需要があるように感じる。
フリーの楽曲が多く出回っており、それを用いた広告が多く見受けられ、「この広告の音楽聴いたことあるな。」とか「このお店のBGMとこのお店のBGM同じだな。」とか、ブランドイメージを損なっているのではないかと思う場面も見受けられる。
そこに、楽曲制作者として、楽曲を提供することができれば、企業や動画投稿者・ストリーマーのブランドイメージを底上げするという付加価値を提供することができるのではないだろうか。
BtoCよりBtoBの方が、売れるにあたって再現性がありそうだと考えたので、様々な例を考えてみた。
しかし、BtoBの仕事を得られるにもある程度は人脈と実績が必要であろう。
大勢の人はいきなり信用や実績が無い者に仕事を任せる危険性を知っている。
極力受け身で音楽だけ生み出し続けられる人にとっては、コンスタントに人々の潜在的なニーズに応えた楽曲を、YouTubeやニコニコ動画、SoundCloud、ブログや個人サイトに楽曲を投稿し続けるとメリットを享受できる土台になりそうである。
一方で、特に個人サイトは、先行利益を得た人が検索上位のトップに居続けるようになっているので、作曲で飯を食うのは一般的な人間にとっては一筋縄ではいかなそうである。
他人のエンタメ活動のブランドイメージの底上げ・人々へのニーズ・そんな人々へ届けようとする思いがあれば、成功するはずである。
そして、楽曲制作からは離れるが、おそらく音楽における最も単純かつ究極のBtoBは、「音楽を教える」ことだろう。
将来音楽業界という大海原に出るミュージシャンの卵に羅針盤を売る仕事がきっと最も需要がある。
ゴールドラッシュの時に採掘者にスコップを売る者、プログラミングが流行ったときにプログラミングスクールを立ち上げる者が最も利益を手にする。
正直言うと、音楽の演奏方法やDAWソフトの使い方、音楽理論に至るまで、様々なコンテンツが既に存在している。
2022年3月9日に正式公開されたSound QuestはWEB媒体で網羅的に莫大な音楽理論の情報を提供しており、楽器の練習・演奏方法・DAWの使い方については主に個人のYouTuberやブロガーがこれでもかというぐらい説明している。
しかし、ポップスは常に更新されているし、見やすさ・分かりやすさ・詳しさにおいては、まだまだ進化し続けることができ、常にコンテンツは作り続けることができるだろう。
ただ、こう考えると、以上のように挙げたものは、よく言えば生存戦略であり、悪く言えば遠回りだなと感じる。
目標をどこに設定しているかによって、個人の見方は変わるだろう。
遠回り中に中途半端に挫折するぐらいなら、自分の作りたい音楽・なりたい像に向けて、正直に突っ走った方が成功できる確率はかえって高いというのも理解できなくもない…。
売れ方も様々なので、個人の強みを改めて見つめ直してもいいかもしれない。
この記事が、音楽分野だけでなく、あらゆる個人に向けて・ビジネスに関して少しでも考えるきっかけになれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
