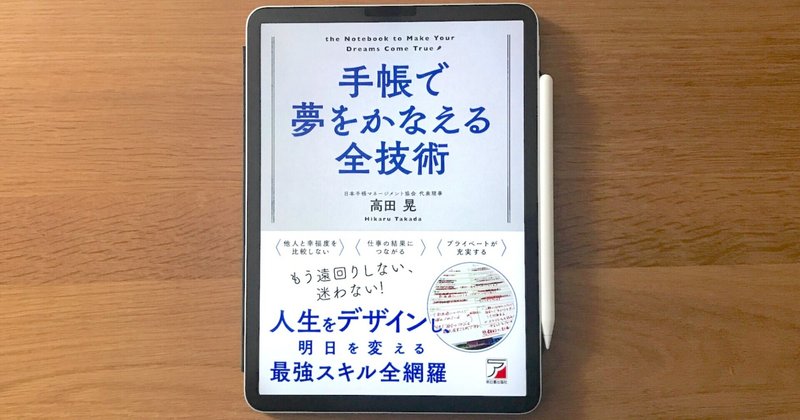
【手帳好きに超おすすめ】これで目標は達成できる。計画を行動に変える1冊『手帳で夢をかなえる全技術』
手帳を上手く活用すれば目標も達成しやすくなるし、挫折しがちだった勉強や運動が習慣化できるようになります。
とはいえ、手帳を書き始めるにあたって「何から始めればいいかわからない」という人は多いと思います。
そんな人におすすめしたいのが、手帳術について網羅的に解説した『手帳で夢をかなえる全技術』という本です。
「これから手帳を始めたい人は、とりあえずコレを読んでおけばOK」という非常に有用な1冊です。くわしくレビューします。
今さら「紙の手帳」を使う理由
手帳を持つということに対して、懐疑的な人は多いと思います。わかりやすくいえば「なんでわざわざ手帳なんか持つの?スマホで予定管理すればよくない?」という話ですね。
たしかに一理あるのですが、本書ではわざわざ紙の手帳を持つメリットについて以下のように解説しています。
「探す」という顕在的な行為においては検索性に優れたデジタルツールに軍配が上がりますが、どこか目的が明確になりきってはいない「見返す」という潜在的な行為では、逆にアナログ手帳が優位です。
たとえば「あのメモどこに書いたっけ?」というとき、スマホやパソコンであればキーワードで検索すれば該当箇所がすぐに見つかります。
紙のメモだと、ページをめくってメモを探さなければいけないので、検索性という点においては雲泥の差があります。
しかし、上記で解説されているように【どこか目的が明確になりきってはいない「見返す」という潜在的な行為】を考えると、話は一気に変わってきます。
紙の手帳を読み返すのは、紙の本を読み返すのと似ているかもしれません。
紙の本はパラパラとページをめくって、何となく読みたいところを探すときに便利です。電子書籍はそういった無目的な読書には向いていません。
手帳でも同じで、過去の記録を読み返すときに「なんとなくページをめくる」という行為ができるのは紙の手帳だけです。
一見すると、「なんとなくページをめくる」ことは無意味にも思えますが、自分でも思いがけないメモと遭遇すると、そこから新しいひらめきが生まれたりします。
なにより、過去の手帳やノートを読み返すのってシンプルに楽しいんですよね。「1年前の今日はこんなことしてたんだな」とか「この頃はまだまだ考えが幼稚だったなー」といった具合に、自分を振り返るのはなかなか楽しいものです。
「なんで紙の手帳を使うの?」という問いに対して【どこか目的が明確になりきってはいない「見返す」という潜在的な行為において優位性がある】と言語化できているのは、なにげにすごいなと思いました。
「手帳を自分に合わせる」ことの重要性
この本では「マイ手帳」という、自分に合った手帳にカスタマイズしていく方針をとっています。そのため、基本的にはシステム手帳を推奨しています。
システム手帳と綴じ手帳は一長一短ありますのでここでは触れませんが、僕が共感を覚えたのは【「自分を手帳に合わせる」のではなく、「手帳を自分に合わせる」】という視点です。
大型の文房具店などに足を運ぶと、「○○手帳」といった形で実に数多くの種類の手帳が販売されています。どれも様々な工夫が施されていて、手に取るだけでもどこかワクワクしてくるものです。
しかし、手帳それぞれに様々な特色があるゆえに、どこかその手帳独自の「使い方のルール」に縛られてしまうケースが少なくありません。
手帳にこだわりがある人ほど、この考えには共感するのではないでしょうか。
僕も手帳に関しては一家言あります。これまで市販の綴じ手帳を使ってきて「週間スケジュールは絶対にバーチカルを使う」とか「土日が小さくなってる週間手帳はNG」といった具合に、自分なりのルールが形成されてきました。
市販のテンプレートに合わせるのはたしかに便利ですが、その手帳が本当に自分の目的や使い方に合ってないと、手帳が持つ本来の効果を発揮できないと思います。
そういった意味でも、カスタマイズ性の高いシステム手帳は有用だし、こだわりがある人ほどシステム手帳を持ったほうがいいのではないかと感じました。
年間目標をデイリースケジュールに落とし込む方法
手帳術の基本として、「大きな目標や予定を決めて、そこから細かい予定に落とし込んでいく」というものがあります。
本書ではそういった手帳術の基本とも言えるポイントを丁寧に解説しており、著者が使っている手帳の実物写真も織り交ぜながら紹介しています。
本の中で紹介されているステップは以下のとおりです。
ステップ① 「人生理念」を決める
ステップ② 1年後、3年後、5年後、10年後の目標を立てる
ステップ③ 「年間計画」と「3ヶ月計画」を作成する
ステップ④ 3ヶ月計画をもとに、「月間計画」と「週間計画」を回す
ステップ⑤ デイリーページで1日ごとの計画を立てる
僕を含め、多くの人が「とりあえず目の前のタスクをこなすために手帳を使っている」状態だと思います。仕事のアポとか事務作業の予定がまさにソレですね。
「人生理念」とか「10年後の目標」とか言われてもピンと来ない人もいるでしょうし、「そういうの意識が高すぎて苦手…」という人も多いと思います。
正直なところ、僕もそっちよりの人間です。「やりたいことリストを100個書きましょう」とか言われるとゲンナリします。
でも、この本を読んでみて「本当に手帳を使って人生を良いものにしたいのであれば、大きな目標を決めることは不可欠だよな」と強く思いました。
大きな目標や計画を実現するためには、絶対に逆算でスケジュールを組む必要があるんですよね。むしろそれをやらないと、目標を立てただけで何もできずに終わってしまいます。
年間目標を決めて、そこから月間計画や週間計画、さらには1日ごとのスケジュールに逆算して落とし込めば、おのずと今日やることが見えてきます。
今までは本格的な手帳の運用から逃げていた感じがあるのですが、この本を読んで「いよいよ本腰入れて手帳を使い始めるか」と思えた次第です。
【難点】この手帳術を完遂すると、無理が生じる
本の中で解説されていることにはおおむね賛成だし、実際に取り入れたいと思えるアイデアがたくさんあります。
ただし、1つだけ難点があります。それは、本書で紹介されているやり方をすべて完遂しようとすると、とてつもなく分厚い手帳になることを覚悟しなければいけない、ということです。
さきほど説明したように、ここで紹介されている手帳術は年間、3ヶ月、月間、週間、デイリーといった感じで、期間ごとにそれぞれ予定を立てることになります。
そうなると必然的にリフィルの枚数が増えますから、手帳が分厚く、重いものになることは避けられません。単純計算ですが、デイリーだけで365ページは必要になるわけですから、リフィルをすべてを揃えるといかに手帳が分厚くなるかは容易に想像できますよね。
分厚い手帳と毎日を過ごす覚悟がある人は良いですが、そうでない人は本書のやり方を完全再現するのは避けたほうがいいでしょう。
それよりも必要なエッセンスだけを拾って、自分の手帳に組み込むのが理想的なやり方だと思います。
たとえば僕の場合、大きな目標を立てて、そこから小さな予定に落とし込むという方法は踏襲しています。ただし、年間目標を立てて、バーチカルの週間レフィルを使って、それ以外はバレットジャーナルで自由に書くというスタイルをとっています。
「本で紹介されているとおり、完璧にやらなきゃいけない」なんてことはまったくないので(著者も本の中でそう言ってます)、気軽に始めてみるくらいで良いと思います。
いずれにせよ、手帳を本気で運用したい人にとっては非常におすすめできる1冊ですので、ぜひ読んでみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
