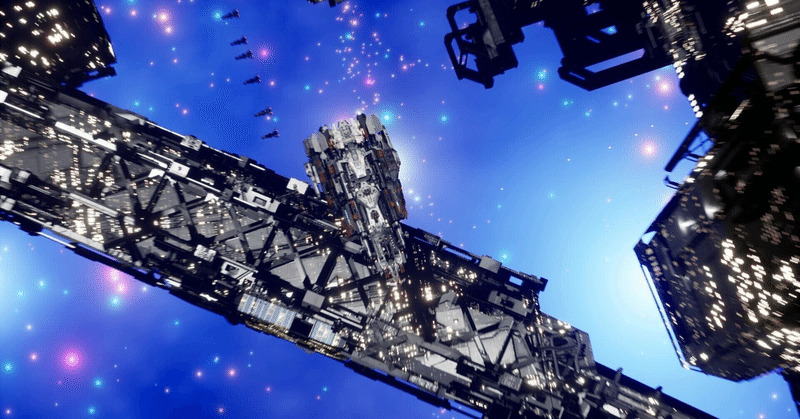
[個人史]中二病から始まる読書
『人生の土台となる読書』用に書いたけど使わなかった原稿です。僕の中二病の目覚めであった筒井康隆の話です。
思春期の頃というのは、もう子どもではなくなってきているけれど、まだ力もお金も自由もなくて大したことは何もできなくて、でもそんな中で何とかして自分を特別と思いたくて、変で異常な本や音楽を好んだりすることがある。俗に言う中二病というやつだ。
僕の中二病は筒井康隆から始まった(当時は中二病という言葉はなかったけれど)。
中学2年のときになんとなく図書館で借りて読んだ『虚航船団』という小説を読んで、度肝を抜かれたのがきっかけだった。
『虚航船団』はこんな文章から始まる。
まずコンパスが登場する。彼は気がくるっていた。針のつけ根がゆるんでいたので完全な円は描けなかったが自分ではそれを完全な円だと信じこんでいた。
「第一章 文房具」では文房具がたくさん登場するのだけど、全員気が狂っている。コンパスは自意識過剰で、ホチキスは誰彼構わず喧嘩を吹っかけ、消しゴムは自分のことを天皇だと思っている。気が狂った文房具たちは、宇宙船でクォールという星を目指している。その星の住民を皆殺しにしろという指令を受けているためだ。
「第二章 鼬族十種」では、クォール星の歴史が語られる。クォール星の住人はみんなイタチだ。この星の歴史は地球の歴史のパロディなのだけど、イタチというのは凶暴な生き物なので、地球のそれよりも少しずつ残虐さが増している。いわば、筒井康隆が悪意を持って描いた世界史になっている。
そして「第三章 神話」では、発狂した文房具たちと獰猛なイタチたちが、ひたすら凄惨な殺し合いを繰り広げるのだ。
全編、わけがわからなくて茫然とした。こんなに狂った読み物が世の中に存在するのか、と思った。そして、そんなにわけがわからないものが滅茶苦茶に面白い、ということに驚いた。
読み終えたあと、頭の中が真っ白になって、ひたすら床に横たわっていた感覚を今でも覚えている。これに比べたら学校とか社会とかどうでもいいな、と思った。
そこから筒井康隆ファンになって、当時出ていた本はほぼ全て読んだ。
(この記事でも筒井康隆の話をしています)
初期の筒井康隆の小説はとにかく不謹慎で刺激的だった。人が大量に殺されまくり、内臓や糞便があふれ、あらゆる権威や常識が笑いものにされていた。
後期になるとそうしたスラップスティックな面は落ち着いてきて、「文章に使える文字が一文字ずつ消えていく」(『残像に口紅を』)と言った実験的な作風が増えてくる。
どの作品も、自分の常識を打ち破るものばかりで、とびきり面白かった。溢れ出る奇想と不謹慎と毒、饒舌さと荒唐無稽さ、常識や良識を軽々と飛び越えていく想像力。
こんなにやばいものの面白さを理解できる中学生は僕くらいだろう、つまらない親や教師や同級生には理解できないものを自分は読んでいるのだ、と思った。
中学生の頃の僕は、友達もあまりいない暗い人間だった。そんな自分の「普通の人間でいたくない」という自意識を、筒井康隆を読むことで支えていたのだ。
あまりにも好き過ぎて、神戸にあるらしい筒井康隆の家を見に行ってみようか、と考えたりしていたくらいだ(本当に行かなくてよかった。迷惑過ぎる)。
大人になってからはそれほど熱心なファンではなくなったけれど、ときどき新作は読んでいる。
近年の作品では、2008年、74歳のときに発表された『ダンシング・ヴァニティ』が、最高傑作の一つなのではないかと思うくらいよかった。
『ダンシング・ヴァニティ』は、同じ文章が少しずつ細部を変えつつ繰り返されるという実験的な作品だ。その繰り返しが音楽のようでもありゲームのようでもあり、平行世界であり得た人生の可能性を示しているようでもある。
筒井康隆はものすごく実験的なことをたくさんやっているのに、それが面白く読めるエンターテインメントにもなっている、というところがすごいのだ。
* * * * *
ここから先は

曖昧日記(定期購読)
さまざまな雑記や未発表原稿などを、月4~5回くらい更新。購読すると過去の記事も基本的に全部読めます。phaの支援として購読してもらえたらう…
ꘐ
