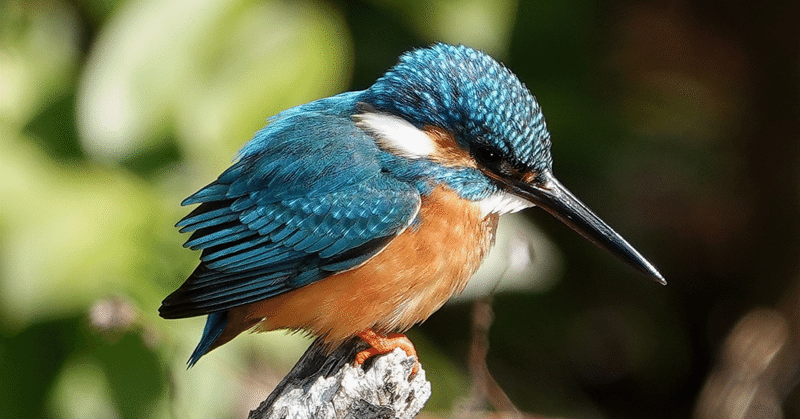
気まぐれな断想 #36
最近読んだ本がとても興味深かった。松村圭一郎著『はみだしの人類学 ともに生きる方法』(NHK出版, 2020年)という本で、著者は文化人類学者。心理臨床に携わる人であれば、いろいろなことを考えさせられ、連想する本だと思う。他の場所に、この本に関する個人的なコメントを書いたので、よかったらご覧ください。
さて今回は、最近のグループでの読書会に参加して考えたことを書き留めておきたい。この日取り上げられていたのは、前回のお題だったMaroda氏の論文に対するBuechler氏のコメント論文と、Dewald氏の公刊された著書の中の事例に対するHirsch氏のコメント論文。後者はシンポジウムの記録らしい。
この日この二つの論文が取り上げられたのは、いきがかり上たまたまだったのだが、両者に共通していたのは、セラピストの不可避的でパーソナルな関与というテーマであった。参加者が感想を述べ合う中で、ある参加者から、治療構造のことが思い浮かんだとの発言があった。治療構造は、まさにセラピストの不可避的でパーソナルな関与を遮断する(ことができる)という前提で設計、構想されているのではないかと改めて思った、治療構造の考えの対極にあるのがフィールドの考えではないか、というのがその主旨だったと記憶している。ここから先は、その発言に刺激を受けての、私の連想である。
確かに、治療構造論は、クライエントの“内的な”心の動きが、“他からの汚染を免れる”形で、“純粋に”セラピーの場に現れて展開することを目指すものだろう。そこに現れたクライエントの“問題”あるいは“歪み”をセラピストが見極めてそれを正しい姿に導く・・・というセラピー作用に関するイメージが、そこにはあると思われる。問題は、そのイメージがどの程度妥当なのかという点にある。
唐突に思われるかもしれないが、そこで私に浮かんでくるのは、“方言話者の語りを標準語話者が標準語の語りへと矯正しようとする”というイメージである。そのような場面では、方言よりも標準語の方が適切、あるいは優位であるという暗黙の(あるいはあからさまな)前提が働いているのではないだろうか。このイメージでは、方言話者が標準語話者から言葉を学ぶことは想定されても、標準語話者が方言話者から学ぶことは想定されないだろう。標準語話者は、方言話者の語りを標準語の語りに置き換える(あるいは枠づける)。ここで考えなければならないのは、翻訳可能性/不可能性の問題である。方言で語られる内容は、その内容やニュアンスを失わずに標準語に置き換えることが可能だろうか? 直観的な私の答えは、ノーである。
多様なニュアンスと歴史的な経験の積み重ねを含んだ方言の語りが、そのかなりの部分を犠牲にし、切り捨てる形で標準語の語りへと還元される。方言話者がそれまでの自分の語りを標準語で語り直すとき、そこで失われるものはどうなってしまうのだろうか。方言で語りうることと標準語で語りうることは決して完全には一致しないはずだ。
もちろん、上に述べた方言と標準語の関係の話は、クライエントとセラピストの関係を念頭に置いたものだ。つまり、治療構造論には、クライエントに固有の経験と言語を、セラピスト≒特定の心理療法理論の言語で語り直すことを目指すアジェンダが隠されてはいないかということを問いたいのである。私たちは、言語が持つ自他への支配力(政治的権力性)に対しても敏感であらねばならないのではないだろうか? なぜなら、心理臨床の仕事のかなりの部分が言葉を通じて営まれるのだから。
あるいは、現行の公認心理師制度=カリキュラムを推進する人たちは、まさにそのような権力性と恣意性を排除するためにエビデンスを重視すべきなのだと主張するかもしれない。しかし、もちろん、事柄はそのようには単純には切り離せない。なぜなら、エビデンスもまた言葉を通じて語られ伝えられるものであるからだ。「エビデンスは客観的な事実であり社会的権力性からは自由である」というような過度に素朴な言説は、かえって“客観的な事実”が社会で流通する中で帯びる権力性の問題を見えにくくするばかりであることに、私たちは気をつけねばならないだろう。
長くなってきたので、議論を省略するが、セラピストの不可避的でパーソナルな関与の問題に正面から取り組むことは、方言を標準語に置き換えるのではなく、方言を方言のままに、個人的なイディオムを個人的なイディオムのままに、自分の経験を語ることへと面接の場を開いていくことにつながることであるように、私には思われる。心理臨床の場が持ちうる可能性の極限の一つが、クライエントもセラピストも、それぞれに自分の個人的なイディオムを駆使しつつ、共にその場にいて、互いに相手のイディオムに触れつつ、相互にそれぞれのイディオムが届き得ない経験の可能性を見出していくことにあるように、私には思われる。
それは、本当に、個別的な、新しい何かを生む営みではないだろうか。心理臨床家の訓練は、心理学の主流の言語=標準語を学び、その使い手になり、方言を標準語へと組み込んでいくこと(それは常に方言=個人的なイディオムの消滅を目指すことになる)にあるのではない。クライエントとセラピストの関係が、一方的な権力性と恣意性に呑み込まれないように気をつけつつ、相互性のバランスを保つことに努め続けることができることを目指すためにあるのだと、私は思う。それこそが、人工知能技術に対するオルタナティブに足りうる、心理臨床の仕事のアートであると、私は信じている。
心理臨床におけるパーソナルな関与の軽視あるいは否定や排除(それは実際にはそこにあるものを見ないようにすることでしかないのだが)は、そこでの私たちの経験や、私たちが使う言葉や、私たちの間の関わりのあり方を、いわば「脱色化」することにつながる・・・という連想についても書くつもりだったけど、それはまた今度。(KT)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
