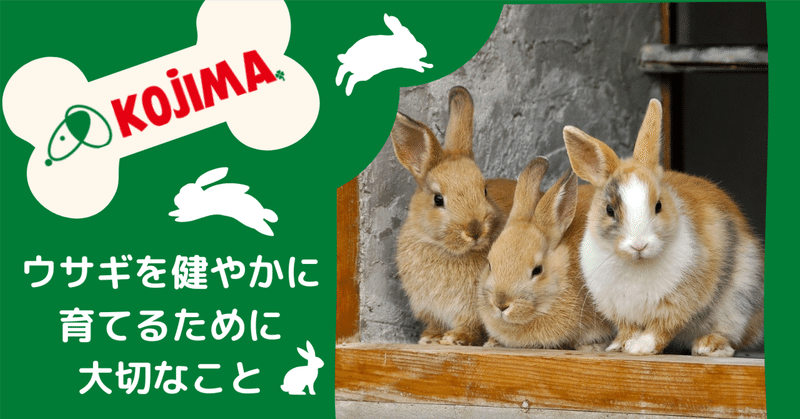
ウサギを健やかに育てるために大切なこと
ウサギと言えば、かわいらしい瞳やまるっとした体をイメージされる方も多いのではないでしょうか。実は、ウサギは多種多様で個性派揃い!
今回の記事では、ウサギの習性や育て方をはじめ、それぞれの種類の特徴や、気をつけたい病気の解説、おすすめのグッズなどをご紹介します。ウサギを飼いたいと考えている方はぜひご覧ください!
高い社会性をもつウサギの習性

ウサギは草食動物で、狩猟動物から身を守る術を身につけてきました。トレードマークの耳は小さな音を聞き分けるため。
キュートな瞳は、薄暗いときに動いているものを見分けるため。俊敏な脚は自分を襲うものから身を守るため。かわいらしさを感じる体のそれぞれが、弱肉強食を生き抜いてきた証です。
また、ウサギは草食動物らしく群れで生活する習性があります。特に野生のウサギは外敵から身を守るために周囲の状況や行動範囲を理解しながら、自分が過ごす場所を複数つくり使い分けてきました。
家の中で過ごすウサギにもこの習性が受け継がれており、室内で一緒に暮らす飼い主様の存在を常に意識しながら、ウサギは自分のスペースをつくります。用を足す場所を覚える個体も多いので、トイレのお世話が比較的しやすいペットと言えるでしょう。
グルメなペット? ウサギの味覚
味覚が人間よりも鋭いウサギは好き嫌いがはっきりしています。主食の牧草に加え、栄養補助食として適量のペレットフードを与えると、健やかな成長を促せるでしょう。
ペットの専門店コジマでは、ウサギが健やかに育つさまざまなフードを取り扱っています。
▼オリジンズ ラビットフード 1.5キロ
▼プレミアムラビットフード 1.5kg
お迎えに適したタイミングは? ウサギの成長スピード

ウサギをお迎えするベストなタイミングをはかるためには、成長スピードの把握が大切です。どんな生活をイメージしているかを踏まえて、考えてみましょう。
生後4週間~8週間頃
乳離れするタイミングで、この時期にはさまざまなことを覚えていきます。まだ幼い時期のため、基本的にはペット専門店やブリーダーのもとで管理をお願いするとよいでしょう。
生後3ヶ月~6ヶ月頃
ウサギにとって、この時期は思春期です。男の子と女の子の差がはっきりしたり、縄張り(行動範囲)を決めたりと、おとなへの成長を見せます。
生後6ヶ月~1年半頃
骨格ががっしりして体つきが立派になり、若いおとなのウサギへと成長する頃です。元気いっぱいで活発ではありますが、さまざまなことを吸収するこの時期はしつけやトレーニングに適していて、一緒に生活をスタートしやすい時期といえます。
生後2年~3年
精神的にかなり落ち着き生活パターンも固まってくるこの頃は、トレーニングも効果を発揮する時期です。飼育するウサギの性格や表情の理解が進み、楽しい時間を共有できる存在へと成長します。
ウサギを迎えるための心構え

ウサギは我慢強い動物で、表情が大きく変わらないと思われるかもしれませんが、実は感情豊かな動物なんです。ワンちゃんやネコちゃんと比べて、飼い主様に馴れるまで時間がかかるかもしれませんがご安心を。
安心・安全な環境をつくり、ウサギと暮らす中で少しずつ表情がわかるようになると、感情が見えて来るようになるでしょう。愛情を重ねていくことで、信頼し合える関係が生まれていきます。
ウサギを迎えた初日に気をつけること

かわいいウサギをお迎えした初日には、嬉しさのあまりついつい触れ合ってたくさん遊びたくなると思います。しかし、そこには気をつけてほしいポイントも。末永く幸せに暮らしていくためにも、以下でご紹介することにお気をつけください。
お風呂はNG
ウサギは自分で毛づくろいして体を清潔に保ちます。そのため、お風呂に入る必要がありません。ウサギは体温調節が苦手で、被毛がびっしりと生えているため、乾かすには時間がかかります。体を濡らすことはストレスになるので避けましょう。
【においが気になる際には】
においが気になる2つの要因としてはケージ内などにある排泄物や、あごの下や肛門付近にある臭腺に汚れがたまっていることが考えられます。
排泄物についてはケージやトイレを清掃し、臭腺が汚れている場合には綿棒やガーゼなどで優しくふきとりましょう。汚れが強い場合は無理にふきとらず、動物病院でケアしてもらうのがおすすめです。
▼うさぎの足裏清潔マット
コミュニケーションにご注意を
ウサギは新しい環境に慣れるまでに時間がかかります。そして、体の大きな人間の存在はストレスになりがちです。最初は静かに見守るようにして、下記のようなことは避けましょう。
・迎えた当初から長時間見つめ続ける
・むやみに触れ合おうとする
・ケージの外で遊ぶ
ウサギを迎えた初日は十分な量の牧草と水を用意したケージでそっとしておき、気になるときには距離を保ち短時間で様子を見るようにしましょう。
▼イージーホーム・ネクスト 70-SCA
ウサギの飼育時に気をつけたいポイント

お迎えしたウサギが健やかでいられるようには、瞳の輝きや毛づやの変化など、ウサギの様子を定期的にチェックして「健康なウサギの状態」をしっかりと覚えておきましょう。
ウサギは我慢強いため、体調の変化に気づきづらい一面があります。健康な状態の姿をイメージできれば、ささいな変化を見逃すことなくウサギの健康を守れます。
ケージはこまめに清掃
ウサギはきれい好きで、ケージ内が汚れているとストレスを溜めがちです。清掃して清潔な状態をキープしましょう。
食物繊維の多いフードを
ウサギのフードは、食物繊維を多く含むものがおすすめです。排泄を促すことで、毛球症対策に効果的です。
丁寧にブラッシング
毛球症を防ぐためには、定期的に丁寧なブラッシングが欠かせません。こまめにお手入れしましょう。
爪切りは1~2ヶ月に1回
爪切りはウサギを抱えられるようになってからはじめます。もし暴れてしまうようなら無理をせず、動物病院や専門店でお願いすると良いでしょう。
少しの運動を
ウサギの運動量は控えめにすることがポイントです。ワンちゃんのように散歩などに連れていく必要はありません。1日1回30分~1時間は部屋に出して遊ぶようにしましょう。
ウサギの健康をチェックするポイント

ウサギは草食動物で、生態系の中では比較的弱い立場です。そのため、体調が優れなくても元気なように振る舞う習性があります。いつもの状態と違うかを細かく気にするようにしましょう。
ウサギは体調を崩しやすく、状態が急変することもあります。もし、何らかの違和感を感じた際には、お近くの動物病院でご相談ください。(ウサギを診察できない動物病院も多いため予めウサギを診ることができる病院をさがしておいてあげてください)
排泄物の状態
排泄は健康の状態を知らせるサインです。大きさや色が変化していないか確認しましょう。変化を把握するために、トイレシーツの色は白・トイレに使う砂は明るい色を選ぶことがポイントです。
▼うさぎの三角トイレ アイボリー
▼Zero ウサギ、小動物、小鳥用トイレ消臭粒 650g
お尻の汚れ
下痢は病気のサインです。場合によっては大きな病気にかかっている可能性もあるため、ウサギのお尻が汚れている場合は、速やかに動物病院で治療をお願いしましょう。
食欲があり、下痢ではないにも関わらずお尻が汚れている場合は肥満の影響も考えられます。毛についたままだと落ちづらくなるため、きれいな状態を保てるようにケアしましょう。
体重が増えている
肥満はさまざまな病気の原因となるほか、体重がかかりやすい踵や脚の裏の毛が薄くなることで皮膚病を引き起こす場合もあります。ペレットフードやおやつは一日の量を調整するなど、少しずつダイエットさせましょう。
体を触ってみる
ウサギは年4回換毛期があり、春と秋には大きく毛が生え変わります。毛は地肌に近いアンダーコート、体の色を表す少し長いガードヘアの二重構造です。毛量が多いウサギは、換毛期にしっかりとグルーミングしてあげるとよいでしょう。
グルーミングの際にウサギの体を触ってみると、小さな傷や膿のたまった膿瘍が見つかることがあります。ウサギは脱毛やソアホック(足の裏の毛が抜け落ち炎症を起こす)などの皮膚病にかかりやすく、早い段階で治療できれば治りも早くなるので、こまめにチェックしてみてください。
▼ウサギのナデナデブラシ
ウサギがかかりやすい病気

ウサギと信頼関係を築いていくと、体調の変化を示すわずかなサインに気づきやすくなります。正しい対応をとるためにも、ウサギがかかりやすい病気を把握してもしものときに備えましょう。
食滞
ウサギは常に食べている動物です。長い時間食欲がなく、排泄がみられないときには食滞となっているかもしれません。腸内では微生物が食べ物の消化を助けていて、何らかの影響で腸内バランスが崩れると異常発酵を起こしガスがお腹にたまっていきます。
食餌がうまくいっていない、異物の誤飲、口腔内のトラブル、消化器官への感染、ストレスなどが原因となる食滞は、早い段階で内科治療をはじめることが大切です。半日排泄がない、食欲不振がみられる場合は速やかに動物病院を受診しましょう。
不正咬合
草を主食とするウサギの歯は一生伸び続けます。牧草中心の食生活ならば自然と歯がすり減っていくのですが、野菜やペレット中心の食生活をしているウサギは歯のかみ合わせが悪くなりやすいと言われています。
歯が伸びてしまうと化膿して炎症を起こしやすくなるため、食生活には気をつけたいところです。
口元から長い歯が伸びている、よだれを流している、食べ物を残すようになったと変化が見られたら、動物病院の受診をおすすめします。
▼ウサギのカリカリキャロット 毛球ケア 50g
発作(眼振・斜頸)
目が小刻みに左右や上下に動く眼振は、内耳や脳にある種の菌が入り込み異常を起こすことが原因と考えられます。眼振は、首が斜めに傾く斜頸を起こしたときに併発しやすく、この状態になると同じ場所をぐるぐると回るようになります(ローリング)。
慌てずに落ち着いて声をかけ、しっかりと抱きかかえて安全を確保しましょう。抗生物質などの薬を投与する必要があるので、速やかに動物病院を受診してください。
また、眼振はウサギの風邪とも呼ばれるスナッフル(鼻炎や肺炎に進行する伝染性呼吸器疾患の総称)が進行する際に見られることもあります。
骨折
ウサギの骨はとても軽く、そのため骨折を起こしやすい動物です。自ら勢いよくジャンプした際に骨折してしまうことも珍しくありません。扉に足を挟まない、無理な抱きかかえないなどの配慮も必要です。
テーブルなど高所から落下した際に足が突っ張っていたり、眼振を起こしている場合は頭や首を無理に動かさないようにして、獣医師に診てもらいましょう。
角膜炎
特徴的な目をしているウサギは、目が顔の横にあり傷がつきやすい形をしています。食事の際に牧草が目に触れたり、ホコリのような小さなごみが目が入ったり、毛づくろいの際に爪があたったりと、何らかの原因で傷がつくと角膜炎を発症します。
ウサギがまぶしそうにしている、涙があふれているなど、ウサギが目を気にする様子が見られたら角膜炎のサインかもしれません。もし悪化してしまうと視力に影響するため、早めに受診しましょう。
熱中症
この夏に特に注意したい症状です。ウサギは暑さに弱く、快適に過ごせる室温は20~25℃・湿度は40~60%が目安とされています。室温が28℃を超えると熱中症にかかるリスクが高まるため、エアコンなどを利用してしっかりと室温を管理しましょう。ケージに直射日光が当たらないようにすることもポイントです。また、車中での放置は避けてください。
暑さを感じたウサギは体を伸ばして横になり、呼吸を早くして熱を逃そうとします。体温が上昇し続けると、耳が充血し赤くなり大量のよだれが出ます。
もし熱中症の症状が見られたら、まずは濡れタオルで体を冷やします。その際には急激な体温低下を避けるため、あまりに冷たい水や氷は使わないようにしましょう。水が飲めるなら、新鮮な水を十分に飲ませます。その後は、早急に動物病院を受診してください。
コジマ公式HPでは、この他にもウサギに多い病気をご紹介していますので、ぜひご覧ください。
まとめ

草食動物のウサギは、体調の変化をあまり見せない習性があり、最初から親密にコミュニケーションを取ろうとせず、少しずつ距離を縮めながら信頼関係を築いていくように心がけましょう。
また、長い毛や歯、軽い骨などなど、体の特徴からかかりやすい病気もあるのでご注意を!かわいらしいウサギは魅力がいっぱい。楽しく心地よい時間を長く過ごしていけるように、大切に育てましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
