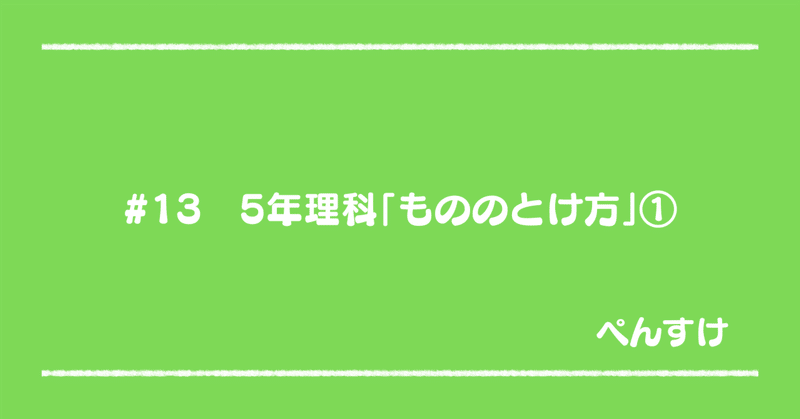
#13 5年理科「もののとけ方」①
3学期が始まり、1週間がたちました。
みなさん1週目お疲れ様でした。
冬休みが明けて、なんだかどっと疲れたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
さて、僕自身もいよいよ授業が始まってきています。
取り組んでいることをアウトプットすることで、誰かの役に立ったら嬉しいです。
5年生は「もののとけ方」という単元に入りました。
授業の最初に実験を見せました。
長い透明の筒を用意します。
片方に栓をして、その筒へ水を入れます。
この筒の真ん中の部分を見えないように隠してしまいます。
(筒の上の方15%くらいと下の方15%くらいは隠さず見えている。)
そしたら子どもたちに問いかけます。
「今からこの筒に食塩をパラパラと入れます。下の見えている部分はどうなると思いますか?」
子どもたちの予想は「食塩が積もっていく」と「食塩はとけるから変化しない」にわかれました。
実際に上から食塩を入れてみると…
食塩はパラパラとしずんでいき、隠された部分へと入ります。
子どもたちはしばらくじっと筒の下の部分を見つめていますが、食塩は現れません。
もう一度やってみても、結果は同じです。
途中でとけてるんじゃないか?となるので、そこで隠していたものを外し、もう一度食塩を入れてみます。
すると食塩がしずんでいきながらとけていく様子を観察することができます。
最初から普通に見せることもできますが、あえて隠しておいたことにより、その部分を観察したい!という熱量が少し上がっていたように感じます。
「負けるな!がんばれ!」と食塩がとけないように応援しているクラスもありました。笑
注意点として、同じ子ばかりが近くで観察しないように、見たら入れ替わるように声をかけていく必要があるかと思います。
何度か繰り返して、全員が観察できたらそこで終了です。
そのあとまた問いかけます。
「とけるとはどういうことでしょうか?」
子どもたちは「消えること」「なくなること」「見えなくなること」などの意見が出ます。
これらは同じような言葉ですが、微妙に意味が違います。
このあと、とけたものの質量の実験があるので、この問いかけがそのときにつながっていったらいいなと思います。
ということで、今回は「もののとけ方」の単元で最初にやった実験について紹介しました。
この実践、本で読んだのか、どこかで教えてもらったのか…
先行のものがあったと思うのですが、覚えていなくてすみません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
