
「ブランドよ、義憤に駆られ立ち上がれ」 FRACTA河野貴伸氏がポスト・コロナショックを語る 【PENCIL&PAPER Mag】
今年に入り、新型コロナウイルスが世界中をかつてない危機に陥れている。
もはや説明するまでもないかもしれないが、短期的に見れば多くの人の命をおびやかす存在であり、中長期的に見れば経済にもはかりしれない影響をおよぼすだろう。
そうした中、ある経営者は「ウイルスの蔓延が、社会の分断をよりはっきりと可視化させた」と話す。土屋鞄製造所を筆頭に、テクノロジーとデザインで日本のD2Cブランドを支援するFRACTA(フラクタ)の河野貴伸氏だ。
社会の分断、と聞くと大げさな響きを帯びる。
特に日本では、それほど意識することがない現象かもしれない。──ではこの「社会の分断」が、私たちにとって、またビジネスにとってどのような意味を持つのだろうか。
河野氏には当初、D2Cが脚光を浴びる現在におけるブランドのあり方を聞く場としてインタビューを行った。しかしこの時世もあり、話が必然的に“ポスト・コロナショック”にも及んだことから、冒頭に挙げた「社会の分断」というテーマを絡めて「ブランドのこれから」について河野氏の言葉を紹介していく。
河野貴伸氏 略歴:
大学在学中、CGや音楽制作に興味を持ったことをきっかけにwindow機を自分で組み、中古のMacを探すところからクリエイティブの道を歩み始める。
個人としてビジネスを拡大させる中、チームで仕事がしたい一心から仲間を集め、FRACTAを設立。会社は15年で50名規模に成長し、スタート時の2名のメンバーは今も活躍中。
当初の中核事業であったECサイト構築が発展し、現在はブランディング施策や社員教育など、経営に限りなく近いレイヤーでD2Cブランドを総合的に支援している。
ブランドは「実装するもの」
──河野さんにとって、ブランディングとは?
web業界に携わって20年以上になりますが、大局として最近のトレンドを見ているとKGI、KPIによる成果マネジメントが一般的になったことで、より短期間に、より高い目標達成率をめざすことが重視されすぎているように思います。
FRACTAは在庫を抱えてビジネスをするブランドの支援をしているので、売上は当然大事。しかし、行き過ぎるとバランスを崩してしまいます。
少し極端ですが、この状況はスポーツでいえばドーピングにたとえられます。一時的に力を発揮して、効果を持続させるには同じこと続けなければならない。また、いずれしわ寄せがくるという点も似ています。
一方で私たちが考えるブランディングは、いわば体幹トレーニングです。イチローや長友佑都が取り入れたことで有名ですが、身体の軸を捉える感覚を身につけ、あらゆる動作を強く、速く、しなやかにする効果があります。ただトレーニング自体は地味なものも多く、単に筋肉を大きくするだけではないので時間もかかります。
ブランディングもこれに似ています。
地味ですが、続けることで体幹トレーニングと同じようにブランドの軸を強固にして、とるべきアクションにより一貫性を持たせ、洗練させる可能性を秘めています。だからこそ、ブランドが長期的に繁栄するためには欠かせないことだと思っています。
──具体的にはどういった施策を行うのか?
たとえばブランドの“聖典”をつくることが一つです。
憲法やルールブックと言い換えてもいいですが、そのブランドが「なぜ存在し、どんな価値を提供するのか」を定義し、社内の誰もが参照できる形にまとめることです。
ただし、それをつくっただけでは「この資料になぜこれだけのお金がかかるの?」という話になります。
そのため、FRACTAでは「implementation」(インプリメンテーション、英語で「実装」)と呼んでいるプロセスを必ずセットにしています。“聖典”をつくる途中や最後にワークショップなどを行い、ブランドにかかわる一人ひとりが「ブランドの体現者」あるいは「宣教師」として行動できるようにマインドセットを共有していく作業です。
たとえば実店舗をもつブランドの場合、販売スタッフの振る舞いや商品のディスプレイの仕方まで、あらゆるところにそのブランドのDNAが流れるようになることがゴールです。そこまでできて、初めてこの聖典が価値になるのです。
──ブランディング支援に携わるメンバーのバックグラウンドは?
学術的なマーケティングを理解したメンバーはもちろん、現場でのグロースハックに長けたメンバーも抱えているので、そのバランスをとった提案をしています。ほかにも商品配送のパッケージやwebをデザインするデザイナーやフォトグラファー、Shopify(ECプラットフォーム)のカスタマイズができるエンジニアなどが在籍しています。
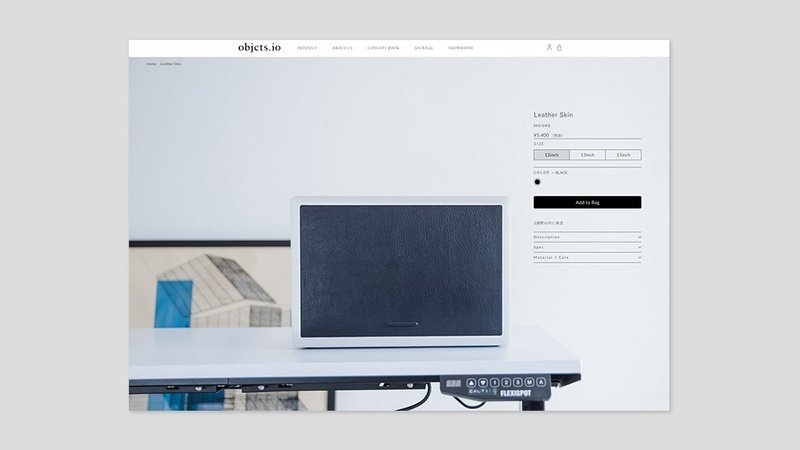

経営者として2020年をどう読み解くか
──EC事業からD2Cにシフトしたのは自然な流れだった?
もちろん中核はECサイト構築支援だったのですが、ほかの事業に注力した時期もあります。
少し抽象的な話になりますが、経営はある種ギャンブルの要素があります。
平時はポーカーのような感覚で、巡ってくるカードは運次第ですが読み合いもできますし、勝てないと思えば勝負をおりて損失を最小限にできます。1回の勝負ではなく、トータルで見れば勝ちやすいともいえます。
ですが、まさに今のような非常時は、たとえるならばルーレットです。
“神のみが回すことができるルーレット”が目の前にあり、いつどこに止まるかわからない。そんな状況で、賭ける人もいれば傍観している人もいるのが今です。
自分の話をすると、こうした非常時に遭遇した時は常に“張って”いて、1勝1敗です。
リーマンショックのときは時流を読むことができましたが、その後に東日本大震災が起きた当時は、デジタルサイネージに注力していたところで節電ムードが高まり、社会の風潮に逆行しました。
今回はというと、早ければあと数か月でルーレットの回転が止まります。その時に、D2Cが当初の想像よりも早く光を浴びると考えています。後で詳しく話しますが、「破壊と再構築」がその鍵になるはずです。
今の状況ではできるだけ多くの命を守る行動が最優先なものの、政府の経済支援に注目が集まっているように、どうビジネスを立て直すかも重要です。
その視点では、傍観していれば失うものがない一方、得るものがないことも忘れてはいけません。
一人の経営者として考えると、そもそも失うとは何でしょうか。
一つの答えはビジネスが立ち行かなくなることですが、それは死ぬこととイコールではありません。最悪のケースを考えれば一時的に仕事や収入、社会的信用を失う不安もありますが、周囲に必ず助けてくれる人がいます。何より、またチャレンジできます。
どう転ぶかわからないルーレットはもう、既に回っています。
「何かを成し遂げたい」と思う人はむしろ張らないことによる後悔もあるだろうし、自分が変化や行動を起こさなくても世界が急変すれば取り残される可能性もある。その意味で経営者としてはリスクを把握した上で、それを背負ってでも次に備えて動くべきタイミングだと思っています。

ブランドよ、義憤に駆られ立ち上がれ
──コロナウイルスによる世界的危機が訪れる中、ブランドは何を考え、どう行動すべきか?
ウイルスがここまで危機的状況をもたらしたのは、人類最初のパンデミックといわれるスペインかぜ以来ではないでしょうか。このときも莫大な死者が出ましたが、現在は飛行機やインターネットが地球を1つにしたことで、新たな被害を生み出しています。
それが「社会の分断」です。
世代、地域、(ウイルス保有・非保有という意味での)個人。日本国内だけ見ても、この3つのレイヤーで分断が起こり始めているのはみなさんも感じていると思います。
最近も南アフリカで外出禁止令に違反した市民が警察に射殺され、周囲にいた子ども3人も巻き込まれた事件が起こりました。日本でも咳をするだけで周囲の人に避けられたり、自称“コロナ感染者”が逮捕されたりしています。
このような感情が発端になった分断に加えて、都市の封鎖、渡航禁止など、物理的な分断も起きています。
グローバリゼーションという、政府や国家が主導した「統合」のあとにきた、コロナウイルスによる「分断」。歴史の転換点なのは間違いありません。
物理学になぞらえれば「揺り戻し」、哲学でいえば「螺旋的な発展」が必ずまた起きるはずで、もしそうだとしたらどのように「再統合」が行われるかがポイントです。
そして私は、その再統合の拠り所が今度は政府や国家ではなく、思想になると思っています。
人と人、あるいは人とブランド。
どちらも地域や世代、文化や言語といった垣根を越えて、思想という“赤い糸”があれば自由につながることができる時代です。発祥の地を問わず、良いものをきちんと届けることで世界中で評価されたプロダクトやサービスはたくさんあります。
だからこそ、国境のような従来のボーダーラインはそれほど関係ありません。ブランドはそのことを理解して、世界に向けて思想を発信し、新しい発展の可能性を探っていくべきです。
最近話題になった話でいえば、LVMHが香水とコスメの工場でアルコール消毒液を生産したり、アウディやコカ・コーラがロゴを変えたりしたことがニュースになりましたが、それも思想の一つの表現方法です。
こうしたブランドは、自分たちの規模でしかできないことが何かを理解したうえで、具体的な行動と共に社会にメッセージを発信しています。これらの活動はもはや、利益を上げるためのビジネスではなく、思想の啓蒙です。
彼らは、社会に対する「義憤」に駆られたのではないかと思います。それを消毒液やロゴといった形で社会に表明することは、ブランドの“聖典”を非常に高いレベルで体現した、矜持だともいえます。
そうした中で日本でのブランドのコミュニケーションを見ると、とかく炎上や物議をかもすことを避ける風潮があります。もちろん公序良俗に反すること、ダイバーシティの時代に合わない倫理感はNGですが、それ以外のことであれば当たり障りのないメッセージよりも「届く人に届くメッセージ」を優先させるべきだと感じています。
反対者がいるからこそ、共感者がいる。100人、1000人の局所的なファンを生み、それを世界でいくつ増やせるか。こうした発想は思想でつながる時代だからできることです。
だからこそ、ブランドとしてどのような思想を持ち、どのように表現するか、その哲学が“ポスト・コロナショック”の時代で問われていくことになるはずです。
取材・文:小野祐紀 写真:花沢菜摘、小中七瀬
PENCIL&PAPER Mag 過去の連載記事:
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
