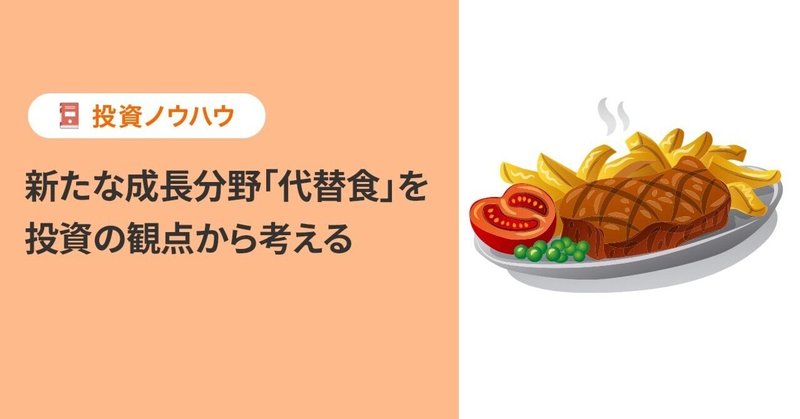
新たな成長分野「代替食」を投資の観点から考える【投資ノウハウ】
食用コオロギなどの昆虫食や、大豆などで作られた植物由来肉など、代替食と呼ばれるものが身近になりつつあります。
今回は、代替食の中でも代替タンパクについて、PayPay証券noteでお馴染みの、佐藤隆司氏に教えていただきました。
国際連合(国連)の発表によると、2021年の世界の人口は前年比8000万人増の78億7500万人でした。今後も人口増加は続き、2030年までに世界の人口は85億人に達し、2050年には97億人に増加すると予想されています。
人口の増加に伴い懸念されているのが、食料不足です。農林水産省がまとめた「2050年における世界の食料需給見通し」によると、2050年の世界の食料需要量は2010年比1.7倍の約58億トンとなっています。人口増加を上回るペースで食料需要は拡大しています。気象変動や災害、戦争など予想が付かない状況が続くなか、拡大する食料需要を賄えるのか危惧されています。
そんな中、解決策の一つとして注目されているのが代替食です。代替食は、2015年、国連によるSDGs(持続可能な開発目標)が採択されてから、環境問題や動物福祉の観点からも注目されています。
今回は、代替食の中でも、特に牛肉や豚肉の替わりとなる代替タンパクについて見ていきましょう。
植物由来肉

現時点で、代替タンパクの代表格と言えば、植物由来肉です。
植物由来肉は、主に大豆やエンドウ豆などの植物を原料として作られています。すでに流通しており、特に今年は、年初に米国で、マクドナルドがハンバーガー、ケンタッキー・フライド・チキンはナゲットを、それぞれがビヨンド ミート(BYND)と共同開発した商品の大規模な試験販売を行い話題になりました。一部報道では、マクドナルドの植物由来肉で作ったハンバーガーは、当初予定の3倍売れたそうです。味や食感が食肉に近づいているとのことです。
日本でも、最近は、ファストフード店で植物由来の人工肉がパテに使われたハンバーガーが販売されるなど、植物由来肉が私たちの生活に身近になっています。シード・プランニングによれば、世界の植物由来代替肉の市場規模は2020年に110億ドル(約1兆4873億円)でしたが、2030年には886億ドル(約11兆9796億円)にまで成長が予想されるそうです。
昆虫食

昆虫食も代替タンパクとして注目されています。日本の一部の地域では、昔から「イナゴの佃煮」など昆虫を重要なタンパク源として食してきましたが、アジア、アフリカ、アメリカ大陸など、多くの地域で昆虫食の習慣はあります。
ただ、特に注目され始めたのは、2013年に国連食糧農業機関(FAO)が、環境への負荷が少なく、栄養豊富なコオロギを食用に推奨する報告書を発表したからです。同報告書によると、コオロギは、家畜に比べ、生育する際に排出する温室効果ガス、水やエサの量が圧倒的に少なく、環境への負荷が軽減されるそうです。
食べ方としては、昆虫を食べるという習慣がない国や地域も多いことから、パウダー状にして練り込むケースが多いようです。日本でも、良品計画(7453)がコオロギせんべい、コオロギチョコを販売し、人気を博しています。
培養肉

この他にも、将来的には培養肉も代替タンパクとなる可能性があります。培養肉とは、動物や魚からとった筋肉の細胞を栄養成分の入った液を使い培養して作る肉です。今年3月に東京大学と日清食品ホールディングス(2897)などの研究グループが国内では初めて、実際に食べることが出来る培養肉を作り出し話題になりました。
培養肉は、大量生産ができれば、家畜を育てるための飼料や、家畜が出す温室効果ガスの問題をクリアできることから、代替食としての期待が高いです。ただ、2013年に英国で培養肉を用いたハンバーガーの試食会が開催された際、140グラムのパテの製造に25万ユーロ(約3565万円)以上の費用が掛かったとされており、コスト面での問題解決が急がれます。
完全食

最後に代替食とは違いますが、フードロスや栄養の観点から注目されているのが完全食です。完全食は、そのひとつの食べ物で健康を保つために必要とする栄養素をすべて摂取できる食品です。最近は、コンビニでパン、麺類、ドリンクとして販売されていることも多くあり、見かけた方も多いと思います。
株式会社グローバルインフォメーションによると、完全栄養食品の市場規模は、2021年~2027年の間に年平均成長率で6.5%成長し、2027年には63億米ドルに達すると予測されています。日本では、日清食品ホールディングス(2897)が開発に力を注いでおり、同社HPによると、現在、約300のメニューを開発中だそうです。
代替食の世界は、まだ黎明期かもしれません。この分野への投資は、IT企業への投資などと違い、すぐに結果がでるものではないかもしれません。ただ、株式投資の本質が「将来価値」の上昇しそうなもの、つまり成長が期待されるものに、自分の資金を投じる行為と考えると、一考の価値がある分野と言えそうです。
記事作成:2022年6月26日
本資料のご利用にあたり、お客様にご確認いただきたい事項を、以下に記載いたしました。
ライター:佐藤 隆司(プロフィールはこちら)



《ライターによる宣言》
私、佐藤隆司は本調査資料に表明された見解が、対象企業と証券に対する私個人の見解を正確に反映していることをここに表明します。
また、私は本調査資料で特定の見解を表明することに対する直接的または間接的な報酬は、過去、現在共に得ておらず、将来においても得ないことを証明します。
《利益相反に関する開示事項》
●エイチスクエア株式会社は、PayPay証券株式会社との契約に基づき、PayPay証券株式会社への資料提供を一定期間、継続的に行うことに対し包括的な対価をPayPay証券株式会社から得ておりますが、本資料に対して個別に対価を得ているものではありません。
また、銘柄選定もエイチスクエア株式会社独自の判断で行っており、PayPay証券株式会社を含む第三者からの銘柄の指定は一切受けておりません。
●執筆担当者、エイチスクエア株式会社と本資料の対象企業との間には、重大な利益相反の関係はありません。
金融商品取引法に基づく表示事項
●本資料をお客様にご提供する金融商品取引業者名等
商号等:PayPay証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2883号
加入協会:日本証券業協会
指定紛争解決機関:特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
●リスク・手数料相当額等について
証券取引は、株価(価格)の変動等、為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化や、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために元本損失が生じることがあります。
お取引にあたっては、「契約締結前交付書面」等を必ずご覧いただき、「リスク・手数料相当額等(https://www.paypay-sec.co.jp/service/cost/cost.html)」について内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお取引ください。
免責事項等
●本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的とし、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定はお客様ご自身の判断で行ってください。
●本資料は、信頼できると考えられる情報源に基づいて作成されたものですが、基にした情報や見解の正確性、完全性、適時性などを保証するものではありません。本資料に記載された内容は、資料作成日におけるものであり、予告なく変更する場合があります。
●本資料に基づき行った投資の結果、何らかの損害が発生した場合でも、理由の如何を問わず、PayPay証券株式会社及びエイチスクエア株式会社は一切の責任を負いません。
●電子的または機械的な方法、目的の如何を問わず、無断で本資料の一部または全部の複製、転載、転送等は行わないでください。
PayPay証券株式会社
https://www.paypay-sec.co.jp/
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2883号
