
色彩力向上講座(3)色彩認知力
研究員のみなさんの基礎色彩能力「色彩力」をあげる色彩力向上講座。5つある能力のうち「色彩認知力」の向上を目指していきます。
[目次]
1. 色の認知力を把握する
2. 色の認知テスト
・色彩認知テスト
・明度認知テスト
・彩度認知テスト
3.色彩認知能力を高める方法
※「3. 色彩認知能力を高める方法」更新。最終更新日2020年4月5日
1. 色の認知力を把握する
○人は視覚優先の判断をする
私たちは様々なものを判断するときに触覚、視覚、聴覚、嗅覚、味覚などの感覚を駆使して判断しています。その中で最も重要な感覚は視覚です。ある研究では五感の働きとして視覚は87%、聴覚は7%、触覚は3%、嗅覚は2%、味覚は1%と言われています。この感覚は対象物でも変化し、ひとつのみが機能するのではなく、複雑に複合して判断していると考えられています。

図にするとわかりやすくなると思います。この数値は実験や対象物でも変化すると考えられますから、覚える必要はありません。「人は圧倒的に視覚優先で判断している」という状況がわかっていれば問題ありません。ところが聴覚が優位に働く人もいます。言葉の意味を理解しやすく、映像化は得意ではない。言語を通してものを理解しようとする人です。サルを絵を書こうとするとサルの映像ではなく、「サルがバナナを食べる」「サルが温泉に入る」という言葉が出てきます。言葉をうまく映像に変換できない人もいます。こうした個人差、特性の差があることを理解しましょう。
○色型人間と形型人間
みなさんは服や傘などの製品を買うときに機能が同じならば、デザインの何を気にして購入するでしょうか? 色でしょうか、形でしょうか?
当然、ものによって色だったり形だったりすると思います。普通は色と形を複合して決めいてると思いますが、人には色に影響を受けやすい色型人間と形に影響を受けやすい形型人間の人がいます。
ここから先は
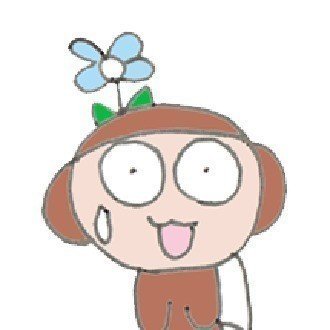
ポーポー色彩研究会
「色を使って問題解決しよう」「色の可能性を広げていこう」をテーマにした色彩心理の研究会です。 マガジンを購読いただくと色彩心理関係のセミ…
いつも応援ありがとうございます。 みなさまからいただいたサポートは研究や調査、そしてコンテンツ開発に活かしていきます。 ミホンザルにはバナナになります。
