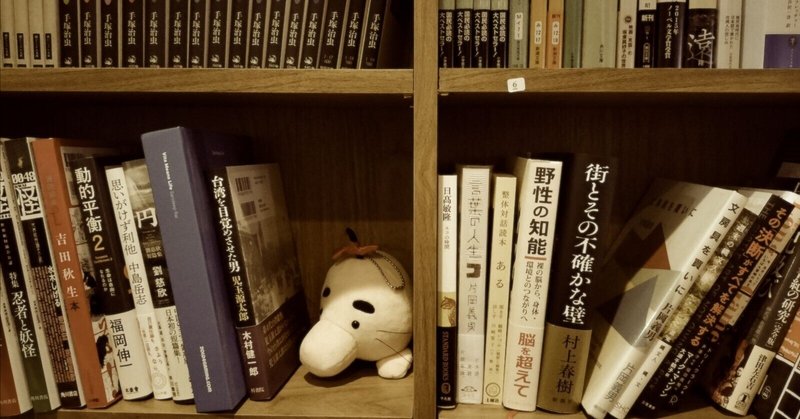
[読書感想文] 時計じかけのオレンジ
ボルシービズムニーマルチックがドルーグたちとベックのガリバーやリッツォをトルチョクしてクロビーまみれにさせたりする小説。
たぶん一回読んだことあるけど、まるで覚えてなかったのでたまにデジャヴ的な「ん?ここ読んだことあるような…」を感じながらもそこそこ面白く読んだ。トルチョックという単語、なんかのマンガとかで見た覚えがあるような… 調べてもわからなかった。
序盤は毎回ルビが振ってある謎の用語が頻発するのに首を傾げるのだが、途中からなんかそういう世界なんだなと気にならなくなってくる。でも途中までは直訳感もある、変わった翻訳だなぁと思ってはいた。
前半はアレックスと仲間たちが暴れまわり、暴力描写がかなりきっつい。酒飲んだり、不良のライバルとケンカしたりするのはともかく、老学者をボコって貴重な本をバラバラにしたり、かなり若い女の子を拐かしたり、しまいには猫好きのおばあさんの家に強盗に入って過失致死して捕まる羽目に。この時点で15歳なんだから全く救えない。
後半はアレックスが刑務所にぶちこまれるものの、悪さをしていたとき同様、ちょっと頭のいい感じに上手く振る舞って司祭を手伝う模範囚になっていたところ、新入りに挑発されて暴力を振るって殺してしまうという、捕まったときと全く同じことをしている。
刑務所内でも殺人をしてしまう15歳という、だいぶどうしようもないガキということで、ちょうどルドビコ法という矯正法を試したがっていた内務大臣に選ばれて治療をされていく。ここの描写もなかなかきっつく、暴力映画というよりももはやスナッフムービーや戦争犯罪の動画を、目を無理やり開けさせられてずっと見るというもの。次第に暴力を見るだけで頭痛がしてきて、自分でも暴力を考えると拒否反応が出るため、なにか優しいことを考えないといけないという思考矯正状態になる。しかも、映画と一緒にアレックスがもともと好きだったクラシック音楽をかけていたため、音楽にも拒否反応が出るように。
実際、研究員に「ほれ、殴ってみろよ」と挑発されても、これまでのアレックスだとブリトバでズバッとやりそうなところなのに「あなたのためになりそうなことをさせてください」とか言ってしまうように。
矯正されたあとに無事社会復帰するものの、家に帰ると知らないおっさんが両親の新しい息子みたいになってて、うろついているところに以前のアレックスを知っている人々や被害者たちに馬鹿にされボコボコにされたりして、最終的に以前押し込み強盗をした「時計じかけのオレンジ」を書いてた小説家の家にまたたどり着き、優しく手当をされる。
で、小説家は反政府マインドも持っていたらしく、アレックスの矯正のニュースを見てこんな政府はいかんよと、反政府仲間と共にアレックスを担ぎ出そうとする。
が、暴力性はなくなったものの、使う言葉がまだナッドサット語なので、それに何かを感じ取ったらしい小説家が平静を失いかけていてやばい。仲間たちはそれに薄々気づいていたので、とりあえずアレックスを隔離するが、隣の部屋でクラシックをかけてアレックスに嫌がらせをし、全てから逃げたくなったアレックスが飛び降り自殺を図る。
ルーカーもノガも折れ、クロビーまみれになったものの一応生きていたアレックスは、なぜか矯正状態が解除されており、暴力的思考やり放題になっていた。その様子をまた内務大臣や医者が見に来ていて、なぜかもとに戻ったことを確認した上で治療され、退院、釈放されてしまう。ここがよくわからん。内務大臣たちは、ルドビコ法の中身がバレて批判されたからもう治療はやめたということなんだろうか。「よろしい、よろしい」じゃないんだが。
そしてキューブリックの映画だとここで終わりらしい。小説版では「幻の最終章を追加」となってて、結局当たり前のようにまた暴力仲間とつるんで好き放題する以前のアレックスに戻るが、昔の知り合いに偶然会って、彼が二十歳になって結婚しているオトナになっていることを知るとアレックスもそろそろオトナにならなきゃなと思って終わり。
確かに映画版だと、暴力振るうと矯正されちゃうよ良くないよ、しかも矯正したって人の根本は変わらないよ無駄だよ、みたいなテーマになってしまうかも知れないが、小説版だとこれはこれでただの暴力礼賛青春小説だし、単に若気の至りだからそのうち落ち着くよ、みたいな内容でどっちもどっちな感じ。
まあ、物語はすべからく教訓があるものである、という考え方自体あまり好きじゃないので別に文句とかがあるわけではないんだけど。
特徴的な語り口やナッドサット語のおかげか爽快に読めるけど、矯正治療されたあとも単に暴力のことを考えられなくなってるだけで根本は治ってないクソ野郎なので、因果応報されてるときはスカッとするけど、娯楽小説というのもちょっと違うような…
解説には「時計じかけのオレンジ」が何を指していたのか、以下のように丁寧に説明してくれているのだが…
『人は自由意志によって善と悪を選べなければならない。もし善だけしか、あるいは悪だけしか為せないのであれば、その人は時計じかけのオレンジでしかない ーー つまり、色もよく汁気もたっぷりの果物に見えるが、実際には神か悪魔か(あるいはますますその両者に取って代わりつつある)全体主義政府にネジをまかれるぜんまいじかけのおもちゃでしかないのだ』
読んでもなんだかよくわからない。なるほどね!だから時計じかけのオレンジか!と思いたかったんだがなぁ。
おまけ:ナッドサット語辞典
マレンキー すこし
ビズムニー あたまにきた
チェロベック おとこ
デボーチカ おんな
ベック ひと
スロボ ことば
グラジー め
グロムキー でかい
プレティ・ポリー おかね
ガン たばこ
ズービー は
マルチック しょうねん
ブリトバ かみそり
ゴロス こえ
ミリセント おまわり
ベスチ こと
ドルーグ ともだち
ルーカー うで
プラティ ふく
スコリー はやく
スタリー としより
オッディ・ノッキー ひとり
サボグ くつ
ノガ あし
ガリバー あたま
クロビー ち
ウーコ みみ
リッツォ かお
ボルシー すごい
プレチョー かた
ロット くち
グルーディ むね
ヤージック した
ガゼッタ しんぶん
ナッドサット ティーンエイジャー
カーマン ポケット
カッター かね
トルチョク ぶんなぐり
ボッグ かみさま
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
