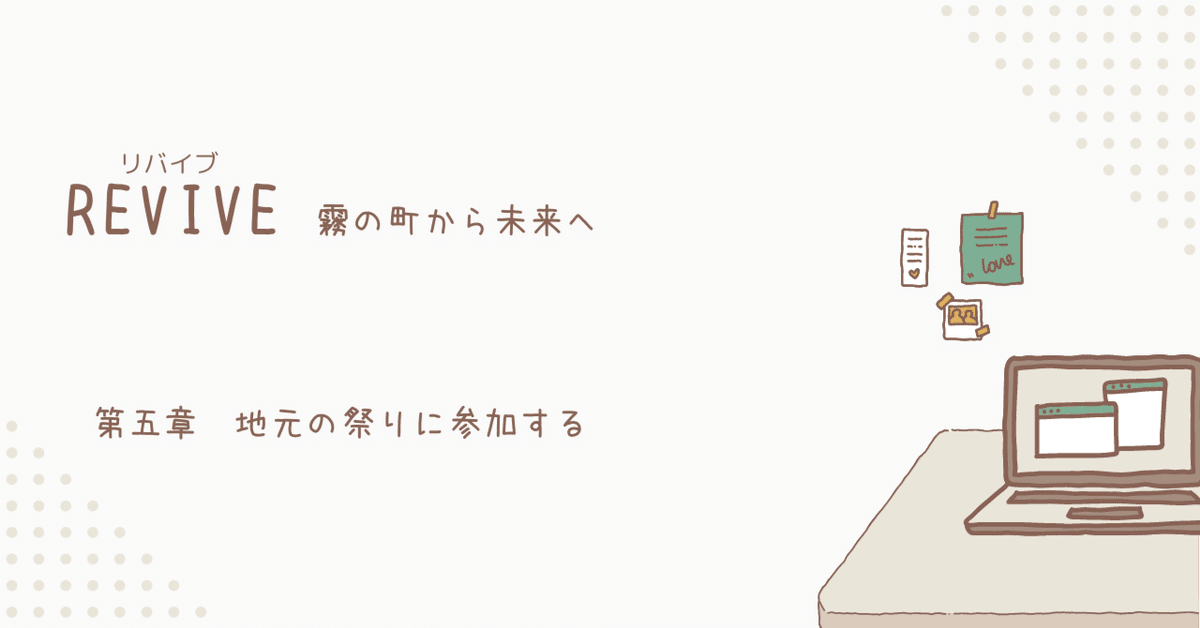
REVIVE 第五章
第五章 地元の祭りに参加する
由香が去ってから、拓真は亀岡での生活に専念していた。彼女との関係を割り切ろうと努めても、その余韻が心の奥底に残っていた。東京での生活を捨て、この地で新たな道を模索することを決意したものの、彼女との未来が途絶えたことは、時折彼の心に影を落としていた。しかし、祭りへの参加が、そんな彼にとって新たな一歩を踏み出す転機となった。
祭りの日、拓真は地元の人々と一緒に準備を手伝った。祭りの飾り付けや会場の設営を行いながら、彼は地元の温かい交流を感じていた。都会では感じられなかった「人とのつながり」が自然と育まれていることに驚きを覚えた。昼過ぎには、祭りのクライマックスである武者行列が始まり、街は歓声と拍手で包まれた。
ふと、行列に参加する武者たちをじっと見つめている少年が目に留まった。彼の目は輝いており、その姿に心を動かされた拓真は少年に声をかけた。
「お前もいつか、この行列に参加したいのか?」
少年は誇らしげにうなずき、「うん、おじいちゃんも昔、光秀役をやったんだ!」と答えた。その瞬間、拓真はこの祭りが単なるイベントではなく、世代を超えて受け継がれてきた誇りであり、伝統であることを強く感じた。鶴見さんの言葉、「祭りにはこの街の本当の姿がある」が、深く理解できた瞬間だった。
祭りの後、夜の静寂の中で拓真は一人歩いていた。先ほどの少年の目の輝きが、彼の心に深く残っていた。祭りはただ過去を振り返るものではなく、未来へ繋がる希望を育む場であると感じた。東京での思い出がふとよぎったが、彼はもはやそこに戻ることはないと確信した。
「やあ、拓真」と声をかけてきたのは鶴見さんだった。街灯の下に立つ彼の顔には、いつもの穏やかで優しい表情があった。
「祭り、楽しめたか?」と鶴見さんは聞いた。
「ええ、とても。今まで見たことのなかったこの街の一面を知ることができました」と拓真は微笑んで答えた。
「祭りはこの土地の魂そのものだ」と鶴見さんは静かに語り出した。「日本のお祭りの本来の目的は、神様に感謝することだ。この『祭り』という言葉は、『祀る』から来ているんだ。そして、日常を『ケ』と呼び、祭りを『ハレ』と言う。祭りは非日常の場であり、日常をリセットして新たな活力を与えるためのものなんだ。ハレの場があるからこそ、日常を生きる活力が湧く。光秀もこの土地で決断を下し、その後の歴史に深く関わった。君も、この街で自分の道を見つけることができるさ。」
「光秀も迷っていたんですか?」と驚く拓真に、鶴見さんは微笑んだ。
「もちろんさ。歴史の英雄たちも、常に揺れ動く時代の中で自分の信念を探していたんだ。迷いながらも信じた道を進むことで、大きな決断を下したんだ。お前さんも、迷いながら進んでいけばいい。」
その言葉を聞き、拓真は自分の心に巣食っていた迷いを受け入れることができた。祭りの持つ深い意味と、日本人が何世代にもわたって大切にしてきた「ハレ」と「ケ」の考えが、今の自分にどう影響を与えているのかがわかったのだ。
その夜、拓真は由香との思い出に再びふけりながらも、彼の進むべき道がこの亀岡にあることを強く感じた。鶴見さんの助言が、彼に新たな視点を与えてくれたからだ。迷いながらも、拓真はこの土地での未来を描き始めた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
