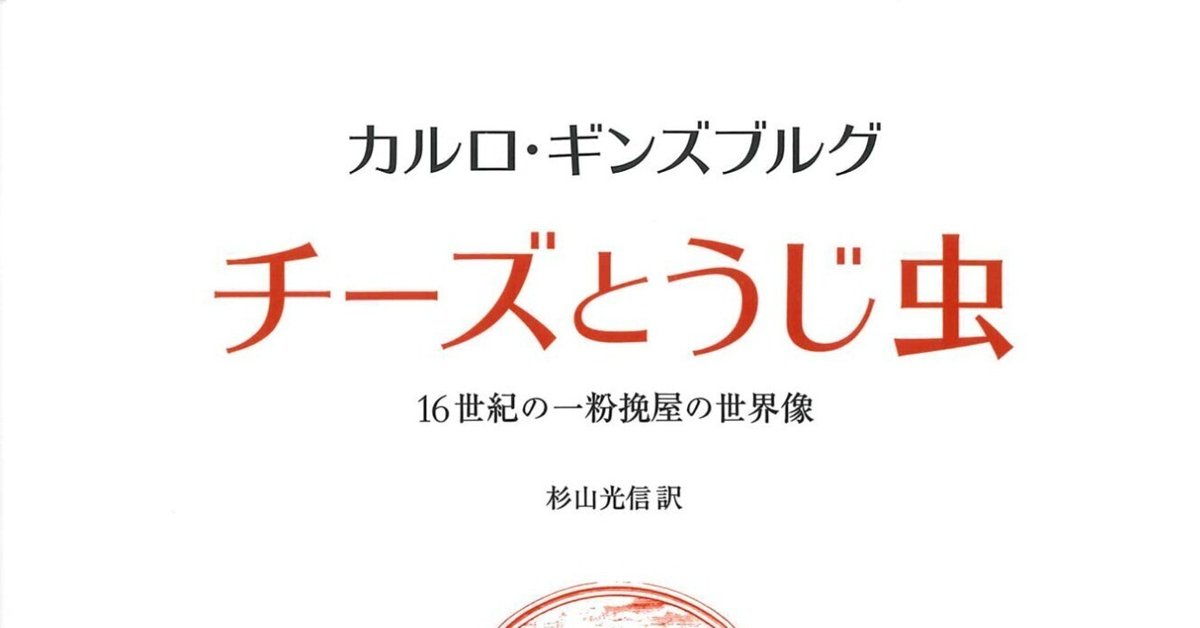
カルロ・ギンズブルグの『チーズとうじ虫』をちゃんと読む(第3回)
カルロ・ギンズブルグ『チーズとうじ虫』を精読するコーナー。第3回は、引き続きメノッキオの宗教観の源流を探ります。
※
メノッキオは印刷本のテキストを恣意的に換骨奪胎する。例えばアルベルト・ダ・カステロ『栄光ある処女マリアのロザリオ』を読んで、聖母マリアを他の処女の仲間たちと同列に帰す(16)。ヤコブス・デ・ウォラギネ『諸聖人の生涯についての伝記』(『黄金伝説』)を読んで、葬儀の間にマリアの名誉が司祭長によって傷つけられるくだりだけを抜き出す(17)。『聖書の略述記』を読んでキリストはメノッキオらと同じようなひとりの人間であるという思想を強化する。『ジュディチオの物語』を読んで「神を愛することよりも隣人を愛することの方が重要である」という思索を得るといった具合である(18,19)。
しかし、『マンテヴィルの旅行記』についてはテキストそのものがメノッキオにとって重要である。イスラム教の『コーラン』のテーゼに触れていた同著の主張と同様にメノッキオは「イエスは神ではなく預言者の一人」と主張する(20)。また同著から異民族の文化に触れ、異対する宗教的寛容を説く。ここに民衆信仰の若干の痕跡が垣間見える(22、23)。
またボッカチオ『デカメロン』の「三つの指輪」からキリスト教、イスラム教、ユダヤ教の中世的な寛容のテーマを得る。ここではメノッキオの宗教的ラディカリズムは(民衆信仰ではなく)同時代のさまざまな異端や人文主義的教養を持つ人々による洗練された宗教的理論形成とむしろ合流している(23)。
メノッキオが生み出した宇宙生成説(チーズからうじ虫が発生するように天使たちが出現するという説)は書物から得たわけではなく、日常的な経験から得たわけであり、聖書の「創世記」よりも科学的である。しかし彼はそれとは知らずに、古代インドの神話からそれを引き出している。『ヴェーダ』(紀元前1000年頃から紀元前500年頃にかけてインドで編纂された一連の宗教文書の総称)との符号の一致は、(ユング的な)集合的無意識でもなく単なる偶然でもなく、世代から世代へ口頭でなされる伝達によるものであると、ギンズブルグは仮説を立てる(27)。
印刷術の発明により概念を得たメノッキオ。「キリスト教、ネオ・プラトニズム、スコラ哲学などにより浸透された用語でもって、メノッキオは農民たちが世代から原初的にして本能的な唯物論を表現しようとしたのである」とギンズブルグは説く(29)。
神について、至上の聖なるお方について、神の精神について、精霊について、魂について語るメノッキオ。そこには比喩に満ちた唯物的な宗教観があった。
メノッキオは天国への言及では飽き足らず、「新しい世界」について言及する。「アダムが耕しイヴが紡いだ時、だれが貴族であったろうか」という言葉が示す通り、堕落した社会に対する変革闘争は、神話的な過去への復帰を目指すのだが、メノッキオも同様に、現在の堕落した教会と、神話的な原始社会を対置させる。メノッキオはルターに好意的なフォレスティ『年代記補遺』をおそらく読んでいた。ドイツですでに勝利を収めていた宗教改革との関連をギンズブルグは示唆する。またメノッキオの「新世界」への願望は、新大陸の発見という地理学的なコンテクストから社会的なコンテクストへと移行したこととも関係があった(40-42)。
メノッキオは2年間の投獄ののち、モンテレアレに帰った。
※
第3回のまとめ。メノッキオはあらゆる書物を換骨奪胎し、ラディカルな宗教観をこしらえるが、唯物的な農民信仰から人文主義的宗教理論までさまざまな思想から影響を受けている。そのなかでも宇宙生成論ははるか古代のインドから民衆の口承を通じて伝わったものである。メノッキオは「新しい世界」を夢見るが、原始的神話のみならず、ルターの宗教改革や新大陸の発見などの影響を見ることができる――という感じでしょうか。(第4回につづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
