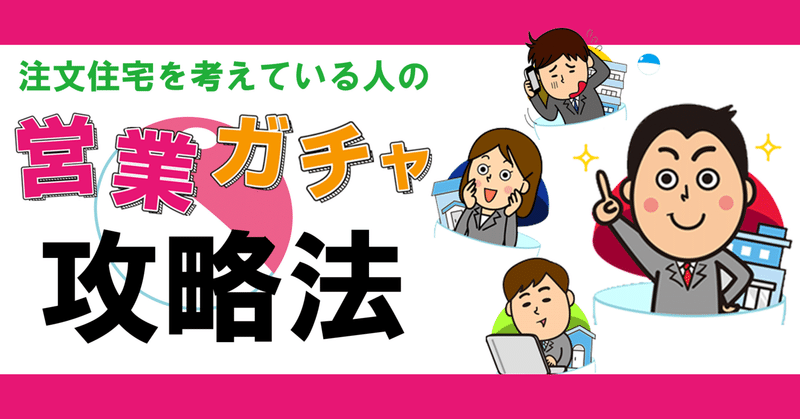
注文住宅を建てようとする人の「営業ガチャ」攻略法 011
住宅ローンの支払いを返済負担率から考えていく
自己資金は少なく、住宅ローンは多く
近年では自己資金と頭金のバランスも様変わりしてきました。昔は住宅ローン金利が4〜5%と非常に高利率であったため「自己資金は多く、住宅ローンは少なく」という常識があり、団塊世代の方などは今でも住宅ローンはできるだけ組まない方がよいとお考えの方が多いようです。
ところが現在は全く反対で「自己資金は少なく、住宅ローンは多く」という常識になってきました。史上最低金利が延々と続いているほか、住宅ローン減税の恩恵が手厚いことがその理由。実際にシミュレーションをしたことがありますが、その結果には大変驚かされました。そのため昔と違って多額の現金を準備しなくとも家は建てられる時代になったと言えます。
ただし土地の売買契約の際には手付金として50~200万円程度を求められることがほとんどですし、また建築会社と請負契約を締結する際も100万円程度は求められるのであまりにも自己資金がないというのは注文住宅に少々無理があることは覚えておいてください。
住宅ローンの年間支払いは世帯年収の30%未満が妥当
自己資金の点検ができれば、次は住宅ローンについて考えていきます。ここでの目的は「返済負担率を何%に設定するか」からです。返済負担率とは住宅ローンの支払い額が年収の何%に相当するかという数字で、一般には30%未満がセーフティラインであり返済の破綻するリスクが低くなると言われます。
まずはざっくり「毎月の支払いは〇〇万円くらいなら大丈夫かな」というイメージから始めましょう。その金額に12をかけた金額が、世帯年収の30%未満かどうかを確認しましょう。
・毎月13万円くらいなら支払えるかな?とイメージする
・13万円×12カ月=156万円が年間のローン支払い額
・156万円÷30%=520万円以上の世帯年収があれば毎月13万円はセーフティライン
より安全なラインを求めるなら25%以内の支払い額に抑えたい。
世帯年収が520万円の場合
520×25%÷12ヶ月=10.8万円以内を毎月の支払い額として抑えたいところ。
しかし特に年齢の若い世帯の場合、今後の産休に伴う収入の減少や教育費がいくらかかるか・生涯賃金がどのくらいになるかということが見えづらい時期にあり、果たして10.8万円が妥当な支払い額であるのか判別しがたい点にあります。
これについて語るとまるまる一冊の本になってしまうのでここでは割愛しますが、手っ取り早いのは信頼の置けるファイナンシャルプランナーに相談をしてから適切な支払額を決定するのもよいかもしれません。
「いくら借りられるか」を算出する
返済負担率から導かれた毎月の支払い額が見えてきたら、次はこちらの住宅保証機構株式会社サイト(https://loan.mamoris.jp/borrowing_income.asp)を利用してみましょう。
返済方法は元利均等払いにチェック、返済期間は35年(ただし年齢が45歳以上の人は「79-主債務者の年齢=入力する年数」としてください)、ご本人様の年収は昨年1年間の年収(自営業の方は所得)を、連帯債務者の年収には配偶者様の昨年1年間の年収(自営業の方は所得)を、返済負担率は30以下で希望するパーセンテージをそれぞれ入力してください。
これは何回でも調整できるので、何回でも試してみるとよいでしょう。のちほど詳細を書きますがここで満足するお借り入れに至らない場合は、返済負担率を上げる必要や連帯債務者の年収を合算する必要があります。
納得のいくお借入金額に到達したら前述の自己資金と合算した額が「お家の総支払額の上限」となり、ここを上限として土地や建築会社を検討していきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
