
完璧主義を魅力に変える
完璧さにこだわる人がいます。ところがよく見ると、こだわるレベルは、人によって随分差があることに気づきます。
「きちんとしているのが好き」というレベルから、「完璧でないと許せない」というレベルもあるし、極端なほど完全性にこだわれば「不潔恐怖」というカタチに現れ、生きづらさを抱えることもあります。
一見、長所でもある完璧さですが、行き過ぎてしまうと、自分やまわりを苦しめてしまうことにもなり兼ねません。完璧主義の正体について知り、長所として生かせる方法はないか、探ってみたいと思います。
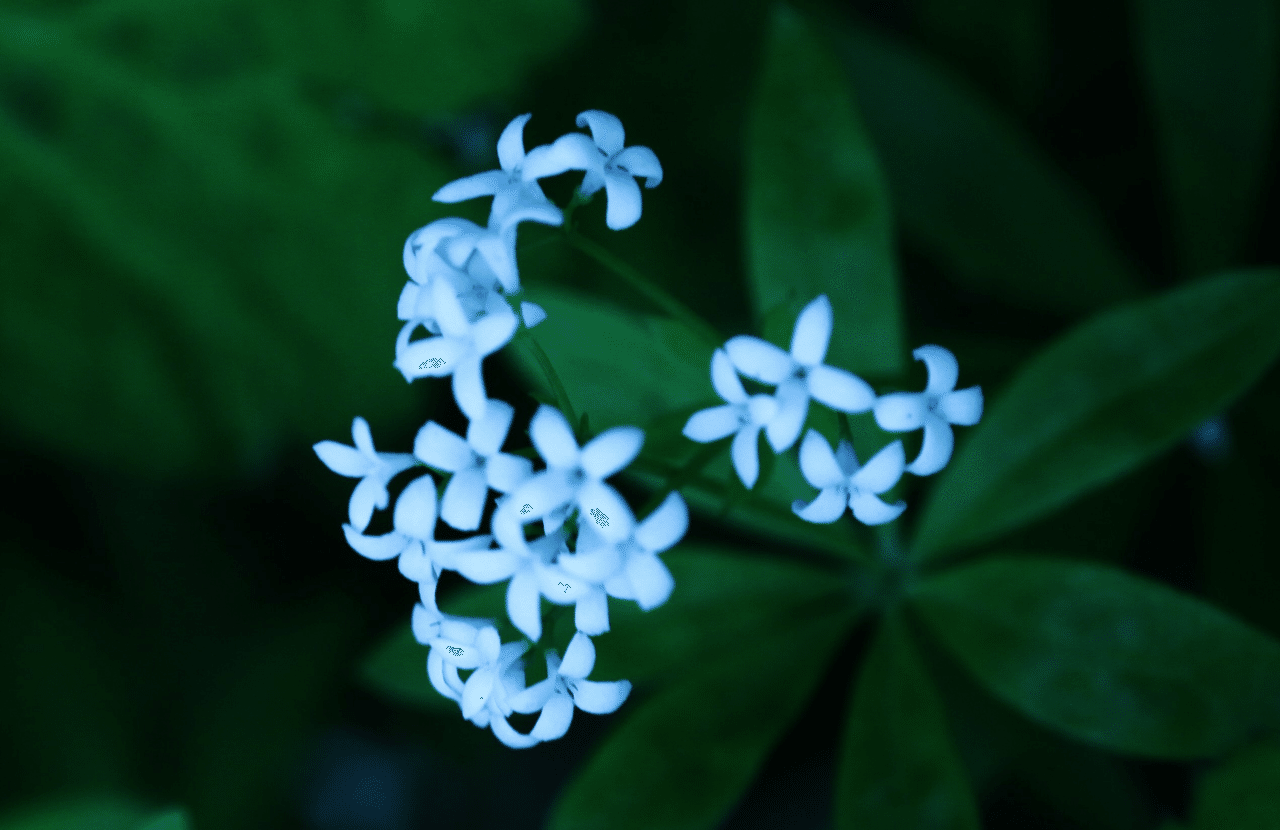
レベル別にみた完璧さ
まず、完璧主義をレベルに分けて整理してみたいと思います。
「きちんとしているのが好き」というレベルであれば、整理整頓が好き、断捨離が得意、といった範囲におさまる完璧さですから、周りにとってもありがたい存在で、信頼感につながります。
ところが、強度が増して「完璧じゃないとダメ!」というレベルになると、一気に緊張が高まります。完璧さを求めるあまり、マイナス面がクローズアップ。対極にある「妥協」が苦手、「融通」が利かない、「許容量」の狭さが露呈。すべて自分でやらないと気が済まなかったり、なんでも口を挟むといった行動が目立つようになります。
「不潔恐怖症」のレベルに達すると、生活そのものに相当な支障が出てきます。外の世界は危険がいっぱいで、ゴム手袋をしていないとドアノブや蛇口に触れられないとか、温泉やプールは気持ちが悪くて入れないなど、行動範囲が極端に狭まれていきます。その結果、神経がすり減り、一人の世界にこもることが増えていきます。次第に、誰からも侵されない、究極の安全基地がないと平静さを保てないほど、常に不安定さを抱えることになります。

全か無かの「白黒思考」
極端な完璧主義の「不潔恐怖」という現象から、深い心理を読み解いていくと、興味深いことがわかってきます。
「不潔恐怖」を医学的に捉えると、実は不潔を恐れているのではなく、自分が異物によって侵されてしまうことを恐れているというのです。
異物に侵される?一体どういう意味でしょう。
日々、人が触れる大量の異物は「他人」です。
つまり、根底にある恐怖の正体は「自分が他人によって侵されてしまう」という過剰不安です。
他人に侵入されてしまう恐怖とは、心の声に耳を傾けてもらえず、他人に支配されてしまう怖さや、その結果、自分を押し殺して生きることを強いられる恐怖でもあります。
なぜ、そのような感覚を持つのでしょう。
それは、育つ背景を紐解いていくと、見えてくるようです。
完璧さにこだわる人は、優れた達成を手に出来た時にしか、評価されなかった経験を積んでいるといいます。
「優れていなければ価値がない」という、親の価値観に縛られて育っていることが多く、これを「条件付きの愛情」と呼びます。
自分は条件を満たすことが出来ているだろうか…と疑心暗鬼になり、小さい頃から、他人に心を許すことが苦手で、心を許して安心させてもらう体験値が乏しいことが要因となっていることが多いのです。
本人も気づかない根っこに、条件を満たせないのはいけないこと、という判断軸を持っており、そのことが自分を苦しめる元凶になっているのです。
親が示す価値観の中には、学歴や職業選択、ブランドにこだわることも多く、あなたの将来のためだからといいながら、実は親の自信のなさを、ブランドを身にまとうことで補っており、子どももブランドの一つになることを強いてしまう…。よくある話です。
ただ大切なのは、単に親を批判すれば解決するということでもありません。
親だって人間です。不完全さを抱えながら、必死に生き抜いてきているので、そのからくりに気づく親は少なく、伝えたところで、到底受け入れられるものでもないようです。

完璧主義の利点
完璧主義のマイナス面を先にお伝えしましたが、もちろん、いい面もたくさんあります。
完璧であろうとこだわることで、努力を惜しまないし、「まだまだ…」と完成形をイメージすることで、パワーがあふれて、意欲を維持することができます。その結果、相当な努力家としての成功体験を積み上げることができます。
また、完璧さを求めて努力することは、美しさへのこだわりを持つことでもあります。美しさの中には、見た目の美しさもさることながら、考え方の美しさや、人間性の美しさなども含まれます。
実際、完璧さにこだわる人は美的センスに優れているし、思考に対しても、乱れや汚れのない「正しさ」や「清らかさ」を磨いていると感じます。これは大変に魅力的な要素です。

完璧主義と強迫的な観念
完璧さの持つ利点を超えて、問題が生じるとすれば、行き過ぎてしまう時。
バランスを失い、倒れ掛かっているのにもかかわらず、まだ止まろうとしない。周囲の助言にも耳を傾けず、独自の思考パターンにこだわり続けようとする時に、問題が噴出してくるのです。
だとすれば、行き過ぎに気づいて、ブレーキを掛けられればいいのです。
更に、調べていくと面白いことがわかってきます。
精神科医であり、作家でもある岡田尊司さんは、完璧主義とは創造的なものではなく、同一を求める反復強迫だとおっしゃいます。
どういうことか、解説しますね。
完璧であることとは、イコール、一点の曇りもないことに特別な価値を置くことなんだそうです。曇りを全て取り除き、乱れをなくすことが最大の目的になるので、例え周囲が苦しんでいようとも、強迫的な観念を止められなくなります。
暴走は、ブレーキが壊れた車のようなもので、ガソリンが尽きるか、壁にぶつかって大破するまで止められません。
そうならないためにも、完璧さへのこだわりを、ほどほどのレベルでとどめることは出来ないものでしょうか。

耳を傾ける・思考パターンを崩す
完璧さを長所として生かすためには、暴走の予兆に気づいて、止められるか否かがポイントです。
ところが、こだわりを持つ本人が、予兆に気づいてブレーキをかけることは、なかなか難しいと思った方がいいようです。それよりも、自分を過信せず、人を頼って、助言に耳を傾けること。これが出来れば、うまく暴走を止められる可能性が出てきます。
事実、自分に向けられる助言は「やり過ぎている」「ブレーキをかけて」という内容が多いはず。せっかくの貴重な助言を無視していると、後で後悔することにもなりかねません。
身体が先に悲鳴を上げ、睡眠不足や過眠といった睡眠への乱れが生じて、身体を壊してしまうこともあるでしょうし、高圧的な態度で相手の口を封じようとすれば、人は離れていき、誰も親身になって助けてくれる人はいなくなります。そうなってからではダメージは大きすぎます。
親身になってくれる人がいるということは、魅力ある存在だということだし、その魅力をもっと生かしてほしいと思ってくれている証拠。
勇気を持って、人を頼る、耳を傾けてみることです。
そして、もう一つは「パターンを崩してみる」こと。
うまくいかない時こそ、思考パターンに陥っていないか、自分を疑ってみるのです。自分では壊したつもりでも、壊し切れていないことがほとんどです。なぜなら、うまくいかない時は、気持ちに余裕を無くしている時なので、自分流=自分の思考パターンへのこだわりが、一層強まる防御に入ってしまうからです。
ここが一番の難所かもしれませんね。
まわりにいる人が必死に助言しても、本人は、パターンを崩すなんて、恐ろしくて考えられないといった様子を見せるので、何を言っても、最初から一蹴するつもりで、身構えているとさえ感じるほどです。そうなっては、無理強いしても頑なになるだけ。まずは肩の力をほぐし、身構えている自分に気づくことから始めましょう。
いずれにしても、まわりにいる人の支援はとても重要です。
少しずつ、少しずつ、固まってしまったコリをほぐすように、穏やかに、そして辛抱強くこだわりを解き、いつもの思考パターンを崩す挑戦を、力強く応援してあげてください。
必ず変化は訪れますよ。
鶯千恭子(おうち きょうこ)
<お知らせ>
いつも鶯千恭子ブログをお読みいただいてありがとうございます!
最新情報をいち早くお届けしていきますので、LINEのお友だち登録をお願いします!こちらをポチッ↓です
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

