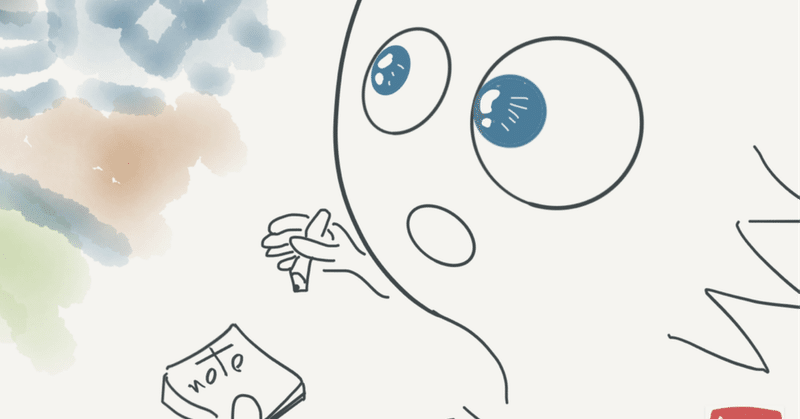
旅行雑誌編集者−1 プロローグ
社会人になって、旅行雑誌の編集業という職に就いた。今でこそアーカイブと現地の臨時スタッフに頼り、記事作成はデスクワークでこなせるようになったものの、かつては現地に出向いで鮮度のいいところを自らの手で掴み取る方法を採っていた。
3か月に一度取材タームがやってきて、オフィスを発つと1週間ほどの取材期間が数回やってくる。短ければ2、3日で帰ってくることもあるが、取材対象がでかいと10日間ほどの長丁場になる。
取材期間中の飲み食いは、個人的なおやつと嗜好品を除いて、すべて経費で賄われる。
取材日数分マイナス洗濯で使い回す衣類をまとめ、ライター兼編集者が2人、カメラマン1人で1チームというのが基本編成だった。
大掛かりな取材だとデザイナーが同行したり、勤務チェックという名目で傍迷惑な上司が物見遊山でついてきたりする。取材終了後のお疲れさま会では毎夜羽目をはずすくせに、部下の粗探しは天下一品で狙った獲物を取り逃すことはない。その鋭さには毎回舌を巻く。上の立場という天下の宝刀が遺憾なく発揮される。指摘すべきところは威厳をもって上から目線で容赦なく降り注ぐ。その卒のなさといったら、社に戻った上司自身に見せてやりたい繊細さである。まったくもってやっかいなお荷物だった。
これから展開していく話は大きく分けて2つの要素で構成されていく。
ひとつは旅行誌編集業という業務についての深掘り、そしてもうひとつは旅行雑誌編集者として捉える旅。偉そうに語ってはいるが、所詮は個人の1視点、参考程度に受け取ってもらえればありがたい。それでも、職業柄ついてまわる腹の中の多少黒っぽく湿った目には業界を裏側から覗いたおどろおどろしさがあると思う。昨今の若い旅ライターとは違った「知ってしまった」者のいやらしさというか。
ま、老練の視点だから万人受けするものではないと思うけど。
というわけで、2つの柱で構成させていただくこととする。
発信情報には癖があることをご承知おき願いたい。商業ベースではないから遠慮もしないし、よいしょもしない。映えを意識したあざとさも入れない。反面、個人的な思い入れはおおいに注ぎ込む。偏向は当たり前、そのせいで理解し難い局面にも出くわすかもしれない。不可解に思われるだろう部分については、可能な限り、その論拠にも触れていこうとは思う。納得いかなければ、どうぞ反論の声をあげていただきたい。
さて初回の今回はプロローグという位置付けである。だが、単にこれから始まりますよで終わったのではつまらない。ひとつ、踏み入った話題にふれさせていただこうと思う。テーマは、取材特権と個人出費の旅行の差異について。
では。
霧島に客室がすべて離れの宿があった。渡り廊下にはこぶりな足下燈が連なり、ゆるい丘陵に筆をふるったみたいにして客室が設えられた粋な和のお宿である。ささやかに案内され館内の空気にふれたとたん、到着の安堵で緩んだ気持ちに警策の一撃を浴びせられた思いがした。背筋が伸び、秋の空気がいちだんと引き締まった。
すべてがあまりに凛としており、徹頭徹尾それが貫かれていた。
必要最低限の案内を受け、部屋に入る。無駄のないお着き菓子、女将手書きの歓迎の口上書き。宿に着いたその瞬間から客は完璧なプライベートに包み込まれ、しゃしゃり出ることをいっさい廃した接待に導かれた。おそれいった。
個人で泊まるにはあまりに高額な宿泊料金に、当時は「取材特権」と、入り組んだ複雑な気持ちの底で縮こまる場違いで腰の座りの悪さのようなものに蓋をして、一晩の夢に浸らせてもらった。
お宿の宿泊料金は、高ければいいというものではない。まるでひとつの街の中で過ごしているようなアミューズメントホテルもあって、それなりの対価を提示してくるところもある。だが、高額な宿泊料金に畏れると失敗する。支払い金額だけが脳内にこだまし続け、大事なところを見誤る。高ければ高いなりに、無理をしてでも泊まってよかったと思える楔が打ち込まれなければならない。
取材はプライベート時間ではない。自分満足は体裁の裏側に潜ませておかなければならない。まず自分を客に見立てて素直に感じ取らなければならないことはわかってはいる。だが、客として泊まりに来ているのではない。その現実が、楽しもうとする気持ちの頭を押さえる。プロたるもの、お宿と対峙したその時に、文章で言い表せる筋道を見出しておかねばならない。
どのように表現すればイメージを違わず伝えることができるのか、写真はその喚起に即しているものが撮れているか、取材時間は常にプライベート感覚のアンテナを立てた仕事モードである。
余談となるが、カメラマンからよく漏れ出た不満がある。「ライティングはいいよね。あとでいくらでも軌道修正がきく。だけど写真は現地で切る1枚1枚が勝負、一期一会は逃せない」
確かに写真はあとから修正はきかない。撮り逃せば後悔ではすまない。
あの時カメラマンに言い返さなかったけど、編集もライティングも「あとであれも取材しておけばよかった」は通用しないのだ。取材対象は日が変わるごとに変わっていくし、取材が終わるごとにあらかたの誌面構成の見当をつけておかなければあとで辛くなる。編集部に戻って追加取材するくらいなら、最初から電話取材で済ませればいいという話になる。情報の取りこぼしは、あってはいけない。旅の恥はかき捨てと言われるけれど、仕事でそれをやっちゃあおしまいよ。
カメラの仕事とはその一期一会の緊迫具合が違うというのか? 質が違うだけのような気もする。
業界には業界なりの特権がある。航空業界にはチケット優遇が、デパートの類なら特価の社販が、飲食関係なら美味い賄い飯など。
旅行誌は業界とは言えないけれど、それなりの特権はあった。社費で観光地に行けるのだ。両手をあげて旅行を楽しめるわけではないけれど、特権は業界を問わず、苦しくても時間に合わせて成果を上げる労働者へのささやかなご褒美である。
「旅行雑誌の編集をやってました」と言うと、いろんなところに行けていいですねと羨ましがられる。だけど、羨まれたほうはそうは思っちゃいない。取材旅行では、いつだってオフィスを背負ってる。日本全国津々浦々、海外取材であっても、どこに行っても遠くに来たあといった脱出感がない。時差のあるリゾート地でもネットでつながっているし、オフィスがちらついているせいでTOKYOリズムが体の芯から離れない。
取材を通して、高額でもプライベートで泊まりたいお宿がいくつかあった。心惹かれた宿に、恐縮することなくいつか純粋に楽しむために足を運んでみたいと思う。自分の財布を開けるからこそ、旅は貪欲に楽しめる。
次回のテーマは決めていない。揺れる気持ちに身を委ね、気まぐれにほじくり返していこうと思う。
よければ続編を楽しみにしていてくださいな。季節が移ろう風を読みながら、気分で綴っていこうと思います。
忌憚のないご意見、ご要望、ご感想、その他もろもろのコメント大歓迎。現世を渡る風が運んでくるのを首を長くしてnote私書箱に届くのを待ってます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
