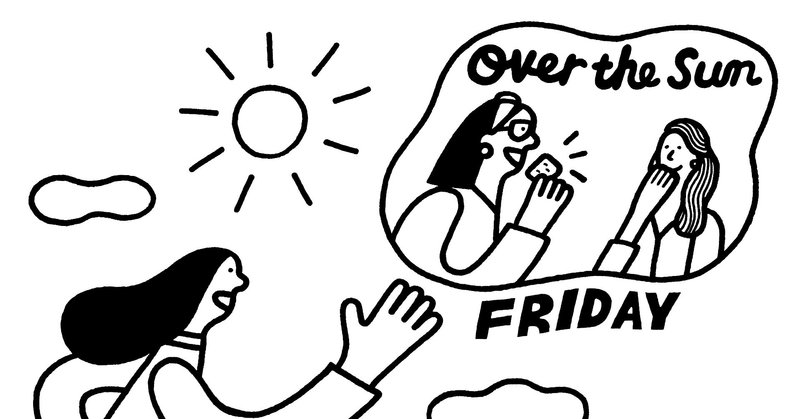
わたしはジェーン・スーさんのことを知らなかった【連載エッセイ「TBSラジオ、まずはこれから」】
ジェーン・スーさんのことなら、もちろん知っていた。
著書『貴様いつまで女子でいるつもりだ問題』はずいぶん前に読んでいたし、Twitterのアカウントだって、もう長い間ずっとフォローしている。
書き手として、また幅広く活躍されているスペシャルな人として。
どうしたって目に入らないわけのない、憧れの人だ。
パーソナリティを務めておられるラジオ『ジェーン・スー 生活は踊る』だって、会社員時代から「おもしろそうだなあ」「聞いてみたいなあ」と長らくずっと、本当にそう思ってきたのだ。
けれどあるとき、実のところ、わたしには「あ、」と思うことがあった。
「これ以上はジェーン・スーさんのものは読まない方がいいかもしれない」
そう思った瞬間があったのだ。
「いつか」のために、ほど良い距離を
それは、とある記事をwebで読ませてもらったときのことだった。
内容は、ジェーン・スーさんのご家族に関するものだ。
もちろんそれが、不快だった、つまらなかった、だなんてそんなはずはない。ジェーン・スーさんの文章というのは、言わずもがなとっても面白いのである。
では、いったいなんだったのか。
それはあまりにも——。
恐れ多いながら、わたしとその人はあまりにも重なる何かが大きすぎてなんだかそれを上手く抱えきれず、またこれ以上憧れてしまうと、
「ああ、きっとこの人に焦がれ、この人が書くものをいつからか真似てしまうかもしれない」
という恐ろしさを、20代のわたしは自分の中に見つけてしまった。
以来、わたしはジェーン・スーさんの書かれているものは読まなくなった。
そんなこともあって、去年から「面白いよ」とたくさんの人にすすめられていたPodcast番組『ジェーン・スーと堀井美香のOVER THE SUN』も、なんだか聴く機会を失い続けることになったのだった。
「生きるとか死ぬとか父親とか」
特に、書籍『生きるとか死ぬとか父親とか』については、一生懸命無理をして、書店でわたしはそれを手に取ってこなかった。
頑張って触れずにきたのだ。
けれどこの春。その書籍はついにドラマ化されてしまう。
そしてなんと、お父様役は、かつて映画の舞台挨拶の取材時、わたしが関係者のフリをして控え室の近くをウロウロと数十分近くうろついた経験さえある、大好きなあの國村隼さんなのだ。(本当に反省をしています)
ところが、ここでもやはりわたしは、まだどうしても見る勇気が湧かなかった。
だけど、皆が口を揃えて何度も何度もこう言うのだ。
「すごくいいよ」
「ゆかちゃんは絶対に共感するよ」
「絶対に見て」
もう、これ以上抗う体力はわたしにはなかった。
だって、本当はずっと見たかったんだもの。
そして、恐る恐るわたしは配信サービスでそのドラマを1話から順に見始めてしまう。
『生きるとか死ぬとか父親とか』(テレビ東京系)は、自由で奔放な70代の父親と、それに振り回される娘の可笑しくてちょっと切ない愛憎物語だ。
娘にとってはこの父が唯一の肉親であり、心配や愛はあれど、同時にいちばんの面倒事でもある。そして「ふたり」には、常になんだか母の不在を感じさせられる、そんなスーさん自身がモデルとなった作品だ。
ドラマは本当に面白い。
役作りの範疇を超えているのではないかと感じてしまうほどの吉田羊さんの素晴らしい演技、國村さんのとぼけながらも色っぽい独特の味わい。
けれど、そのストーリーと細かな描写にわたしは本当に本当に困ってしまうのだった。
わたしとか父親とか
わたしにも、離れて暮らすたったひとりの父がいる。
誰に選んでもらったのか、洒落たハンチング帽なんかを被ってはいるのだけれど、お金には縁がなく、「ここで食べよう」と誘われたフードコートで大量に注文を言いつけられても、会計は全てわたし持ちだ。
「お父さんとふたりには絶対にしないでね。約束ね」
と幼い頃からいつも懇願し続けてきたというのに、花のように可愛く笑う明るくやさしい母は、そんな父を置いて、わたしが26のとき旅立ってしまった。
兄弟もないから、わたしと父は本当にふたりだ。
けれど、夫婦にとってわたしは一人目の娘ではなく、母は生まれるときに命を落としてしまった姉のことで人知れず深く傷ついており、そんなことも含めてひとり娘のわたしをそれはそれは可愛がったものだった。
そして「C型肝炎」「癌」。それはいずれも、わたしのかけがえのなかった「家族」に影を落とした、とてもとても忌まわしい言葉で、そんな思い出を少しでも塗り替えたいのか、父は時折、よその赤ん坊を抱いては「家族が増えるのはええことやなあ」と、こちらを見る。
なにかそれ以上のことも言いたげにしているけれど、わたしは今も独り身のまま、東京で物書きなんかをして暮らして、母が姉を亡くした30歳も超えてしまった。
そんな父の様子をたまに綴ることもあるのだけど、わたしの職業がいったいぜんたい何なのか。一緒にわたしの寄稿文が掲載された冊子を探して歩いたことさえあるけれど、なんだかわかっているような、わかっていないような……そんな父なのである。
ドラマとわたしの背に広がる背景は、恐ろしいほどに酷似していた。
ただ違うのは、スーさんは【人生の酸いも甘いもつまみ食い】した、わたしよりもうんと大人の女性であること。そして、素晴らしいお仕事を本当に本当にたくさんされていることだった。
劇中にはもちろん、月~木曜日に生放送されている『ジェーン・スー 生活は踊る』も出てくる。と言っても、「TBSラジオ」は「TBXラジオ」とされ、番組名は主人公・蒲原トキコの愛称から文字った『トッキーとヒトトキ』とされているのだけど。
実際の番組同様「悩み相談」のコーナーがあり、それがまた絶妙にいい。
相談者に「目を逸らしてはダメよ」突きつけるようにリアルを語りながらも、ぎゅっと腕では肩を抱いて寄せてくれているような、そんな心強さとあたたかい何かが本当に伝わってくる。ラジオならではの距離感だ。
「きっと実際も、こんな番組なのだろうな……」
徐々に正体のよくわからなかった恐ろしさは、憧れと恋しさのようなものが入り混じった気持ちと混じり溶けて、わたしはスーさんにぎゅっと肩を抱かれたい、と。本当はずっとそう思ってきたのだろうと、この胸でようやくわかり始めたのだった。
局を越えた『トッキーとヒトトキ』
そして、ラジオの声に触れる、そんな機会が巡ってきた。
なんとその劇中ラジオの『トッキーとヒトトキ』が局の枠を超え、先日TBSラジオで実際に放送されたのだ。
吉田羊さん、アナウンサーとして登場する田中みな実さん、そしてジェーン・スーさんのお三方によって繰り広げられた1時間。
わたしは夢中になって聴き、また何度も聴き返した。
特に「40歳を超え、全てが終わってしまったように感じる」というお悩みに対する、スーさんの言葉は、わたしを打ちのめしながら抱きしめてくれた。
「今まで自分が人にあててきた“ものさし”が、順番が回ってきて、今度は自分をその“ものさし”で測って辛くなる」
大切なのは、
「そのときにそのものさしを外すことができるか」だと。
そう、わたし自身も、いつからか「年齢」に縛られ、「年齢」の呪いに苦しんでいるリスナーのひとりだった。
数年前、年下の同僚に年齢を揶揄され続け、会社に行くのが辛くて辛くて仕方のない時期があった。
相手にとっては、きっと軽くなじるような冗談のつもりだったのだと思う。
けれど以降、わたしは自分の年齢について触れることが怖くなり、自分の年齢を隠したりするようになってしまった。
わたしの周りの素敵なひとたちは、みんなみんな「これでもか」と歳を増すごとに一層自由で楽しく、そんな姿がとてもきれいなのに。
そんなことは、本当によくよくわかっているのに。
それでも、「30超えた人と一緒にされても」「世代が違うんで」「一生ひとりで生きていくって決めてる人とは違うんですよ(笑)」そんな言葉を毎日毎日向けられることで、わたしはにこにこと「ひどい!」なんて笑いながら、奥底が痛くて痛くて悲しくて仕方なかった。
「30」という重石のようなものをいくつも背負った気分で、ここ数年をずるずると這うようにして生きていた。
けれどそれは、スーさんの言うとおりだったのかもしれない、と今さらになって気づく。
必要以上に傷ついてしまうのは、本当は、若いころのわたしが「30って、女性の区切りよね」と心のどこかで思っていたせいなのだ。
本当は「年齢を重ねるって怖いことよね」というのは、わたし自身が胸の内で思い続けてきたことだったのかもしれない。
年齢を越えること、距離も越えるもの
そうして、ようやくわたしはPodcast番組『ジェーン・スーと堀井美香のOVER THE SUN』にたどり着くのだった。それはもはや、処方箋のような導きだ。
そして今、思うこと。それは、
「もっと早く聴いていれば」
と、ただその言葉に尽きてしまう。
たとえば去年から聴いていれば、辛い想いを抱えずに済んだ夜があったのではないか。そんなふうにさえ、本当に思えるのだ。
スーさんと美香さんは、ほどくように肩の力を上手に抜いて、おもしろかっこよく、時にかわいく40代の「今」を大笑いしながら話している。
おばさんだ、もうこんな年齢だ、だなんて卑下したり蓋をする必要はどこにもなくて、越えてみた、そこにしかない〝太陽の向こう側〟のような楽しさや輝きが人生にはあると。
年齢を重ねることは怖いことなんかじゃないと、たわいもない雑談の応酬で教えて続けてくれる。
心細いとき、不安になるときには繰り返し聞きたいような、リスナーごと“ぎゅっ”と抱きしめてくれる番組だった。
わたしは、ジェーン・スーさんのことをよく知らなかった。
知りもせずに心のどこかで焦がれ続けた人に、知って今、ますます本当に焦がれている。
かつて真似をしてしまうかもしれない、と恐れた。
けれど今は「真似をしたい」と心から思っている。
たどり着けるわけなどなくても、すこしでもスーさんのような「誰かを抱きしめてあげられるひと」にわたしも近づくことができたら。
今週も駆け抜けて『OVER THE SUN』が聴きたい。
スーさんの「よくぞ金曜日までたどりつきました」の声が早く聞きたくて、溺れるように、溺れぬように、夢中で生きている33歳の毎日だ。
中前結花/エッセイスト・ライター。兵庫県生まれ。『ほぼ日刊イトイ新聞』『DRESS』ほか多数の媒体で、日々のできごとやJ-POPの歌詞にまつわるエピソード、大好きなお笑いについて執筆。趣味は、ものづくりと本を買うこと、劇場に出かけること。
llustration:stomachache Edit:ツドイ
(こちらはTBSラジオ「オトビヨリ」にて2021年7月2日に公開した記事です)
