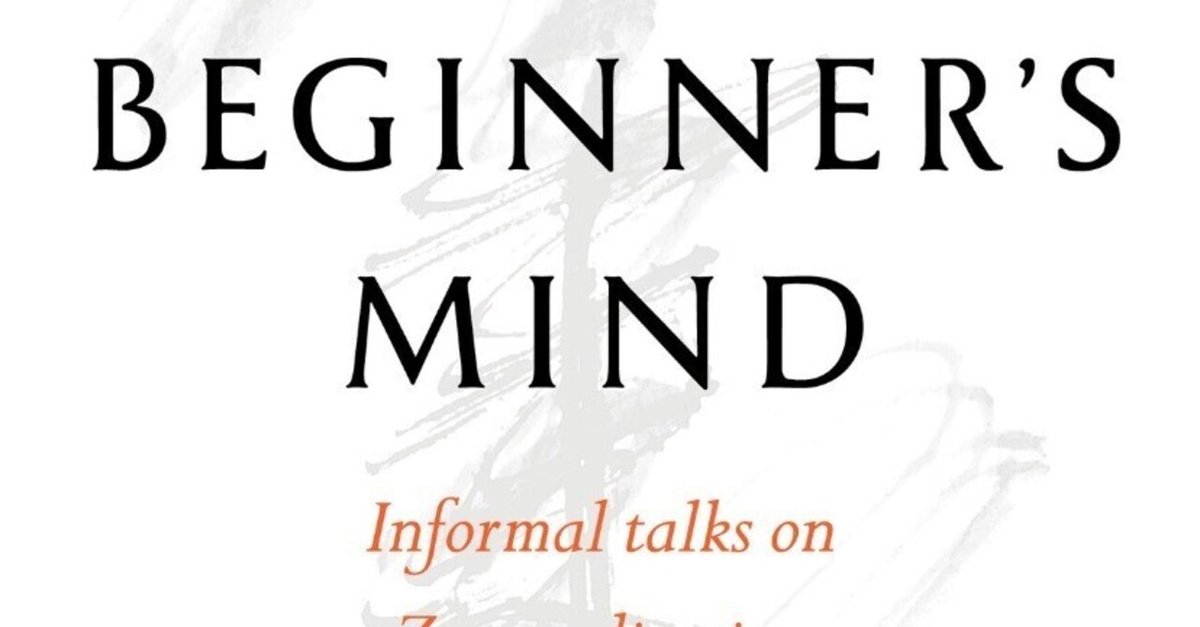
【洋書多読】Zen Mind, Beginners Mind(183冊目)
『Zen Mind, Beginners Mind』という洋書を読了しました。
これは、アメリカにマインドフルネスメディテーションや禅の思想を広めた功労者の一人と言われる鈴木俊隆という曹洞宗のお坊さんの講話集です。
アメリカ人に「禅」とはなにか、「悟り」とはなにか?座禅をすることの意味とはなにか?をわかりやすく説明したものです。
僕が読んだのは(出版)50周年記念版です。それくらい長く読みつがれているんですね。
タイトルにもある通り、「初心」こそが禅(メディテーション)をする者にとって大切だ、ということを書いています。お勉強ばかりして頭でっかちになってしまうことを戒める意味でもあり、「ただ座る」ことがもっとも悟りに近づくために必要なふるまいである、ということが書かれています。
マインドフルネスメディテーションのインストラクターとして、とてもためになる一冊でした。
英語は易しいが、禅の思想は難しい
アメリカの瞑想思想に大きな影響を与えたとして本書でも紹介されている「二人のスズキ」。お一人はこの鈴木俊隆老師ですが、もうひとりはかの有名な鈴木大拙老師です。
鈴木大拙の『日本的霊性』は、人文科学学系必読の書だと思っていて、日本人だったら読んでおいたほうがいいと思います。もちろん、僕の教養ではこの稀代の名著が何を言わんとしているのかはさっぱりわからないですが、ここにはスゴイことが書かれている、というのはわかります。
で、それがきっちりともうひとりのスズキ老師の『Zen Mind Beginners Mind』にも受け継がれているといいますか…禅の考案のような問答を書いてあるので、いくらアメリカ人にわかりやすく…と言っても結構難解です。
英語は易しいけど、書いてあることは哲学的でさっぱりわからん。そんな感じの書物でした。
で、その哲学的な書物をもって「仏教は哲学ではない、哲学と思っているうちは悟りにはたどり着けない」みたいなことを書いてあるので、凡人の僕にはもうどうしていいものやら皆目見当も付きません。
何がわからないのか分かるのが、英語力が伸びたということ
41歳で英語を学び直し初めてからはや5年、ほとんど毎日欠かさず英語学習を続けてきました。
それなりに読める文章、聞ける音源が増えてきた中で思うのは英語力伸びってつまるところ「何が分かっていないのかがわかる」ことなんじゃないか?という気がしています。
5年前、いや3年前でもいいですが…の僕なら、この文章を読んで「ちんぷんかんぷん」なことは分かっても「ではどうしてちんぷんかんぷんなのか?」がわからず、自分の英語力の低さの責に帰して落ち込む…ところだったと思います。
でもまあこれだけ毎日毎日来る日も来る日も英語を読んだり聞いたりしてればそれなりの文章は読めるようになるわけで、そうなるとこの『Zen Mind Beginners Mind』のように、内容が抽象的でわからないのか、使われている単語が難しすぎてわからないのか、あるいはネイティブの自然な表現/スラングのたぐいが多すぎてわからないのか、はたまた文法的に間違っているので読めないのか…といったことが見えてくるようになるんです。
そうなればもうしめたものです。前みたいに「読めなかったらどうしよう…」と言ってビクビクする必要もないから、思い切って読めないものにあたっていけます。読めなかったら読めなかった時に「それでも読みたい!」と思える本なのか、投げて別のに移りたいと思う本なのか、判断すればいい。
先にいろいろ考えて不安になっていても仕方がないわけで、とりあえず読む、みたいなことができるようになってきますし、わからないのはわからないまま飛ばして読む、という多読的読み方も、全然自然にできるようになってきます。
あーそう言えばこれって「先のことをごちゃごちゃ考える前に呼吸(=今やっている動作)に意識を向けなさい」「わからないものをわかろうとするのは、仏性の本質から外れた行為だ」「これをすることで何が得られるんだろう?と考えだしたらもうそれは禅ではない」という本書が主張している「マインドフルであること」の本質とめっちゃにているなぁ。
多読って「マインドフルに読むこと」という意味なのかも知れませんね。
この記事が気に入っていただけましたら、サポートしていただけると嬉しいです😆今後の励みになります!よろしくお願いします!
