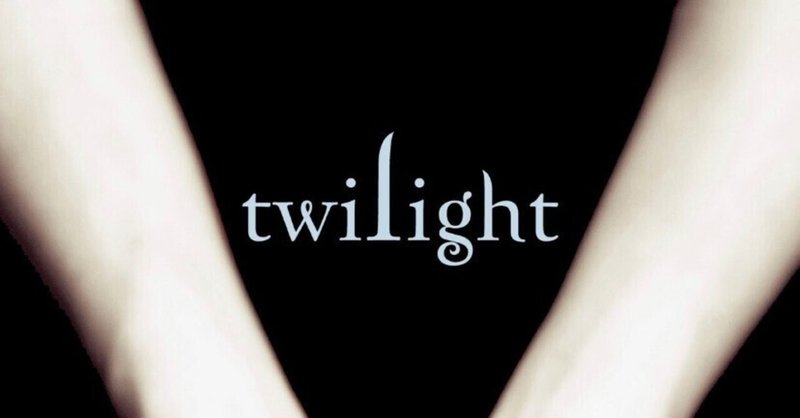
【洋書多読】Twilight(216冊目)
『Twilight』 By Stephenie Meyer
総語数: 118,975 words (by「英語多読におすすめ|定番の洋書75選」)
開始日:2023年4月8日
読了日:2023年4月24日
多読総語数:8,111,814+ ? words(※)
洋書の多読を英語学習に取り入れている「タドキスト」の間で評判のYA小説『Twilight』を読了しました。
少女とバンパイアとの禁断の恋を描いたファンタジーとして、洋書多読ファンのみならず世界中の女性のハートを鷲掴みにしたという本書。
本国アメリカではハリーポッターの次に売れたファンタジー小説として有名なんだとか。
ネットには現役の、そして元乙女による、本書に対する熱烈な賛辞が溢れていて、ベラとエドワードが織りなす恋愛ゲームが洋の東西を問わず、いかに世の女性を虜にしてきたかを窺い知ることができます。
個人的に最近はYLレベル(読みやすさレベル)7.0以上の中級洋書や、ネイティブが読むような文芸書を読めるようになってきたところなので、ぜひこの名著を堪能してみたいと思い手にとったのですが、物語の甘さとは裏腹の、とても手痛い読書体験となってしまったのでした。
かつて乙女だったことがないノンネイティブの男性が『Twilight』を読む難しさについて
僕にとって、この『Twilight』の多読は非常に手強く、難しかったです。
決して自分の英語力の未熟さを棚に上げて本書を論じるつもりはないのですが、僕が本書を読むことに感じた、英文の難易度によるところ以外の「難しさ」について、共有してみたいと思います。
といっても、単語のレベルや文法に関しては、そんなに大きな難しさを感じることはありませんでした。
少女たちだけでなくネイティブの大人も虜にするような小説ですから、小学生の子どもに向けて書かれたような読みやすい英文ではありません。しかしながら決して読解に難解さを感じさせるような種類のものでもなく、全体的には比較的読みやすい部類に入る文章で書かれていたと思います。
『ハリーポッター』シリーズの英語に毛が生えた程度、といえばいいでしょうか?おそらく、全英文の90%程度はきちんと意味を取りながら読みすすめることが出来ていたと思います。
しかしながら、読んでいてしばしば意味がわからなくなり、時に読むのが辛いとさえ思わせられることがあったのは、おそらく残りの10%に詰め込まれていたと思われる、本書のエッセンスゆえでしょう。
まず、僕は乙女であったことがこれまでの人生で一度もなかったので、女性が狂喜乱舞するような心の襞を描いた(と思われる)記述にことごとく共感することが出来ず「ふーん、女心とはそう言うものか」「ってか、めんどくさいなぁ、女性って…」としか思うことが出来なかったです(ごめんなさい)。
見も凍るような超絶美男子のバンパイアに見つめられただけで、その声を聞いただけで、ましてや手と手が触れ合っただけで激しくジャイアントスゥイングしてしまう女心に、僕の鈍感な中年男性のマインドは全くついていくことができませんでした。これが難しさの一つ目。
それから「ファンタジー特有の単語、言葉遣い」が二つ目です。人間が(本書の場合はバンパイアですが)空を飛んだり、車なんかをホイッと持ち上げたりという「現実にはありえないこと」の描写が続くと、僕はお話のプロットを簡単に見失ってしまいます。
というか「自分の英文解釈が間違ってんのかな?」と思ってしまうんですね。
これはこの次に読了することになる『Howl's Moving Castle』でも同様でしたが、とにかく話の展開が追えないというか、読んだ前の段落からいきなり展開がガラッと変わってどうしてその場面になっているのか、どうしていないはずの登場人物がいきなりそこに出てくるのかなど、混乱してしまうんですね。
魔法や超能力っぽい力の発動がそこに追い打ちをかけてきます。ファンタジー特有の単語とか情景の描写もなかなか理解するのに骨が折れます。こちらは慣れればどうにかなるのと、『Twilight』自体が高校生(と高校生に扮したバンパイア)の日常を描いていることからまだわかりやすかったですが、『Howl's Moving Castle』のような超絶ファンタジーになるともう意味がわかりません。
この辺が多読洋書の難易度を示す「YLレベル」が7.0〜8.0と振れ幅が大きいことの原因になっているんじゃないかと思います。
とはいえやっぱり面白かったです
とここまで書いておいてこんな事を言うのもなんですが、やっぱり面白かったからこそ最後まで読みおおせることが出来たんだと思います。
最後の最後、ベラの首筋にエドワードがくちづけようとするシーンは、永遠に変わらない美を愛するのか、あるいは移ろい変わりゆく、壊れやすいもののうちに美を見出し愛を感じるのか、というある種の哲学的な、つまり「永遠」を信じるのか、それとも全ては「無常」なのか?という、東洋と西洋を分かつ哲学・世界観を読者に問うているようにも思われて、思わず「おお」と唸らされました。
物語としての面白さを十分に堪能することが出来たとは到底言えませんが、二転三転する展開にはやっぱりそれなりにハラハラさせられましたし、(女心の描写は全く手に負えなかったものの)英文の難易度自体も僕にはちょうどよいもののように思われて、いい英文読解の練習にもなりました。
これだけ売れて話題になった本なので、映画化ももちろんされていますし日本語訳もでています。そちらを参照したりしながらもう一度チャレンジしてみてもいいかな?という気もしています。
この記事が気に入っていただけましたら、サポートしていただけると嬉しいです😆今後の励みになります!よろしくお願いします!
