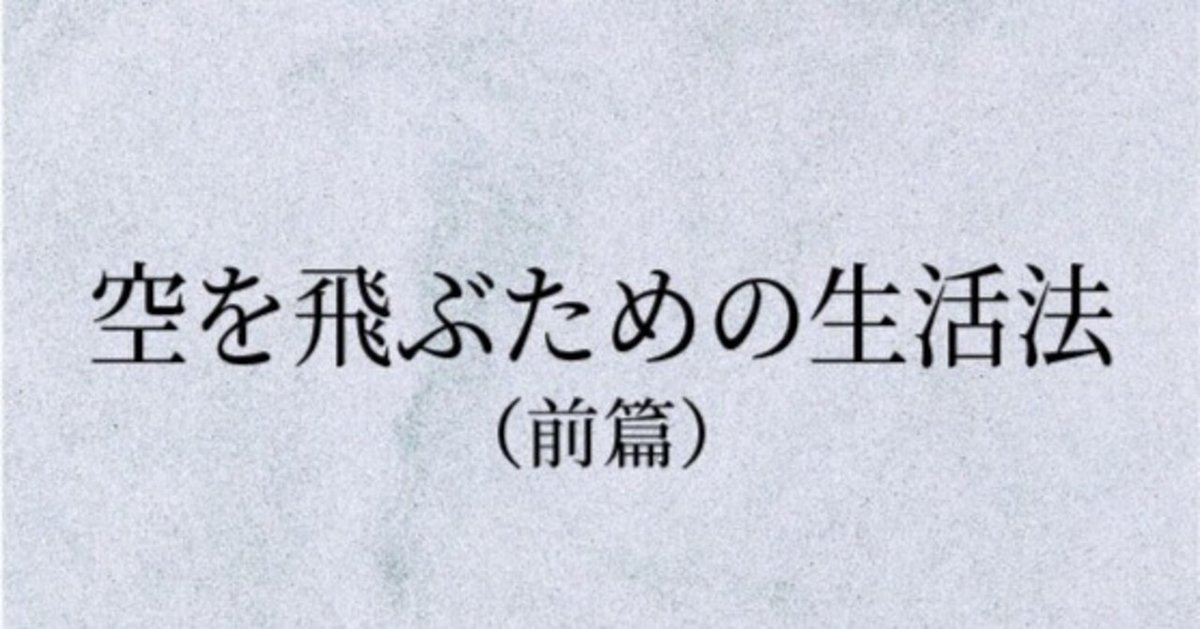
空を飛ぶための生活法(前篇)
1
おかびいつう
おかびいつう
おかびいつう
その短い残響は一ヵ月のあいだ小原の耳から離れることがなかった。地下鉄のホームで乗客の列に並んでいるとき、近所のスーパーマーケットで特売の野菜を選んでいるとき、あるいはワンルームの部屋に窮屈そうに置かれたベッドの上で目を閉じているとき、ふとその言葉が耳の奥で響き始めることがあった。蝿の羽音みたいに耳元をかすめては離れていき、忘れた頃に再び戻ってくる。日が経つと、それは何かをしつこく訴えかけるように毎日彼の頭のまわりを飛び回るようになった。あの夜の会話において、それは特に深い意味を伴う言葉ではないはずだった。何回も繰り返された言葉というわけではない。たんなる相手の口癖のようなものだと思い、小原は気にせず聞き流していた。だが流されてはいなかった。一ヵ月のあいだ、その言葉は彼の耳の裏にぴたりと張りつき、然るべきときがくるのをじっと待っていた。
その夜、仕事から帰ってきたのは十二時過ぎだった。小原はシャワーを浴びながら、途中のコンビニで久しぶりに買った缶ビールを飲んだら、すぐに眠ってしまうつもりでいた。年の瀬が迫り、残業が連日続いて、休日出勤も当たり前になっていた。小さな制作会社だから仕方ないと割り切ってはいたが、疲労はたまる一方だった。目の奥が重く、喉がひりひり痛み、背中や太腿には吹き出物ができている。風呂場から出ると、軽く眩暈を覚えた。結局缶ビールには手をつけずに、彼はベッドの上に横たわった。エアコンが温かく乾いた風をかたかたと送り出している。クリーム色の天井を見つめながら、彼はしばらく何も考えずにいた。案の定、いつもの短い言葉が耳の奥で響き始めた。耳をすまし、目を閉じて、深呼吸を繰り返しながら、気持ちを落ち着かせようとする。
「おかびいつう」
小原は素早く身を起こした。実際誰かが耳元でそう呟いたような気がした。だが部屋の中にはもちろん彼以外いない。呟いたとすれば彼しかいない。おそらく眠る寸前、無意識に口をついて出たのだろう、彼はそう思う。試しにもう一度、今度ははっきりと声に出してみる。
「おかびいつう」
誰もいない部屋にむかって発されたその言葉を耳にすると、彼はどこか居心地が悪くなった。見ず知らずの人間が突然部屋に上がりこんできたような違和感が漂う。缶ビールを手に取り、頬に当ててみた。少し冷たさが残っている。
小原は一ヵ月前のことを思い出した。金曜日の夜、出張で東京に来ていた楠から突然連絡があり、せっかくだから会おうということになった。楠は大学時代の数少ない友人だった。顔を合わせるのは十年ぶりだったが、最終の新幹線で大阪に帰らないといけないということで、一時間ほどだけ品川にある小さなバーで二人は肩を並べた。酒を軽く飲み、互いの近況を話し合い、特に何の気がかりもなく別れた。だがそれから三日後、楠は横浜駅の近くにある高層ビルの屋上から身を投げてしまった。テレビのニュースでは、週明けの正午、昼休みのサラリーマンが行き交う歩道に、突然男が空から落ちてきたということだった。ちょうど人波が途切れたときだったから誰も巻き添えに遭わなかったが、二、三秒違えば観光旅行中の韓国人の団体に突っこんで悲惨な事態を招いていただろうと、レポーターは深刻な表情を浮かべた。アスファルトの道路には乾いた血の跡がまだ残っていた。現場となったビルは眩しい空にむかって動じることなくそびえ立っている。
テレビの画面をじっと見つめていると、小原は次第にわけがわからなくなってきた。たしかにその三日前の夜、自分は楠と会ったはずだ。彼は昔のように太い腕を組んで、ときどき大きな声で笑い、ウィスキーのロックを口にしていた。しかし淡々と流れるニュース映像を見ているうちに、その夜のことが、ただの夢のように思えてきた。記憶に自信が持てない。どこかで夢と現実を取り違えてしまったようで、小原は一ヵ月のあいだ物事をうまく考えられずにいた。ただ、楠のふと口にした言葉だけが彼のまわりをいつまでも飛び回っていた。
小原は大きく息を吐いた。そしてベッドの下からパワーブックを取り出し、テーブルの上に置いて、電源を入れた。何年も前に中古で買った三世代ほど前の型のものだ。デスクトップが立ち上がるまで時間がかかる。そのあいだ彼は思い直して、缶ビールのプルトップを開けた。
おかびいつう。この言葉はそもそも日本語なのだろうか、検索サイトの入力欄にカーソルを合わせたまま、小原はキーボードを打とうとした指先をふと止めた。たとえばアラビア語の可能性だってある。もしそうならばどうすることもできない。たとえ日本語であったとしても、まだ研究段階でしか使われていない学術的な専門用語だったり、あるいはどこかの業界だけで限定的に通用しているような隠語だったりするかもしれない。とりあえず【おかびーつー】と入力し、リターンキーを押してみる。しかしそれは世界中の誰にも使われていない文字列だと判明する。検索結果ページのどこにも【おかびーつー】は表示されていない。そのかわり【おか】と【びーつー】や、【おかびー】と【つー】に分割されて使用されているページがリストアップされる。それらをいくつか開いてみた。アニメ好きの男が書いている日記や、若い体形を保つために情報交換をする掲示板などのページだった。それらの内容が楠の言葉の意味と何か関係があるようにはあまり思えなかった。【おかびいつう】あるいは【オカビーツー】で検索しても同じような結果だった。目についたページをしばらくクリックし続けていくが、手がかりになるようなことは見つからない。他の言葉と聞き違えたとは思えなかった。小原がピーナッツの殻を剥いていると、隣に座る楠の低くはっきりとした声が聞こえたのだ。何かの話が始まるのかと思って、小原は楠に視線をむけてみた。だが楠はコンクリートの壁をじっと見つめたまま、それ以上何も言わなかった。そして何かを思い出したように別の話をはじめた。
小原はビールを口にして、今度は漢字やアルファベットに変換して検索をはじめた。【岡ビーツー】【岡be2】【岡尾通】【丘微意痛】【緒か美位too】……、まったく意味をなさない文字の組み合わせを何通りも試してみる。ほとんどの文字列はどんなページとも一致せず、一致したとしても中国語のページがリストアップされるだけだった。それらのページを開き、画面をスクロールさせながら、配置された画像だけを眺めていく。たしか学生時代に楠が受けていた外国語の授業は中国語ではなかったはずだ。でも仕事上必要になって習ったのかもしれない。輸入の契約を結ぶために海外にも行ったりするのだと言っていた。
何回もクリックを繰り返していくうちに、あるページが小原の目にとまった。石造りの古めかしい建物の外観。部屋の奥まで並べられたいくつもの本棚。大きな窓からの光に照らされた長細い木の机。そんな画像がシンプルで落ち着いた色調のページに配置されている。どうやらかなり歴史の深い図書館のホームページのようだった。小原は大学にあった図書館のことを思い出した。楠はいつもそこにいて本を読むか、あるいは小説を書いていた。そのことが中国の図書館と繋がっているのかもしれない。とりあえず図書館のページを細かくチェックしていく。だがどれだけ文字を追ってみても「おかびいつう」という音と一致するような漢字の配列を見つけることはできない。そもそも中国語の発音と日本語の音読みが一致しているわけではない。そう考えると、夕方の誰もいない図書館で大きな背中を丸めながら文章を書き続けていた楠の面影は頭の中から消え去っていった。そのかわり【おかびいつう】だけが依然として宙にぽつんと残されていた。
検索を始めてから一時間以上が経っていた。缶ビールはすでに空になっている。小原は思いつくかぎり、平仮名とカタカナと漢字とアルファベットの組み合わせを打ちこんでいった。まるで桁数だけ教えられている金庫のダイヤル番号を探し当てるみたいに、一字ずつ変換していっては、開かない扉の頑丈さを確かめる。そろそろ体が眠りを求めていた。頭の中もぼんやりしている。あと五分したらパワーブックの電源を落とそうと彼は思っていた。だが【丘B2】と打ちこんでリターンキーを叩いたとき、鍵のはずれる小さな音が鳴った。
検索結果に現れたのは一つのページだけだった。タイトル名はそのままページのUR Lにされている。クリックすると、何もないウィンドウが開いた。そこには文字も画像もない。一瞬息がつまってしまうような真っ黒な画面がモニター全体に広がった。小原はマウスから手を離す。もしかしたらコンピューターウィルスにでも感染したのかもしれないと思った。だがよく見ると、ページを下方へスクロールできるようになっている。どうせ古いコンピューターだし、何か起こったら買い替えればいい、そう開き直ってページをスクロールさせていった。しかし画面には何も現れてこない。どこまでも真っ黒なままだ。フリーズしたのかと疑いそうになるが、画面端のスクロールバーはほんの少しずつ下へ移動している。小原は一瞬、海底にゆっくり沈んでいく潜水夫のような気分になった。まわりは闇ばかりで何も見えない。だが確実に海の底へ落ち進んでいる。聞こえるのは自分の呼吸音だけだ。ときどき水深計に目をやりながら、心を落ち着かせていく。やがて彼の両足は海底にぴたりと接地する。そこで一行の文字を発見する。
空を飛ぶために 丘B2
真っ黒な画面に、その一行が浮かび上がっている。そしてその下には、文字を入力できる長細い空白の欄が用意されている。
小原はぼんやりとした頭を叩き起こし【丘B2】という文字をじっと見つめながら、数分のあいだその意味を考えていた。彼に思いつけたのは一つの推測だけだった。これはこのページの名称、あるいはページの管理人の名称かもしれない。かなり奇妙な名称ではあるが、これだけ数少ない言葉の中で、載せられているべき情報の種類といえばまず自らの名称だろうと彼は思った。【空を飛ぶために】。画面をさらに見つめる。次第にその言葉は楠と繋がっているように思えてくる。楠がこの世でいちばん最後に選びとった行為――空を飛ぶ――彼は自らの体をビルの上から空中へと放り投げたのだ。
そのページがコミュニケーションを図るために存在し、【丘B2】が相手側の名称だとするなら、きっと二行目の空白欄は閲覧者自身の情報を入力するためのものだろうと小原は思った。しばらく迷ったが、結局彼は自分のメールアドレスを打ちこんだ。リターンキーを押すと、画面は再び何もない真っ黒な状態に戻った。スクロールはもうできず、ページは完全にクローズされた。このことによって新手のネット詐欺や何かのトラブルに巻きこまれるかもしれないという危惧はもちろんあった。そういった面倒くさいことが起こる可能性が少しでもあれば、彼はできるかぎり近寄らないようにしてきた。しかしその夜はひどい疲労と睡眠不足のせいで、それ以上頭を働かせることができなかった。ただその瞬間、彼は何かを求めていた。何かはわからない。そのどこかにある何かがふっと現れ、彼の指先を動かして、最後にリターンキーを押させた。あるいは単純に休養と睡眠を欲していただけなのかもしれない。どちらにせよコンピューターの電源を落とすと、彼はエアコンを止めるのも忘れて、ベッドに横たわった。そしてそのまま朝の七時まで夢を見ることなく眠り続けた。
2
私たちのページに小原がたどり着けたのは幸運だった。なぜなら彼がページを発見した四時間後、私たちはウェブ上からそのページを完全に削除したからだ。小原は私たちにアクセスしてきた最後の訪問者だった。
削除の理由は、ここ数年間でページへのアクセス数が急増し、丘B2のユーザー数が私たちの設定した定員数に早くも到達したためであった。それは当初予測していたよりも半年ほど早い結果だった。丘B2へのアクセス方法はウェブ上にだけ存在している。他のどのサイトにもリンクされていないし、他の媒体を通じて告知も宣伝も一切おこなっていない。ユーザーが丘B2のことを第三者に口外することについても原則的には許可していない。もし口外したとしても、新たなアクセス者に対してはその身元や人間性などを徹底的に調べ上げ、丘B2のユーザーとして適正な人物かどうかを厳密に判断している。つまりほとんど誰にも発見されないような小さな扉にもかかわらず訪問者が続々と増え、しかも彼ら・彼女らの多くは私たちの審査をくぐり抜けられる資質を備えていた。
定員数を制限するのはユーザーを確実に管理するためである。現状よりユーザー数を増やす予定はないし必要もない。私たちは営利団体ではなく、ユーザーから料金を受け取っているわけではない。料金を受け取らなくても、丘B2を運営していくだけの充分な財が私たちにはある。ユーザーとのあいだに金銭を介しないこと。その前提がこの場所では重要な意味を持つ。
そのかわり、各ユーザーの個人情報を私たちは完全に把握する。何らかのきっかけでページを発見してアクセスしてきた者が現れると、まずその人物に関するあらゆる情報を可能なかぎり手に入れていく。私たちが全力を尽くし、時間をかければ、どんな些細な情報でも知り得るのだ。学歴、職歴、信仰、生い立ち、交友関係、犯罪歴から、年収、ペットの名前、定期券の有効期限、指輪のサイズ、車検証の番号など本人さえ憶えていない情報や記憶まで手中にすることができる。そのようにして金銭の代わりとなる信用を見定めていく。小原薫――彼の打ちこんだメールアドレスと通信経路に残ったIPアドレスを手がかりにして、私たちは彼についての情報を一つずつ手繰り寄せていくことにした。
男。三十二歳。生まれ育った大阪にはもう何年も帰省していない。不景気の時世もあって、大学を卒業した後は比較的求人率の高い東京の会社に就職することにした。それから十年のあいだ印刷業や編集制作など三つの会社を渡りあるいた。仕事内容はすべてDTPオペレーションだった。好きな仕事というわけではないが、朝から晩までマッキントッシュに向かい続けることは苦痛でなく、むしろ彼の性格に合っていた。誰かに偉そうにしたり、媚びたりする必要はなく、多くのことを話す必要もない。話しかけられたら答えるが、自分からは必要なこと以外ほとんど話さない。ときには一言も話さずに一日を終えることもある。物静かで、事を荒立てることを好まない。ミーティングではいつも端の席に座り、聞き役にまわる。あいつはいつも傍観者だなと自分の陰口が交わされているのを耳にしたときは、気づかれないようにその場を通り過ぎた。年収は約四百二十万円。経済的にあまり余裕のない生活だ。週に一度外食をするだけで、ほぼ毎日自炊している。健康を気遣って、肉は買わずに野菜ばかり食べている。小田急線沿いの古いマンションに住み始めてからは五年が経つ。管理人はいつも不在で、エレベーターは風邪をこじらせたみたいにがたがたと震えている。間取りは1K。部屋にある電化製品は一昔前のものばかりだ。洋服も中国製の安いものが多いが、ワンシーズンのうち必ず一着は質の良いものを買うようにしている。煙草はすんなりやめられた。ニュース以外はテレビをつけないかわりに、映画や音楽を鑑賞する時間が多い。趣味といえるほどではないが、地図を見るのが好きだ。例えばポケットサイズの地図を開いて、都内のある町を構成している道路状況を細かく調べたり、一つの道がどこの町まで伸びているのか、あるいは途中でどこの道と繋がっているのかを調べたりする。その巨大で不規則な交錯図を頭の中でイメージしていると、なぜか彼はリラックスでき、よく眠ることができた。精神衛生上、他人の悪口を言わないようにしているし、誰のことも憎まないようにしている。親しく付き合っている友人はいない。自分は不幸なのか幸福なのか、金を持っているのか持っていないのか、あるいは友人が多いのか少ないのか、そういった種類の基準は彼にとっては重要でなかった。彼の生き方、それは消え方であった。そこにいるのに、いない。その中にいながら、いつのまにかこっそり消えている。ガラスのむこう側に彼はいる。そこで酸素を吸い、二酸化炭素を吐いている。
半年前まで彼には付き合っていた女がいた。ウェブデザイナーの広田汲子は小原より五つ年下だった。二人は仕事の関係で知り合った。週末には映画館や買い物に行き、落ち着いた店で食事をして、そのまま小原の部屋に泊まっていくこともあった。二年のあいだ関係は平穏で順調だったし、年齢的にも結婚の話が出てもおかしくはなかった。しかし一方で、汲子はもう小原と会わないことを決めていた。はっきりとした理由は彼女自身にもわからない。ただ今のままいつまでも彼と一緒いるということがうまく想像できなかった。小原は汲子からそう電話で告げられた。まるでヘッドフォンから長く静かに流れていた演奏が突然ぷつんと絶たれたような気分だった。彼はその夜、一人でステーキハウスに入った。そしていちばん高価なサーロインを注文して、皿の上を見つめながら、ひと切れずつゆっくりと咀嚼していった。久しぶりに口にした牛肉は舌の上で柔らかく溶けていくばかりだった。
小原がユーザーとしての資質を備えているのか、私たちは判断を下そうとしていた。彼が丘B2に入会することを積極的に希望してきたわけではないことはもちろん知っている。彼は私たちに関する情報を一切持たぬまま、たまたまアクセスに至った。だから彼のアクセスを無視することはできる。あるいは私たちからのメールを受け取ったとしても、彼は何の反応も示さないかもしれない。それならば彼に関する調査をすぐに打ち切り、はじめから小原薫という男は存在していなかったとする方が、より有効な時間の使い方になるのかもしれない。だが同時に、私たちは知っている。私たちが捉えているよりも人生は思いがけぬものであり、ある場合には光がまったく届かない深い領域で人間同士を厄介なほど絡み合わせていることを知っている。かつてユーザーであった楠礼次の思いがけない死が小原薫を囲むガラスの壁を静かに震わせていることを、私たちはすでに知っている。
3
大晦日、三十分だけ雪が降った。買い物に出かけようとしている親子連れやトラックから荷を降ろしている宅配便のドライバーは、そのあいだ熱心に空を見上げていた。小原の部屋のスピーカーからはクラシックギターの演奏が流れていた。ちょうど彼は新聞を広げて足の爪を丁寧に切り揃えていたところで、窓の外の変化には気づいていなかった。
ページを発見した翌日から、小原は毎日受信メールをチェックし続けていた。頭のまわりを飛び回っていた「おかびいつう」の響きはもう聞こえてこない。そのかわり送信したアドレスの行方が気がかりだった。かなり奇妙なページのつくりだったし、結局卑猥な勧誘メールなんかが返ってくるだけのことかもしれない。しかし楠が死んだことと何か関係がある可能性も否定できない。そう考えると彼はどんな反応が返ってくるのか知りたかった。部屋に帰ると、すぐにパワーブックの電源を入れた。だが毎日確認しても、それらしきメールは一向に返信されてこない。アドレスを入力し間違えたのかもしれないと思い、もう一度検索してみたが、すでにあの真っ黒なページはどこのサーバーにも存在していなかった。
そのあいだも汲子からのメールはいつものように届いていた。会わなくなってしばらく連絡を取り合っていなかったが、あるときから彼女は短い文章を送ってくるようになった。たいした内容ではない。気がついたことをメモにしたような数行のものを、一ヵ月に一度ぐらいのペースで送ってきていた。ひどい喧嘩別れをしたわけではないし、二年付き合っていたのだから、当分はこんなやりとりを続けていくのかもしれないと小原は思った。汲子のメールに気づくと、彼はいつも指先を少し緊張させてクリックする。
このまえの電動自転車はなんだか気持ち悪かった。
坂道を上ろうと、スイッチを入れたとたん
知らない人たちがわっと集まってきて、みんなで荷台を押してくれて
勝手に自転車が進んでいくみたい。
商店街は人だらけです。よいお年を。
小原はコーヒーカップに口をつける。電動自転車。いつのまに彼女はそんなものを買ったのだろう。以前のメールをさっと読み直してみたが、どこにも「電動自転車」という単語は見つからない。汲子からのメールは断片的なものが多かった。内容も相手が小原である必要はないし、特に返信を必要としないものにも思える。だが彼はとりあえず返信の文章を打ち始める。
今月はやっぱり忙しかった。いろいろイレギュラーもあったりして。
こんどの正月も、たぶんいつもどおりです。
それだけ打って、そのあとが続かない。他に書きこむことが思い浮かばない。頬杖をつき、自分の打ったつまらない数行を目で追っていると、ただそれは自分自身への確認であることに気づく。
――こんどの正月も、たぶんいつもどおりです。
ふいに、汲子と付き合っていた二年という時間が下手な嘘みたいに薄っぺらに思えてくる。唯一、最後の電話で耳にした汲子の冷静な声だけが本当らしく響いてくる。
送信者名「丘B2」からのメールが届いたのは、年が明けてからだった。その日の午後、小原は床屋に行き、駅前の本屋で雑誌を何冊か買い、翌日から始まる仕事のためにクリーニング屋でジャケットを受け取った。部屋に戻ると、パワーブックの電源を入れ、洗濯物を取りこんだ。受信に気づいたのは、冷蔵庫に残っていたブロッコリーを茹でるために湯を沸かしているときだった。件名は「空を飛ぶために」。彼は反射的にカーソルを合わせて、クリックした。
あなたのコードは【乃木坂】です
1月15日 20時
ブルーヒルズB201
以下の場所まで
メッセージの下にファイルが一つ添付されている。開いてみると、東京世田谷区のある一画の地図が映し出された。赤い矢印が指している建物の敷地面積はまわりのものより一回り大きい。
鍋の湯が吹きこぼれて、ガスコンロの上で音を立てている。小原は台所に行って、火を止めた。やはりこれは何か犯罪的な策略のようなものだろうか、彼は立ち上る湯気をしばらく見つめた。ブルーヒルズB201。メールが指し示している場所は、おそらくマンションか雑居ビルなのだろう。本棚から地図を出し、世田谷区のページを広げてみた。何度か調べてみたことのある地域だった。高級住宅街の中にある中層の建物、そこの地下二階にある部屋。メールの情報からはそこまでしか推測できない。ただ誰が想像しても、その部屋に老若男女が集まって、肩を組みながらエーデルワイスを歌っているような牧歌的な光景は思い浮かばないだろう。
空を飛ぶために――その言葉から、小原はドラッグのようなものを連想したが、その可能性は低いとも思っていた。もしドラッグを売り買いするなら、インターネットのような足がつきやすい方法はとらないはずだ。とにかく何か特殊なことがその部屋でおこなわれている、それ以上の光景は思い浮かべることができなかった。
結局小原は返信することにした。アドレスを送信してからすでに一ヵ月近くが経っている。その一ヵ月のあいだに自分の身元が引きずり出された可能性もあると彼は考えた。機密性の高い集団で、相手の身元をある程度調べた上でメールを出しているのかもしれない。たったメールアドレス一つでどこまで個人を特定できるのかわからないが、もし「丘B2」という存在が自分のことをすでに知っているのなら、この時点でやりとりを絶ったとしても遅かった。自分はもう最初の一歩を踏み出している。しかし次の一歩を踏み出す前に、彼には質問しておきたいことがあった。それはここしばらく煙のように漂っていて、いくら考えても掴むことができないことだった。彼はそれを文章にした。
なぜ楠はビルの屋上から飛び降りなければいけなかったのか?
その一行だけを打ちこんで、小原は返信ボタンをクリックした。そして台所に戻り、もう一度湯を沸かして、ブロッコリーを茹でた。パスタも準備していたのだが、食欲の半分は手品にかけられたようにどこかに消えていた。ブロッコリーにドレッシングをかけただけで夕食を済ませると、食器を洗い、風呂に入った。それからベッドに入るまで何回か受信を確認してみたが何も届いていなかった。彼は自分の打った一行を読み返してみた。やはりそれは誰かにむけての質問というより、たんに自分自身への問いかけでしかないように思われた。
――なぜ楠はビルの屋上から飛び降りなければいけなかったのだろうか?
4
楠の死の原因に私たちが絡んでいるかもしれないと小原は疑っていたようだが、楠礼次が自ら命を絶ったことは私たちの管理範囲を超える出来事だった。彼のコードは【江坂】。ユーザー歴は十年近くで、彼ほど私たちが提示したルールを頑なに守っていた者はいなかった。ユーザーの中でも私たちが大きな信用をおける人間の一人だった。そして彼のように、現実の空にむかって自分の身を投げた者はそれまで誰一人としていない。
楠が死んだ直後、私たちは彼に関する情報を久しぶりに引っぱり出した。大阪の裕福な家に一人息子として生まれた彼は、小さい頃からすでに優秀だった。科目ごとに一人ずつ家庭教師をつけられ、模擬試験の成績が上位から落ちることは決してなかった。運動神経も抜群で、小学生の頃は少年野球に通い、中学から大学を卒業するまでは大柄な体格を活かしてラグビーで汗を流した。快活な性格で、人当たりも良かったので、彼のまわりにはいつもクラスメイトたちが集まっていた。高校では生徒会長を務めて、教師からの評判も高かった。父親もそんな息子に満足していた。百人以上の社員を抱える繊維関係の貿易会社を一代で築いた豪放な父親は、息子に後を継がせるために文武両道の教育を厳しく徹底的に仕込んできた。一度、息子が十五歳のときに中学校の友人たちと一緒に家出をしたときは、警察署の前で息子の頬を何回も殴りつけた。
父親の知らないところで、楠がひそかに心を傾けているものがあった。家族が寝静まった真夜中、彼は机にむかって小説を書いていた。子供の頃から小説を読むのが好きで、特に海外文学を多く読み漁り、いつかは自分もオリジナルの物語を書いてみたいと考えていた。そんな想いもあって、大学の入学願書を提出するときは父親の意向に背いて文学部を選んだ。父親からは法律や経済などの実学を専攻しろと言われていたが、彼は断固として首を横に振った。家出をした十五歳以来、二度目の反抗だった。その頃には彼の体は父親より一回り大きくなっていて、六法全書を破り捨てられるぐらいの筋肉はついていた。静かで揺るぎそうもない息子の目に青臭さを感じながらも、父親はそれ以上何も言わないことにした。
大学でも楠のまわりには多くの友人が集まった。ラグビーの対抗試合では一年生ながら多くのトライを決め、喝采を浴びた。しかし彼自身は以前ほどまわりの者に多くを語らないようになった。そしてあまり笑わないようになった。人が大勢いる場所は避け、できるだけ一人でいるようにした。他人との付き合いが面倒臭くなったというよりも、自分自身に飽き始めていた。自分はひどくつまらない人間で、ひどくつまらない人生を送っている、ふとそんなふうに思えてくることがあった。誰と会ってもみんな同じ人間に見え、何を食べても同じ味に思えた。
小原と知り合ったのはその頃だった。空席だらけの心理学の講義で、いつも頬杖をついていちばん前の席に一人で座っている彼に声をかけたのがきっかけだった。真面目そうで、背はすらりと高く、鋭く尖った顎で穏やかな話し方をする。いつも地味な服装をしているせいか、しなやかに動く白くて長い指が妙に目立っていた。楠は小原を誘って、一緒に飯を食べたり、酒を飲みにいったりした。ほとんど楠が喋り、小原が興味深そうに相槌を打つことが多かった。しかし小説や映画の話題になると、小原がそのような分野に深い知識を持っていることに楠は感心させられた。そして楠もそれまで口にする機会のなかった考えを披露することができた。
小原と話していると、楠はなぜか落ち着いた心持ちなることができた。馬鹿な話をして大声で笑い合うことはないかわりに、美術館の中を進みながら小声で言葉を交わすような静かな親密さを感じることができた。それまでまわりに集まっていた者の中には決していないタイプの男だった。小原はどこか俺の心を捉えるものを持っている、楠はそう感じていた。たしかに小原の中には誰も入っていけない部分があったが、ふわりと押し戻されるような素っ気なさも楠にはどこか心地よかった。
卒業を控えた年のことだった。それまでひそかに書かれていた楠の小説が新聞社主催の新人賞に選ばれた。それほど有名な賞ではなかったが、現役の大学生が受賞したというニュースは広まり、学内はその話題で持ちきりだった。少部数だが単行本にもなり、出版社はこれからもっと話題になるからと早く次の作品を書くように促した。楠のまわりには以前よりもさらに多くの者たちが近づいてきたし、受賞の話はもちろん彼の父親の耳にも届いていた。
ある夕方、二人は大学の図書館で時間を潰していた。ほとんどの学生はもう帰宅していて、少し離れたところに五、六人の男女のグループが喋っていた。ときどき憂鬱そうな咳払いが館内に響きわった。憂鬱そうにしているのは楠だった。
「あかんわ」楠は芝居がかったように呟いた。
「どうした」小原は手元の映画雑誌から顔を上げた。
「もう終わりや」
「だから何」
「ひどい目にあった」楠は低く小さな声で言った。「朝の電車でずっと吊り革を握ってた。誰も席を譲ってくれんかった。前途有望な新進作家が目の前にいるのに」
小原は笑った。「それは失礼や」
「またぎにでも間違われたかな」楠は微笑んで、太い腕を組んだ。「でもほんまは大したことじゃない。ただ、親父が腹を立ててるだけや」
「へえ」
楠は腕組みをはずして、今度は顔の前で両手を組んだ。「四年間何も口出しせえへんかった。それやのに陰で何を勝手なことしてるんやって。毎日怒鳴り散らしてるわ」
「あんまりやな。読んでもないのに」
「読むわけないよ。そんなものが家にあったら、窓から投げ捨てるやろう。そもそも小説なんて読む柄じゃないし、人生にそんなものは役に立たんと思ってるから」
「極端な意見やな」小原は小さく笑った。
「昔からそうや。とにかく絶対俺に後を継がせる。それは俺が生まれる前から決まってたことやし、今さら他の仕事に就くなんて選択肢はどこにもない。たぶん親父は人を思いどおりにするための方法を一つ残らず知ってるな」
男女のグループの話は盛り上がっているようで、たまに誰かが興奮して奇声を発した。すると飼い犬を制止するように他の者が注意して、申し訳なさそうに二人にむかって頭を下げた。
「小説を書きたいとは思ってる」グループの方を見ながら楠は言った。「書きたいとは思ってるけど、わからんな。もし親父がいなかったら、この頭と体は出来てなかったかなと思うときもある。ある意味では親父に作り上げられたものやから」
「それもちょっと極端やな」
「そりゃあ親子やから」楠は冗談めかした。「ただ、親父のものじゃないものもある。ただし俺のものとも限らん。ときどき白くて柔らかいものが勝手に体の中を動くねん。結構気持ち悪いもんや。そいつがこの指の中に入って動かしてるような気もする。どう思う?」
小原は肘をついてしばらく考えて「楠の飼ってる幼虫のことはよくわからんけど」と冷静に言った。「楠の小説には興味があるよ。心ひかれる場面もある。これからも読みたいと思う。続けていくには充分価値のあることやと思うけどな」
「貴重な意見や」楠は言った。「ありがとう。うれしいわ」
楠は視線を外した。視線の先には小原の美しい指があった。彼は小原の指を眺めるのが好きだった。その手が小原から切り離されて、ひとりでに動き始め、スケート靴のように滑らかに自分のもとに近づいてくるところを想像していた。窓の外では風が木の枝を強く揺らしている。だが楠にとってその風景はどこか違う世界のことだった。
「就職はどう?」楠は訊ねた。
「たぶん東京かな」
「東京?」
「東京でしか決まりそうにないな」
「ほんまに」
「厳しいし、仕方ないな」
「それでもいいんか」
「せやな。どこでも同じかな」小原は笑った。
小原が東京で就職するということを聞いて、楠の鼓動は早まった。動揺を抑えることができず、早々に小原と別れた。
小原と知り合ってからそれまで、彼はまだ自分の本当の気持ちを認められずにいた。最初は自分でもよくわからなかったが、小原と会い、言葉を交わし、酒を飲んでいるうちに彼の中で何かが脈打ち始めた。それはときどき彼の心を切り、彼の頑丈な肉体を切った。彼は戸惑い、頭を抱え、両腕を抱えるしかなかった。こんなことはただの妄想にすぎないと強引に思いこもうともした。だが小原への想いは少しずつ形作られていき、いつのまにか手のひらに乗せて、はっきりと触れるぐらいになっていた。あとはそれにサインをして認めさえすればきちんとした居場所が確保される。だがやはり彼はその想いを再び暗い奥底に葬り去ることにした。そんなものを誰かの目の前で、ましてや小原の目の前で明らかにするわけにはいかない、楠はそう思った。それでいいのかもしれない。もう二度と小原に会うことがあるかどうかもわからないし、話をややこしくする必要はない。こんなことはたいしたことではないのだ。捨てるべきものを捨て去り、残ったもので生きていくだけのことだ。
卒業後、結局楠は小説を書くことをやめ、父親の会社に入ることに決めた。彼の書いた小説はその後特に好意的に迎えられることもなかった。出版社の話題づくりは失敗に終わり、楠の受賞は砂浜に落ちた砂のように誰の記憶からも消えていった。小原が東京へ発った後、彼と小説のことをきっぱり忘れて、楠は仕事に打ちこんだ。毎日誰よりも遅くまで残業し、誰よりも早く仕事を覚えた。父親もそれまで以上に彼に厳しく接するようになった。彼が父親に反抗することはもうなかった。ただ黙々と働いた。そうすることで残りの自分自身を使い果たしてやろうと思った。だがそれでも、彼の中の白くて柔らかいものはまだ葬り去られることなく、暗い奥底でうごめいていた。それは彼の皮膚を食い破り、なんとか外側へ飛び出したがっていた。
そしてある夜、楠は私たちの部屋のドアを開けることになった。
楠のユーザー登録の審査段階で、すでに小原薫の名前は私たちの資料に浮かび上がっていた。しかしその時点では小原について深く調査することはしなかった。彼は遠く離れた場所に住んでいたし、その先楠と深く関わりあうことはないだろうと予測していたのだ。実際十年間、楠は小原と何の連絡も取り合っていなかった。二人はそれぞれの町で、それぞれの十年を過ごした。しかし楠はビルから飛び降りる三日前、小原に会うため東京へ行った。たった一時間の会話。そのあいだに楠はアクセス方法のヒントを口にした。楠がルールを破ったのは初めてのことだ。
私たちは審査をクリアした小原にメールを送信することにした。おそらく彼は部屋を訪れるだろう。私たちは慎重に、注意深く、そしてあくまで中立的に小原を迎え入れることにする。
5
一月十五日。出るものといえば欠伸しかないほど暇な一日だった。年末の忙しさはすっかり消え、眩しい日差しと暖房の風が狭いフロアをゆるやかに暖めていた。小原の隣に座る赤木は頬杖をつきながら、気持ち良さそうに眠気に身をまかせていた。ときどき電話の音で目を覚ますと、わざとらしく姿勢を正して、肩まで伸びた髪の毛先を神経質そうに細かく整えた。
「やべ、また下がった」赤木は爪を噛みながら、携帯電話の画面を見つめている。「結構下がるなあ。想定外だな。でもいいや。また買っちゃお。ここで売るわけにはいかないっしょ。強気強気」
トレーディングを始めると、赤木はいつも小声でぶつぶつと呟きだす。内容はいつも同じだ。買ったり売ったり、上がったり下がったりと同じような言葉を繰り返す。小原は隣で聞き流しながら、コンピューター内の不要なデータを整理していた。
「薬ってなんか飲んでます? 小原さん」赤木がふと訊ねた。
小原はゆっくりと赤木に視線をむける。「飲んでないな。目薬はたまにさすけど」
「ああ。目薬っすか。はは。なるほどね。メーカーはどこですか?」
「詳しくは知らないな。たまにしか使わないし」
「製薬会社って買いらしいんですよね、今。ほら、エイズとか癌とかあるじゃないですか。いわゆる不治の病っていうやつ。それにばっちり効く薬を今研究中みたいなんすよね。それでもし薬が完成したら、製薬会社が契約っていうかライセンス? みたいなもんを我先に取りにいくから、今のうちに買っとけっていう話なんすけど、正直それってどうなんですかねえ」
「さあ。そういうのには疎いからね」
「いや、俺も全然強くないんすけど、でもやっぱり買え買えっていうのはなんか怪しいっていうか。俺の指針っていうのはその逆で、みんな売りまくって、すっごい安くなってから買うんですよ。そうしたらまず損はしませんよ。少なくとも大損害はまぬがれます。固い手です。どうすっか、小原さん。株、はじめたりとかします?」
小原は首を横に振った。「まずは新聞を読まないとね」
「新聞は俺も読んでませんけどね。はは」赤木はモニターにむかって作業を始めた。「この前の正月も実家には帰らなかったんですか?」
「ああ」小原も自分のモニターにむかった。「帰らなかったよ」
「仲悪いんすか、親と」
「なにかと忙しいからね」
「ははは」赤木はモニターを見ながら、またわざとらしく笑った。「小原さんてやっぱり、なんかおもしろいですよね。いい人だ。はは。ちょっと変わってますけど。大阪弁も喋らないし。はは」
赤木は欠伸をしたり、携帯電話をいじったり、インターネットのサイトを見たり、ときどき席を立って女子社員に話しかけたりしていた。小原はタイムカードを押す時間が来るまで、ペットショップの折込広告に使うインコの画像を細かく補正し続けていた。
小原がコートを着て会社を出ようしたとき、赤木は鞄の中からプラスチック製の小さな置物を出してきた。手足の長いビキニ姿の女のフィギュアで、遠くにむかって大きく右手を上げている。左手には〈SUN&PEACE〉と書かれたパラソルを持っている。五センチぐらいの大きさだが、精巧なつくりのものだった。
「沖縄のおみやげです。正月に行ってきたんです。やっぱ最高っすよ、沖縄。枕元にでも飾ってやってください、それ。はは」
土産にしては何の包装もされていなかったが、とりあえず小原は礼を言い、ズボンのポケットにフィギュアを突っこんだ。赤木は頭を軽く下げ、にやりとしながらモニターに視線を戻した。
結局、小原が送った質問のメールには何の返事も返ってこなかった。何の返事もない相手に対して、彼の取る選択は二つしかなかった。相手の指定した日時と場所に行くか行かないか。だが行かないのなら最初からメールを送ったりはしなかった。会社を出た後、彼は地下鉄に乗り、渋谷で降りた。そして目についた食堂で蕎麦を食べ、本屋に入って雑誌を何冊か買った。東急電車のホームは人が溢れかえっていたので、ベンチに座って電車を何本かやり過ごしてから、比較的空いている各駅停車の電車に乗った。目的の駅には十分もかからなかった。改札を出ると、スーツ姿の人々は利口な犬みたいにそれぞれの帰路についていった。小原は駅の柱にもたれて、いつも使っているポケットサイズの地図を開いた。駅の近くを大きな国道が走っていて、そのまわりを縦横に細い道が整然と敷かれている。鉄道会社が開発した典型的な町のつくりだった。時刻は七時半を少し過ぎている。小原はあらかじめペンで印をつけていた位置を確認して歩きだした。
宝石店や洋服店やレストランが並んでいるのは駅前だけで、道を進んでいくとすぐに薄暗い住宅地に入った。街灯が少なく、庭木の揺れる音が聞こえてくる。両側に建ち並ぶ家々は大規模な住宅展示場のようにどれも同じに見えた。どの玄関先にもセキュリティ会社のシールが貼られていて、防犯カメラが赤いランプを光らせている。地図に目をやりながら曲がり角を確認していると、ドーベルマンを連れたダウンジャケット姿の男が横を通り過ぎた。暗闇の中で立ち尽くす小原の全身を、男は疑り深そうな目つきで見まわした。男は小原が何をしにきたのかまったくわからなかったし、小原も男が何を思っているのかまったくわからなかった。
見かけたのはその男だけだった。角を三回曲がってT字路の突き当たりにある建物まで進むあいだ、まるで小原が通り過ぎていくのを息を潜めて待っているかのように住人たちは誰も姿を現さなかった。試しに振り返ってみたが、素早く頭を引っこめる者はもちろんいない。小原は建物の前で立ち止まり、地図を開けて、それまでたどった道筋とまわりの様子を確認してみた。目の前にあるのがたしかに目的のマンションだ。それは彼の想像よりも大きくはなかった。三階建てぐらいの高さで、壁はすべて白く、消しゴムのように横長だった。つるりとした外壁には洗面所の鏡ぐらいの窓がいくつも並んでいる。部屋がどのように仕切られているのかは見わけられなかったが、それはマンションというよりこぢんまりとした図書館を思わせた。入口の自動ドアの両側には太い柱があり、そこに打ちつけられた銀色のプレートに「Blue Hills」と小さく彫られている。何の変哲もない建物だ。高級住宅街の中にうまく溶けこんでいる。
小原は建物を見上げた。一瞬、楠が飛び降りたのはその建物のような気がした。ただそんな気がしただけだ。彼が実際に飛び降りたのは横浜にあるビルだ。ここから落ちたとしても手足を骨折するぐらいだろう。それにこの場所で楠がむかったのは屋上ではなく、地下のはずだった。地下への階段は自動ドアの脇にあった。入り口の構えが大きく目立っていたせいで、その横にあった細い螺旋階段をつい見落としてしまいそうになる。小原は階段の下を覗きこんでみた。やはり白く塗装されていて、幅は一人が通れるほどしかない。腕時計の針は七時四十五分を指している。小原はもう一度あたりを見回した。冷たい夜の風が吹いている。
送られてきたメールには〈B201〉とあった。だが地下一階らしきフロアはどこにも見当たらない。小原の足音だけが円柱形の空間に響きわたるだけだった。やがて階段はコンクリートの地面にぶつかり、そこから薄暗い廊下が続いている。足元を弱々しく照らす間接照明だけを頼りに小原は進んでいった。突き当たりにドアが一枚あり、インターホンの上に〈B201〉と書かれたプレートが貼られていた。そこが地下一階なのか地下二階なのかはさほど重要ではなさそうだった。鉄製の頑丈そうなドアが目の前に一枚ある、何よりもそのことに意味があるようだった。とても頑丈そうだ。何か爆発が起こってもびくともしないだろう。ドアノブ以外は、覗き穴も郵便受けもない。小原はまた腕時計を見た。さっき確認してからほとんど時間は経過していない。鼻から空気をゆっくりと吸いこみ、口から静かに吐き出す。それを三回繰り返したところで一歩前に進んだ。坂道の前でギアを入れ直すときのような気持ちになってインターホンを押した。ベルの音はしない。何の音もしない。故障ではないはずだと彼は思う。天井の隅に設置されている防犯カメラのレンズがこちらをじっと監視している。分厚いレンズが遠隔操作によって音もなく前後に動いている。小原はふと、さきほどすれ違ったダウンジャケットの男を思い出した。あの男は本当にただの通りすがりだったんだろうか、もしかしたらドアのむこうの人間は自分が今夜何の雑誌を買ったのかも知っているのかもしれない、そんなことを考えながら一分ほどドアの前で待っていた。
「ドアを開けてお入りください」
女の声がしたのは意外だった。本当に声が聞こえたことを確かめるように小原はインターホンをじっと見つめた。二十代ぐらいの若そうな声だったが、コンピューターでつくった人工的な声にも聞こえた。紙に書いた文字を読み上げているような抑揚のない言い方だった。彼はしばらくその場を動かなかった。だがそれ以上相手の声は聞こえてきそうになかったので、言われたとおりにノブを回し、慎重にドアを押し開けた。
そこは正方形の部屋だった。誰もいない。誰かがいたような気配もない。明かりはやはり間接照明で薄暗く、耳鼻科の待合室のようにひんやりとしていて窮屈そうだった。あるいは部屋のすべてが灰色に統一されていたせいでそう感じたのかもしれない。天井、壁、床、奥の部屋に通じるドア、何かもが灰色だった。部屋の真ん中にあるテーブルも灰色で、卓上用のデジタル時計も灰色だった。小原はそっとドアを閉めた。ここには灰色以外のものはないのだろうか。まわりを訝しんでみた。だがその部屋で灰色でないものといえば、小原自身とテーブルの上の白い紙だけだった。紙はメモ用紙ぐらいの大きさで、テーブルの中心に置かれている。小原はテーブルに近づき、紙を手にとって、そこに印刷されている字を読んだ。
〈空を飛ぶためのルール〉
・この部屋では声を出さない
・この部屋では時間を守る
・この部屋のことを他言しない
小原は二回繰り返して読んだ後、紙を折りたたんでポケットにしまった。〈声を出さない〉ということは、ここで誰かと言葉を交わす必要には迫られないという意味だろうか。奥の部屋に通じているらしいドアに目をやった。時間どおりに行動することは苦手ではない。他言しないことも問題ないだろう。特に知らせる相手もいないのだ。いずれにせよこの三つのルールを守りさえすれば、空を飛ぶことになるのだろうか。喉がひどく乾いている。そして唾を飲みこむ音がやけに大きく響く。
「鞄をテーブルの上に置き、コートと靴を脱いでください。できるだけ身軽になることをお勧めします。二十時二十分になったら、奥のドアを開けてお入りください」
さっきと同じ、女の事務的な声だった。どこから聞こえてきたのかわからない。どこにもスピーカーらしきものはない。玄関にあった監視カメラも見あたらない。のっぺりとした灰色の壁が取り囲んでいるだけだ。だがそれでも自分にじっとむけられている視線を小原は感じずにはいられなかった。どんな顔色をして、どんな姿勢で立って、次にどちらの手を出すのか、はるか遠い場所にいる何者かが自分を注意深く観察している、そんな固く冷たい空気が張りつめているのを感じた。彼は思わず後ずさり、入り口のドアノブに手をやった。鍵は掛けられていない。自分はここで何も見なかったし、何もしなかった。そう忘れ去って、そのまま外に出ていくことはできた。小原はドアノブを握ったまま、しばらく立ち尽くしていた。音もなく時間が進む。まるでガラスケースに囲まれている実験用のマウスになったような気分だ。
結局小原が取った行動は肩に掛けていた鞄をテーブルの上に置き、コートと靴を脱ぐことだった。彼は楠と最後に会った夜のことを思い出していた。なぜ楠が死ぬ前に自分に会いにきたのかを考えていた。なぜ、おかびいつう、などと楠が呟いたのかを考えていた。もしここで何かに巻きこまれたとしても、彼のまわりに困る人間は誰一人いない。奥の部屋に進んではいけない理由らしい理由は特に見当たらない。靴下からひやりと伝わってくる床の冷たさを感じながら、彼はデジタル時計の点滅を見つめていた。
八時十九分から六十回の点滅を数えた。小原は深呼吸をして、奥のドアに近づいた。〈この部屋では時間を守ること〉と紙に書いていた。八時二十一分に変わってしまう前に、彼は勢いよくドアを開けた。すぐに黒いカーテンが現れたことに少しためらいながら、その中に身を滑りこませてドアを閉めた。まわりには真っ暗な空間があるだけだった。何も目にすることができない。後ろを振り返ってみる。閉めたドアの隙間から少しの光も漏れていない。どんな小さな光も徹底的に排除されているようだった。試しに両手を顔の前で広げてみたが、そこにあるはずの自分の手さえ確かめることができなかった。ゆっくりと手を前に伸ばしてみると、布らしきものに触れた。最初に掛かっていたカーテンと同じ手触りだ。両腕をゆっくりと左右に回してみる。どうやら洋服店の試着室のようにゆったりとしたカーテンがまわりを取り囲んでいるようだ。指示を待つべきなのだろうか、彼は立ち尽くしていた。この状況が意味するものをなんとか掴もうとした。だがいくら考えても眼前の闇には何の意味も見つけられない。闇はどこまで見つめても闇でしかなかった。
小原は気持ちを落ち着けようと、ズボンのポケットに手を入れた。固い物体に触れて、そこに入れていたものを思い出す。赤木がくれた女のフィギュアだ。彼はそれを取り出し、手の中で回転させてみた。しばらくそのとげとげした突起に触れていると、赤木の笑った顔が思い浮かんだ。女のフィギュアというより、甲虫の死骸にでも触れているような感じだった。彼は再び腕を伸ばして、カーテンを掴み、指先でゆっくりたぐり寄せると、端を握ったところで動きを止めた。そして片方の腕をカーテンが開いたと思われる空間に慎重に伸ばしてみた。何にも触れない。むこう側に進むことはできそうだ。だが足を進める前に、彼は手にしていたフィギュアを闇の中に怖々と投げこんだ。かつん、と固く乾いた音が響いた。残響はある程度の部屋の広さを想像させた。おそらく何も当たらず、フローリングらしき床に落ちたのだろう。女の声は何も言ってこない。だがフィギュアが投げこまれ、自分がカーテンのむこう側へ踏み出そうとしているのをどこかから見ているはずだ。彼はまず右足からゆっくりと前に出していった。
崩れ落ちそうな橋を渡るように、小原は短い歩幅で慎重に暗闇を進んでいった。何よりも彼を不安にさせたのは、触れるものが何もないことだった。何かにぶつかることを防ぐために、伸ばした両腕を左右に動かしていた。しかしどれだけ動かしても、彼の細い指先は暗闇をなぞっていくだけだった。この広そうな部屋に何もないはずがない。それなのに何もない。シャツの下で汗が滲む。彼はふと立ち止まってみた。そして静かに息を吐く。あるいは部屋の中に何十人もの人間が立っていて、自分が通り過ぎるのをぎりぎりで避けながら、じっと観察しているのかもしれない。試しに思いきり腕を振りかぶって、目の前の空間を削りとるように振り下ろしてみた。だがやはり何の効果もない。ただフローリングの冷たさだけが足の裏から伝わってくる。小原はカーテンが下がっていた入り口あたりを振り返ってみた。しかし一体どの方向から自分が歩いてきたのか、すでに見当がつかなかった
「今から起こることに決して声を出さないように」
小原は反射的にまわりを見回した。もちろん何も見えない。さっきの女の声だ。音量も同じだ。だが何かが違っていた。スピーカーを通していない生の声のような気がした。女はこの部屋にいて、直接話しかけているのかもしれない。だからといってどのあたりから声が聞こえたのかははっきりしない。三六〇度が闇に塗りつぶされているせいで、音の伝わり方も普段と違っていた。
突然、ずうん、という重たい音が部屋中に響いた。まるで大型機械のコンセントを力まかせに引き抜いたときのような何かが死んでいく響きだった。やがて黒々とした濃い闇があたりに充満していった。さっきまでの闇とは明らかに種類の違う、正真正銘の完全な闇が訪れた。瞬きを何回繰り返しても、闇の濃さはまったく同じだ。瞼を開けているのかどうかさえ疑わしくなる。もし目の前にツタンカーメンのマスクがぶら下がっていたとしても、その輝きに少しも気づくことはできないだろう。小原はもう一歩も動くことができなかった。彼のまわりには恐怖しかなかった。その漆黒の中で立っていると、自分という人間が真っ黒に塗り潰されてしまったみたいに思われた。一体どこに自分の腕があり自分の脚があるのか、明確に感じとることができない。目と鼻と口の感覚が混ざりあい、何もかもが一点に凝縮されて、最後にはすべて消えてなくなってしまうような圧迫感に襲われた。
もうそれ以上進むのを諦めて、床の上にしゃがみこもうとしたときだった。小原の手を、誰かがそっと掴んだ。思わず声が出そうになって、彼は素早く手を引っこめようとした。だがその手は子兎を抱くときのような優しい力で小原の手を離さなかった。小さく柔らかな手だ。やはり若い女の手のようだったが、どこかしっかりとした意志が感じられる握り方だった。彼をどこかに連れていこうとしている。決して強引にではなく、病弱な患者を暖かい中庭へ案内するような慈しみに満ちた誘い方だった。先に進まなければいけないことを小原に思い出させるように、その手は彼の手を引いてゆっくりと進みだした。
その温かな手によって自分の手がひどく冷たくなっていたことに小原は気づいた。同時にその手と繋がっていることで、自分という人間が暗闇の中でも存在していることを確認することができた。そしてどこかに進んでいるという感覚を取り戻すことができた。恐怖は少しずつ薄らいでいった。それでも一つ、奇妙なことがあった。小原の斜め前を進んでいるはずの足音が聞こえてこないのだ。聞こえてくるのは、ひたひたという彼自身の足音だけだった。それでも相手の手は彼の手を優しく握り、どこかにむかってまっすぐ連れて行こうとしている。手だけが空中に浮いているのか、それともゴムのように長く伸びた腕が彼を引き寄せているのか。いずれにせよ彼が感じとれるのは手の感触だけで、すぐそばで他人の体が動いている気配などはどこにも感じられなかった。
手の力が止まったとき、小原も足を止めた。反射的に手が伸びているあたりに目をむけると、相手の手がすっと離れた。彼は思わず手を伸ばして、もう一度手を掴もうとした。しかしそこにはもう何もなかった。手が離れてしまうと、再び汗が滲み出てきた。歩調は遅かったものの、手に引かれながらおそらく三分以上は歩き続けてきた。いったいなぜここで放り出されたのか、主人をなくした犬のように再び不安が満ちてきた。できるなら大声を張り上げて、自分を連れてきた者を呼び戻したかった。だがその不安は、彼の左肩に再びそっと手が置かれたことですぐに静まった。落ち着いて腰を下ろしてみましょうというふうに、その手は穏やかな力で小原の左肩を押さえていた。小原は深呼吸を何回か繰り返した後、相手の手に従った。腰を下ろした場所は、どこまでも沈んでいきそうなソファか、あるいはゆったりとした大きめの椅子の上だった。座面はさきほどの手を連想させるような柔らかさだ。小原は相手の顔がありそうな場所を見上げる。するとその視線に反応したように、相手はもう片方の手を小原の右肩に置き、両手で彼の体を軽く後ろに押した。小原は相手の顔のあたりを見つめたまま、ゆっくり上半身を後ろに倒す。背もたれは四十五度ぐらいに傾けられていて、彼はその角度にぴたりと背中を合わせた。全身が優しく包みこまれているような座り心地だった。あらかじめ彼の体形を採寸して作られたのかと思うほど、肘掛けや背もたれや足置きが絶妙なバランスで彼の体を支えていた。ばらばらに解けてしまいそうだった体をぴたりと張りつけながら、彼は汗が引くのを待った。
「どうぞ充分に心を落ち着けてください。草刈り男が干草の上で眠るように」
女の声は頭の上のあたりから聞こえてきた。事務的な響きはない。羽毛が舞うような空気の揺れが耳をくすぐる。
「心を沈みこませて、深く沈黙することです。沈黙こそがこの部屋では何よりも重要になります。私たちが沈黙の底に残したものを、あなたは沈黙の底から掬いとる。沈黙の底にこそ自由に飛び渡れる空があるのです」
女の声が少し自分に近づいたような気がした。小原は二つの目を大きく見開いて、そこにある姿をなんとか認めようとする。だがどんな小さな光も認められないのは依然として変わらなかった。椅子の上で女の声を聞いていると、手足の力がすうっと抜けてきた。女の声はいつのまにか左耳のすぐそばまで移動している。
「今のように目を開けたまま、じっと暗闇を見つめていてください。それは真っ暗な空です。次第にあなたの空がそこに映し出されます。それはあなたのための空です。映し出されないなら、映し出されるまで見つめ続けてください。助言できることは一つ。あなた自身を夜の雲のように静かに漂わせることです。何の条件もなく、何の前提もなく、何の目的もなく、ただ漂わせるのです。空の下には街があります。海があり、森があり、砂漠があり、戦場があります。そこでは様々な問題が語られ、人々は手を取りあったり、傷つけあったりしています。山に見えるものは人の死体が積み重なったものかもしれないし、川に見えるものは人の血が流れているものかもしれません。しかし、よく考えてください。あなた自身はそんなものと何の関係もないのです」
やはり近くに人がいる気はしない。柔らかい声の塊だけが耳元でふわふわと浮かんでいる。小原は右手の人差し指を少し動かそうとした。だが実際に動いたのかどうか確信が持てない。汗はすっかり引いて、胃のあたりがやけに温かかった。
「安心してください。危害が加えられることはありません。あなたの背中に翼が生え、真っ暗な空を自由に飛びまわれることを願っています。おかびいつう」
ボリュームのつまみをゆっくりと下げたみたいに最後の言葉が消えた。役割を果たした女の声はそれから聞こえなくなった。
小原は椅子の上で少しも姿勢を変えなかった。瞬きもほとんどしていない。女がどこに行ったかよりも彼が気になっていたのは、全身がごく弱い力で引っ張られているという感覚だった。いつのまにか何十本もの糸が体中につけられていて、何十人もの人間が一人ずつそれらを引っ張っている、そんな感覚だ。ハンモックの上で寝転んでいるときの緊張にも似ている。例えば彼らが同時に思いきり糸を引っ張ると、自分の内側と外側が一瞬にしてひっくり返ってしまうような感じだった。
小原は夜空について考えていた。ハンモックに揺られながら、どこの空でもない架空の夜空を眺めている。それは何のためでもない空だ。誰も口出しをしてこないし、誰にも発見されることはない。いくら飛び回っても、誰にも文句を言われることはない。そんなふうに考えながら、彼は暗闇に目を凝らしていた。やがて彼は気づく。どこからか風が吹いている。弱く温かい風だ。吹いたり止んだりを繰り返しながら、彼に近づいてくる。左から右へ、右から左へと吹きぬけては、彼の足先や、彼の膝や、彼の太腿や、彼の腹を撫でていく。そして胸の上あたりまでやってくると天井にむかって一気に吹きあがる。それはやがて彼の体をそのまま吸いあげていってしまうような大きな風になった。
だがやがて、どこからか音がした。コンクリートに杭を打ちつけるような硬質な音だ。その瞬間、風は消えた。架空の夜空はただの闇に戻った。小原の体は重力という宿命を思い出し、クッションの中に深く沈みこんでいく。聞こえてきたのは心臓の鼓動だった。小原自身の心臓だ。彼の体を地上に引き戻すように、彼の心臓は硬く乾いた音を部屋中にしつこく響かせ続けていた。
6
灰色のデジタル時計は二十二時三十分を表示していた。小原薫は再び私たちに手を引かれて部屋を横切っていき、待合室に通じるドアを開けた。そして靴を履き、コートを身に着け、ショルダーバッグを肩にかけると、少し疲れた表情を浮かべて部屋から出ていった。外ではちょうど冷たい雨が降り始めていた。アスファルトの道路がまだらに濡れている。何度か試してみたものの、彼は結局その夜うまく飛ぶことができなかった。
初めて部屋を訪れたときから自由に飛びまわることができる者などまずいない。何も目にすることのできない状況に身を硬くして意識を集中できない、あるいは集中が長く続かない者がほとんどである。飛ぶためには暗闇に慣れていくしかない。何回か部屋を訪れることで、自分を暗闇に少しずつ同化させていくしかない。その夜、小原の集中力が途切れることはほとんどなかった。たしかに最初は戸惑い、心を乱していた。しかし体を横たえてからはだんだん落ち着きだし、暗闇にむかってしっかり目を見開いていた。その点では、彼は他のユーザーよりも飛ぶ才能に長けていた。
それにもかかわらず小原の体は最後まで地面を離れることができなかった。それは石のせいである。彼の心の底にしっかりと括りつけられている冷たく重たい石。私たちは彼のそばに近づくことで、その存在をはっきり感じとることができた。それはどれだけ深く沈黙し、意識を集中させても、そう簡単に取りのぞけるものではない。石はずっと前からそこにあった。最初は川に投げて遊ぶような小石にすぎなかった。しかし長い年月が経つにつれてそれは少しずつ成長し、今では両手で持ち上げようとしても微動だにしないぐらいに大きくなってしまっている。その暗く重たい存在に、小原はときどき全身に汗をかいて目覚めることがあった。ぐっしょりと濡れたシャツを脱ぎ、あらかじめ用意している新しいシャツに着替える。なぜこんなものを抱えて生きていかなければいけないのか、小原自身よく理解できなかった。ただ彼にできることは、その石に慣れていくことだった。もうどこにも動かすことができない石にもたれながら、心静かに本を読んだり音楽を聞いたり、あるいは地図を開いたりするしかなかった。そうすることで全身に汗をかいてしまうぐらいの不安や孤独を忘れることができた。つまり彼はその石とうまく距離をとりながら今まで暮らしてきたのだった。
小原がそのようなものを抱えて生きていることを、広田汲子は薄々と感じていた。彼のふとした表情や言葉の中にどこか冷たさを感じることがあったし、ベッドに入っているときに彼が朝まで寝つけないでいることも知っていた。そんなとき彼女はなぜか地震のことを思い出した。崩落した家屋から避難してきた人々が学校の体育館で眠っていたときの様子がぼんやりと思い浮かんできた。
汲子の父親はかつて神戸のテレビ局に営業部長として勤務していて、母親は短大を卒業したあと実家の旅館を手伝っていた。二人は共通の知り合いを通じて結婚し、神戸市内に新築の家を買って、二人の子をもうけた。だが汲子が生まれてすぐ、父親は東京支局への転勤を命じられ、都内のワンルームマンションで単身赴任することになった。東京での仕事は繁忙を極めたが、毎年四、五回は神戸にいる妻と二人の子供のために両手いっぱいのプレゼントを抱えて帰ることにしていた。
余計な心配をさせないためにと父親が毎月送ってきた金額は、三人の生活を以前よりも裕福にした。母親は二人の子供になるべく良い服を着せ、レストランでなるべく良いものを食べさせ、父親の残していったメルセデスに乗って旅行に出かけたりした。別に子供たちを甘やかそうというつもりはなかった。ただ父親が家にいないことへの不安をどこかで紛らわしたかっただけだった。いずれにせよ恵まれた環境の中で、汲子の兄は次々に買い与えられるテレビゲームに夢中になるような、多少わがままでのんびりとした性格に育った。汲子は真面目で大人しく、いつも母親の言うことを素直に聞く娘だった。学校でも成績が良く、県内で最も難関なエスカレーター式の女子校に入学できたことは近所でも評判になった。小さい頃から習っていたピアノは特別上手だったわけではないが、時間を見つけると鍵盤に十本の指を這わせてリラックスした気持ちで弾いていた。父親がいなくても、三人は特に問題のない生活を送っているように思えた。
汲子が十七歳になった年の冬だった。その日の早朝、何の前触れもない激しい揺れに家族三人は否応なく揺り起こされた。まるで象の大群が床下から這いあがろうとしているみたいな振動だった。三人は寝巻きのまま外に駆けだした。まわりでは同じように外に出てきた住民たちが大きな声をあげている。それはテレビのすべてのチャンネルが何日にもわたって放送するほどの大地震だった。テレビカメラは崩壊した神戸の街を映し続けた。市街地ではビルが真っ二つに折れ、橋は崩落し、高速道路は積み木のように倒れていた。ライフラインが切断されていることが判明すると、道路は渋滞し始め、線路の上に人の行列がどこまでも続いた。
汲子たちは一週間ほど近所の体育館で見ず知らずの人々と避難生活を続けた後、大阪にある父親の実家のマンションにむかった。東京からなんとか駆けつけた父親もしばらく一緒に身を寄せることなった。半年ぶりに顔を合わせた四人だったが、懐かしがる余裕はどこにもなかった。ただ慣れない生活と先行きへの不安が彼らの体を固く緊張させていた。神戸の家は地盤から崩れて斜めに傾いており、役所の人間によって「全壊」と書かれた紙が貼られることになった。とりあえず建て直す手続きをとらなければいけない。だがひっくり返った家の中をいくら捜しまわっても、大切にしまっていた家の権利書はどこにも見つからなかった。役所で調べてみると、家の名義は父親の名前ではなく、聞いたこともない金融業者の名前に変更されていることがわかった。定期預金も見事に空っぽになっている。それは父親が誰にも秘密にしていたことだった。彼は東京で複数の愛人をつくり、彼女たちとの関係のために次から次へと金を工面し、ついには家の権利書まで担保にしていたのだった。
母親は朝から晩まで泣き続け、兄と父親は顔を合わせるたびに喧嘩をした。毎日怒鳴り声や泣き声が部屋中に響きわたった。一ヵ月のあいだ、食べるものも食べないような生活が続いた。そしてついに暴力団らしき男が力まかせにマンションのドアを叩いたとき、母親は離婚を決意した。自分はこれから子供と三人で暮らしていこうと思った。父親も口にするべき言葉はすべて出し尽くしたようで、黙って離婚届に判を捺した。
そんな騒動の中、汲子だけは沈黙し続けていた。朝起きてから、誰の目を見ることもなく学校に行った。そして放課後は図書館に寄って一人で受験勉強をし、帰ってくると誰ともほとんど言葉を交わさないまま布団の中で眠った。誰も知らない秘密の場所に自分自身を隠してしまったように、どんなに騒がしいことが起っても表情一つ崩そうとしなかった。しかしたった一度、父親の不甲斐なさをきつい調子で責め立てたことがあった。二人きりでエレベーターに乗っていたときである。父親はじっと娘の率直な言葉に耳を傾けていた。だがとうとう我慢ができずつい娘の頬を平手で打った。エレベーターが一階に着くと、父親は逃げるように立ち去った。娘の方を一度も振り返ることもないまま。汲子はその場から一歩も動こうとしなかった。彼女は何もかもから切り離されてしまっていた。ドアが閉まり、エレベーターは汲子を閉じこめたままゆっくりと上昇していった。
母親の実家である旅館も半壊状態になっていたため、三人は西宮で小さなアパートを借りることにした。荷物はほとんどなく、夜になるとリビングに三組の布団を並べることにした。ある日、汲子は東京にある美大に願書を出したことを母親に伝えた。とても冷静で、落ち着いた声だった。自分にはやりたいことがあり、それは東京の大学でしか学べない。奨学金を申請して、生活費はアルバイトで稼ぐ。だからどうしても東京に行きたいと。それまで自分のもとで従順に育ってきた娘が突然そんなことを言い出したことに、母親は戸惑った。また一人家族が減ることを思うと眠れない日々が続いた。だが娘の人生を自分の思いどおりにするわけにはいかない、母親はそう自分に言い聞かせた。
だが実際、汲子の心の中には何もなかった。やりたいことなど本当はどこにもなかった。とにかく神戸から離れ、家族から離れたかった。地震が起き、乱暴な言葉が頭の上で飛び交っているあいだ、どこからか伸びてきた大きな手が自分の体を掴み、その場から引き離して、どこか遠い場所に連れていこうとしているのを彼女は感じていた。彼女が求めていたのは、ただの移動だった。その移動を実行できる日をずっと待ち続けていた。パート勤めの母親と頼りないフリーターの兄を残すことになっても、彼女は一人でどこかに移動することを心の底から渇望していた。
そのようなことを話したのは小原にだけだった。汲子は上京してから関西に住んでいたときのことをなるべくまわりに話さないようにしていた。出身地を訊ねられれば神戸だと答えたが、地震の話にはならないようにすぐ他の話題に切り替えた。
その日の打ち合わせが終わったとき、すでに日は暮れていた。大手の食品メーカーが売り出す新商品の販促会議に汲子も同席させられていて、そこに紙媒体の担当者として小原も出席していた。本来なら一時間で終わるような話だったが、なぜか途中でクライアントが不機嫌になって筋の通らない要望やクレームを持ち出してきた。汲子と小原の上司たちは困惑し、再検討するということで話がまとまったときには三時間が過ぎていた。現地で解散した帰り道、汲子は小原と目についたチェーン店の居酒屋に入った。二人が付き合っていることは誰にも知られていなかった。
「ねえ、さっきの会議室に何かいなかった?」汲子は突き出しの煮物を一口つまんだ後、そう言った。
「なんやろう。何かおったかな」小原はネクタイを緩めながら、首をかしげた。
「何も聞こえへんかった?」
「たぶん」
「部長たちが一生懸命話してる最中にずっと、ちゅんちゅん、って聞こえてたよ。天井の隅っこあたりから」
「ほんまに」
「うん。きっとあそこで鳥が迷ってたんやと思う」
「鳥?」
「わたしそれが気になって、打ち合わせどころじゃなかった」
「へえ、全然気づかんかったな。鳥なんて」
「最初は何も聞こえなかったけど、むこうがだんだん苛々し始めてきて、部長たちが返事に困ってきたときぐらいからかな。突然、ちゅんちゅんちゅんって、かすかに聞こえてきたんよ」
「きっと部長の泣き声やろ」
汲子は小さく笑った。「昔、小鳥を飼ってたことがあったの。白くて、くちばしが茶色くて、鳥籠に一匹だけ入れてた。学校から帰ると餌をあげて、手の上に乗せてよく遊んでたわ。その鳴き声によく似てるなあって、今日思ってたの。ほんとにそっくり」
「それは気になるな」
「でも鳥の声なんてどれも同じかな」
「今はどうしてるの」
「地震の後、いつのまにかいなくなってた」
「東京まで追いかけてきた可能性もあるね」
料理が運ばれてきた。不毛な会議に長時間付き合っていたせいか、二人とも食欲があまりなく、並べられた皿も少なかった。汲子は途中でワインを注文した。
「どっか、いいとこは見つけた?」小原は訊ねた。
「いいとこ?」
「このあいだ旅行にいこうかって言ってたから」
「ああ、そうやね。うん」汲子は何かを考えるようにグラスに口をつけ、唇を軽く拭った。「どっかあった?」
「そうやな。海外でもいいとは思うけど。今の季節やったら、スペインとかポルトガルあたりが涼しくていいかもしれへん」
「たしかにきれいそう」汲子はそう言いながら、割り箸の紙袋で箸置きを作り始めた。「ねえ、飛行機って少し速すぎない?」
小原はグラスを空中で止めて、汲子の目を覗く。汲子も小原を見つめる。大きい瞳をまっすぐ彼にむける。
「たしかに速いよ」小原はとりあえず言った。「恐ろしく速い。たまに、よくもあんな塊が空の上を飛んでるなって思うことはあるよ」
「なんか、ときどき、ついていけない気がする」汲子は小鉢の上に視線を移した。「例えば日本が舞台の話やったのに、突然『私は今モロッコにいる』みたいな一行が現れた感じ。何がどうなったのかわからへんの。目の前の景色を疑いたくなる」
「そうやね」と小原は微笑んだ。「ドアを開けて中に入って、何時間かして外に出たら、もうそこはモロッコやった。それじゃあたしかに強引やね。気持ちはまだ羽田に残ってる」
「わかる?」
「わかるよ。うん」
汲子はワインを半分ほど飲んだ後、化粧室に行った。週末ということもあって、店の中は次第に混み始めていた。若い客の団体が大声で互いをからかったり、店員たちが忙しそうに料理を運んだりしていた。汲子は鏡の前で髪を整えながら、小原が一人で頬杖をついて目の前の壁をじっと眺めているところを想像した。席に戻ると、やはり彼は想像どおりの姿勢をしていた。
「地震のときって、もうあっちにいなかったんやね」汲子は訊ねた。
「もうこっちやった」
「テレビで見てた?」
「うん。テレビでしか知らん」
「大阪はそれほどひどくなかったもんね」
「らしいね。次の日からはみんな普通に会社に行ってたみたいやから」
「両親も大丈夫やった?」
「ああ。いちおうその日に電話したけど誰も出なくて、何日か後に留守電が入ってた。心配しなくていいって。それだけ。風呂場のタイルに少しひびが入っていただけで、深刻なことは何もなかった」
「ふうん」
「でも、テレビでは毎日ひどい様子が映ってたな。なんかすごく遠い場所のような気がした。そのときそこに汲子がいたなんて、なんか信じられへんよ」
「へえ、どうしてやろ」汲子は短く笑った。
「神戸の二人は今でも一緒に暮らしてるの?」小原は体の位置を少しずらして訊ねた。
「さあ、知らない」両手で支えたグラスを見つめながら汲子は答えた。
「お兄さんはどんな仕事?」
「知らない」
「そうか」
「何も知らんわ」
少し沈黙があった。汲子は鞄から手帳を取り出し、後ろの方のページを開いてしばらく考えこんだ。
「ねえ、北の方に行ってみたい」ふと思いついたように汲子は顔を上げた。「北海道でも東北でも、そのあたりならどこでもいいと思う。とにかく電車に乗って寒いところに行ってみたいわ、わたし」
「それじゃあ探してみる」小原は頷いた。「会議室の鳥もついてくればいいけど」そうつけ加えた。
「そうやね」汲子は言った。「ありがとう」
だが結局、旅行の話が実現されることはなかった。その半年後に二人は別れることになったからだ。
小原に別れを告げた夜、汲子はホットミルクを入れ、小さな音量で音楽をかけて、長いあいだベッドに横たわっていた。いつもと同じ静かな夜だった。なぜ別れを切り出さなければいけなかったのか、その理由は自分でもはっきりと掴むことができなかった。ただ心のどこかで、捨てられたのはきっと自分の方なんだという気もしていた。きっと今頃、彼はいつもと変わらずに食事を作っているところだろう、そして食器を洗い、風呂に入って歯を磨いた後、姿勢一つ崩さずに本を読み始めるに違いない、そんなことを想像していた。
彼女は夢を見た。鳥がいつまでも頭の上を飛びまわっている。だがどこを飛んでいるのかはわからない。鳴き声だけが聞こえてくる。目の前には崩れ去った神戸の街がどこまでも広がっていた。電柱が折り重なり、砕けたアスファルトの残骸が転がっている。その中を彼女は空っぽの鳥籠を手にして、いつまでも鳥を探し続けていた。
7
夜の十一時半を過ぎていた。新宿駅の構内には雑踏が絶えまなく続いている。ふざけ合って笑い続けている大学生たち、キャリーケースを引きずって夜行バスの停留所にむかうトレンチコートの女、柱にもたれながら缶ビールと柿の種を交互に口にするスーツ姿の男、擦り切れたスポーツバッグを大事そうに抱えているホームレス。二月でいちばん冷えこんだ夜だった。吐く息は白く、風は通り魔のように耳を切りつけていく。小原はニットキャップを被り、マフラーを巻いて、手袋をはめた手をコートのポケットに突っこみながら改札を出ると、新宿通りを進んでいった。
呼びこみの店員やふらついた酔っ払いをよけながら、細い脇道に入る角まで着くと、彼はポケットから地図を出した。いつも持ち歩くようになったため、いたるところに細かい皺ができて、破れかけている部分もある。インクも色褪せていたが、いくつかのページには赤色の油性ペンによって何本もの線が引かれていた。渋谷、赤坂、六本木、池袋。まるで幾何学的な図形をいくつも重ねたように何本もの道路が赤く塗られている。それは彼が歩いてきた道を表すしるしだった。彼は目の前に伸びる薄暗い脇道を覗いた。そこに漂う冷たい空気を思いきり吸いこむと、その中を進み始めた。
新宿にはまだ赤く塗られていない道がずいぶんと残っていた。初めての道を通るとき、彼はできるだけゆっくりとその場所の光景を見定めていく。立ち並ぶ雑居ビルにはどんなテナントが入居しているのか、どんな名前でどんな色の看板を掲げているのか。建物の形と古さ、電信柱の元に積み上げられたごみ袋、剥がれかけた政党のポスター、サドルのない自転車、路上に散らばった飯粒、人影が移動する窓の光、壁越しに聞こえるカラオケの歌声、巨大な鍋で熱しているような油の臭い。そんなものの一つずつを自分の中に残していく。晩秋の紅葉を眺めていくような歩調で進む彼を、何人かの通行人が舌打ちして追い越していく。
町名が変わる地点に着くと、彼は地図に一本の赤線を引く。そして踵を返し、今通ってきた道を戻っていく。途中で分岐していた、さらに細い道に入るためだ。とりあえず一つの地域の中で交差しているすべての道を歩いていく、それが彼のやり方だった。入口と出口があり、人が通れる幅ならば、野良猫の棲み家のような路地でも入っていく。そして金網やガス管や水たまりの一つ一つを自分の中に残していく。心がけることは一つ。何も考えないこと。夜の湖のように頭の中を静かにすること。そしてその底に目に映るものをゆっくり沈ませていくこと。信号が変わると同時に人々が歩き出した。タクシーは長い列をつくり、中国語の混じったざわめきが飛び交いはじめる。誰が中国人で日本人なのか、まったく見分けがつかない。小原は虚ろな目を左右に動かしながら真夜中の東京を徘徊し続けていく。
ほとんど休むことなく歩き続ける。いよいよ体の芯が凍てついてきて、ふと気づくと、知らないうちに夜が明けている。ビルのむこうでは空が白み始めている。冷たい風に吹き飛ばされたみたいに、人も車も数えるほどしか見あたらない。カラスがごみ袋から何かを引きずり出そうとしている。駅にむかっていると、一人の若い警官が小原に近づいてきた。薄い唇で微笑を浮かべている。遠くを見るような細い目を小原から外そうとしない。
「ご苦労さん。これから帰り?」警官は言った。
「ええ」小原は息を吐くついでに言った。
「ああ、そう。大変な仕事だね。ホストの人には見えないようだけど」
「仕事じゃないんです」
「あ、そう」
「飲んだ後、始発まで少し時間を潰してただけです」
「ふうん。なるほど」
スーツを着た男が小原の横を足早に通り過ぎていった。遠くの交差点を夜行バスがゆっくりと曲がっていく。
「ちょっと訊きたいんですけどね。ここらへんで赤いマフラーをした男性って見かけなかった?」
「え」
「黒いコートに赤いマフラーを巻いて、身長は百七十センチぐらいの男の人」薄暗い部屋の中を覗きこむみたいに警官は小原の顔を見つめていた。
「さあ」小原は首をかしげた。「見かけなかったですね」
「……ちょっと変わった人とかも?」
「ええ。全然」
「ほんとに?」
小原は白い息を吐いた。「知らないな。知らないけど、今あなたの目の前にいるのは変わった人なんでしょうか」
警官は無表情に小原の顔を見ていた。「いや、そういうつもりじゃなかったんだけどさ。この近くの漫画喫茶でちょっとした問題があったもんだから、何か知ってたら教えてほしいと思っただけなんだけど」
「わからないです」小原は先を進もうとした。
「あ、そう。わっかりました。でも、もし何か思い出したら教えてくださいよ。そこの交番にいますから」
警官は無線機にむかって何かを話しながら立ち去っていった。
部屋に帰って熱いシャワーを浴びた後、インスタントのコーンスープに湯を注ぎ、エアコンの設定温度を上げ、パワーブックの電源を入れた。時刻は七時半。小原はスープを少しずつ飲みながら、地図の上に新しく引かれた赤線を一本ずつ見なおした。受信されたメールは汲子からの一件だけだ。
ピアノをもう一度習おうと
最近、そう思っています。
毎週土曜日のお昼から、近所のスタジオで。ほんとはキーボード講座だけど。
カルチャーセンターっていうのは、結構いい響きです。
健全な小市民になったような気がします。スタジオへは電動自転車で。
あいかわらず見ず知らずの無口な人たちに運ばれています。
小原はベッドに横たわり、目を閉じた。頭の中は真っ暗で、手足は濡れた木材みたいに重い。眠りの波はすぐそばまで近寄っていたが、瞼の裏の一点に集中してなんとか意識を保っていた。時計のアラーム音が鳴り響く。彼は起き上がり、スイッチを切る。部屋の電気を消し、コートを身にまとって、鞄を手にすると、月曜日の会社にむかった。
その日は朝からトラブル処理に追われることになった。刷版用のデータ不備の修正、すでに納品していた車内広告の誤植のクレーム処理、そしてスケジュール調整のミスでクライアントに提出するプレゼン用の紙面を至急作成しなければいけなかった。営業チームの電話は鳴りっぱなしで、小原や赤木はデータの作り直しのためコンピューターにかじりついていた。どれもこれも原因のはっきりしないトラブルだった。二十人足らずの社員数で、業務の流れは切符を買って電車に乗るぐらい単純なものだ。それぞれの担当者はきちんとチェックしていたはずだし、そのようなミスはそれまで一度も起こったことがなかった。誰もが腑に落ちないような表情を浮かべながら対応に追われていた。
小原たちが昼食をとったのは二時を過ぎていた。とりあえず目途がついたところで、赤木がめずらしく誘ってきた。二人が入ったのは会社から歩いて十分ばかりのファミリーレストランだった。
赤木は疲れた様子で窓の外に目をやり、煙草をふかしていた。「最近やけに顔色いいっすね、小原さん」
「そうかな」小原はランチサービスについていたコーヒーを口にした。
「なんか肌に張りがあるっていうか、睡眠もきっちりとって、毎日充実してるぞっていうオーラが出てますよ。なんか趣味でも始めたんすか?」
「いや、別に何も。睡眠もそんなにとってないけどね」
「でも疲れてる様子は全然ないですけどね。前とたしかに違いますよ。寝る時間けずって、何か怪しいことでもやってるんじゃないですか? はは」「ほんとに何もしてないよ」小原は首を横に振った。
「へえ。でもナチュラルにその状態って、なんかうらやましいですね。俺なんか最近ほんと駄目なんです。女とは連絡がつかないし、東証の方もあんまりぱっとしないし。それと明日から有給取ってスノボに行く予定だったんですけど、今日のトラブルでどうやら休めそうにもないですし。そのうえ便秘気味。まじでむかつきますよ!」
赤木の甲高い声が空席だらけの店内に響く。彼の眉毛が忙しそうに上がったり下がったりするのを小原は眺めていた。
「今日のって誰のせいなんですかね」赤木は溜め息をついた。
「さあ。初歩的なことだし、誰も確認を忘れるはずはないと思うけど」
「営業の人ら、鬼気迫ってましたね。トイレで睨まれましたもん、俺。おまえのせいかみたいな感じで。事務の女の子もこそこそ噂立ててるし。それとなくこれは誰それの責任だよねって話してましたよ。かなりジメッてましたね」
「でもとりあえず、なんとかおさまりそうだね」
「それでも会社的なペナルティはきっと請求されますよ」赤木は眉間に皴を寄せ、灰皿に煙草を押しつけた。「俺から見れば、たぶんチーフあたりが怪しいんじゃないかと思いますよ。あの人、いつも最初の打ち合わせとか派手な場所にだけ顔出して、そこで調子のいい、でかいことばっかり言ってるでしょ。あとで帳尻合わせに苦労するのはいつも下の人間ですよ。吹けば飛ぶようなこんな小さな会社で、ブランドのスーツ着て、おれが仕事とってきてるからお前らが食えていけるんだみたいな態度でしょ。ほんとにろくでもない馬鹿ですよ。それでも社長とかは、次はやっぱりチーフにまかせたいと考えてるんですよね。あの社長ものん気だし、人を見る目もないし、何もできないから。他のみんなもいつも毒づいてますよ。この会社が潰れるのも時間の問題だし、早く次の仕事見つけなきゃって」
赤木はそれまでそういった話を何回も繰り返し話していて、小原も繰り返し聞いてきた。その話を聞くとき、小原はいつも動物園の檻の中で甲高い声をあげて暴れまわる猿の姿を思い浮かべた。
「赤木くんは?」小原は訊ねた。「辞めるつもりなの?」
「俺っすか? そうっすね。ここまで文句言っといてあれなんですけど、正直どっちでもいいんすよ、俺。みんなみたいに生活がかかってないぶん、あんまり深入りしないようにしてるっていうか。むかつくとこはむかつきますけど、でもそれだけ。あとは適当にやることにしてます」
「副業でもやってるの?」
「ほら俺、株やってるでしょ。だから実際仕事してなくても、全然暮らしていけるんすよね。今流行のライフスタイルっていうやつです。会社に来るのは、ただ世間的な体裁と小遣い稼ぎのためっすよ」
店員がテーブルに近づいてきて、二人のコップに水を注いだ。そのとき早いテンポの着信音が鳴った。赤木はジャケットの内ポケットから携帯電話を取り出し、話し始めた。相手は親しい友人のようだった。それまでとは違う荒っぽい調子の言葉が次々飛び出してくる。小原はふと前に目をやった。赤木の携帯電話からストラップがぶら下がっている。以前彼がもらった沖縄土産のフィギュアと同じものだった。
「これ、ちゃんと飾ってくれてます?」電話を切った後、赤木はフィギュアをつまんで訊ねた。
「ああ」小原は頷いた。「テレビの横に」
「ほんとかな、ははは」赤木は先に席を立った。
会社を出ることができたのは九時を過ぎた頃だった。すでに指定された時間には遅れていたが、それでも小原は渋谷で電車を乗り換え、いつもの駅で降りると、駆け足でブルーヒルズにむかった。人のいない住宅地を通り、地下への螺旋階段を降りて、インターホンを押してしばらく待った。だがいくらドアの前で立っていても、何の声も返ってこなかった。ノブは左右どちらにも動かない。監視カメラはあいかわらずじっとこちらを見つめていた。そこには洗濯機の底を見下ろしているような無関心な視線があるだけだった。この部屋では時間を守ること――小原は仕方なく踵を返し、階段を上がっていった。
駅前にコーヒーショップがあったのを思い出したのでそこで休むことにした。エスプレッソを注文して、いちばん奥の席に腰を下ろすと、鞄から一冊の本を取り出した。ずいぶん前にもらった本で、カバーには小さな染みがついている。学生時代に楠の書いた小説が単行本化されたものだ。部屋に通い始めるようになってから、小原はその小説のことをなぜか思い出した。最後に読んでからずいぶん時間が経っていたが、ストーリーを思い出しているうちにもう一度読んでみたくなった。栞を挟んでいたページを開き、カップに口をつけ、文字を追い始める。新たに読みだして、もう四回通読していた。だがそれでも彼は飽きることがなく、十年前に書かれた物語を繰り返し読み続けていた。
眠気に襲われることはほとんどない。部屋を訪れる日時が決まると、その前に必ず真夜中の街を歩き回ることにしていた。しかしだからといって睡眠不足に悩まされることはなかった。小原が求めていたのは睡眠ではなかった。睡眠よりも静かで、夢を見るよりも現実から乖離できるものが部屋の中にはあった。
楠の小説を読み進めていくうちに、小原は思わず笑みをこぼしていた。それを見た店員同士がこそこそと囁きあっている。彼は表情を戻し、足早に店を出た。帰りの電車はまだ帰宅の人々で溢れかえっていた。彼は吊り革にしがみつきながら、その夜本当は暗闇の中に身を投じていたはずの自分の姿を想像した。
8
小原が飛べるようになったのは、二回めに部屋を訪れたときだ。それからというもの私たちが送信する日時のとおりに、彼は毎回部屋を訪れるようになった。彼は私たちの予想よりも早くに自在に飛べるレベルに達し、部屋を訪れることを強く望むようになった。
飛ぶことに慣れてくると、大抵のユーザーは自分自身に何らかの変化を与えたがる。酒や煙草をやめたり、服装の趣味を変えたり、髪の毛を剃ったり、食事を減らしたり、引っ越しをしたりする。楠礼次の場合は男を買うことをやめた。そのような変化を起こすことで、彼ら・彼女らは暗闇にさらに身を馴染ませようとする。
深夜の徘徊以外に、小原が始めたことはもう一つあった。自分が飛ぶときの様子を、彼は書きとめるようになった。部屋で感じた一つ一つを言葉に置き換えながら、自宅のパワーブックに長い時間むかうようになった。そこには長大な文書データが日々保存されている。私たちはいつものようにそれにアクセスする。
「……歯痛がはじまった。いつものやつだ。毎年この時期と決まっている。気温のせいだろうか。右下のいちばん奥の歯が凍てつくみたいにしんしん痛みだす。我慢できないことはない。何年か前に行った歯医者にはろくな治療をしてもらえなかったけど、いつも一ヵ月も経てば何事もなかったようにおさまるものだし、なんとなくやり過ごしてきた。歯痛で嫌なことは、いろんな顔が思い浮かんでくることだ。今まで出会ったいろんな人間の顔といろんな言葉が頭の中に勝手に浮かび上がってくる。それまですっかり忘れていたはずの人間の顏が、すっかり忘れていたはずの言葉を喋り始める。いったいそれがどういう人間で、いつの話のことだったのか、昼だったか夜だったか、まわりに他の人間はいたのかどうか、次々と瑣末なことが思い出されてくる。いくら追い払ってもだめだ。ほんの小さな隙間があれば彼らはするすると煙みたいに忍び寄ってくる。そして自分達の記憶を思い出させようとする。きっとそれらは歯の中に無理やり詰めこまれていたものだ。忘れていたものからの痛みだ。でもたいしたことじゃない。それはただの痛みの記憶だ。どうせいつかはおさまる。ただ再び風が吹き始めるのを待っていればいい。風がきれいさっぱり運び去ってくれる。
部屋の暗闇では、歯痛の様子がいつもと違ってくる。暗闇を進んでいると、何も見えないのをいいことに、痛みは自己主張をはじめる。勢力を拡大し、頭の中から飛びだそうとする。映画のスクリーンみたいに記憶を目の前に大きく映しだす。この映しだされた記憶こそがおまえ自身なんだと主張し始める。空気の塊を口の奥に無理やり押しこまれている感じがして、ときどき頬に手をやる。
『あなたの心には石があります』
メールにそうあったのを思い出す。
『あなたが空を飛ぶためには石を取りのぞかなくてはいけません』
盲腸の手術前の説明みたいだ。なんで石なんて喩え方をしてくるのか。石といわれても、やはりこの歯痛のことしか思い当たらない。
最初のときのように心臓が激しく鼓動することはもうなくなった。たとえ歯痛が始まっても、椅子の上で風が吹き始めれば、きれいさっぱり忘れることができた。椅子の上では、いつものように地図を想像すればいい。それが地上から離れていくための方法だ。地図の上に引いた何十本もの赤い線。複雑に入り乱れている道路。その無限の交錯が目の前に浮かびあがるまで、思いきり両目を見開き、暗闇を凝視し続ける。しばらくすれば風が勢いを増してくる。頭の上から、背中の下から、足元から、あらゆる方向からの風が胸の上で混ざり合う。全身の血液が頭にむかう。両耳がひどく熱くなる。まるで火のようだ。瞼を閉じないでいると、血が滲むような赤い点がいくつも目の前に浮かびあがってくる。やがてそれは細菌が成長するようにゆっくりと一本の線に繋がり、途中でいくつもの分岐を生み出しながら他のいくつもの線と交錯していく。尽きることのない増殖と連結と増殖と連結と増殖と連結……。それはどこまでも縦横無尽に走っていく血管だった。巨大な血管の網が暗闇の奥底まで立体的に広がっていく。その中のどこかに自分がいるはずだ。そのどこかを自分が歩いているはずなのだ。信号が点滅を繰り返し、電信柱が立ち、ガードレールが並んでいる。郵便局と交番が隣り合い、大型モニターが広告を映し続けている。あのとき歩いたあの渋谷の交差点がそこにある。強く吹き続けている風を肺の奥底まで思いきり吸いこむ。
本当に自分の求めているものを知っている人間はいったいどれだけいるのだろう。もしそれを知ることができたなら、その時点で求めているものの半分はすでに手に入れているのではないだろうか。半分を手に入れた人間は、その半分だけで生きていける。残りの半分はたいしたことじゃない。どうせならそのまま空っぽにしておいてもいい。自分がいったいどんな人間で、どんな立場に立っていて、どれだけの給料をもらっていて、そこがどんな場所かなんてたいしたことじゃない。それは空っぽの半分の方に属することなんだ。
体が地上を離れるのは半分を捨て去ったからだ。頭を後ろに反らしてみる。そこに背もたれはもうない。両腕をゆっくり垂直に下げていく。指先に肘掛けの一点だけ触れる。おそらく三十センチほどだろう。椅子の上で横たわったままの姿勢で、肉体はいつのまにか宙に浮き始めている。別に何かの力に強引に引き上げられているわけじゃない。ただ肉体が地上に別れを告げて、暗闇の中でぽっかり浮かんでいるだけだ。
はじめはうまく理解できなかった。自分の体がいったいどんな状態にあるのか、やはりピアノ線か何かで全身を持ち上げられているだけなのかもしれないと疑うしかなかった。それから逃れてみようと、上半身を勢いよくひねった。すると床の上に勢いよく転げ落ちてしまった。全身を手さぐりで調べてみたが、別に何の小細工もされてはいない。ただ、ある異変が起こっていた。床の上に投げ出しているはずの脚。その二本が水の上に浮かんでいるみたいに上下に微動しているのだ。指先を太股の下にもぐりこませてみる。一瞬、呼吸が止まった。そこにはたしかに二センチぐらいの隙間があった。指先を尻の下まで移動させてみる。そこに本当に何もないことを確かめる。本当に浮かんでいるかどうかを確かめる。〈この部屋では声を出さないこと〉ルールの一つにそうあった。ただ実際のところ、自分の肉体がたった二センチ浮かびあがるだけで、人は声を出すことさえまったく忘れてしまうものである。
浮かぶことに慣れていけば、少しずつ高さを更新していくことができる。手足をゆっくりと伸ばし、バランスをとれば、ベッドで眠るように体を水平に保つことができる。自分の部屋の固く狭いベッドで横たわるよりも、寝心地がよく、リラックスすることができる。目を閉じ、胸の上で両手を組んで、最小限の呼吸を繰り返していく。そうしていると、温かく透きとおった水が体の隅々まで流れていくような気がしてくる。とても穏やかだ。何も目にすることはないし、何も聞こえてくることはない。そこには主張もないし、反論もない。苦情もないし、弁解もない。悪口もないし、説教もない。保身もないし、犠牲もない。宣伝もないし、虚勢もない。連帯もないし、孤独もない。ただ弱々しい風が頭から足の先まで通り過ぎていくだけだ。自分を繋ぎとめようとするどんなに細い糸からも解き放たれる。自分を守ろうとする自分からも解き放たれる。重力から解き放たれさえすれば、人はあらゆるものからもっと自由になれるのだ。どうせならそんなふうにして死んでいきたかった。どんな代償を払っても、自分がそれを求めていることを自分はすでに知っている。人はそれを逃避と呼ぶかもしれない。だが自分は自分の求めるもののために、自分の半分をいつも殺しているのだ。
たぶん楠もこんなふうにして宙に浮かんでいたのだろう。何かの側から、何かのシステムから、何かの関係から身をほどきたかったに違いない。楠の書いた小説を読み返してみてそう思う。彼はあのとき、本当に自由に小説を書いていた。体裁や面目や形式というものに捕らわれることなく、自分の書きたいものを余すことなく書くことができていた。偉そうな出版社や評論家たちからどう評価されようと、それは一人の人間が持つ幸福な能力であることに違いなかった。小説としての出来上がりはたしかに未熟な部分があったかもしれない。稚拙な表現や不自然な会話が目についたかもしれない。だが私が楠の小説に求めるものは、素晴らしく良く書かれた小説の姿ではない。彼という人間が書くことを通して獲得した戦利品を私は目にしたかった。
最近、楠のことをよく考える。学生時代に彼と交わしたいろんな話を思い出す。卒業した後、父親の会社で働きながら、ひそかに部屋に通っていた彼の姿を想像してみる。小説はもうまったく書いていないと、あの夜彼は話していた。目の下には隈が浮かび、唇は白く乾いていた。そういえば昔、二人で酒を飲んでいたときにちょっとしたトラブルが起こりかけたことがある。
そのとき楠はひどく酔っていた。まだ日が昇っているうちから飲み始めて、仕事を終えた会社員たちが店に入ってくるころには、トイレに行くにもまっすぐ歩けないほどになっていた。父親と何かあったのかと訊ねても、彼はまともに答えようとせず、そのとき書いていた小説のことを話したり、ただ微笑んでいたりするだけだった。
たしか六、七人ぐらいの団体だったと思う。スーツを着た三十代ぐらいの連中が入ってきた。女も何人かまじっていて、みんな会社の同僚という雰囲気だった。店はすでに朝の市場みたいに溢れかえっていて、彼ら全員が席につけるような大きなテーブルは、私たち二人の隣にしか残っていなかった。彼らは乾杯をすると、すぐに機嫌よく盛り上がり始めた。しばらくして、その中の女がこちらをじろじろと見ていることに気づいた。真っ赤な口紅を塗った、鼻の大きい女だった。こちらの様子に何かおかしなところを発見したみたいで、仲間の話に相槌をうちながらも、吹きだしてしまいそうなのを必死に堪えているようだった。女は隣の男に耳打ちして、何かをこそこそ伝えた。男もこちらをちらりと振りかえると、手で口を塞いで、女と二人で同じように肩を揺らしていた。
たしかに私も酔っていた。楠ほど飲んでいなかったにせよ、長時間彼と付き合っているうちに高ぶった気分になっていた。いつもなら相手にしないことにも敏感になっていたのかもしれない。連中が何を笑い合っているのかはわからなかったし、実際はたいしたことじゃなかったのかもしれない。しかしいくら冷静になろうとしても、心臓の動きは速くなっていった。唾を何回も飲みこみ、グラスを床に叩きつけたい衝動を懸命に抑えなければいけなかった。連中は自分を見て笑っている。連中に笑われるようなものが自分の中にある。連中はそれを指さして面白そうに笑っている。胃の中のものが逆流してくるようだった。男が女に耳打ちをし、女は堪えきれずに高い声で笑う。耳障りな声だった。私は勢いよく立ちあがった。あとで面倒なことが起こるとしても、とりあえず男の黄色く光る歯を粉々にしないと気がすまなかった。
しかしいつのまにか楠は私の腕を掴んでいた。彼の目はもう酔っぱらってはいなかった。いつもの冷静な目で私を見つめ、首を横に振っていた。それでも私は連中のテーブルに近づいていこうとした。だが楠の強い力に押さえられていると、一歩も動くことはできなかった。連中の方を振り返った。二人はこちらのやりとりを不思議そうに眺めていたが、その様子もまた馬鹿にするようににやにや笑っていた。楠はそれを黙って見ていた。これはいったい何だろう、私はふと思った。連中はこちらを見て笑っている。それを見た私は連中を殴りにいこうとしている。このことにどんな意味があるんだろう。心臓がこんなに激しく高鳴っていることにどんな意味があるというのだろう。
楠が笑いだしたのは突然のことだった。前触れもなく何かが爆発したような笑い声の大きさに、まわりは一瞬静まりかえった。私も唖然とした。彼は腹にあるものを全部吐き出してしまいそうな豪快な笑い方で、天井を仰いだり、腹を抱えたりしながら大きな体を揺らし始めた。いったい何が起こったのか、いったい何がそんなに可笑しいのか、店の誰もが怪訝そうな表情で彼を眺めていた。だが彼はまわりの様子をかまうことなく、椅子やテーブルを吹き飛ばしてしまうぐらいに大きく野太い声を響かせていた。笑っているあいだ、彼はずっと私の腕を掴んでいた。まるで本当に気がふれてしまったんじゃないかと思えるような強い力だった。にやにや笑っていた二人は私たちと関わりになるまいと視線を外していた。そして気持ち悪がるようにときどき首をひねっていた。
ふとスイッチが切れたみたいに笑うのをやめると、楠は私の腕を掴んだまま、店を出ようと立ち上がった。私は彼に引き連られるままレジにむかった。店員は目を合わせようとせず、怖々と釣り銭を渡した。
外では冷たい風が吹いていて、やけに明るい満月が夜空に浮かんでいた。私たちは駅にむかって歩きだした。改札を抜けて、ホームへの階段を上がるまで互いに何も話さなかった。『じゃあまた』それだけ言って楠は階段を上がっていった。酔っぱらっている様子もなければ、恥ずかしそうにしている様子もなかった。ただ、なんとなく申し訳なさそうな表情を浮かべているだけだった。楠の姿が見えなくなると、私は彼と別の階段をあがっていった。
暗闇の中で楠のことを思い出していると、以前よりも楠という男に近づいているような気がした。楠は死んでしまったのだという実感は今になってもまだ持つことができない。なにしろ久しぶりに再会した後に、テレビのニュースで知っただけなのだ。ときどき彼は本当には死んでいないんじゃないかと思うことがある。暗闇の中に彼の存在を感じることがある。自分のすぐ横で、同じように宙に浮かんでいると感じることがある。もしかすると楠はこの暗闇に身を隠し続けているのかもしれない。光に満ちた世界よりこの暗闇の中で生き続けることを選んだのかもしれない。そんなふうに思っていると、いつものように彼の声が聞こえてくる。
――なんや、まだそこまでしか浮かばれへんのか――楠は言う。
――そうやな、まだこれぐらいや――私は答える。
――俺のごつい体でも、もうちょっと高いところまでいけるぞ
――でも、一ヵ月足らずでこの高さやったら上出来やろ
――せやな。まあまあ上出来や――楠は笑う。――やっぱり思ったとおりや
――やっぱりって
――ちゃんと飛べてる
――飛べるってわかってたんか
――ああ
――どんなところで?
――さあ――楠は笑った。――はっきりとはわからんけどな。でもそういうタイプやろうとは昔から思ってた
――飛ばしてどうなるんや――冗談めかして訊ねた。
――別にどうもなれへんよ。せやけど飛べるんやったら、飛んだほうがええかなと思って
――もう長く飛んでるみたいやな
――長いな
――十年ぐらいか?
――十年ぐらいかな。ちょっと長すぎたのかもしれん
――長く飛びすぎたってことか
――そういうことかな。しかも最後の方はかなり高く飛んでた
体を少し横に回転させて、声が聞こえる方にむけてみる。だがそこにはやはり何も見えない。いつもの闇しかない。
――なんかあったんか――そう訊ねてみた。
――なんかって?――何でもなさそうに楠は答える。
――ニュースで見たよ。飛びおりたんやろう
――そうか。知ってたんか
――びっくりしたよ
――ニュースで流すほどでもないと思うけど
――今でも信じられへんよ
――やっぱり最後にああいうふうに会うのはよくないことやな。悪かったと思う
――別にあやまることはない
――腹立ったか?
――いいや
――でも、ここでこうやって話すには、ああするしかなかった
風が強くなる。体がほんの少しだけ高く浮き上がった。地上との距離がまた遠くなったのだ。これからも部屋に通い続け、飛び続けるならば、たぶんもっと離れていくことになるだろう。きっと楠が飛び降りたビルぐらいの高さまで飛んでいくはずだ。
女の手が肩に触れた。そろそろ終了の時間らしい。例えばもっともっと高い位置に体が浮かんでいったなら、女の手はどうやって私の体を引き下ろすのだろう。長い棒か何かで合図をするのだろうか。それでも届かなくなったら、いったいどうやって引き下げるのだろう……」
小原はほぼ毎日このような文章を書き続けている。一日に書く量は日ごとに増え続けている。これはその中のほんの一部にすぎない。私たちは毎日彼のコンピューターにアクセスにし、彼の文章を読み続けている。
私たちは飛べる環境をユーザーに提供するだけである。彼ら・彼女らが部屋で体験したことに私たちが干渉することはないし、誰にも干渉されるべきでないと考えている。暗闇の中では様々なことが起こりうるが、それは彼ら・彼女らだけの体験だと捉えている。ユーザーはそこで何かを見たり、何かを聞いたり、何かを獲得したり、何かを失ったりする。だがそれらがどんな形のものにせよ、それはそもそもユーザー自身が求めていることだと私たちは判断している。
(後篇へ続く)
(2008年作)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
