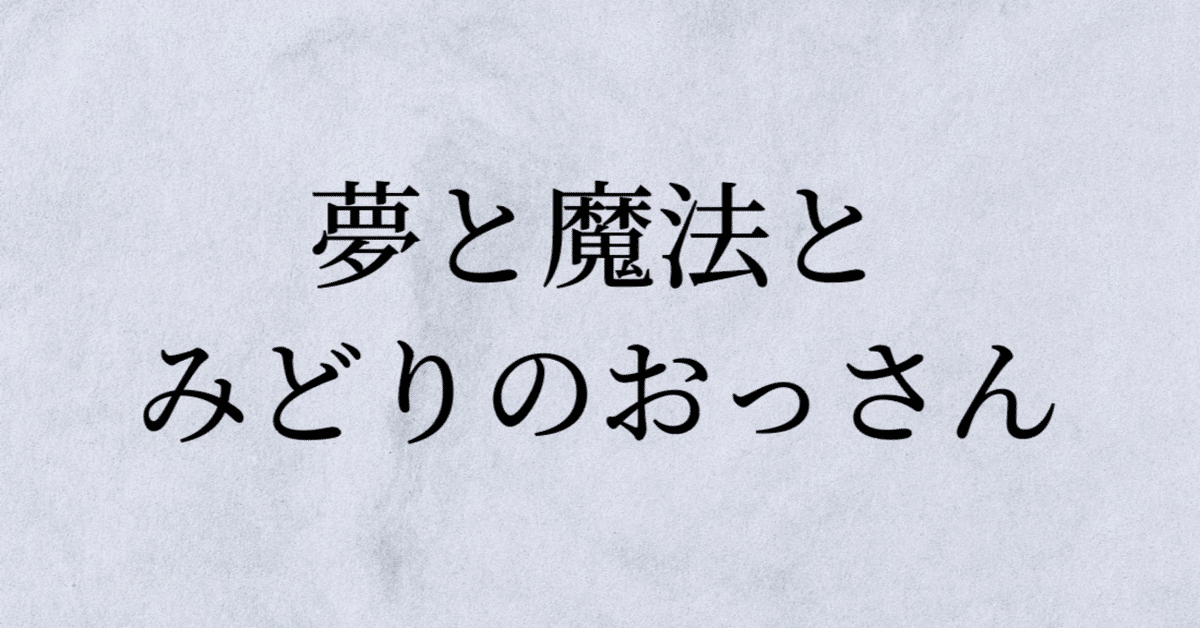
夢と魔法とみどりのおっさん 第二話
■あなたは真面目に会社に行ってるくちですか
烏帽子田さんについての情報を教えてくれたのは組子さんだった。
組子さんは、半年ほど前に僕の部屋のちょうど真上の部屋に引っ越してきた一家の娘である。学年でいうなら小学五年生のはずだが、彼女はすでに小学校に通っていなかった。彼女は自分の教室をマンションのエントランスホールや、入り口の前にある植えこみの縁の上に設定していた。そして毎日そのあたりに腰を下ろして分厚い本を手にしながら、目の前を行き交う通行人をやる気のない門番みたいに朝から夕方まで退屈そうに観察していた。ある朝マンションを出ようとすると、僕が会社に行く時間帯がなぜ他の人よりいつも数時間遅いのか、彼女は訊ねてきた。出版社というのは朝はそんなに忙しくないものなんだよと答えても、組子さんは納得しなかった。他の会社は朝から動いているのになぜ出版社だけ朝は忙しくないのか、それで取引先の会社の人は迷惑しないのか、もし朝に重大なトラブルが起こったらどのように対応するのか、組子さんはさらに質問を浴びせてきた。だけど電車に乗らなければいけない時間が迫っていた僕にはそれに答える時間がなかった。時間がないのならなぜもっと早く出勤しようとしないのかと彼女は食い下がった。ごめんね、また今度、僕が足早に立ち去ろうとすると、彼女は僕の背中にむかって呟いた。
「キッズ」
組子さんにとってほとんどの人々はキッズという範疇に属していた。彼女の見解によると、子供たちは当然キッズで、大人とよばれる人々もただ背丈が伸びて言葉遣いがまどろっこしくなっただけで、中身はキッズのままであった。両者に多少の違いはあるものの、両者とも本質的にキッズであることには違いない。キッズとは具体的にどういうものなんだろうと訊ねると、「そんなこと普通に人を見てればわかることじゃないですか」と彼女は僕を一瞥した。そんなこともわからないあなたもつまりはキッズの一員なのですよと言わんばかりのクールな視線だった。彼女が目にしている世界は、とにかくキッズに満ちあふれているのであった。
組子さんが何よりも納得できないのは、そんなキッズだらけの世界にもかかわらず、やはり自分もそこに依存しなければ御飯を食べていけないことだった。キッズが物を買うからこそ会社が儲かり、キッズが茶の間であぐらをかいているからこそテレビCMが流され、キッズが罪を犯すからこそ警察キッズが権力を振るい、キッズが自動車を乗り回すからこそエコロジーという産業が生まれたのだ。そして何より、彼女の両親キッズがキッズだらけの会社に毎日通って、キッズ向けの商品を開発し、客キッズから金を受け取り、その金で彼女は毎日御飯を食べているのである。
「最悪です」組子さんは溜め息をついた。
「そこまで思いつめなくても」
「死にたいくらいよ」
とりあえず組子さんがキッズ世界に対して開始した抵抗は、学校に行かないことだった。彼女にとって学校というのは人間の脳味噌をつんつるてんの豆腐に変えてしまう留置場でしかなかった。なぜそんな阿呆臭くて息苦しい場所に毎日通わなければならないのか、彼女は頭の先から足の先まで理解できなかった。だけどマンションの前を通り過ぎる大人キッズを毎日眺めていると、結局キッズというものは大人になっても会社という留置場で勾留されることを選ぶものなのだと理解した。彼女はキッズ扱いなんかされたくなかった。自分のことも敬称をつけて呼ぶようにと僕に注意した。
「組子さん」僕は声をかけた。
「なんでしょう、浜本さん」組子さんは本のページから目を離さずに言った。彼女が手にしているハードカバーの表紙には『コニー・ブック著作全集』とあった。
「コニー・ブック、読んでるんだ」
「知らないでしょう」と組子さんは冷ややかに言った。「あなたの知らないドイツのノン・キッズですよ」
組子さんはマンションの入り口の植えこみに腰をかけ、地面に届かない両足をぴたりと閉じていた。茶色のスニーカーは従順な双子の子犬のように彼女の命令をじっと待っているようだ。
「このあいだ取材に行ったよ」
「取材って、烏帽子田さん?」組子さんは神経質そうな切れ長の目をこちらに向けた。
「うん」僕は組子さんのとなりに腰を下ろした。「でも記事にはできそうにないね。あの人は最後まで顔写真を撮られることを嫌がったんだ。珍しい職業を長年続けている人物の紹介記事なので写真を載せないわけにはいかないんですと説得しても、首を縦に振らなかった」
「嫌がる理由はなんでしょう」
「もし自分の頭が雑誌なんかに出たら、きっとあの王国の人たちは黙っていないだろうって」
「頭?」
「着ぐるみ師としての年季が入った頭だよ」
僕は、王国の観衆の前で鼠の頭がはずれて、烏帽子田さんの禿げ頭が露呈してしまったことを話した。
組子さんは眉間に皺を寄せながら、ずっと僕の話を聞いていた。そして話を聞き終えた後もしばらく何も言わず、路上に嵌めこまれているマンホールの蓋を深刻そうに見つめていた。まるでマンホールの下に何か不気味なものでも潜んでいて、それが這い上がってくるのを心配しているような表情だった。『コニー・ブック著作全集』はおとなしい鳩のように、膝の上で彼女の白いあごを見上げている。
そのあたりは古い木造の家屋や鉄骨のマンションがひしめき合っている住宅地で、昼間でも人通りが少なかった。少し先の電信柱では緑色のつなぎを着た作業員キッズが電話工事をおこなっていた。その下をたくさんの家具を積みこんだ軽トラックが通り過ぎていく。空には雲一つなく、五月らしい気持ちのよい風が吹いていた。
「烏帽子田さんのことはどうして知ったの?」
組子さんはまだマンホールの蓋が気になる様子だったが、仕方がなさそうにゆっくりと顔をこちらに向けた。「なんでしょう」
「なんで知ってたの? 烏帽子田さんのこと」
「なんでって、なんでもです」組子さんは『コニー・ブック著作全集』をぱたんと閉じた。「パソコンでちょちょちょいって調べてたんです。王国のことを。そしたら変なサイトがあってね。これまで鼠の中に入ってたキッズのリストが載ってたの」
「意外だな。組子さんもあそこに興味があるんだ」
「別に好意的な意図で調べてたわけじゃないですから。まずは敵を知らないといけません。とても長い戦争になるんだもの」
「戦争?」と僕は繰り返した。「なんかテレビゲームみたいだ」
「ゲームみたいな戦争をしているのはキッズの方です」と組子さんは冷静に言った。「わたしの戦争はキッズの戦争じゃないもの」
「そういうふうに何かに抵抗したりするのも、ある種のキッズじゃないのかな」
「キッズは抵抗なんかしないです。抵抗するふりをして格好をつけるだけです。キッズは本当の抵抗なんか絶対しやしないんだから」
ランドセルを背負った五、六人の男の子キッズが僕たちの前を通り過ぎていった。ちょうど組子さんと同じぐらいの年頃だ。彼らが夢中になって話していたのはうんこの話題だった。各々のうんこの形状や色がどのように異なっているか、毎日いろんなものを食べているのになぜうんこはいつも同じなのか、彼らは大声でそれぞれの見解を述べたり笑い合ったりしていた。
「今の、わたしが通ってた学校のキッズです」
遠く離れていく男の子キッズの後ろ姿を見つめながら組子さんは言った。
「知ってる子?」
「さあ、どうでしょう。わからないです。まわり子の顔なんて何も憶えてないから。どんな子がいたのか、クラスがいくつあったのか、どんな教室でどんな先生がどんな授業をしてたのか、全然頭の中に残っていないんです」と組子さんは首をかしげた。
「誰か気の合いそうな友達もいなかったんだね」
「そもそも友達づきあいっていうものが駄目だったんです。テストの点数が上がって喜んだり、前の晩に見たテレビの話で盛り上がったり、陰で誰かの悪口を言ったり。そんなもの最初からまったく駄目だったの。典型的なキッズの人たち」
「たしかにそういう人間はどこにでもいるけどね。僕の会社にもいる。でもさすがにうんこの話題はあまり聞かないな」
組子さんは頭の中で何かを整理するようにスカートの端を丁寧に揃えた。「親はね、学校に行かなくなったわたしをすぐに病院に連れて行ったんです。何も訊かずに、何も話をしようとせずに。まるで故障したテレビを電気屋に持っていくみたいにね。あの二人は他の誰かがどうにかしてくれると思ってたんです。性根からキッズなの、あの二人は。わたしは医者から何を訊かれても一言も話さなかった。話すことなんて何もなかった。だってそもそもわたしはどこも悪くないんだもの。それで困った医者は腕組みをしたまま『何でもいいから、この子に何か子供らしいことをさせた方がいいね』って言ったんです。ねぇ、それってあまりにもキッズらしい発想だと思いませんか?」
「組子さんのことをキッズだと思いたがってるんだろうね」
「というかキッズだと思いこんでるんです。かなり強く」と組子さんは肩をすくめた。「さっそくあの二人はデパートで買ってきたぬいぐるみとか金髪の人形とかを家中に所狭しと並べ始めました。それまで自分たちがそういうものを買い与えてやらなかったのがいけなかったんだろうと考えたんです。それでもわたしが学校に行かずに、全然話をしないでいると、今度はあそこへ行こうって言い出したの」
「なるほど。夢と魔法の王国。典型的なパターンだ」
「わざわざ日曜日に早起きして、電車で浦安まで行きました。すごく嫌だったんですけど、仕方ないから付き合ってあげたんです。でも予想どおりでした。なんでみんなあんなに楽しそうにしてるのか、わたしにはよくわからなかった。両親もわたしのことなんてすっかり忘れて、はしゃぎ回ってたんですよ。わたしの方が保護者みたいに二人の後ろをついて回ってました」
「話を聞くだけだと、組子さんの親とはぜんぜん思えないね」
「それでね、あの色鮮やかな世界の中で歩き回っていると、わたし、だんだんと気持ち悪くなってきたんです。何の乗り物にも乗りたくなかったし、何のグッズも欲しくなかったし、変なキャラクターに近寄ってもらいたくなかった。途中でだんだん疲れてきて、冷や汗みたいなのが出てきたから、ベンチに坐って、胸がむかむかするのをずっと我慢してたんです。頭がきゅっと締めつけられるみたいに痛むし、寒気もしてきたの。それでね、ついに吐いちゃったんです」
「すごい拒絶だね」
「そう。お昼に食べたとろろ蕎麦が、地面の上に全部ばぁーって」
「……目に浮かぶよ。見事な情景だ」
「するとね」と組子さんは眉間に皴を寄せた。「二人が急いですっ飛んできて、真っ青な顔してわたしを抱えて帰っちゃったんです。かなり困った顔してました。わたしのことなんかより、みんなが楽しんでる雰囲気を壊してしまったことを気まずく感じてたのよ。それから何日経ってもすごく気にしてて、結局引っ越しまでしたんですから。馬鹿みたいな話。でもそのことがあってから特に何もしようとせず、腫れ物に触るみたいにわたしのことを扱うようになったんです」
組子さんは植えこみの縁からぴょんと飛び降り、お尻を軽く払うと、腕時計を見た。どこかの換気扇から魚を焼く匂いがしてきた。ちょうど昼飯どきだった。
「あなたは真面目に会社に行ってるくちですか」と組子さんは訪ねた。
「たぶん、そのくちだと思う」
「何の疑いも抵抗もなく?」
「盲腸の手術のとき以外は休んだことはないな」
「やっぱり浜本さんもキッズなのかしら」
「自分ではよくわからないな。でも組子さんの話を聞くかぎり、できるだけキッズでないように努力したいと思うけどね」
「でもわたしが思うに」と組子さんはしばらく空を睨んだ。「烏帽子田さんはたぶんわたしと同じですね。ノン・キッズよ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
