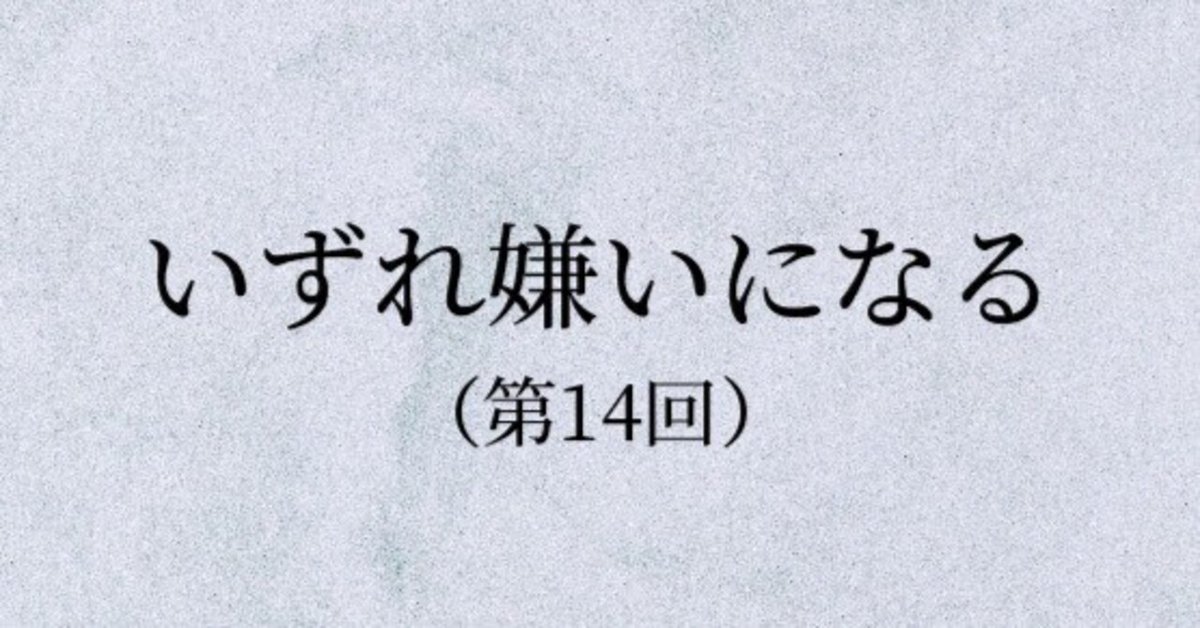
いずれ嫌いになる(第14回)
14
「どうもわざわざありがとうございました」
月曜日の昼休み、青年はワタルのもとにやってきて礼を言った。そして謝礼に交通費を加えた封筒を手渡した。
「むこう、何か言ってました?」青年は何かを気にしているように訊ねた。
「別に。何も言わずに帰ってきたよ」
「あ、そうすか。そうですよね。何も言わないすよね」
玄関に出てきた彼女と青年とにどんな関係があるのか、ワタルはいろいろ想像してみたものの結局何も訊かないことにした。
「結局あの箱の中には何が入っていたんだろう?」
「それは本当に俺も知らないんすよ」青年も納得いかない表情を浮かべた。「俺も一緒で、結局はそれを運ぶだけの役割なんすよ」
なぜマンションの女のことは知っていて箱の中身については知らないのか、こっちこそ納得いかないと思ったが、ワタルはそのままその場を離れた。それよりもあんなところで自分とあの女が再会したことの方に意味があるように思えた。だけど顔がはっきり思い浮かんでこない。思い出そうとすると、昔の小学校のときの顔が、すらりとした大人の女の体をともなってマンションのドアからひょっこり出てくる。
「こんなところで何してるのよ」
あれは本当に土手のベンチで話した女の子だったのだろうか。でもそれ以外の何者でもあるはずがない。ワタルはポケットの中に手を滑りこませる。彼女は音叉を持っていた。まるで自分があのマンションを訪れることをすでに知っていたみたいに。そして自分からあの箱を受け取ることをわかっていたみたいに。
「宇宙人」
その日の帰り、ヒロミからメールが届いていた。
メールが遅れてごめんなさい。
遅れてしまうような事情があったの。
いろんな事情がここ何日で起こった。
あなたともう会えない事情も起こってしまったわ。
半分は私の責任だし、半分は夫の責任。
あなたには責任はないはずなの。そうでしょう?
メールができる環境もあともう少しで失われます。
でももしまだ何か繋がりが残っているなら
そのときまでさようなら。
リクライニングシートに深くもたれながら、ワタルはその文面を何度も読み返した。店に立ち寄るつもりはなかったのだが、ひどく腹が減っていて、どうせならメールをチェックしようと思いついた。モニターの前にはスープだけになった担々麺の器が置かれていた。ときどきれんげでスープを掬っては床にぼとぼと落とす。カーペットの上で染みが秘密の地図のように広がっていくのがおもしろかった。「もしまだ何か繋がりが残っているなら」。そんなものはもうどこにも残っていない。自分はいろんなものを切り捨ててきたタイプの人間だ。切り捨てることで自分でいられる人間なのだ。もしかしたらとワタルは思った。最近のセックスでワタルはうまく勃起することができないことがあった。いくらヒロミに手伝ってもらっても無理だった。それが理由かもしれない。自分に責任があるとしたらそれだ。自分は不能になりかけているのかもしれない。
ワタルはリュックサックを手にして、立ち上がった。もうその店に来るつもりはなかった。戸を引いて、ブースから出ようとした瞬間だった。ちょうど目の前を通り過ぎようとしていた男の右腕とワタルの体が軽くぶつかった。男はびっくりして立ち止まったが、ワタルの顔をちらりと見ると、もとの進行方向に向き直ってちょこんと頭を下げ、トイレの方へ消えていった。見たことのある男だった。何度も店の廊下ですれ違ったことがある。小太りで、縮れた髪を肩まで伸ばし、こめかみにめりこんだ黒縁の眼鏡をかけて、いつも同じ茶色のワークシャツを着ている。もしかしてこの店に住み着いているのかもしれないとワタルは思った。でもどうだっていい。もうここには来ないのだから。
レジで清算を済ませ、自動ドアから店を出たときだった。ワークシャツの男が後ろから声をかけてきた。
「すいません」
ワタルは振り返る。「はい?」
「あの、さっきぶつかりましたよね?」
「え」
「いまさっきのことですけど。なんかちょっと変かなと思って。こっちだけ頭下げて、おたくからは何もなかったもんだから」
男は眼鏡の奥から瞬きのない細い目でワタルをじっと見ている。小さく粘ついた声だったが、そこには絶対に折れようとしない硬質な響きがあった。
「いや、確かに大したことじゃないとは思ったんですけどね。でもおしっこしながら、やっぱり一応社会人としての常識っていうか礼儀というものも、ないがしろにしちゃいけないんじゃないかなと思い直して」男は話しているあいだ、店内の自動販売機で買ったペットボトルの緑茶を小刻みに振っていた。
「ちょっと小走りだったよな」ワタルは言った。
「は?」
「小便が漏れそうだったのかどうかは知らないけど、こっちは普通に出ていこうとしただけだから」
男は戸惑った表情を浮かべた。「何言ってるんですか。お互い様だっていう話をしてるんじゃないですか」
ワタルはズボンのポケットに手をしのばせた。その底にあるものはいつも冷たくて固い。平気で誰かのことを血だらけにもできる。
「おまえみたいな蛆虫と話してたら、口と耳が腐ってくんねん。はよ失せろ」
「なんですか。急に下手な大阪弁なんか出しちゃって。そんなんでびびると思ってるんですか」
男はねちねちと文句を呟いていたが、ワタルは背中で聞き流し、店から離れていった。ポケットの中では手のひらがぐっしょりと汗で濡れていた。それが気にくわなかった。なぜこんなことで汗をかかなくてはならない。
部屋に帰るとすぐに熱いシャワーを浴び、久しぶりに買った缶ビールをときどき口にしながらギターを抱えた。そしてコンポセットから流れてくる演奏に合わせながら『アルハンブラの思い出』を弾いた。指の動きはさすがに鈍くなっていたが、メロディの抑揚の付け方などは感覚的に憶えていた。というより昔弾いていたときよりもその曲の深みのポイントが見えてきたような気がした。
なぜ唐突に大阪弁が口をついて出てきたのか、自分でもよくわからなかった。子供の頃以来だった。さっき調弦で使った音叉がテーブルの上に置いたままだ。ワタルはそれを手に取ってテーブルの角を打ち、耳に近づけた。そして目を閉じながらボウリング場を思い浮かべた。
薄暗くひんやりとしたレーン。丁寧に並べられた色とりどりの玉。向こうの闇では獲物を捕らえる罠のように十本の白いピンがぶら下がっている。確かにトウコもそこにいた。しかし彼女もまたその場所に含まれた一部だった。彼女は手招きをしてワタルを闇のさらに奥深くへ誘おうとする。拒む理由は何もない。ないはずなのにワタルの足は動かない。自分というものがなくなってしまうような気がしてならない。
ワタルは目を開け、ギターを床に寝かせると、トウコの家に電話をかけてみた。何か考えてのことではなかった。勝手に指がボタンを押していたのだ。闇の中をいくつものコール音が通り過ぎていく。トウコと話すのは十年ぶりだった。受話器を取ったのは中年の男だった。
「トウコさん、おられますか?」
「どちらさんですか?」
「……」
「まず自分の名前を名乗るのが常識でしょう」
「もう実家にはいないんですか」
電話は切られた。おそらくトウコの父親だろう。トウコの父親が自分のことを嫌っていたことをワタルは思い出した。そして今でもまだ嫌っているのだ。昔と何も変わってはいない。いや、ますます嫌いになっているはずだ。ちょうど自分が何もかも嫌いなままでいるのと同じように。だけどそのときは無性にトウコに会いたかった。あの二人きりのボウリング場で昔と同じように身を寄せ合って話をしたかった。
母親から手紙が届いた。いつ電話しても出ないから、手紙で知らせることになったと冒頭に書いてあった。実は妹が生まれることになるということだった。予想外のことで、こんな歳になって出産することに自分でも戸惑ったのだが、できたからには産むしかないと思う。できれば近いうちにでも一度帰ってきてほしい。便箋一枚に簡潔な文章で、そう書いてあった。
妹? ワタルはしばらくその意味がわからなかった。なぜ自分に妹ができるのか、それはいったいどういうことを意味するのか。自分と関わりのない場所で人が一人生まれる、それぐらいの印象しか持てずにいた。
だんだんと仕事を辞めたい気になっていた。別にそれまでも熱心に仕事に取り組んでいたわけではなかったのだが、ヒロミと会わなくなってからというもの、自分は別に今いる場所にいなくてもいいような気がしてきた。職場の業務システムのいろんな不備が目につき、面倒くさいことはアルバイトの人間に丸投げする上司たちのことが鬱陶しくなってきた。会社の繁忙期は七月だし、ボーナスも出る。それが済んでからワタルは辞意を伝えた。
「あ、そう。わかりました。じゃあ上の方に伝えておきます」
それだけ言うと、上司は事務所へ続く階段を上がっていった。
ワタルは次の仕事を探そうとしなかった。しばらくのんびりと暮らしてみるのもいいかもしれないと思った。大体朝七時頃に目を覚まし、朝食を食べると、近くの図書館に行って本を読み、気になる本があると借りた。それから横浜の街をうろついたり、東京まで出て新宿や渋谷なんかをうろついたりした。何の目的もなかったが、まわりの人々も特に大事な目的を抱えているようには見えなかった。一度、マンションを訪れたことがあった。青年に用事を頼まれたマンションだ。もう一度あの女に会ってみてもいいと思った。しかしインターホンを押しても誰も出なかった。しばらく様子を窺ってみたが、結局その部屋にはもう誰も住んでいないようだった。
不確かな日々が続いた。とてつもなく長い行列に並んでいるうちに、自分自身が不確かになっていくような日々だ。そろそろ大阪に帰ってみようかとワタルは思った。母親の手紙が着いてから五ヵ月が経っていたが、互いに何の連絡も取り合っていなかった。もう生まれているかもしれない。父親と母親、そして新しい妹が三人で暮らしているところを想像してみた。同時にそこに自分は含まれないことに気づいた。別にそれでもいい。顔を見るだけだ。顔だけ見たらすぐに帰る。もうあんな家には今さら戻りたくもない。
すぐに帰る? 自分はどこに帰るというのだ。このアパートの部屋だって家賃が払えなくなった時点で追い出される。それだけのことだ。そういうことを考え出すと、ワタルは暗いボウリング場をまた思い浮かべることになった。
トウコが家族の元を離れて暮らすようになってから六年が経っていた。大学で知り合った一歳上の男との結婚生活は一年も経たないうちに終了することになった。それからは仕事を見つけて、実家に戻らずに近くのマンションで一人暮らしをすることにした。子供がいないうちに別れて良かったとトウコは思っていた。もし子供がいればどちらが親権を取るかの問題などもある。あの男が親権を欲しがるとは思えないが、自分が子供を引き取ることになれば今度は自分の父親が関わってくる。そんな関わり合いの中でトウコは身を縛られたくなかった。
中堅の広告代理店の営業部でトウコは派遣社員として働いていた。美大で商業デザインを学んだこともあり、本当はデザイナーとして働きたかったのだが、経験がないということでとりあえず営業部に回された。あとは君の頑張り次第だと上司から肩を叩かれた。クライアントの要望を制作部に伝えるときに自分でもかなりしっかりとしたラフを描いて、積極的にデザインに関わろうとした。だが何年経っても彼女の席は同じままだった。営業部からデザイン部に異動することなんてまずない話だということをトウコは耳にした。一人暮らしをしてからデザイナーとして自立することを、トウコは一つの目標として掲げていた。それが社会で生きていくための第一段階だと思っていた。だけどそうやって努力してきた五年間がすべて無に帰してしまったように思えた。トウコは会社を辞めることをすぐに決めた。会社は引き止めたが、トウコの意志は固く、できれば早いうちに辞めたいことを付け加えた。
デザインの専門学校に入学願書を出していたが、開始は九月だった。それまで暇を持て余した彼女は買い物や美容室に行ったりした。そして書店で料理本を買った帰り、昔通っていた楽器店まで寄ってみようと思いついた。大学に入ってからというものギターにはまったく触っていなかったし、楽器店にも閉店して以来訪れたことはなかった。夏の日差しで熱くなったサドルをまたいでペダルを漕いだ。国道脇の歩道を走り、信号待ちで額の汗を拭いながら、トウコはかつて通っていた道のりを懐かしく思い出していた。
ミドリカワ楽器店のあった場所に近づいてきた。やはりその建物のシャッターは下ろされたままだった。道路を挟んだ斜め向かいから彼女はその古ぼけた佇まいを眺めていた。店の前には誰かが立っていた。見慣れた背中だった。撫で肩で華奢な背中にすらりと長い脚。ワタルは建物の真ん前に立ち、考えこむように二階あたりを見上げていた。ハンドルを握るトウコの手は汗ばんでいた。そして近くのファミリーレストランの陰に身を隠した。窓際で遊んでいた子供が店内から不思議そうに彼女を見ていた。ワタルを見かけた瞬間、トウコは自分の場所が突然スポットライトに照らされたような気がした。まわりに誰もいない。だからつい隠れてしまったし、ましてや声などかけられなかった。
ワタルは何をしているんだろう。いまどこにいるんだろう。そんなことしか考えられなかった。
「人は変わっていくもんやからな」
ミドリカワ楽器店の店長は、何も話そうとせずに立ち尽くしているワタルを見かねて微笑んだ。「しゃあないことやわ。あんたがこんなに大きなったのと同じで、うちもいろんなものをなくしてもうた」
その病室は糖尿病患者が集められている六人部屋の病室で、他の部屋と比べると重苦しい空気はあまりなかった。イヤホンを付けてテレビを見ながらくすくす笑っている者や、ひたすら携帯電話の画面を見ている者や、部屋の入り口に立って看護師たちにむかって家族の愚痴をこぼしている者などがいた。ミドリカワ楽器店の店長はいちばん奥のベッドに横たわっていた。窓からそそぐ八月の午前の光が彼女の顔を眩しく照らしていた。若い頃から慣れ親しんできたドレッヘアはすっかり刈り落とされ、女性刑務所に収監されているような短髪が茶色く光っていた。右脚の膝から下は失われていた。部屋にはエアコンの冷風が吹きこんでいたが、彼女は暑いのか、掛け布団をベッドの足元に丸めて畳み、その上に左足だけをのせていた。重度の糖尿病は末端部分の壊死を引き起こすという知識ぐらいはワタルでも持っていた。
「ようわかったな。ここの病院にいるって。しかもこんなおばはんのこと、よう憶えといてくれたわ」
店長はそばのパイプ椅子を指さして、ワタルに座るよう促した。
「店の前で会った人が教えてくれたんです。店長ならここにいるって」ワタルは腰を下ろした。喉が少し乾いていた。
「会ったって誰に?」店長は身を少し起こした。
「女の人ですね。店長と同い年ぐらいの」
「あ、そうか」店長は再び枕に頭を乗せた。「それは妹やわ。うるっさい妹やねん」
「ここでギターを教えてもらってたって言ったら、丁寧にここの場所を教えてくれましたよ」
ワタルがそう言うと、店長は短く笑った。彼女が笑うと、右の太股も奇妙な動きで揺れる。「それにしてもあんた全然変わってないな。背はかなり大きなったけど、顔はあんまり変わってへんで。それにその喋り方な。ほんま懐かしいわ」
「自分ではかなり変わってしまったと思うんですけど」
「そうかな。うちには同じように見えるけどな。歳のせいかな」
「入院してからどれくらいなんですか?」
「はは。なんやそれ。そんなんどうでもええがな」店長はそう言いながら、ベッドに付いているハンドルを回して、物が食べられるぐらいの角度に上半身を起こした。「でもまあ一年ぐらいになるわ。これでもましになった方やねんで。入院したときは朝起きても、まぶたが開けへんかってん」
ワタルは彼女の失われた右脚に目をやった。膝のあたりでパジャマの裾がぎゅっと結ばれている。店長との再会までに十五年が経っていた。十五年の歳月は彼の知らないところで人から一本の脚を奪っていた。
「ずっとわからなかったことがあるんです」ワタルは言った。「どうして突然店を閉めたんですか?」
「ああ、そやな」店長は胸の上で指を組んで、天井を見つめた。「あれは迷惑かけたな。ほんま申し訳なかったと今でも反省してるわ。ほんまはもっと早くに知らせておくべきやったやけどな」
「なにか事情があったんですね」
「事情っていうか恥ずかしい話やねんけどな。息子が警察に捕まってもうたんや。ほんま情けない話やわ。あのろくでなしの息子が友達を殴ったみたいでな。それでそのときちょうどうちの体調も悪化してきたところで、めっちゃパニくってもうたんや。とりあえず店を開ける状態じゃなくなってもうたんやわ」
「あの、よく本を読んでた人ですよね」
「そういえばあんた、一回レッスン受けたことあったかいな。とにかくお客さんにはほんま迷惑かけてしもたわ」
ワタルは彼が童貞だということを思い出した。この母親はそのことまで知っているのだろうか。逮捕されたときも彼はまだ童貞だったのだろうか。
「今はどうしてるんです?」
「さあな」店長は短くなった自分の髪を気持ち良さそうにごしごし擦った。「行方知れずやわ。しばらく家におったんやけど、すぐに出ていってもうた」
突然テレビの音が大きくなった。となりの患者が寝転ぼうとした勢いで、イヤホンの端子がテレビから外れたのだ。どうやら漫才の番組みたいで、すぐにイヤホンは付け直された。「すいませんな」と患者は小さく誤ったが、一瞬割りこんだ笑い声が病室に気まずい空気を残した。
「あんたは何してんの?」店長が訊ねた。
「何もしてないですよ」
「働いてへんのかいな」
「つい最近まで横浜の倉庫で働いてたんですけど、辞めてきたんです。当分はぶらぶらすることになりそうですね」
「最近の子はそんなん多いな。ニュースでもようやってるわ。職場を転々としながらさまよってる子ら」
ワタルは苦笑いを浮かべた。ニュースで伝えられるような若者のタイプに当てはめられたことがなんだか可笑しかった。
「昔、たまにな」しばらく沈黙があった後、店長は言った。「あんたがギター教室に来てた頃、うちの息子とあんたがなんとなく似てるなぁって思ってたことがあってん。この子が大きなったら、ひょっとしたらうちの息子みたいになるんちゃうかなぁって。でも違うかったな。あんたの方がたくましいし、立派にやってる。もういじめられてないし、仕事はしてないけど、強く生きてる感じがする」
店長は天井にむかって小さめの声で話し続けていた。空中に何かを描いているような店長の黒い目をワタルはずっと見ていた。
「でも、よう考えればあんたは子供の頃からたしかに強かったわ。いじめられてたけど、何にも屈してなかった。あんたの強さはちょっと変わってんねんな。たとえばまわりに誰もいなくて、一人でおらなあかん場合なんかは、あんたは強く平然といられると思う。普通の人間やったら挫けそうな状況でも、あんたやったら逆に生き生きしてくる。むしろそんな状況を望んでるふしもある。そうちゃうか?」
「それもニュースでやってたんですか」
「ちゃうちゃう。これは昔、あんたの演奏をじっと聴きながら思ってたことや。せやけどな、たとえば誰かと一緒に何かをやったり、話し合ったり、協力し合ったりせなあかん場合になったら、あんたはきっと弱くなるタイプやわ。集団の中で自分の居場所をどこに見つけたらいいのか、わからなくなる。だからこそ、そんな状況からはできるだけ距離を置こうとする。できるだけ一人でいようとする。そうやろ」
「たぶんギター売るより占いの方が向いてますね」
「はは、そうやな。ほとんどうちの想像やけどな。えらい説教臭くなって悪いな。でも息子のことがあって、そういう種類のことをよう考えるようになったんやわ」
「息子さんはどんなタイプなんですか」
「あれはただのろくでなしや」店長は笑った。「あんた、両親のことは好きか?」
「そうだな」ワタルは腕を組んでみた。「好きとか嫌いとか、あまり考えたことないな」
「うちは最近になって親子が必ずしもわかりあえるとは限らんねんなと感じ始めてきたわ」店長は顔の前で手のひらを合わせた。「しょせん人間同士やから、合う合わんもあるやろ。でもそれでもやっぱり一緒にいて、相手のことをわかろうとよく考えたりするっていうのもある種の強さかなって」
窓の外では雲が多くなってきた。店長の顔に射す光もだいぶ弱くなってきた。まだ昼前だったが、ふと気づくと夕刻のような静けさが病室に漂っていた。
「ギターはまだ弾いてるんか?」
「ぜんぜん」
「そうか。残念やな。もしまた横浜に帰る前に来る機会があったら聴かせてほしかったけど」
一瞬眩しい光が部屋に射しこんだ。ワタルは目を細めて微笑んだ。「もう何も憶えていないですから」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
