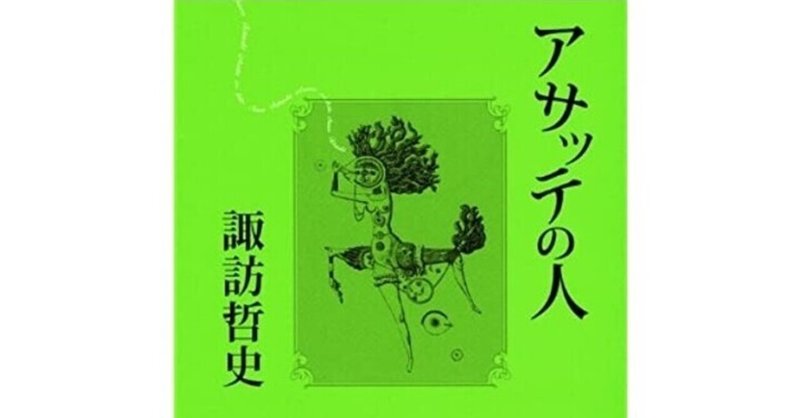
◆読書日記.《諏訪哲史『アサッテの人』》
※本稿は某SNSに2021年11月8日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
諏訪哲史の小説『アサッテの人』読了。

本書は著者が群像新人賞、芥川賞をW受賞した長編作品。大学では独文学の種村季弘に師事していたという関連からか、冒頭にはアルトーの引用があり、本書の装画もスワンベルグである。
この本のそういったシュルレアリスムを意識した構えが気になっていて同じ著者の『ロンバルディア遠景』という妙な魅力を持った本を読んでみたいと思っていた。その前哨戦として著者の出生作である本書を読んだという訳である。
確かに、前衛的な小説を書こうとあがくその試行錯誤のじりじりした感覚は好ましいものの、若干青臭さのようなものが鼻につく。
アヴァンギャルドをやるには肩の力が入り過ぎているようだ。
だが、その力みを突き抜けて傑作たらんとする足掻きも感じるのだが、いかんせん本書に何度も出て来る「定型」の軛から逃れられていない。
典型的な「定形からはみ出そうとし、前衛であらんと試行錯誤する真面目な人」と言った感じの作品である。
怜悧な、論文のような分析的文体を扱いながら今までにない方向を目指そうとする姿勢は面白いのだが、著者も自ら言っているように自家撞着を起こしているように思える。
手記、日記、聞き書き、覚書、図面……等々様々な文章をパッチワーク的に組み合わせて「小説」から逸脱しようと言う著者なりの手法も、ぼくにはニーチェの『ツァラトゥストラはかく語り』が真似たスタイル――、歌あり詩吟あり自己対話ありアフォリズムあり……というあらゆるスタイルを混合した「メニッペア」又は「メニッポス的風刺」と呼ばれる古風な西洋の俗流文学のスタイルを思い起こさせた。
更に言うなれば、自らの文章や自らの書いたものを几帳面に分析せずにおれない自意識過剰な感覚に大坪砂男の短編『黒子』と似た印象を受けた。
また、微妙な強迫観念的な「ありそうでないもの」の虚構を打ち立ててリアルに作り上げていく方法などは安倍公房の『箱男』を連想させられた。
――つまりは、この著者が、この小説のメイン・モティーフとして描写したがっている「逸脱を志向する人」の様々な要素が、いずれもどこかで見た事があるようなものばかりなのである。
ここら辺、永遠に「凡俗から脱け出して天才に至りたいと願いながらもそこに至れずに七転八倒する凡人」の悲劇が間接的に現れてると思う。
ある種の「天才」というものは、このようなジレンマを経験せずに、喫せずして逸脱してしまうタイプの人間に多い呼称なのだと思うのだ。
だからこそ、そういう人にはそういう人なりの悩みや修練やらが必要で、だからこそ更に凡俗の人間には至れない境地に至れるものなのだろう。
本書の著者のアプローチは、少々正直すぎた。
ただ、前半はどこか実存的に言語学的な問題を扱っているかのようなテーマ性を感じて期待を感じる部分はあったのだが、それさえもこの小説に出て来る「叔父」同様、最後まで突き抜けず不徹底に終わった感は否めない。凡俗の悲しさである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
