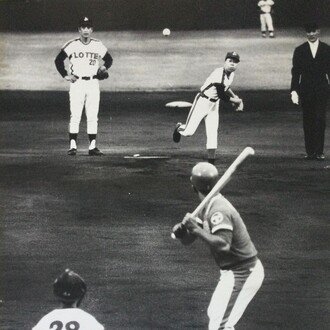【全史】第2章 オリオンズの傍流?本流?「永田ラッパ」/ 1948(昭和23)年~1950(昭和25)年
(1)1948(昭和23)年~1950(昭和25)年 永田雅一の球界登場とゴールドスターの誕生
第1章はオリオンズ史の「本流」である、毎日オリオンズの歴史を辿ったが、オリオンズにはもう一つの「流れ」がある。オリオンズの系譜では「本流に合流した傍流」になるが、ある意味、こちらも「本流」と言えるのかも知れない。
第1章では、毎日新聞側からの視点で記したので、大映社長永田雅一に対して一部は偏った見方になっていたと思うが、この章では、その永田の視点から傍流の歴史を辿ってみたい。
「永田ラッパ」「昭和の妖怪」「日本映画の父」「フィクサー」「ワンマン」…。
永田のあだ名の数々である。このあだ名を見るだけで、永田という人物が分かるようだ。
そんな永田が「プロ野球参入」に興味を持ったのは、本業である映画会社・大日本映画製作株式会社(以下大映)のためだった。
永田が映画の世界に足を踏み入れたのは、1925年に日本活動写真(現日活)京都撮影所に入所したところから始まった。太平洋戦争が開戦する直前の1941(昭和16)年、戦争に向けたプロパガンダを進める内閣情報局は、映画会社の集約に動く。この時、永田の裏の動きで大映が設立された。初代社長は人気作家の菊池寛を担ぎ出し、永田は専務に就任したが、実権は永田が握った。
戦後1947(昭和22)年、菊池寛が公職追放されると永田が社長に就任。永田も一時戦犯疑惑が向けられるが、自らの弁明と嘆願活動もあり、すぐに解除され永田は渡米する。アメリカでの大映作品の上映とアメリカ作品の買い付けのためだった。しかし、商談ははかどらなかった。そのアメリカで永田はあることを耳にする。
「アメリカではプロ野球の球団を持っていることは尊敬されるそうだ。日本でプロ野球のオーナーになれば、アメリカでも商談が進むと思うのだ」。
永田はインタビューで球団を持つに至った理由をこの様に語っているが、もう一つ理由があった。それはGHQとの面談でホイットニー少佐からプロスポーツに関わることを提案されたからだ。当時、公職追放されていた何人かの面倒を見ていたが「スポーツによって日本国民に活力を与えられること、追放中の人物もスポーツに関わることは問題ないこと」を聞かされたのだ。当然、この時、GHQが国民の活力の一つとしてプロ野球を後押ししていることも知ったはずだ。
永田は球団結成を決める。思い立つと、すぐ行動に移すのが永田という男だ。大映球団の結成に向け具体的に動き出す。そんな時、中日ドラゴンズで騒動が発生する。
中日ドラゴンズの系譜は戦前の名古屋軍に遡るが、戦中、戦局の悪化に伴い、プロ野球界も苦難の時代に突入した。中部日本新聞社(現・中日新聞)の支援を受けていた名古屋軍も、戦時体制の下、中部日本新聞社が経営を続けることが難しくなった。そこで、球団は中部日本新聞社社長・大島一郎オーナーの個人出資で乗り切ったが、名古屋軍の理事だった赤嶺昌志が残った選手をあの手、この手で選手をかばい、つなぎ止めた事が戦後のドラゴンズ復活につながっていた。
そして戦後、1947(昭和22)年、球団名を中部日本ドラゴンズと改名。すると、中部日本新聞社は出資していなかったにも関わらず球団経営に介入し赤嶺と対立した。そして、居場所を失った赤嶺は退団した。これに、戦中に球団を維持するために奔走した赤嶺を慕っていた選手が反発。中日ドラゴンズの25選手中、12選手が赤嶺を追って退団する騒動が起こっていた。
この受け皿になったのが、新規参入を目指していた永田の大映球団だった。赤嶺を球団役員に迎え入れるとともに、赤嶺を追って退団した7選手を入団させた。逆に、永田はこの騒動があったからこそ、大映球団の結成を思い立ったのかも知れない。
翌1948(昭和23)年1月10日、永田は満を持して「大映球団」として日本野球連盟に加入を申請する。しかし「球団が増えると、ようやく出て来たプロ野球の人気低下を招きかねないと反対する声が大きく、新規加入は認められない」と跳ねつけられる。日本野球連盟に対抗するべく、前年47(S22)年に発足したもう一つのプロ野球リーグ「国民野球連盟」が存在したが、その中心球団「大塚アスレティチックス」と大映球団が巡業試合を行っていたことも問題視された。加えて、永田に対する警戒感があったことも後の資料で明らかになっている。
そこで挫けないのが永田という男だ。「新規加入は認められない」ならばと、既存球団の買収に方針を転換する。ターゲットは前年から球団運営に乗り出したものの、本社で赤字が問題となっており、本業でもつながりが深い「東急フライヤーズ」だった。永田は、東急グループの総帥・五島慶太が「球団売却を決めた」という情報を聞きつける。旧知の間柄である五島と接触し、好感触を得ていた。
しかし一転、東急は球団を手放さないことになった。役員会で「球団を維持すべき」との声が上がったという。声を上げたのは経理担当役員の大川博だった。大川はその後、東急球団の運営を任され、東映社長として東映フライヤーズのオーナーとなり、永田と再三ぶつかることになるから面白い。
そこで、永田は再度方針転換し、東急に資本参加を申し入れる。東急側では反対の声も上がったが、本業のつながりもあるため「無下に出来ない。資本参加なら断れない」(五島オーナー)と「1年限りならば」と承諾する。ここに「急映フライヤーズ」として、翌1948(昭和23)年2月28日、日本野球連盟に承認される。資本参加という形だが、永田のプロ野球界への第一歩となった。
さて、この時、もう一つの合併も承認された。前述の1シーズンで解散した国民野球連盟の「大塚アスレティチックス」が、運営に苦しんでいた「金星スターズ」を買収。両球団が合併する形となり、同じく2月26日、大塚がオーナーとなった「金星スターズ」がスタートした。
この大塚と金星の合併にも永田が一役買っていたと言われている。大塚アスレチックスの大塚幸之助大塚製作所社長と永田は懇意にしていたからだ。大映単独参入のネックとなった巡業も行っている関係だったからだ。
永田が単独参入を断られた際、日本野球連盟の鈴木龍二会長が「金星スターズ」を買収したらどうかと勧めた。しかし、永田は金星スターズを大塚に譲り、自らは急映フライヤーズの資本参加に留まったのは、永田自身がまだプロ野球界に警戒心を抱いていたのではないかと思われる。
約束通り、永田は1シーズンで急映フライヤーズを離れ、大塚が持っていた金星スターズを買収した。大塚の本業が一転経営難に陥ったため、250万円で大塚が購入した球団を1,000万円で買収した。永田の「困っている姿を見ると、素通りできない」という情けの厚さが分かるエピソードだ。
永田は球団名を「大映スターズ」と改め12月21日に承認され、念願の球団オーナーとなった。翌1949(昭和24)年から大映スターズとしてペナントレースに参入した。2リーグ制となる前年である。
話しは逸れるが、永田の多彩な営業戦略が垣間見れるエピソードを紹介したい。この大映と大塚の巡業は九州で行われたが、当然、まだ世に出ていない球団とほとんど知られていない国民野球連盟の球団の試合では、盛り上がりに欠けていたと思われるだろう。しかし、巡業は各地で盛り上がった。何と、永田の命令で大映所属の俳優が次々と現地入りして盛り上げたという。採算度外視のイベントかと思われるが、これは映画のキャンペーンでもあった。相乗効果が生まれ、球場も映画館も満員になったそうだ。テレビがない時代ならではのエピソードだが、永田の営業嗅覚の鋭さが感じられる。
ここで、オリオンズの傍流の元となる、永田が買収した金星スターズにも触れておきたい。
戦争が終結した1945(昭和20)年、早くも既存球団が「復活宣言」を出し、東西対抗戦が行われたことは前述したが、翌46(S21)年にはリーグ戦が復活する。この時、復活宣言した読売、名古屋、阪神、阪急、近畿日本(後の南海)、朝日(後の松竹)の6球団に加え、新たにセネタース(後の東急)とゴールドスターが加盟した。このゴールドスターが大映スターズのスタート地点である。
一説では、このゴールドスターのスポンサーは田村駒商店であり、戦前の大東京ライオンの流れを汲むものだと言われている。しかし、球団の系譜を見ると、戦前の東京ライオンは松竹ロビンスに引き継がれており、ゴールドスターは戦後の新球団の扱いである。調べると、終戦直後の混乱が、この両球団に関係していた。
東京ライオンは1937(昭和12)年に大東京として発足した球団だ。野球好きだった田村駒商店の田村駒治郎社長は、大東京新設時から資本参加した。そして、翌38(S13)年には球団の全株式を取得して球団のオーナー企業になって収まった。その後、戦中は朝日軍、戦後はパシフィック→松竹ロビンスと球団は存続しているので、前述のゴールドスターとは系譜としては交わらない。
ところが、松竹ロビンス側の歴史を紐解くと、意外なゴールドスター誕生の裏話が出て来る。
戦争が終結し、日本野球連盟会長・鈴木が呼びかけ、終戦直後に表明した復活宣言に、朝日軍の代表として誰が出席したか不明だが、朝日軍は加わっている。しかし、戦中にチームは奈良県御所市(当時は御所町)の傘下の軍需工場に疎開していた。チームを一任されていた工場長の橋本三郎は、田村と連絡がつかなかったので、独断でチームを「ゴールドスター」として日本野球連盟に加盟を申請してしまった。
ただ、選手たちは疎開中に田村駒から一切の連絡が無かったことに「見捨てられた」と大いに不満を感じていた。そんな後押しが橋本の背中を押したのだった(一説には、橋本が独自に球界参入を狙っていた、という話もある)。
田村は激怒して抗議したが、鈴木の説得を受けて納得。朝日軍をパシフィックに球団名を変更し、新たにチームを作った、というのが真相である。
つまり、ゴールドスターは球団の系譜上は新球団であるが、中身は戦中の朝日軍であり、系譜を朝日軍から引き継いだパシフィックだが、中身は新チームだったのである。
オリオンズのもう一つの系譜であるゴールドスターの誕生は、終戦直後のゴタゴタから生まれた球団だったのである。
次回は、いよいよパ・リーグのために動き出す永田を追っていく。
(2)1951(昭和26)年 永田雅一の「プロ野球の理想」

話しが「ゴールドスター」の誕生秘話に流れてしまったので、話を永田に戻したい。ただ、マリーンズファンならば、オリオンズの「もう一つの流れの傍流」の誕生経緯は知っておいてもらいたいと思い記した。
ここから先は
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?