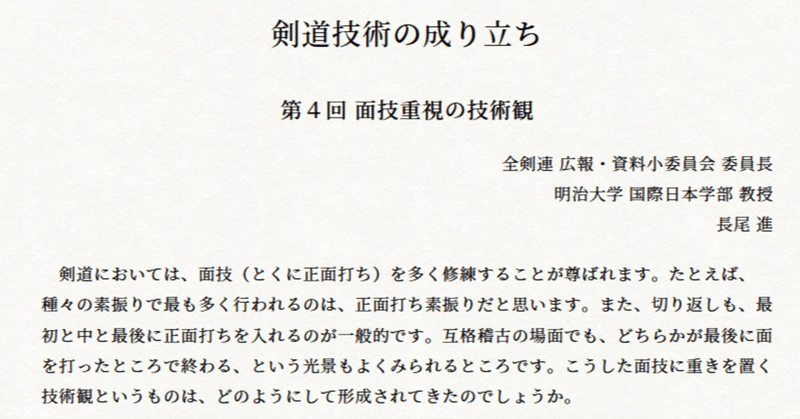
剣道では『肩への袈裟斬り』が打突部位とならなかった理由についての考察。
きっかけは、「月刊秘伝」編集部@hiden_babさんの、ツイートを拝読したことでした。私は剣道史について勉強していますが、剣道がどのような技術史・思想史を経て現代の形へと成立したかという問題の中で、面技中心の技術観の成立に関わる歴史は極めて重いウェイトを占めており、先行研究も多数存在致します。そこで、この機会に自分のこれまでの剣道史についての勉強内容を私見も交じえながら要約してみたいと思います。素人の拙い要約ですが、ご興味のある方はご笑読下さい。
質問ですが、“なぜ、剣道では『肩への袈裟斬り』が有効打とされなかったのでしょうか?”
— 「月刊秘伝」編集部 (@hiden_bab) April 1, 2023
この場合、左胴で言われる(?)ような「刃筋が狂いやすくなる」は、切り返し稽古の存続、左右面の有効打としての存在から却下とさせて頂きます。どなたか、合理的な説明をいただくことはできるでしょうか?(S)
①実際に肩首を打ち合った素面素小手の試合記録。
剣道の前身、あるいは初期の剣道そのものである剣術の撃剣稽古……榎本先生の定義に拠るなら、頑丈な防具を着用してのシナイでの自由打突……が発達する以前、木刀や袋シナイを用いた稽古が行われていた事は、皆様ご存じかと思います。幾つかその実例の記録をご紹介致します。
まず、有名で情報が多いものとして『疋田豊五郎入道栖雲斎廻國記』が挙げられます。新陰流開祖上泉伊勢上の弟子、疋田豊五郎の廻国記です。この廻国記には見所が多いのですが、今回はシナへ(袋シナイ)を使った打突部位に着目してみます。使用回数を大雑把に数え上げてみたところ、

頭・13回
首・3回
手・6回
腰・1回
足・1回
肩・1回
鼻・1回
となっておりました。記述の半分が頭ですね。さて、荻生徂徠の鈐録には、
敵ノ頭ヲ目当ニシテ打ツヲ第一トスルハ、治世ノ結構ナリ
という言葉が残されています。
相手の頭を狙うのは太平の世のやり方である(非実戦的である)という意味合いの批判です。
しかし、この疋田豊五郎廻国記に記された立ち合いの時期は16世紀末から17世紀初頭であり、鈐録が著された18世紀初頭より100年以上も遡ります。
つまり、戦国時代末期でも、廻国修行の場に於いては、使用する得物がやシチュエーションなどは後世の試合に比べて遥かに無秩序ですが、その中にも一定の競技性やコンセンサスが存在したことを意味するのではないでしょうか。
疋田豊五郎より少し時代は下がりますが、宮本武蔵の言葉として、小倉碑文にも
且つ定めて云く、敵の眉八字の間を打たざれば勝ちを取らずと。毎に其の的を違はず
とあり、江戸時代初期には、相手の頭を狙って打つ事に対する規範意識が既に存在していたようです。疋田豊五郎のシナエでの打突部位が頭が有意に多いのは、その黎明期と見ることも可能かもしれません。
ちなみに、袈裟懸けは実戦的な太刀筋、というイメージは強いですが、それは本当に正しいのでしょうか?
幕末明治の剣士渡辺昇は、実戦の所感を「真剣での太刀筋はこの一通り」と相手の肩口に竹刀を掛けて説いた逸話が残っていますし、同時期の神道無念流の大家・根岸信五郎も戊辰戦争での所感を体ごと袈裟懸けにぶつかっていくしかなかった、と中山博道に説いています。吉村先生の神風連の乱の刀創のご研究でも、太刀筋の分類の中で、左袈裟斬りの傷が全体の二割を占め、突出していました。

この理由を、吉村先生は
神風連の参加者も武士として、所属する流派で稽古をして、左袈裟、右袈裟、いずれの斬り方を使えたものだと思われるが、闘争の興奮・緊張状態において、まず振りやすい左袈裟が多用されたものと考える。
と考察されていますが、とても納得がいく御高察です。
素肌での実戦の斬りあいに於いては、袈裟が頻出したと考えるのが妥当だと私は考えています。
参考リンク:日本刀を片手で使う技と剣豪疋田文五郎回国記にある片手打ちの逸話
②防具の発達と、素肌稽古との過渡期。
袋シナイの普及の後、正徳年間に直心影流によって防具が完成され、宝暦年間に一刀流中西派によって改良が進んだとされます。しかし、その普及は流派や地政学的条件によってまちまちで、完全に統一されるのは明治を跨がなければいけませんでした。
榎本鐘司先生は、1832年に著された『四芸沿革考』を参照して江戸時代の試合形態を考察されていますが、
素肌で木刀使用の打ち合い試合
竹ひご面(顔面のみ覆う)を付け木刀で打ち合い試合
布団付竹ひご面及び小手を付け、袋シナイ使用
布団付面、小手、竹具足(胴)を付け、四つ割り竹刀を使用して試合
の四段階に変遷を纒めています。直心影流が3中西派の改良が4です。4には長竹刀を当時の撃剣界に持ち込んだ大石進による改良の影響も大きいです。
これらの採用の段階は流派によってまちまちで、他流試合の際にそれらを擦り合わせながら行った記録が多数残っています。
出羽国・武田軍太「武元流剣術実録」では、素面素小手で簓刀(袋シナイ)を用いることを他流試合の条件とし、相手がどうしても防具を使用したいと申し出た場合も、自分達は素面素小手で勝負を行っています。
金面(面がね)と皮帽子(面布団)という用語が使用されており、当時の山形県の防具の発達段階が垣間見えますね。
この「武元流剣術実録」には、他流試合を行う時は、道場を訪問した者が、赴いた先の道場の流儀に従うのが慣例である、という旨の記述があります。

上記のような感覚は、近い時代の直心影流と鏡心明智流の試合の記録からも見てとれますが、面白いのは、桃井春蔵と菊池伝次・大野喜亦の試合は「入門するかどうかの力試し」という名目で防具着装で行われ、次は他流試合という名目で素面素小手で行われています。
さて、この試合も打突部位を見てみましょう。 勝敗と打った部位は、軽米先生の『直心影流の研究』から引用致します。
防具着装の試合

左小手 4回
右小手 2回
足 1回
小手(不明) 1回
正面 1回
部位不明 1回
素面素小手の試合

首 5回
面 5回
頭 1回
眉間 1回
脇腹 2回
肩 2回
小手(腕) 2回
試合運びは時によって変わるので、確定的なことは言えませんが、明らかに素面素小手の試合の方が打突部位の自由度が高く、防具着用の上での試合は、基本的に打突部位を防具に限定しているように思われます。
首や肩といった部位の打突も多く、二刀で首を挟む、空いた片手で掴んでから打つなど用法も様々です。
同時に、真正面という記述も多く見られ、真正面を打って勝つことに対して一定の規範(価値)を見出しているようにも思われます。
剣術の中に撃剣稽古が受容されていく過渡期の面白い記録です。
③幕末から明治にかけての面技重視の価値観の形成
さて、上記のように『防具着装の上で稽古する場合は、防具を打突部位とする』というコンセンサスが、剣道具の発達史に随伴して成長してきました。
これらは、所謂幕末の新流――北辰一刀流、神道無念流など、江戸に大道場を構え、シナイ稽古を専らとする道場では、常識的なものとなってきたようです。
北辰一刀流千葉周作の『剣術修行心得』では、
名人と雖も、面籠手胴の三か所しか攻撃してこないので、それらを擦り上げ、切落し、引き外しなどして応じれば負けるものではない
と説いていて、打突部位のみを打つことが常識化していることが伺えます。
これらの中に肩首が入らなかったのは、初期の面が皮帽子などと呼ばれたように頭上から発達したこともあるでしょうし、肩への打突は鎖骨骨折などのリスクが高く危険だったこともあるでしょう。
突き胴が打突部位として発達するまでにも、大石進らによる防具の改良を待たねばなりませんでした。
これら、剣道具の発達と並行して、『面を打って勝つ事こそ、至上の価値である』という価値観の醸造が、剣道史の中で存在致します。
これらについては、長尾進先生の論文『近世・近代における剣術・剣道の変質過程に関する研究~面技の重視と技術の変容~』が最も詳しいので、ご興味のある方はそちらを読んで頂きたいのですが、かいつまんで要約致します。
修行方法論としての面技の重視は、男谷の講武所の時代からその端緒が見られます。
竹刀を三尺八寸に定め、流派を超えて撃剣(剣道)を行った講武所の頭取、窪田清音は、
うち所は面の真中と左右と裏篭手をうつべ し(中略) 夫がうちにも、面を数々多くうたんことをおもふべし
面に篭手に数多くうつべきことなれど、夫がうち面をうつことをむねとして、十度のうち面を七度、こ手を三度うちならふべし
と説いています。現代の剣道の稽古風景にかなり近づいてきましたね。
また、面は打ちにくい場所故、優先して稽古しなければならない、という修養主義は、諸流に見られます。
例を挙げば、天真白井流では
業の内上段より快く面を打を構第一とす(中略)至てなしがたき業なれば
と評価しています。
また、現代剣道の祖の一人、内藤高治も敵に対して面を打つが一番打ち悪い、と述べており、その言葉の原型は、水戸東武館を通じた北辰一刀流の教えであり、遡れば、千葉周作の『相下段・相星眼ニテ向フノ面ヲ打ツ節』の『甚ダ無理ニテ節二当ラヌ』という説諭であり、幕末では珍しくない考え方だったことが伺えます。

これらの風潮は、先の実戦で一番使い易い(出やすい)技は袈裟である、という話からすると、競技・あるいは修養論に偏って、とても非実戦的なものに思われるかもしれません。
しかし、幕末という動乱の時代にあって、これらのドクトリンに基づいた稽古を行って育った剣士達も実戦の場に出ることになりました。
そこで起こった変化を、競技的な技術の再実戦技化だと私は考えます(ここは私見です)
先に名を挙げた神道無念流の根岸信五郎は『撃剣指南』で、戊辰戦争の経験を元に
敵手ノ頭部中真即正面ヲ撃打スルコト二心ヲ用ユベシ
と、上段からの面打ちに利があると説いています。
西南戦争で抜刀隊を率いて勇名を上げた隅元実道も、兵字構え(上段)の実戦性を、
面の急所なるには、多少の前後も、何処の局部も、及ばさればなり
と説き、自流の剣術試合審判で、面を最高得点とし、小手、胴、突き、と点数に傾斜をつけて評価しています。
これらは、撃剣で鍛えた世代が実戦の場で戦って発生した、観念的な技のバトルプルーフの獲得と、技の実戦技としての再評価と言えるでしょう。
④剣道に於ける打突部位の標準解釈
上記、難しい部分から稽古すべし、という修養論と、技の正道として最も適うものが正面打ちである、という観念は、剣道が学校教育として普及する時代にはほぼ定着し、広まっていきました。
大日本剣道史を著した堀正平も、技に正奇があり、
何事を学ぶにも正則を先にして変則を後にすべし
と説き、面については正面から遠間で打つことを正則と説いています。
また、
実戦で一番斬りやすいところは肩であるという。面の練習ができていれば肩を斬るのは易々たるものである。また面を打ち外しても肩は斬れる
と説き、面を打つことが正則、肩首を打つことは変則である、という観念を明白に述べています。
これらの言葉を、当時の大家が異口同音に説いているので、戦前の武徳会の時代には、剣道の打突部位制定理由の『標準解釈』として広まり定着したものと考えられます。
(繰り返しになりますが、これらの観念は、大筋は幕末の講武所~江戸の大道場では、既に大筋に於いて共有されてきたものです。北辰一刀流の剣術六十八手は面技が筆頭としてあげられ二十手が収録されていますが、肩に落す技は存在致しません)
『最も実際的な学生剣道の粋』を著した富永堅吾も、
面業は剣道の業の内で最も大切な業であり(中略)多く修行し、而も最も正確に練らなければならない業
と説いて剣道教育を主導しました。
富永と同じく、初期の剣道教育に携わった金子近次は、
何故 正面、篭手、右胴、前突の四 ヶ所のみを選定して練習するかの理由は (中略)全身の内で最も重要なる機能の存在して居る場所を撃突さるれば他の所に比して戦闘力を早く失ふ所と、全身中で最も撃突するに 困難な所との二の見地からして以上の四ヶ所を選定したのである
と、実戦性を含めて説いていますね。
剣道十段として戦後剣道を主導した斎村五郎らも、これらの路線を踏襲しています。
纒めると、剣道は、一刀流等から正面を打って勝つというドクトリンを濃く継承した武道であり、それが防具の発達という物理的制約に随伴して発生した打突部位観念が車の両輪の如く結合し、正面打ち志向、肩首を打つ事を戒めるという風潮が出来上がったと考えられます。
例外的な例として、幕末には『外処を打つ』と称して防具以外を打ったり(脇つぼを突く、と称する腋下部への突きの記録があります)する例もあったようですが、剣道の近代化に伴って消滅していきました。
戦前には、片手技などで水平に横面を打ち、『抜く』と称して鼓膜を破る行為が常態化していたりしたそうですが(剣道日本より)、危険が大きかった事や『横技に大家なし』という言葉を用いてそれらを戒める風潮もあり、横面はこめかみから上に留まっています。
⑤余禄
剣道に肩打ちが存在しない理由を、歴史的経緯を含めて、上記のように考察してみましたが、如何でしょうか。
余禄として、現代剣道で私が触れた肩打ちの技を幾つかご紹介致します。
剣道をされている方は、そんな誰もが知っていること、と思われるかもしれません。
・肩は有効打突になるか。
私が最も尊敬する先生の言葉で感銘を受けたのが、面を首を傾げて逸らすな、です。首筋や肩口に刀が落ちても人は死ぬ、面打ちが首筋に勢い良く当たったら、私は迷わず旗を上げる、と仰ったのを良く覚えています。
現在の競技で旗が上がることはまずないでしょうが、その気持ちは忘れずに稽古をしたいものです。
・首筋に竹刀をかける使い方
首筋に竹刀、稽古や試合の場では、良くあります。
鍔競りからの崩しで、首筋にかけた竹刀で一瞬体勢を崩して体を入れ替えたり、あるいは、小柄な相手に小手を打たれたら、肩口に竹刀をかけて残心を潰されることもある、と荒いやり方を先生に習ったこともあります。
私も実際に肩口から竹刀で潰され、両膝をつかされた事がありますが、圧が強くてびっくりしました。
荒稽古は最近は少なくなりましたが、残ってる所には残っています。現代の剣道にも有効打突ではありませんが、肩口にかけた竹刀を使う技術があちこちに散らばっているので、触れてみるのも面白いかもしれません。
⑥参考文献等
図書
論文・参考サイト等
NDL
撃剣指南
武道宝鑑
剣道集義
武道教範
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
