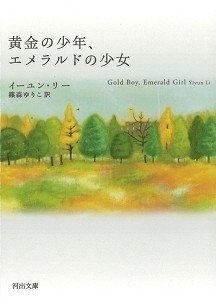第二回おぺんぺんの会
第二回おぺんぺんの会では、課題図書の太宰治の「女生徒」とアラン・シリトーの「漁船の絵」、当日図書のイーユンリーの「流れゆく時」について話しました。第一回目の議事録のしょぼさを反省したので、今回は長いですよ!!
太宰治「女生徒」(新潮文庫『走れメロス』収録)
(虎)実は今回の課題図書二つにはテーマがあってね。それは独白形式の一人称の小説。しかも「女生徒」は女目線、「漁船の絵」は男目線。でもテーマでこれからもやっていくとなると大変なので、図らずもそういうに二編が選ばれたということにして。
(ラ)うん。
(虎)「女生徒」はそもそも太宰がファンの女の子から日記が送られてきてね、その日記を元にして小説にしているわけ。
(ラ)ほぇ〜!
(虎)その日記のほとんどをそのままにして1割自分で手を加えたって言われてるんだよ。太宰ファンのアリアケナントカさんっていう人の文体をそのまま残して書いてるわけよ。この女の子は18、19歳くらいでしょ? 多分。高校生とかさ、大学入ってちょっとくらいとかさ。やっぱその当時の、当時はどうだかわかんないけど、その年齢特有のさ、二転三転する様子がさずっと描かれてるじゃない。醜い醜い!って思ったら、可愛い可愛い!って思うし、友達と仲良い!仲良い!って思ったらなんか急にいやんなってプイってなるし。ジャッピーのこと殴ってたと思ったら可愛がるし。本当にその情緒の不安定さというかね。情緒不安定っていうとなんか精神病っぽくなっちゃうけど揺れ動く思春期の女性の心の機微っていうのがすごい細かく、なおかつ具体的に描かれてる。料理とかもさ、
卵のかげにパセリの青草、その傍に、ハムの赤い珊瑚礁さんごしょうがちらと顔を出していて、キャベツの黄色い葉は、牡丹ぼたんの花瓣かべんのように、鳥の羽の扇子のようにお皿に敷かれて、緑したたる菠薐草ほうれんそうは、牧場か湖水か。
こういうのとかも非常に面白いというか。実際、目にしてないとわかんない独自性があったりとか。この短編の長さって60ページに満たないくらいの長さだけど、60ページの間でどれくらい時間経過してるかって言ったら1日でしょ。朝起きてから、寝るまでじゃん。これがやっぱり長編だと難しいよね。短編ならではの時間設定。こういうダラダラと自分の思いだけをダッーっと書いてるだけのものって1日を描くだけで60ページになるわけでしょ。でも逆に360ページにはなんない。疲れちゃうんだよ。読んでる方も。細かいところまで描かれてさ。だから程よいよね。短編ならではだよね。あと女性の気持ちをなんで太宰はここまでわかるんだって思うよね。
(ラ)うん。
(虎)当然、日記もらってるからわかってるんだろうけどさ。それでもやっぱり小説になっているわけなんだから、しっかり踏み込んでいかないといけないわけでしょ? 逆に女の人だったら描けない気がする。
(ラ)そうなの?
(虎)描けない気しない? 女性の作家でここまでなんていうか合ってるか合ってないかは別としてよ? コロコロコロコロ変わるような、その時どう思ってどう感じたかとかさ、あんまり見たことないよね。
(ラ)たしかにこんな可愛いらしさが残る感じにはならなそうだよね。
(虎)もう少しリアルな感じになるよね。あんまり女性、女性言いたくないけど、これが文学の面白さなんだと思う。逆に女性がさ、男性のことを書いて、女性が書いたとは思えないほど男性のかっこよさを描いてるってなったらさ、それはやっぱり文学の面白いところなんじゃないのかな。やっぱその友だち云々もそうだけど母親に対する感じなんかもね。複雑な思いとかさ。
(ラ)男の人出てこないよね、労働者くらい、もしかしたら先生もだけど細かく描かれてないよね、あとは死んだお父さんとかさ。
(虎)読んでるとやっぱりイライラしてくるもんね。
(ラ)そう?
(虎)バカだなぁとか思ったりしちゃうじゃない。時代背景を考えるとさ、いいとこのお嬢さんなんだよ。
(ラ)それはわかるね。
(虎)戦時中でさ、物も少ないのにさ、5月になったらキウリを食べたいわとかさ、ぽりぽりとか言ってさ。それで修身の話してるでしょ? 学校で修身の話してて、修身なんて一生懸命やってたらバカ見るわとか書いてある。この戦時真っ只中の話だろうに。要はなんか太宰っていうのは戦争とキリスト教だよね。キリスト教っていうかキリストだよね。それを感じる部分があって、”女がキリストなんていやらしい”とか言ったりね。あといわゆる普通の小説に比べるとさ、点が多いよね。
(ラ)あとさ、「は」とか「を」とかも抜けてたりするからテンポがいいよね!
(虎)例えばどこ?
(ラ)・・・
(虎)まだ?
(ラ)・・・ 見つからなかった。
(虎)・・・まあいいでしょう! でも恥ずかしくなっちゃうなぁ大人になってこういうの読むと。
(ラ)そう?
(虎)基本的にはこの女の子自己陶酔しまくってるじゃない。
人のものを盗んで来て自分のものにちゃんと作り直す才能は、そのずるさは、これは私の唯一の特技だ。
このズルさにも嫌になるとか言ってるけどさ、はいはいチュッチュって感じだよね。雑誌の悪口言ってるところとかもおもしろくて。なかなか的確なことは書いてあるけれども個性がない、深くない、ダメダメばっかり言っていて正しいものはない、正しいものを書いてそれを言ってくれれば私はその通りにするみたいなこと書いてあるでしょ? キリストを待ってる感じするよね。はい、次々!
アラン・シリトー「漁船の絵」丸谷才一 訳、河野一郎 訳(新潮文庫『長距離走者の孤独』収録)
(ラ)ちょっと話すこと考えるから待ってね。
(虎)え、考えてなかったの?
(ラ)だってそんなにうまく話せないでしょう
(虎)うまく話せなくていいよ。訓練だから。
(ラ)「漁船の絵」はさっきの(太宰治)と違って10年くらいのことを書いてるでしょ?
(虎)そうだね。
(ラ)だけど、思い出してるときのことを書いてるってことだよね。しかも、二人の話を書いてるけど、男側からの話しかないから、本当かどうかわからないっていうか、すごいロマンチックに書いてるけど、女側はそんなふうに思ってないかもしれないって思いながら読んでたんだけど、いい話だなぁって。なんでかっていうと、いい話っぽく語られてるけど女がやってることは結構ひどい。本を燃やしたり絵が欲しいって言ったのに質屋にいれたり、金貰うためだけに来て、でまた絵欲しいって言ってすぐ質屋にいれるじゃない。
(虎)うん、ひどいよ。
(ラ)だけど、そのことすら死んじゃった今現在からしたら良い思い出みたいに男の中ではなってる。
(虎)そうだと思うよ。男性側からいうと、男ってそういうところあると思うんだよ。結構ひどいことされても、当時はむかつくし、目潰ししてやろうかなって思ってると思うんだけど、そういうことは残さない。たぶん、どっかで自分をよく見せたいって思ってるんだと思う。この主人公は。シリトーかもしれないけど。独白形式だからこうしか書けないじゃない。三人称だったら書けるかもしれないけど。
(ラ)あとさ、あの頃の若いテンションみたいなのが10年ぶりに会ったときにはもうなくなってたってことでしょ。完全に女の人は好きじゃないじゃん。
(虎)男も好きって感じではないでしょ。
(ラ)え、好きでしょ?
(虎)もう一回結婚したいとかそういう感じじゃなくて。いい女だったなっていう好きよ。
(ラ)でも結婚しようって言われたらするって。
(虎)するでしょ。最初はだって10代とかでしょ。好き好き好き好きって感じでしょ。それから時間の幅があってさ、一回離婚してるわけだからさ。実際は籍を抜いてなかったみたいだけど。
(ラ)しかもさ、会って喋ってることってさ、昔の再現みたいなことしてるでしょ、時間が進んでるようで進んでない。女はその時間を過ごすことでお金が貰えるっていう。しかも6年一緒にいた人がいたしね。でもそういうことをさ、男は悪く言うわけでもないじゃん。
(虎)ちょっとスカしてるよね。まぁでもそういう感じなんじゃないの?
(ラ)もしこういう立場に大虎さんがなったらブチ切れ?
(虎)経験したことないからわかんないよ。
(ラ)最後の文章だけさ、〜だからいけなかったんです。っていう言い方なの、いいよね。でもさ、俺たちは二人ともって言ってるけどさ、女の方はしてたよね。愛のために。結婚しよって約束してたよね?とかさ。それが向こうの気持ちがなくなったから成立しなくなっただけだよね。なのに俺たちはとか言って。
(虎)それはそうなんだけど、小説としてはそれでいいのよ。
(ラ)どうして?
(虎)そういうふうに書かれてあることでその小説がよくないものかというとそうじゃない。バカだなぁこの男は、で終わり。そういうところだぞ、終わり。男にとってはそう思っちゃってるわけだからね? これが一人称の小説の面白いところでね。
(ラ)そうか!そういうことか。
(虎)これが神の視点とかだったら、全然違うけどね。客観的に書かれたりすると著者は責められるけど。自分が見て自分が感じたものを独白形式で書いてるから、男にとってはの話だから。
(ラ)泣いちゃう話でしたね。
(虎)短い中でこんだけ時間の幅を描いて。いろんなことがあったけど、大したことはないじゃない。男の生活もさ、金持ってなさそうだけどなんか充実してそうじゃない。本読んで、映画観て、酒飲んで!
(ラ)なんなりと生活出来ちゃってるのも切ないよね。もし、生活力なかったり、やけ起こしたりしてたらまた違うかもしれないけど。
(虎)どっか飄々としてるんだと思うんだけど、隠れたロマンチシズムがあるっていうのはさ、憧れちゃうよね。素直になれよって思うけどね。
(ラ)素直になれなさっていうのは自分が一番分かってるよね。
(虎)でもそれも27年経ってようやくわかったんだよね。
(ラ)遅いよ〜。
(虎)だから切ないんだよ。でも僕一番気になったのが、
それは鱈や穴子の骨みたいにひっかかって、ときどき夜ベッドでそのことを考えてると、気が狂うほどくやしくてやりきれなくなる。
(虎)タラやアナゴ食ってるのかって思ったよね。思わなかった? 骨が喉に刺さるといえば金さん銀さんの金さん思い出すよね。
眼玉が溶けるくらい泣きたいと思った。
(虎)ここも激切なだよね。目玉溶けるくらいってすごいやん。熱湯だよ?
イー・ユンリー 「流れゆく時」 篠森ゆりこ 訳
(河出書房新社『黄金の少年、エメラルドの少女』収録)
(虎)アイリンはすごい平凡な人だよね。
(ラ)でも、アイリンはなんでもやろやろ!っていうタイプなんだよね?
(虎)それも小説の難しいところでさ、アイリンの視点で描かれてるからこういう風に語られてるけど、状況がそうさせてるっていうのもあるよね。
(ラ)契り交わすのも?
(虎)契り交わすのが彼女が言い出したっていうのが本当なのであれば、後半も結婚させればって言わせる状況を二人が作らなきゃいけないじゃない。それが何かって言うと、自分は結婚していない、でも後の二人は結婚して子供もできている。生まれも1日違いである、っていうのは、本人は平気だろうけれども、二人からしてみると除け者にされてるんじゃないかって本当は思っていたんだと思うよ。
(ラ)アイリン自身が?
(虎)じゃないとあの一節はないと思うよ。
除け者にされたように感じていないか、二人が心配しているのは愛林にもわかった。
(虎)除け者にされないように結婚したら?って二人に促したんでしょ。契りもなんか分かんないけど、そういうことがあったんじゃないかって推測できるでしょ?
(ラ)空気読んじゃう人ってこと? たしかに自分の息子がポルトガルに行くって決めた時も言っても仕方ないって次の次のことを考えて何も言わないもんね。
(虎)弟と妹に気づかれないように砂糖きび食わせとくとか。気遣いしすぎちゃうところがあるかもしれない。だとしたらこの後、この三人が再開する可能性っていうのは残されてるよね?
(ラ)最後?
(虎)だって彼女は考えすぎちゃうんだから。孫にも言われてるように。
(ラ)孫は、アイリンが思ってるけど言わないようにしていることをズカズカ言ってくるからしんどくなっちゃうんだよね。
(虎)しんどくなるけど、救いにもなると思う。だって、アイリンの論理ってめちゃくちゃだもん。
(ラ)でも一回は手紙を出してるわけじゃない?
どんな言い逃れを見つけようとも、三人のうち借りを負ったままなのは愛林だけ。
(虎)おかしいでしょ? でも借りがポイントなんだと思うよ。
あなたには梅に対して息子という借りが、私に対しては娘という借りがある。
(虎)おかしいでしょ?そもそも。不条理だよ。アイリンにとっては。
(ラ)二人にとっては関係ない人を責めた方が気持ちが楽っていうのはあるけどね。
(虎)そうそう。本来から梅は蘭を責めるべきだし。でも元を辿ればみたいな、でもそうなると宇宙の爆発から責めなくちゃいけなくなる。そうでしょ? 人類の存在の否定の話になっちゃう。だから、どっかでこの負の連鎖は止めなきゃいけない。アイリンにとって不条理なんだよ。
(ラ)それで、どうして再会の可能性があると思うの?
(虎)自分のこと責めすぎだから。30年経ってるわけだから。もしかしたら借りが…とか言っちゃったってなるかもしれないじゃん
(ラ)向こうも?
(虎)アイリンが気にしすぎだよ。あまりにも。気が利いて仕方がないわけでしょ。それは所々に書かれてる。それでもこれを物語化するってことはどこかに救いがあるわけでしょ?ない?
(ラ)むしろ、契りのことなんて忘れる方がいいんじゃないかな、考えなくて済むから。
(虎)考えちゃうんだよ。不条理だから。なんかのきっかけでトランクから出てきた、孫娘が気になる写真を大っきくした。意味ありげじゃない。なんでそんなことしたの? 必然性がなくなっちゃうじゃない。物語にする必要なくなっちゃうじゃない。可能性の話だよ。
(ラ)インが言ってることは正しいけど、アイリンはインが若いから理解されないなぁって思ってるわけでしょ。インが言ってることはアイリンに伝わってない気がするけど、それでも可能性はあるの?
(虎)でも会話してるから、可能性はあるでしょ。会話しないと始まらないし伝わらないんだから。
(ラ)そういうことか。
(虎)罪を憎んで人を憎まずっていうことでしょ。中国は残念ながらそうじゃないみたいだね。
娘は未来を奪われたのに、どうしてあの子には未来をあげなきゃいけないの。
(虎)ひどいよ許してよって思うね。
一人称の語りって詳細なようですごい偏りがありますね。でもそれが正しいとか間違ってるとかじゃなくて受け止める、と大虎さんに教わってまた一つ本の読み方を知れたいい会でした。
次回!第三回おぺんぺんの会の課題図書は・・・
・青山七恵『かけら』収録「かけら」
・ガブリエルガルシア・マルケス『エレンディラ』収録「この世でいちばん美しい水死人」
・内田百閒『東京日記』収録「サラサーテの盤」
の三編です。当日図書は、夏目漱石の夢十夜です。
ラザニア