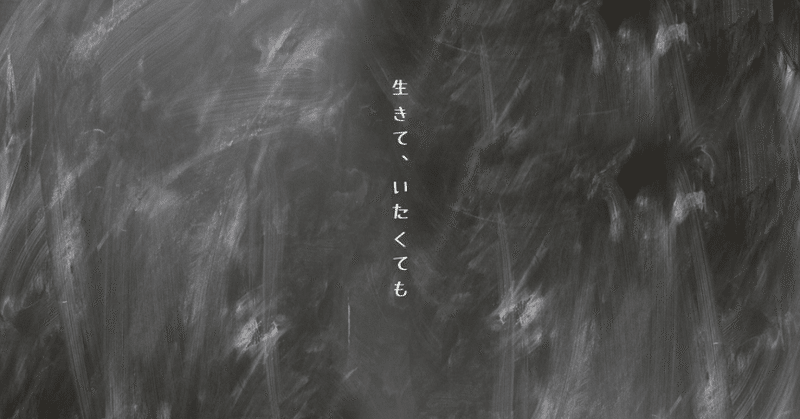
生きて、いたくても――Oct#15
我々が虐殺を免れる唯一の方法は、殺戮者に回る事。それは間違いなく、復讐を為すのに相応しい提言だ。だけどそれは額面通りじゃなくて、コノテイションを交える為に引用された章句でもあった。偶見の狙いを如実に表している。文化祭と言う区切られた空間、特別な時間に乗っかって、彼女は「何か」をやる魂胆だ。
「って言ったけどさ……、いざ自分で考えるってなるとね……難しくて」
偶見から、プランの基本理念や方向性などの概要は聞いている。把握出来たと思うし、僕としても彼女の趣旨に沿う様、一日考えてはみた。けれど、説明書だけが入ったプラモデルの箱を渡されたみたいに、理解は出来ても形に出来ない。
だとすれば。
「偶見。放課後って、空いてる?」
彼女もそれは頭にあったのか、じっと僕を見つめた後、頷いた。
三上は変わらずの定位置に居て、新しい作業をしていた。例の作品はコンクールに搬入していてこの場になく、今は審査の最中だそうだ。
その方面に明るく、相談出来る相手。僕と言う人間の小さな円の中なら、彼女以上の適任は居ない。偶見からの異論も上がらず、正しい判断だと言う確信を強める。
説明は、偶見に任せた。発案者の方が当然、コンパクト且つ詳細に話せる。復讐と言う部分は伏せるにしても、大体は分かって貰える筈だ。三上が何かアイディアを出してくれたら、多少方向がずれていたとしても、それを元に僕たちが再構成してもいい。
「って感じなんだけど、どう?」
「……二人して、そんな事考えてるんだ? でも、中身は何も決まってない」三上が小さく笑う。「何か、見切り発車だなぁ。それじゃあ今の所、やりたい、ってだけなんだね。確認するけど、例えば『ハプニング』とか『プランク』みたいな」
「うん、そうだね。つまり……『パフォーマンス・アート』を」
パフォーマンス・アート。文字通り、身体的な行動で起こす表現芸術の全般を指す。六〇年代に活発化した動向で、作品の非物体化による感覚基準の変革、行動に付随するメッセイジ性などの側面を持つ。また、技術や美しさなど、従来の美術が必要とする成分よりも、それ自体のコンセプトを最重要視した「コンセプチュアル・アート」の一形態と数える事も出来る。偶見がスローガンに設定したフレイズも、「ネオ・ダダイズム・オルガナイザーズ」と言う前衛芸術集団の第一回展に於けるマニフェストの流用だ。
僕たちのコンセプト。それが「復讐の代行」だった。
例えば、「机の上に花を生けた花瓶を置く」と言う行為を受けたとして、大抵の人は不愉快になる筈だ。つまりは「死んだ」事に見立てられたものだから。だけどその行為に全くの因果や関連性がなければ、単に「机の上に花を生けた花瓶が置かれている」だけだ。
僕たちは、それを応用した。何でもない行為を、僕たちの中でのみ「復讐」として勝手に見立てればいい。客観的には全く意図が把握出来ないとしても、こっちにとっては有意なのだ。僕たちが起こすのはその原理の延長線上、復讐を中核にしたパフォーマンス・アートになる。何も復讐と言う行為を、攻撃だけに探る必要はない。全ては価値観と意味づけの問題だ。
「どれくらいの規模を、想定してるの?」
「うーん……行動自体は小さく纏めて、活動範囲は広くって感じかな」
「小規模で広範囲、って事かな。んー、成る程ね。――ちょっと教室にメモって言うか、ノート、取りに戻ってもいいかな」
思いつきや考察、実際に見た作品の所感など、美術活動に関連した諸々の事を雑多に纏めているノートだ。適用出来そうなアイディアに覚えがあるのだろうか。領域が幅広い。
「珠ちゃん、ついて来てくれる? 行き帰りの間に、もう少し詳しく聞きたいな。宮下君は、ここで待ってて下さい」
「――えっと、宮下先輩、でしたよね?」
部員でもなければ知り合いも居ない、偶見と三上が退出してしまうと僕だけが明らかに場違いで、自分を異邦人の如く感じていた。そこに話し掛けてくれたのが星岡さん、二年の女子生徒だった。現役メンバーは二年以下だから、自然と後輩だけになる。
「もしお暇なら、そんでよかったら、前のみか先輩の時みたいに、私の作品にも感想貰えませんか? お詳しいみたいですし」
「え、あ、うん……でも、僕でいいの? 他の皆の方が、本業と言うか……」
「皆知ってるんですもん、互いの手の内って言うか、何だろ? 新鮮な目で見て貰いたいじゃないですかー。何でもいいんで、思った事とか、気になる所とか!」
しどろもどろな受け答えのまま流されて承諾したものの、初対面の相手と話すのは苦手だった。普段は上手く話題を出せないし、今は向こうから振ってくれたけれど、どれくらいのバランスで感想を述べるべきかも悩ましい。兎も角、キャンヴァスに目を向ける。
画面は全体的にヴィヴィッドに近いパステル・カラーで、漫画やアニメイションと言った二次元的なイメイジ、或いはキャラクター的な人物・動物・造形などが配されている。賑やかな構成、調和した混沌。「ネオ・ポップ」の類型と取るべきだろうか。
「そうだね、まずはやっぱり、見ていて楽しくなる絵、かな、えっと……」
「本当ですか! そう思ってくれますか、よかったぁ」
僕は何とか言葉、詳細で的確な言葉を探そうとしていたのだけれど、星岡さんはそれこそが要点だと言う様に喜んでいた。
「私、別に絵画とかって深い意味なんか要らないと思うんです。あっ、とね、これは私見ですよ? お気を悪くしないで下さいね?」
「いい、と思うよ。その、芸術観って、大事だと思うし」
「あ、さんきゅーです。それでそれで、何かを主張するのに芸術を使う人も居ますけど、所詮それって、芸術はただの手段でしかないですよね。芸術ってやっぱり、本質として『見て楽しむ』ものなんです。だから私、絵に意味なんてなーんにも込めてません。見た時の印象がその人にとっての全部で、楽しい気持ちになってくれたらそれが私にとっての全部です」
素直で純粋、それでいて、中々奥妙に一つの真理を捉えている気がする。ひたすらに楽しさだけを求める、これも一つのコンセプチュアル・アートでありながら、表面以上のものは何もないと言う自己矛盾的な否定が伴っている。常に意図的であろうとする分野のアートと真っ向から対立した批判的な考え方、僕は面白いと思う。メタファーとかも嫌いそうだ。
星岡さんの作品群は確かに僕の心を明るくほぐしてくれて、それを取っ掛かりに、彼女以外にも、多様な作品に対して批評を求められた。モネの「睡蓮の池、夕暮れ」を逆さに模写し、その絵の正しい上下を示す為にたった一つの人影だけを描き加えた「森の入り口、朝」と言う奇想の作品や、至る所に林立する電信柱とそこに架かる電線から、特に構図で映えるものを探して描く「電柱のコンポジション」シリーズなど。僕もおずおずと返しつつも楽しんだ。随分、全体的にレヴェルが高い。
そうして絵の感想と言う単一な応酬だけを繰り返す内に、少しずつ場に馴染めて、ゆっくりと話題も広がり始めた。これまででは考えられなかった、新しい繋がり、感触。
僕の未来が動いたとして、要因を集約すれば「偶見と出会った事」ただ一つだけだ。そこから分岐して、派生して、発展して。僕の「未来図」に偶見が置かれただけで、明らかな変化が訪れている。
なら、この復讐を価値あるものにだって出来る筈だ。それも、偶見に手を引かれてばかりではいられない。この手で置くべきなんだ。未来の分岐点を。
「やっほ、ちょっと遅くなったかな」
一〇分程経った頃、扉を開けた偶見は僕を見て、明らかに笑った。
「ううん、大丈夫。話、させて貰ってたし」
「みたい、ですね。だから本当に、いつでも来てくれていいんですよ」
部員たちから、同意の声が上がる。
「私の方も、意図は掴めたと思います。だから今回、試しに一度、計画は私に任せてくれませんか? だってこれ、何も文化祭の一回だけで終わらせなくても、いいですよね?」
「え? えっと……」
予想外の提案だった。その目的上、どこかで一回切りだと勝手に決めつけていたけれど、考えてみれば「復讐」にしたって、それが単発である理由や必要性はどこにもない。寧ろ全部を返し切ろうと思ったら、一回では足りない気さえする。
但し、「復讐」を伏せて話した三上に全てを任せるとなると、僕たちの意に沿わないものになる可能性があった。偶見と目を合わせると、彼女は意味あり気に頷いてみせた。偶見はこの目的を知っているのだから、三上に委ねても達成には問題ない、お墨つきと見ていいのだろうか。
「……うん。それじゃあ、お願い出来るかな」
「お気に召すかは分かりませんけど、方向性は示せると思います」
「ありがとう、言い出しておきながら人任せで悪いけど」
「人任せなんて、そんな。立候補ですから」
そう言って、少し企みがちな笑顔を見せた。
「早速、準備しますね。色々手伝って貰うかも知れませんけど」
「それは、勿論」
「えっと……それじゃ二人共、明日の放課後は予定、空いてますか?」
僕は元々放課後に何か用事がある方が珍しいし、明日も問題はない。偶見も同様の答えだった。そもそも僕たちの両方が、明日と言わず今日この後も予定はなかったけれど、三上は既に構想の中から進めておきたい部分があるそうで、明日まで持ち越しとなった。
「だから、また改めて、計画を聞いて欲しいんです」ノートの紙を軽く叩く。「私たちだけが定義する、ちょっと新しい運動を」
