
結構なお手前で。
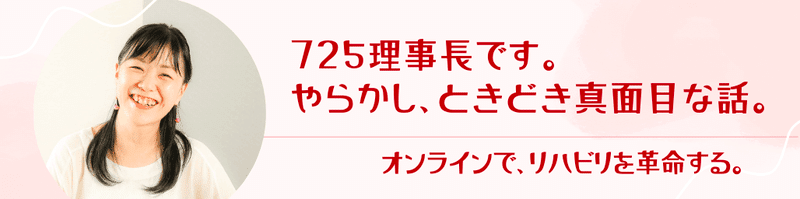
抹茶が飲みたいですね。
「抹茶が飲みたいですね。」
と、そう漏らしたのは80歳代の堀田さん(仮名)である。
堀田さんは薬剤性の嚥下障害を患い、誤嚥性肺炎のために度々入院していた。嚥下の状態に改善がなく、口からの食事が危険になったため、入院時に胃瘻が作られ、在宅ケアが始まった。そして私の訪問による食事指導も始まった。
精神疾患を長く患っていた彼は几帳面で、「もう食べてはいけない」と自覚しており、口にする飲食物を厳しく制限していた。食べたいものを尋ねても、「特にないよ。もう歳だから」と、消極的な返事ばかりだった。しかし、私の訪問を通じて、少しずつ食べられるものが増えていった。
そんなある日、突然、冒頭のセリフが彼の口から聞かれた。
「抹茶がお好きなんですか?お茶道具はお持ちですか?」と尋ねると、「昔、ちょっとだけ楽しんでいたよ。正式には習ってないけどね」と彼は言った。
そして、戦後の思い出を語った。親戚のおじさんから教わったお茶の作法、友人と飲んだ思い出など、彼の話は止まることなく続いた。
幸い私も抹茶を嗜んでいたことがあり、多少の知識を持っていた。「じゃあ、週末のお買い物の時にお抹茶と茶筅を準備してもらえますか?試してみましょう」と提案し、次回の訪問を約束した。
抹茶×とろみ剤
堀田さんは少し水分を摂るとむせてしまうため、とろみ剤を使う必要があった。そのため抹茶を点てたいという彼の要望に対し、とろみ剤をいつ投入すべきかについて悩んだ。
最初からだと抹茶を点てられないだろうし、最後に混ぜるのも気が引ける。それでも、どうにかなるだろうという根拠のない自信もあり、挑戦することを決意した私は、翌週の訪問日を迎えた。
訪問すると、堀田さんは早速抹茶、茶碗、茶筅を喜び満面で出してくれた。
「どうやってとろみ剤を入れましょうか?」と私が言うと、堀田さんはおもむろに手を動かした。
薬剤性の症状で手が震える堀田さん。彼は抹茶碗に抹茶を入れ、そこにとろみ剤を追加した。「え、今、とろみ剤を入れて大丈夫ですか?」と私は驚きつつ尋ねたが、彼は無言でお湯を注ぎ、茶筅で混ぜ始めた。
「本当にとろみがつくのかな?」と思いつつ彼の動きを見守ると、彼の動かしていた手が止まった。
思い出を、味わおう。
ひとしきり茶筅を動かしたのち、堀田さんはゆっくり茶筅を持ち上げた。
その茶筅にはとろみ剤で固まった抹茶が付着していた。
私たちは思わず笑った。
「なんか、すごいことになっちゃいましたね。」と、私たちは笑いながら新たな創作物を眺めた。とろみがついているような、ついていないような、なんとも不思議な飲み物が出来上がっていた。
「飲んでみます」と堀田さんは言い、自ら点てた抹茶を一口飲んだ。最後まで飲み干し、茶碗をテーブルに置いた。
「結構なお手前で。」と彼は空になった抹茶碗を見つめ、満足そうに笑った。
とろみ剤を入れるタイミングが完璧だったとは言えない。ダマもあり、抹茶も完全に混ざっていなかった。しかし、それでも堀田さんは一杯の抹茶を楽しそうに飲み干した。
専門家の関わる理由は。
専門職は仕事柄、リスクをいち早く見つけることができる。そのためリスクを見つけたからには、食べさせない・飲ませないと言うことが発生してしまう。
けれど自宅で過ごしている人にとって、家族と同じものが食べたい。テレビに映る美味しそうなレストランに行きたい。友人と飲みに行ったり、買い食いなんてしてみたい。
若い頃の食の思い出を、もう一度味わいたい。
それが当たり前じゃないだろうか?
専門職の指導は、「手段」であってほしい。それは、「リスクを知るための手段」ではなく、「食べるための手段」だ。
食べるための手段を提供する。そのための活動が、私たち専門職には求められていると思っている。
誤嚥ケアを社会の当たり前に。
一般社団法人オンライン臨床では、専門職にとっての当たり前を広めるため誤嚥ケアの10個の基本をまとめた「誤嚥ケア検定」を作成した。
この記事の第1章「とろみ剤を一歩進めよう」の記事は無料で公開している。その理由は至ってシンプルだ。
誤嚥ケアを社会の当たり前にするため。
ぜひ大切な方とのだんらんの時間を過ごすためにも、読んでもらえたらと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
