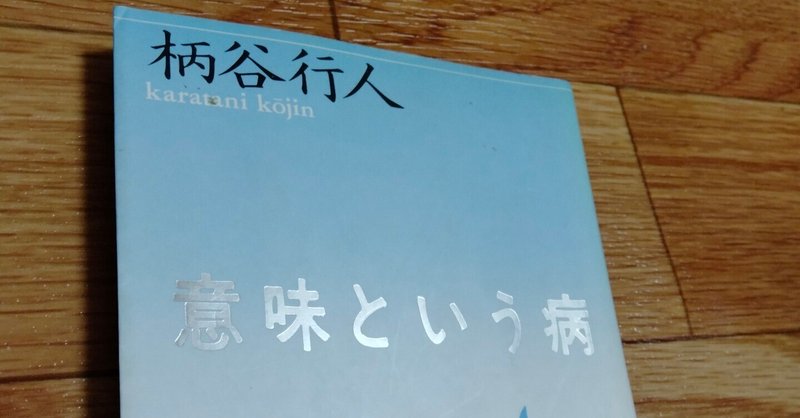
【書評】『意味という病』:柄谷行人
語り得ないものについて語ること、そこで生じる理解と誤解ともどかしさ。僕が物心ついたころからずっと抱えていた違和感、それが「意味」という病だったんだと本書を読んで初めて気づいた。
著者は(自身も抱えているであろう)どうしようもなく拭いきれないような「病の症例」を、他の作家や哲学者の文章のなかに発見しては、その病状を例示してみせる(その行為自体が、あたかも「反復強迫」のようだ)。
だが、この病のやっかいなところは、はじめから「正常」がないところにある。したがって、根本的な治療法などもちろんない。それでも(或る人々にとっては)問わざるを得ない問いである。だから病なのだ。
「意味」だけではない。この世界には、その種の「そもそも根治できない病」「存在していること自体が発生源であるような問い」が存在する(実務家からすれば、それこそ「意味のない問い」なのかもしれないが)。
柄谷行人氏が稀有な思想家である所以は、「病」の在り処を示すだけでなく、なぜ自分はそれを問わざるを得ないのか、では自分はどうするのかという「処方箋」をその都度出そうとするところにあると思う。
それは、氏のその後の展開(文芸批評の枠を超えた、哲学や数学に関する原理的な論考、現実的な社会問題への提言と実践)にも顕れている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
