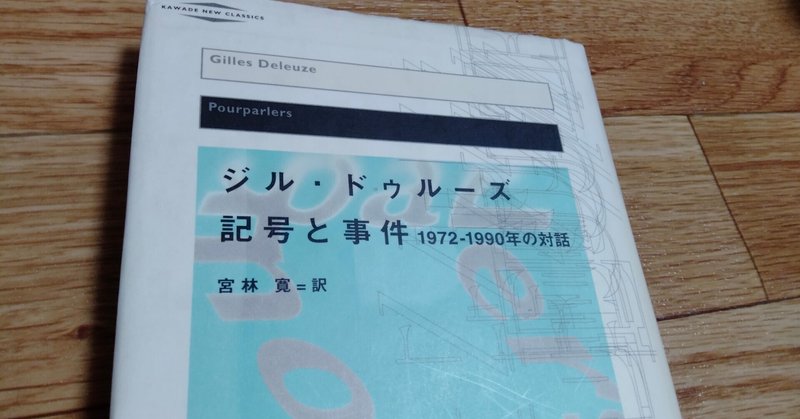
【書評】『記号と事件: 1972-1990年の対話』:ジル・ドゥルーズ
難解な哲学書を理解するには、哲学者本人が語るライトモティーフを知ることが一番の近道だ。その意味で、本書はドゥルーズの哲学を理解する上で最適の入門書である。
ドゥルーズの一連の著作やその中で磨き直された概念、そして映画・芸術・科学といった幅広い分野への言及が、どのような関心や意図をもってなされたものなのかが率直に語られている。
その語り口も、含蓄とユーモアに溢れてなお切れ味鋭く、まさに「ドゥルーズかく語りき」といった次第。フーコーの晩年の行き詰まりについての冷静な洞察も、彼が語ると生々しい。「管理社会について」の冴えにいたっては、さながら予言者のようだ。
また「記号と事件」というタイトルも、ドゥルーズ哲学の核心を「言い得て妙」だと思う。たとえば、僕たちは「そこに一本の川がある」なんて口にする。だが、本当は「とめどない水の流れ」(事件)に「川」という概念(記号)を当て嵌めているに過ぎない。
止むことなく動き続けている森羅万象から「同一性」を抽出すること。それが「記号」の使命だとするなら、ドゥルーズはそこに異質的で流動的な出来事の「事件性」を取り戻そうとしたのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
