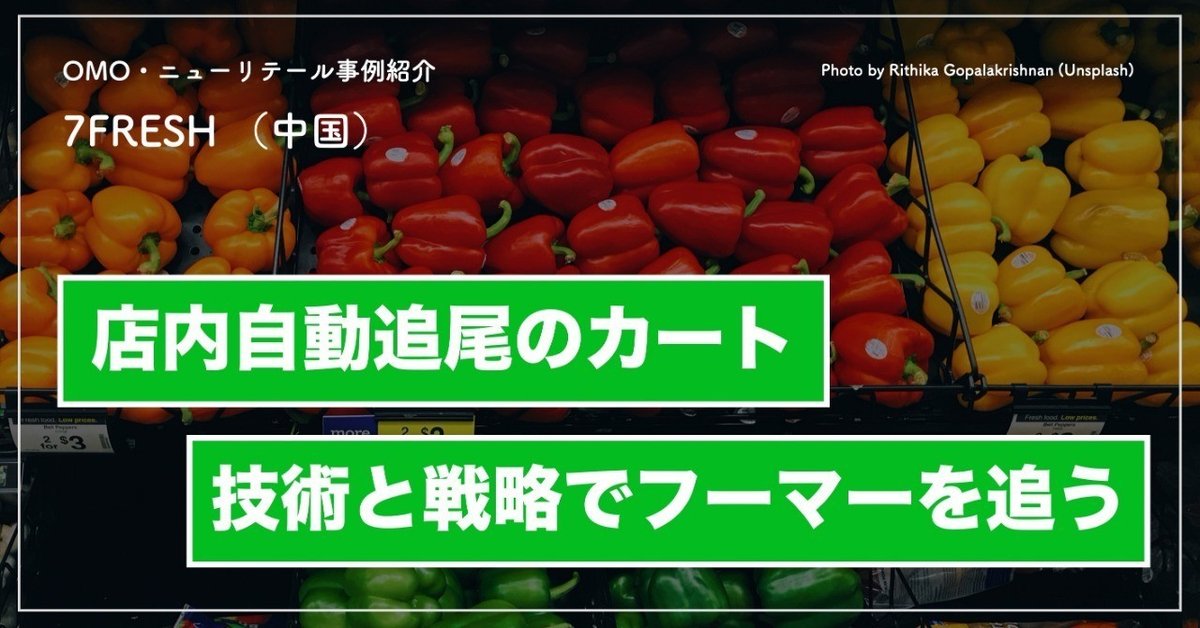
ハイテク技術や店舗形態で差別化。「ボーダーレスリテール」を掲げる京東(JD.com)の次世代型生鮮スーパー|7FRESH
【一言で言うと】スマートショッピングカート等のハイテク技術を導入した生鮮スーパーを運営。OMO戦略で一歩先をいくアリババを追いかける中国Eコマース•ナンバー2。
基本情報
展開する国:中国
設立:2018年(京東集団の設立は1998年)
ジャンル:スーパーマーケット
売上高:約7兆7709億円(2018年、京東集団全体の数値)
何が特徴か
Eコマースの分野でアリババのライバルである京東集団(Jingdong Jituan、ジンドンジートゥァン)、またの名はJD.comが2018年にスーパーマーケット業界に進出した。1年半ほどの運営を経て戦略を変更、「盒馬鮮生(Hema Fresh、フーマーシェンション)」で一歩先を行くアリババを追いかける。
1.物流の雄・京東がスーパー業界に参入
京東が2018年から展開しているスーパーのブランド名は「7FRESH」(七鮮超市、チーシェンチャオシ)。「一周7天毎天新鮮」(週7日いつでも新鮮)というキャッチコピーから名前の由来が分かる。
ライバルのアリババはすでに2016年から「盒馬鮮生(Hema Fresh、フーマーシェンション)」を展開し、社会現象にもなった。2019年4月現在で、中国各地に140以上の店舗を擁している。物流では優位に立つ京東がそこへ参入する。
OMOという用語も、当時、アリババのCEOだったジャック・マーが2016年に提唱したコンセプトだから、京東では使わない。京東の創業者CEO・劉強東(Liu Qiangdong、リュウ・チィァンドン)が口にするのは、顧客にオンライン、オフラインを感じさせない「無界小売(ボーダーレスリテール)」である。
2.スマートショッピングカートが商品を運び、支払いも済ます
2018年1月、北京にオープンした「7FRESH」の第1号店は「盒馬鮮生」を入念に研究したと思われるところが随所にあった。人気は魚を目の前で調理してくれる海鮮コーナー、支払いはSNSの支払いアプリや顔認証、商品のQRコードをスキャンして参照する詳細情報、店舗から3キロ以内ならば30分以内の宅配サービス。
もっとも京東ならでは特徴もある。物流でロボットやドローンを広く活用しているだけあって、驚かされるのはスマートショッピングカート。「7FRESH」に入店するには専用アプリが必要だが、このアプリでショッピングカートのQRコードを読み取ると、カートがずっと付いて来てくれる。過去の購買データがあれば、お勧めの商品のところへ案内もする。
人にぶつかりそうになれば、自動で方向転換や停止する。買い物が終わったら、支払いの列にカートだけで並び会計も済ましてくれる。顧客は30分後にサービスカウンターに取りに来るか、宅配を頼んだ場合は家で待っていれば良い。

顧客の後を付き従うスマートショッピングカート/Photo by JD.com京東日本株式会社
3.戦略変更後も目指すのは「ボーダーレスリテール」の実現
当初は「2018年中に50店舗、5年以内に1000店舗を展開する」という野心的な計画を掲げていたものの、2019年5月現在、中国各地で15店舗が営業しているに留まっている。
実は2019年4月に「7FRESH」事業の統括責任者が交代し、戦略の練り直しが行われた。その結果、従来の「7FRESH」は「七鮮超市」として生鮮食料の販売とイートイン事業を中心にグレードアップし、その他に北京や、今のところ未進出の上海及びその周辺地域では「七範児(チーファンアール)」や「七鮮生活(チーシィエンションホー)」などの新業態を展開することとなった。
「七鮮超市」が売り場面積が2千から4千㎡ほどであるのに対して、新業態の店舗はそれより狭い。
「七範児」は「喫飯(Chifan、チーファン、ご飯を食べる)」に引っ掛けた名称だ。ビジネス街に展開し、ビジネスパーソンのオフィスでの飲食の需要に応える。さらに各種イベントを開催して近隣で働く人たちの交流も促進するという。予定されている売り場面積は6百㎡から1千㎡だ。
「七鮮生活」はもっと小さい店舗で、2百㎡から3百㎡の売り場面積を予定している。24時間営業でもっぱら身近な生活圏の需要に応える。オンラインからの注文も可能で、店舗から半径1.5km範囲への配送にも対応する。小ぶりな店舗ながら、オンライン・オフラインからアクセスできる生活サービス拠点になり得る勢いだ。
新型「7FRESH」(七鮮超市)は2019年5月、「七範児」と「七鮮生活」はそれぞれ2019年12月に第1号店を北京にオープンした。
ゆくゆくは京東集団の各種ビックデータと合わせて活用し、周辺住民が必要なものを揃え「家庭から冷蔵庫をなくす」ことを目指したいという。
Banner Photo by Rithika Gopalakrishnan(Unsplash)
参考
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
