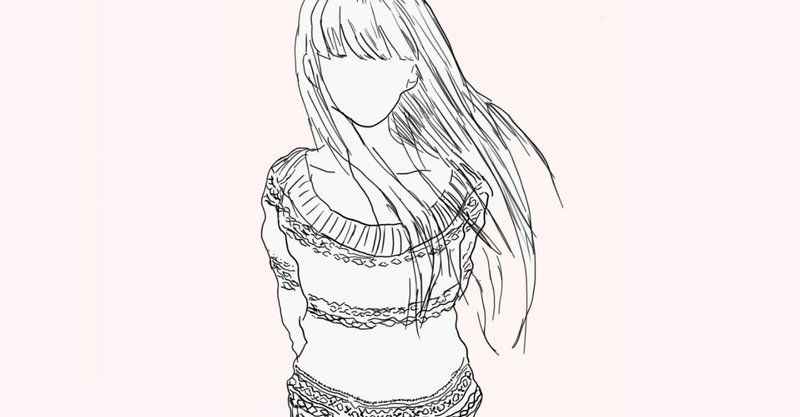
「おやすみプンプン」を読む|完結|
「おやすみプンプン」には「甘えの構造」がある。
これは、「高校生編」での母親との死別後に登場する、南条幸との恋愛、感情の縺れからくる離反、という展開の中で、俄にあらわれてくるものだ。
叔父の雄一から「プンプンの母親そっくり」とも評される幸は、別れた後もなお、まるで保護者のように、けっしてプンプンを見捨てようとはしないのである。
この奇妙な”絆”は、何か。
プンプンの「ついぞ親とは、わかりあえなかった」という怨念は、同じ境遇にいた愛子との、アダルトチルドレン同士の共感覚として、そのメンタリティに顕在化してくる。
成長後の愛子との再会前、例えば学生時代のプンプンは「非行」傾向はあったにせよ、進学校に通ってもいて、警察の手を煩わせるといった過激さはもっていない。気が小さいだけともいえるが、自己を冷静に客観視できている。
ところが愛子と邂逅した後は一転、殺人から暴行、無軌道な逃避にいたる、数々の凶行に及ぶようになる。
この”謎”については、アダルトチルドレン=愛着障害という観点から、読み解くことができるだろう。
愛着障害の人は、子ども時代に満たされなかった大きな欠落を抱えている。その克服は、ある意味、子ども時代を取り戻し、そこでできなかった甘えを甘え直し、やりそこなった子どもらしい体験をやり直すことかもしれない
つまりプンプンの「犯罪行為」の数々は、とくに母親の心にむかってぶちまけることができなかった不平不満の、箍が外れたストレートな表現ともいえるのだ。
換言すれば、概して少年期にいわれるところの、非行により親を狼狽させ、悲しませる等といった迷惑をかけることの「やり直し」をしている、と見ることができるのである。
その「甘え」の唯一不壊の受け皿として、幸がいる。プンプンを探しに訪ねてきた幸を見て、叔父の雄一はこんな科白を吐く。
僕ァね、プンプンがどこで何をしていようとかまいませんよ。それが彼の決断であるならば。ただね、僕にはわかる。プンプンが本当は何を求めていたのか…(おやすみプンプン/浅野いにお)
1.マトモさからの逃避
この作品には強烈な倒錯性(浅野いにおのエゴといってもよいが)があるのだが、それがもっとも強く出ているのは、プンプンや愛子の関係性よりも、それ以外の「マトモな人たち」との関係性の描かれ方においてである。
その関係性にはパターンがあり、相手に対する心無いふるまい、あるいは、自分の世界の外にいる者へ向ける投げやりな眼差し、というものだ。ほんとうに嫌な奴らなのである。
あたりまえだが、プンプンと愛子たちは「マトモな人」たちから痛烈なしっぺ返しを食らうだろう。この作品で描かれる「関係性」とは、つねに「マトモ」と「マトモじゃなさ」のはざまでの、反転をくりかえす振り子のようなものであった。
このような事態は、社会学者の宮台真司がかつて言っていた「島宇宙」という概念を使えば、うまく説明を与えることが出来るのかもしれない。
だが私が個人的に、もっとも興味深いと感じるのは、この交わりえないかのような両者の並列が、プンプン~の世界を構成する「前提」とされている点である。この図式については、いっけん妥当にも思えるが、果たしてそうだろうか?
一般的に「あの人はマトモじゃない」というとき、「自分はこの人とは折り合えない」という「拒絶」の意味が含まれている。ともに同じ文明に属する人類ではあるが「自分には殆ど関係ない世界の人だ」というワケである。
けれども、「あの人はマトモだ」というときは、どうだろう?それはそれとして、指示されている「マトモ」が真であるとは決していえないだろう。一体誰がマトモさをジャッジできるというのか。
「マトモ」とか「マトモじゃない」ということは、本質的に容易に区別できることではないのである。
他方、わたしたちはみんな「マトモじゃない」ともいえるだろう。
現代では、ネット上で自分の心理を開示(曝す)することが、当たり前になってしまった。タイムラインを眺めれば、人々が皆、内面に現実とは違う世界を持っていることがわかる。
近代以降の共同体で教え込まれる「マトモ」という存在理由=決められた目的を達成することへの志向性とは別の、事物をそのような意味には解釈しない、もうひとつのパラダイムとして。
2.浅野いにおのメンタリティ
浅野いにおが自身について語ったものとして、吉田豪の「人間コク宝 まんが道」がある。ちょうど、プンプン~連載時におこなわれている点も含めて、貴重な資料である。注目したいのが、漫画家になる以前の10代、思春期の思い出である。
育った実家が、半分ぐらい不良になっちゃうみたいな、ヤンキーになっちゃうみたいな場所だったんですよ、、、(略)僕、同級生にカツアゲされたことがあって、、、(略)頑張って説得しようと思ったんですけど、やっぱり何を言っても聞かないですよね、、、(略)いまだにそういう人が一番脅威です(人間コク宝 まんが道/吉田豪)
その後、渋谷のモアイ像で暴漢にカツアゲをされたうえに、街を一緒に徘徊した話が続く。
それで僕は全財産取られたんです、、、(略)その男がたまたま「何してんの?」って僕のところにまた現れて、、、(略)ヤバいと思ったから「原宿ってどこですか?」とかごまかして、原宿まで案内してもらったんです、、、(略)そのときの僕の口のうまさといったらなかったですよ!相手をおだてて気分よくさせなきゃいけないんで(人間コク宝 まんが道/吉田豪)
いかにも「おやすみプンプン」にでてきそうな話だったので、引用した。実際に作中でも、文脈もクソもなく、突然事件にまきこまれて手痛い目に遭うというシーンはみられる(この手法はゼロ年代以降に隆盛したライトノベルでも顕著に現れるものだ)
なによりも、この暴漢に対する、浅野の卑屈な行動は興味深い。それを本人が嬉々として語っているのだから、ことさらに奇妙である。まるで暴漢と同じく自分もマトモではないのだと言いたげである。
ホントそのとき殺されると思ったんですよ、田舎者なんで、、、(略)そのとき僕の中で一回死んだみたいな部分があって、、、(略)僕、もともと優等生だったんで、そこまで思いっきりドロップアウトする勇気ってなかったのが、そこでちょっと踏ん切りがついたというか(人間コク宝 まんが道/吉田豪)
浅野がどのように育ったのか?について、いっさい語られてないので知るよしもないが、わざわざ「優等生だった」と自称するほどに「マトモさ」が、自己規定に強く反響していたようだ。
これについては中条省平が、
浅野が描きたいのは、、、(略)つねに眺める者の視線をさえぎる都市の風景、感情の開放を許さない人間社会の閉塞感だから(マンガの論点/中条省平)
とその世界観についてうまい説明をしているが、それにもかかわらず、これだけでは割り切れない感覚も残る。
上記のインタビューでは、友達の意中の人を奪った話や、女装願望など、より露悪的な内容となっていくのだが、このような「マトモさ」への麻痺/無感覚の表明は、現代社会の心理上の傾向として、たしかに顕在化してきているものではないか。
だが無感覚になることで何かを克服した気になっているのかもしれないが、それは錯誤でしかない。自己の無力感や不安から逃れるために無感覚になっているだけなのだ。
3.愉快犯
浅野は「マトモさ」から逃避したい。とはいえ、勘違いしてはならないのだが、本心では、やっぱり逃避を望んでいないのである。
そもそも浅野は確信犯なので、むしろ読者たちの思考を予測して、インタビューでは、わざとらしくヒントを与えている、と考えるべきなのだ。
本稿ふくめ、ネットに散見される無数の「おやすみプンプン論」は、肯定的なものも、もしくは批判的なものも、浅野の思惑通りに言葉を引き出されて「書かされている」だけのものである。
特に終章「愛子編」を読むと、否応なく読者は湖岸にたたずむナルキッソスの立場に置かれてしまう。
だから、いつの間にかプンプン~を仮託して「自分語り」をしているだけ、という罠にはまり込む。その姿を見て、きっと浅野はほくそ笑んでいることだろう。
だが他方で、見過ごせないのが、「生きること」の意味を"強さ"や"弱さ"に還元しようとする、プンプンの態度である。
そういう事かって感じですよ。僕は結局僕だよ。今も昔も。、、、(略)愛子ちゃん、こんな半端じゃ駄目なんだよ。僕はね、君の全部を受け入れるつもりなんだから。頭のてっぺんからつま先まで。もっと本気出せよ。田中愛子。(おやすみプンプン/浅野いにお)
僕はとても後ろ向きな人間かもしれないけど、今なら誰よりも速く走れる気がするんだ、、、(略)後ろ向きで走ったりしたら、すぐそこが崖でもわからないのにね、、、(略)僕は嬉しい。自分がこんなに強い人間だったなんて。愛子ちゃん、絶望をありがとう(おやすみプンプン/浅野いにお)
端的に”強くあること”が存在理由であると信じ込むことによって、なんとか社会=「外の世界」と自らをつなぎとめている。浅野にとって「社会」とは、「前向きに」というお題目のもとに、規範や倫理感を守って、マトモに生きている人々を象徴している。
最終話で登場する、晴見俊太郎の描かれ方(自分の人生が楽勝すぎて、頭がどうにかなりそうだ...という科白を吐く)を見よ。
ところが、これは現代の「表現者」が陥っている”症状”ともいえるのだが、社会と対立する自身の欲望や信条をかたく守りながら、それでもなお、社会のなかで「アウトサイダーとして」生きようともしている。その承認欲求だけが、極めて強い。
すごいよ、愛子ちゃん。もう何も怖くない、、、(爆笑)、、、結局僕はこういう奴なんですよ(おやすみプンプン/浅野いにお)
このシーンでプンプンは「悪魔」に形態変化して、たからかに「みずからを嗤う」
このとき、自己の欲望を抑圧する社会に対する、プンプンの「憎悪」を、大半の読者は「自嘲」と解釈するだろう。その「嗤い」が、自身ひそかに抱いている欲望に向けられることに、耐えられないだろうから。
このようにして浅野は、読者や評者にとっての虫の良い読み方を先取りして、甘えさせるのだ。
くりかえすが、これは周到に用意された罠だ。
4.「少年」のままのプンプン
この浅野の悪意に満ちた「いたずらっぽさ」の真意とは何であろうか?
「ボーイズ・オン・ザ・ラン」って、ほんとにいまの漫画だと思ったんです。たとえば童貞をこじらせてるみたいなことを大っぴらに言う、ミュージシャンでいうと峯田和伸さんみたいな感じが僕にはほとんどなかったんで(人間コク宝 まんが道/吉田豪)
いま僕は「おやすみプンプン」って漫画やってるんですけど、ちょっとそういう要素が入ってきているのは完全に花沢さんの影響で(略)...僕にも花沢さんみたいなネガティブな要素はすごいあって、まだそれをハッキリと漫画には描いてないなと思ったんです。(人間コク宝 まんが道/吉田豪)
上記は「プンプン~」についての本人の弁だが、この「花沢健吾を意識している」との発言は、業界の四方山話をするかわりに、
それ以上の創作の苦悩や懊悩について語ることを拒否している、というような、創作の核心については、けっして踏み込ませない何ものかを感じさせる。
だからこそ、それゆえに、気持ちが透けて見えるということもあるのであるが。浅野いにおは何を求めているのか?
この作品を、マトモな作品=「文学」として認められたいと欲していたのだ。しかも、連載の途中でその試みがけっして達成されえないことを悟ったかのように思える。
プンプンの、肉親や同級生たちの関係性だけの「子供の世界」からの脱出が企てられている「フリーター篇」を読むと、それがわかる。この章の中心となるのは、南条幸だ。
高校を卒業後まもなく、幸と出会ったプンプンは「漫画の共作」という、おもいがけない形で半ば強引に「社会」と関わることになる。ところが、本来ならここで、(社会人として)さまざまな人々との親交や対立、葛藤を経験することになる筈が、全然そうはならないのである。
下記は、出版社への「持ち込み」の場面、
不幸自慢ってウザいんですよ、まあ一言甘ったれんなって感じですね...(略)オナニー漫画なんですよ...(略)とにかく面白さは漫画の絶対条件です、暗い世の中だからこそ、読者は前向きで分かりやすい共感を求めています(おやすみプンプン/浅野いにお)
あなた何と戦ってるんですか?僕?読者?それとも社会?実は自分自身だなんて使い古された文脈よしてくださいね(おやすみプンプン/浅野いにお)
この場面は、浅野自身の体験が反映されているのかもしれない。
上記の話者は、市場原理にもとづいて「部数」や「読者の共感」といった、わかりやすい成果を追求するだけの編集者だが、この業界人のステロタイプの他に、すくなくとも社会領域においては、まともな意味での「他者」が登場することはない。
一方このようなドン詰まり・閉塞感のガス抜きといわんばかりに、幸やそのとりまき達との「青春群像」は、まるでひとときの夢のように生彩に満ち満ちている。
だとしても、プンプン本人が幸に「自分はあなたのペットでしかない」と自嘲するように、その関係性はつねに非対称だ。
功成り名遂げるためにあらゆる努力を払う幸と、いつも受身で卑怯で非力なプンプンとでは、つりあうはずもない。
常識的にいえば、この主人公はもっと真剣に人生の算段について考えないといけないだろう。やたらと悩んでいる描写は多い。だけれども、肝心の生活のバランスシートや、将来の展望についての具体的な方策については記されない。
むろん「漫画だから」というエクスキューズは可能だ。漫画なのだから、リアリティに拘泥する必要はなく、いくらでも虚構を描いてよいのである。だとしても、それにしても、作者のやり口はズルいのである。
まあここだけの話、あの人もねえ...単行本はそこそこだけど、雑誌牽引するだけの人気はないし、雰囲気でゴリ押ししてるだけで、中身は薄っぺらですからねー...サブカルというかサブカル風味?(おやすみプンプン/浅野いにお)
これも編集者の科白だが、浅野本人の自己認識であることは、あきらかだ。
この作品は「雰囲気でゴリ押し」で「中身は薄っぺら」な「サブカル風味の作品」でしかないってボクも分かってるんですよ...とヌケヌケと作中に書き込む、この胆力はなかなかと思う。あらかじめ、みずからが虚構であることを語る、そのこと自体により、完全に虚構になってしまう一歩手前で踏みとどまっている。
結局、プンプンは偶然(これも文学作品においては禁じ手)により、大人になった愛子と再会してしまうと、それまでの人生の目的のいっさいを放棄し、幸を裏切り、例の「マトモさからの逃避」のニヒリズムに回帰していくのである。
浅野にとって人生は、虚無なのだろうか。
5.孤独な闘いの記録
ところで、もう忘れている人も少なくないだろう、2010年に東京都が出した、
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正案は、思いがけない問題提起をもたらした。
漫画に登場する「18歳未満っぽい非実在青年も保護の対象にすべき」というのである。
この改正案は、非実在青年はすべからく保護するか、あるいは、どのような表現ならセーフであるいはアウトなのか?、
という議論をすっ飛ばしての提出だっただけに、かなり狂った印象をあたえた。
結局は各方面の猛反発をまねき、頓挫したのであるが。
だがもし仮に、この改正が施行されたとしたら「おやすみプンプン」が規制対象となっていたのは確実と思われる。
「プンプン~」には、同時代の読者から「共感」を喚起させるためのアイテムが、数多くちりばめられているのだが、もっとも重要なファクターを担っているのが「エロ」だった。
たとえば、プンプンの叔父の恋人「翠」との初セックスの生々しい描写。それまでのトーンからの落差に戸惑う読者もいたと思う。ことに未成年なんかは。
以降、放恣なセックス、殺人や自殺などなど、非実在青年たちの性的/陰惨表現が無遠慮にあらわれ、またプロットを推し進める動力源ともなっていた。
これが未成年の読者たちの「童貞/処女ならではの知らないゆえの全能感」を増幅させる"装置"でありえたことは、誰も否定できまい。これこそが「鬱漫画」「メンヘラ漫画」の代名詞と揶揄される所以だが、これはむしろ作者の望むところなのかもしれない。
というのも、浅野がここまで露悪的になっていったことと、改正案との間に微妙な含みがあるように思えるからだ。いうまでもなく2010年当時、バリバリの連載中(6~7巻あたり?)だったのだ。
ふりかえると、この時期あたりから"陰惨さ"の度合いが急速に増していったのは「意思表示」としての意図もあったのではないか?と、勘繰りたくなる。
私が見るところでは、浅野はずっと「危ない橋」を渡っていたようである。むろん、それは浅野以外の作家、たとえば山本英夫や新井英樹、山本直樹など前世代のクリエイターにも該当することだ。
もっとも、彼らと比較したときに、最後まで手加減をせずに過激な表現を追及するというような、潔い態度が見られなかったという点で「おやすみプンプン」は特筆に値する。
この作品はすっかり最後まで描き切られた。そこには約7年もの連載期間があるわけで、描きはじめた当初と、その後の挑発的/陰惨になっていった事との間の、心境の変化も加味しなければならない。
だが、この決して短くない月日の間に、激しく揺れ動きながらも、いずれの方向性にもコミットされなかったのである。結果として、ポルノのような、恋愛漫画のような、アウトかもしれないけれど、セーフかもしれない、という、どっちつかずなものになっていった。
つまり判断は読者にまる投げした、ということだ。でありながらあくまで挑発的にエロを描きつづけ、なおかつ自分の描いているものが何であるのか、はっきりしめす意志もないのである。
ゆえに、このような作品を鑑みたときに、「非実在青年を保護すべき」と世に問われたこと自体は、たとえ時代の空気に逆らうものだったとしても、公共の視点に立てば、筋の通ったものであったと、いえるのではあるまいか。
この歴史の「IF」は、浅野いにおのような存在を知る、重要な手がかりにもなるだろう。この作品はポルノなのである。そういえる根拠が多すぎる。と同時に現にマーケットに広く流通しており、多くの人々を魅了し支持されてもいる。
ただしそれはいつかポルノの烙印を押され、葬られるかもしれない。そればかりか、もしそうなったとしても、このどこかふざけているような感じのする作者は、平然としているのかもしれない。
6.社会とプンプンの距離
浅野が一貫して選択したのは「反社会」という態度だった。
このプンプン~の世界における「反社会性」については、別途きちんと考えなければならないだろう。
反社会とは、とりもなおさず社会へ背くことだが、この対立を突き詰めると、哲学的な存在論になる。「社会」的存在の根底にある意識とは、「学習」する態度であり、目的にむかって進歩し、みずからの世界をつくり変えることである。
言い換えるならば、まず目的を達成するまでの時間があり、来るべき"つくり変えられた世界"へむけて、まっすぐ行動する自己がある。ということはつまり、そのような行動者の自己のあり方、および目的と世界との従属関係に、否をつきつけることが「反社会」ということになる。
また、もしそうなのだとしたら「反社会」という意識においては、未来に向けて学習・成長し、乗り越えるべき「問題」など、端からありもしないということになる。
ならばプンプンはどうか?というと、いささかアダルトチルドレン的な性質を保持しつつ、「みずからの世界を変えたい」という欲求は、強いのである。
ただし留意しなければならないのは、その欲求を堅持するためにこそ、「マトモさからの逃避」に囚われ続けているように見える…という点である。
この作品はプンプンと愛子との「ロミオとジュリエット」である。そう乱暴に断じてもよい。プンプンと愛子との「再会」という宿命が全ての目的なのだから。
だからそれ以外のライフイベントに対しては、本質的に無関心というアナーキー的態度をとるのである。これはプンプンにかぎらず、幸、関や清水といった同級生たちも同様に、それぞれが(社会的意識とはかけ離れた)欲求をひそかに抱き、それゆえ葛藤や対立が生じているのである。
それではプンプン~の世界の「時間性」とは、より具体的には、どのような形であわられるのか?
母の死後、プンプンはしばらく叔父夫婦と同居しているのだが、それまで失踪状態だったプンプン父(福島で福祉関係の仕事をしている)が訪れてくる。
プンプン父に対する、プンプンや叔父たちの態度は「冷ややか」である。父と息子のコミュニケーションの、そのあまりの噛み合わなさは、憐れである。
プンプン父は意を決すると「一緒に暮らさないか」とプンプンに申し出る。「ふたりで一からやりなおそう」というのである。月日が流れ、すっかりみすぼらしくなった父親を目の前にして、プンプンは自分が変わり果ててしまったことを自覚するばかりである。
プンプンは今、目の前に座っている人の言っていることが、よくわかりませんでした。一からやり直すといっても、その一というのは果たしてどこのことだろうか?なんだか、とってもこの人はふざけている気がしました。(おやすみプンプン/浅野いにお)
プンプンが憤っているのは、親としての責任を放棄していた過去をすべて水に流して「父としての責任をとらせてくれ」という、その筋の通らなさ、虫の良さなのだろう。
だいたい、今さらどのような「責任のとり方」があるというのか?
わざわざ言う必要もないが、仮に「一からやりなおした」としても、「普通の父子」があたりまえに長い時間をかけて築いていくはずの、濃密な関係性は取り返せはしない。
この申し出は断られる。プンプン父が帰った後、一部始終を見ていた叔父の雄一は、プンプンを外に連れ出し(プンプンが犯してしまった)翠との情事のことも含め、腹を割って話をする。
プンプン、人として生きていくうえで大切なものってなんだと思う?
…(略)一番大事なのは「覚悟」なのさ…(略)君が引き込もろうが、殺人犯になろうが知ったこっちゃない(おやすみプンプン/浅野いにお)
ただもし君がそれを他人や環境のせいにしたら、俺ァ貴様を日本刀でたたっ切る…(略)自由に責任があるってことを忘れちゃいけないのさ…(略)君が君でいる限り、この世界は君のものだ(おやすみプンプン/浅野いにお)
このシーンはとりわけ印象深い。
作者はあきらかに、プンプン父を軽蔑の対象であるかのように描いているが、しかしここで雄一のいう「覚悟」なき者というのは誰かというと、それはけっしてプンプン父でも、プンプンでもない。
この「父と息子」という神話的ともいえるシーンの眼目とは、プンプン父とプンプンの「覚悟のとり方」の無残な齟齬、取り違いにある。
傍から見ていた雄一は、それがよくわかっているのだ。
ビルの屋上で夕日を眺めながら、感情がたかぶり、堪らなくなった雄一はワナワナと涙を流して、上記の科白をいうのだが、一方で、この一連のシーンの彼らの姿は、どこか滑稽味にあふれている。
もっとも、この滑稽さは、プンプンを相手にしたものではなく、けだしプンプン~の世界における「神様」を目当てにされたものであろうが。
そしてこの滑稽さにより「神様」は癒され、その怒りは解かれるのである。
ここで、おやすみプンプンの世界の「時間性」とキャラクターの関係性があきらかになる。
それは神話的に円環した「時間」であり、社会的領域とは、かけ離れたものなのだ。
言い換えると浅野は、「マトモさからの逃避」というニヒリズムを、神話がまさしくそうであるように、死を前提としない限り成立しえないものとして描くことを望んでいる、ということなのだ。
7.プンプンの世界は、透明な悪意の被膜で覆われている
ここで最重要人物、愛子のことについて言及せねばなるまい。
愛子の母親は新興宗教の狂信者で、布教に熱心。父親は家族の介護を必要とする。また、こうした特殊な境遇のせいで、愛子は学校で疎外されるのを余儀なくされ、転校を繰り返す。
然し家族に対する愛子の視線は、醒めきっている。実は何時だって何もかもを捨てたがっている。
「ねえ、、、他人同士が好きになったり付き合ったりするのって、、、何なんだろうね?」「優しい家族がいるのに、さらに愛情を求めるなんて欲張りだと思う」「どんなに好きで彼氏彼女になったりしても、きっと永遠に他人以上の存在にはなれないんだ」「、、、でもわたしはそんなの嫌だ。余計なものは全部捨てて、ただ、あたしだけを見てほしい」(おやすみプンプン/浅野いにお)
「きっとあの人は、わたしなんていなくても一人で幸せになれる人なんだ」「、、、結局また、わたしは一人ぼっちなんだ、、、プンプンにはわかる?」「、、、好きな人の為に家族とか夢とか自分の持っているものを全部捨てられる?」(おやすみプンプン/浅野いにお)
小学生だてらにプンプンと鹿児島への遁走・駆け落ちを企てたり、小学生編から中学生編にかけてスタンスは一切変わらず、愛子は清らかな存在であった。言い換えれば、まったく空疎な存在である。
だとしても、引用したようなメンヘル感情を他人にぶつけるのは、まさに「甘え」だ。まだ子供のプンプンはこれを「拒否する」=「裏切る」
以上が前編(というものは明記されていないが)である。この漫画の魅力はとにかく「(4巻までの)愛子が可愛い」ということに尽きていた。そのせいか以降、この美少女はいなくなって作品全体が、どこかおかしくなっていく。
溜めに溜めて再登場する後半部の、成長後の愛子は、どっぷり暗黒面に落ち込んでいて、禍々しい。そして前編の子供のメンタリティそのまま、ふたりは地獄へ一直線に落ちていくのである。
終章「愛子編」においてようやく、プンプンの「覚悟」が、どういう形をとるのかが描かれる。そこではお馴染みの「マトモさ」との折り合いをつけようとしていた、どっちつかずな態度はいっさい放棄されている。
…これからはただ、あるがままに感じて、思うままに行動すればいいのかもしれない。他人から見ればとうに終わった人生なのだろうが、もしそう後ろ指を指すなら、それがどうしたと言い返してやるんだ(おやすみプンプン/浅野いにお)
この「行動」とは、大量生産社会のもとで高度に機械化され、決められた目的を達成することのみにより幸福が保証されている状況のなかで、あえて煮ても焼いても食えないような人間として「行動」することであろう。
この志向性と相似する例を挙げるならば、(アーティストの彦坂尚嘉が言及している)70年代のポルノ解禁と呼応するように展開した、女性解放闘争、ゲイによる地位向上運動、がある。そしてこの背景には現代文学の「悪趣味化」があった。
さらにはインターネットの台頭により、いわゆる表現の「鬼畜系」が多数出現したのが90年代後半~ゼロ年代の状況であった。これは人間の「悪」が全面化した世界に他ならない。
…けど、悪意の塊のような人間が、身勝手ながさつさを平然とまき散らして、他人の人生を台無しにしている現実というのが一方であって(おやすみプンプン/浅野いにお)
この世代の代表たる浅野いにお=プンプンが憎悪する対象とは、大量生産社会の「ゲーム」をやめようとはしない人間たち、
いつも表面だけしか見ない消費者、決められたレールを走ることこそが勝ち組であると思い込んでいる俗物、自己愛性人格障害のクレイジークレーマー、等々である。
しかし、だからといって「無抵抗」や「従順」を峻拒し、社会領域に闘争をしかける、というわけでもない。プンプンたちが「決意」している態度とはとどのつまり、「ゲーム」に熱中し、惑溺している者達から、徹底的に「離れる」ことなのである。
あまり人と関わらないで、…ただ毎日を暮らす…もし子供ができたらその子には何も縛られない自由な生き方をしてほしいな…ううん、やっぱり…やっぱり子供なんかいないほうがいいに決まってる…もし同じ事を繰り返してしまったら…それは不毛過ぎる(おやすみプンプン/浅野いにお)
ここで愛子が「不毛過ぎる」というのは、もしプンプンのごとく「妥協」を拒否した者が、下手に勝利でもしたら、そのときはその者自身が、相手と同じ穴の狢になってしまう、ということなのである。
したがってプンプン達がとれる選択肢は、最初から、きわめて限られているのである。
だって僕は今とても満たされているんだから…僕は人生の全てを投げうって君を救うことが出来たという事実(おやすみプンプン/浅野いにお)
このプンプンの語る独りよがりな「勝利」には、死臭が漂っているが(作中、プンプンは幾度も心中をほのめかすが、その都度、愛子に拒否される)、破滅の先にある浄化こそが人生の総決算にふさわしい、というわけだ。
改めてこのような見立てをすると、ありふれているというか、プンプンの「凡庸さ」が浮き彫りになってしまうのであるが、しかしこのほとんど捨て身の特攻をかけて敗れ去るような、その様にこそ信用できるものがあるのは、疑いようがないのである。
僕は…僕は、強くなった。失うものもなければ、守るものもない。不安も葛藤も優しさも。これが自分が求めていた理想だったんだ(おやすみプンプン/浅野いにお)
「感情の開放を許さない人間社会」の抑圧に対し、現実の不安から逃れるために自分の世界へ逃避する、その無垢性と破滅的なエネルギーの放出こそが、この作品の過激さの源泉となっているのだが、
この世界で「自分に正直になる」ということの代償は、あまりに大きいものである。それはひたすらにつらい孤独な闘いであり、荒野を生きることであるばかりではなく、自分に関わる人間をも破滅に引き込むことなのだ。
プンプン/愛子は、向こう見ずに狼藉を働き、社会を愚弄するようなタブーを口にし、落ち着いて考えることもせず、つねに思いつきで行動していき、結局なにもかも上手くいかなくなるのである。
にもかかわらず不思議と言わねばならないのが、それでもなお「社会」に対して一縷の希望を抱き続けている、という点である。二人は、「いい人」である「おじさん」を頼り、鹿児島へ向かうのである。
一方で、そのふるまいは徹底的にふしだらであり、罰当たりである。あらゆる場所で、無軌道なセックスに耽るのである。ここで浅野が描きたかったものとは、「カオス」なのである。
最も象徴的なのが、鬱蒼とした森でのセックスの細密描写である。どことなく温かで、チャーミングな雰囲気の、イメージがハレーションを起こしているようなシーン。そのすぐ前まで、殺すだの殺さないだの修羅場があったのだから、本当におかしい。
プンプン~の世界は、透明な悪意の被膜で覆われている。
8.愛子は何故死んだか
この作品は、浅野いにおの悪意の産物といえる。ゆえに「愛子が何故死んだか?」等という論考を、大真面目にぶつことほど、作者からバカにされる行為はない。
それでもあえて論考するならば、無防備かつ無謀な行動により、(真に)死の危険に身をさらしていたのは、プンプンだったのか、それとも愛子だったのか、ということに帰結する。
あたし、少し落ち着いて考えてみたんだけど…これからの事、もっと現実的に考えて計画しないと。あまり先走って行動されると君もあたしものちのち後悔する事になるし(おやすみプンプン/浅野いにお)
プンプンは…少しおかしい。…たとしたら、僕以外の全員がおかしいんだ。
それ…お母さんと同じ事いってる(おやすみプンプン/浅野いにお)
愛子は、「カオス」が破滅への道であり、いつか報いを受ける時がくることを、かなり早い段階で確信しているのだが、(七夕の短冊のシーンなどからも示唆されている)
プンプンはというと、口にする言葉こそご立派だけれども、その実体はというと、信じやすい愚かな子供として描かれている。
あやまって愛子の母を殺してしまったことを悩んでいる様子が描かれるが、これすらも愛子の嘘だったことが後に判明する。本当は愛子が殺害していたのである。
「愛子編」の本当の主題とは、「なぜ屑を殺してはいけないのか?」という問いに対して、「理屈」をいくら並べてもたいした駁論にはならない、というものである。
これこそタブー中のタブーであり、これを公に言い出す者はつるし上げられて、社会全体から「排除」されることになるだろう。
…きっと無理し続けようとしても、…いつかあるべき所に戻るんだ…君はもう考えるなって言ったけど、そう言い切れる君は少し強くなりすぎたんだよ…
君が期待してるよりもずっとずっと、…あたしは平凡な人なんだ…(おやすみプンプン/浅野いにお)
この最期のやりとりで、愛子は「自己否定」という認識に至る。
「あたしは平凡」であると言っているが、むしろプンプンよりも「考えないように」努めていたのではないか。
すこしでも「考えて」しまえば、それまで二人の過ごした時間が、あの悲惨な現実のなかに堕してしまうのだから。
だとしても、「考えるな」という、あまりに身もふたもない認識のもとに全能感に浸るプンプンよりも、自分が平凡であるという認識のもと、「嘘をつくのはもうおしまいにしよう」と言う愛子の方が、はるかに「非情」であり、「透徹」している。
と同時に、その態度は、たとえ社会的な意味とは異なったものであったとしても、心がこもっている。プンプンのいう仰々しい御託や説教よりも、ずっと無垢で、まっすぐな人間らしさがある。
愛子は自己否定を完遂すること、すなわち、死ぬことで、「あの退屈で平凡な日常」を捨て去り、人間性を快復させたのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
