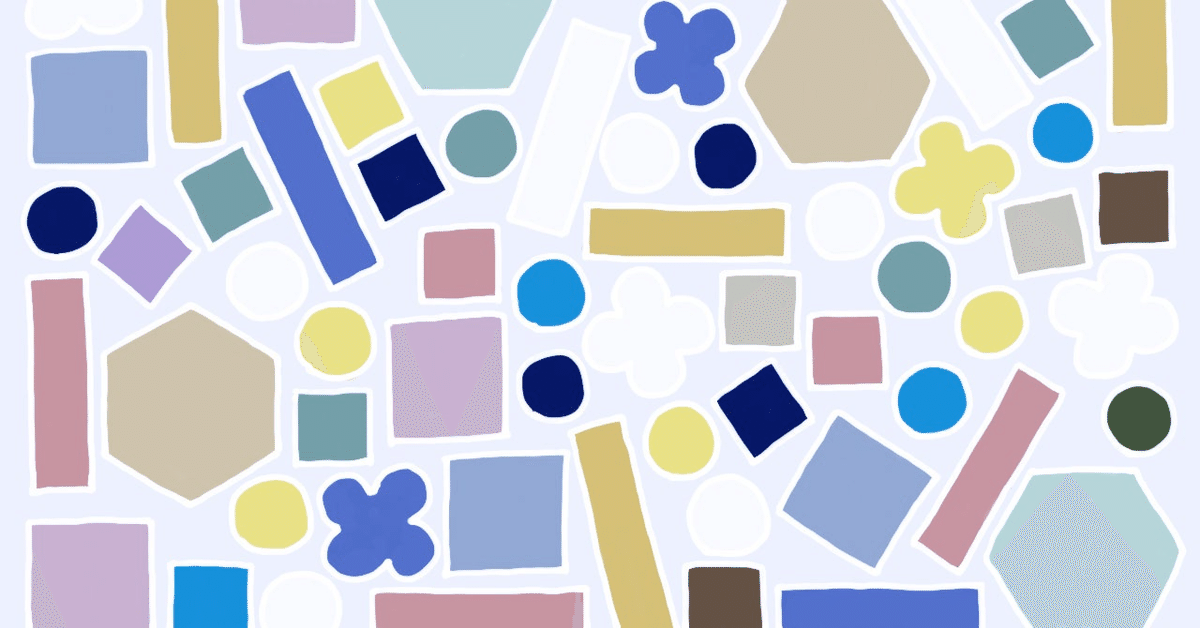
セガコナミナムコ以外の音ゲーがなぜつまらないか考察してみる。
いろんな音ゲーが出て、そして消えていく・・・、そんな状況ってのは昔からずっと続いてきたわけですが、今も残っている昔からある音ゲーってやっぱりこれからも残っていくんだろうと思わせる何かがある気がします。
題に挙げた三社以外が出した音ゲーも残っているものは残ってるし、題に挙げた三社が出した音ゲーも残念ながら稼働終了したゲームはたくさんあるわけで、とはいえ何故にそんな違いが出るのだろうか、というのを今回考察してみようと思います。
音ゲーの楽しさとは何か
3つ要素があると思います。
デバイスの特性に対応して素早く正確に操作できた時の快感
様々なリズムに対応して正確にデバイスを操作できた時の快感
認識が難しいオブジェクトに対して正確に対応できた時の快感
1は、各音ゲーは「太鼓の達人」「beatmania」「チュウニズム」などそれぞれが持つデバイスとそのレイアウトによってゲーム性が変わるわけですが、最初期のプレイにおいてはその特性を把握してプレイできた、という快感を得ることでまたその快感が得たいと思い継続的にプレイしたくなったりします。
2は、いろんな曲をプレイしていく中ではリズム難といわれる譜面が出現することがありまして、いわゆる4つ打ちやトリル系などではない、一見リズムが不規則に見えるような譜面というのがあるわけですが、それを正確に対応できた時にすごい快感を覚えるわけで、その快感をまた得たいと思い、同じ曲をプレイしたりします。
3は、いわゆる高難度初見プレイや、beatmaniaではソフランや発狂だったり、チュウニズムのワールズエンドだったり、太鼓の達人の鬼譜面だったりする、そもそも表示される譜面がごちゃごちゃしすぎてよーわからん、っていう状態を抜けたときの快感ってやつです。どうなっとんねんこれ、っていう譜面を一瞬で解析しデバイスを操作しクリアできた、という快感があり、その快感をまた得たいと思い、同じゲームをプレイしたりします。
お気づきかと思いますが、これらの3つの要素はそれぞれプレイするステージにおいての継続性を促す要素でもあります。1は初級者、2は中級者、3は上級者、が主として持つモチベーションになるかと思います。もちろん、それぞれの要素はそれぞれのプレイヤースキルにおいて重要性が変わる、というだけで、初級者にも2や3の要素はありますし、上級者にも1や2の要素はあります。これらの要素が積層してそれぞれのゲームをプレイするモチベーションになっているといえます。
逆に言えば、これらの要素にネガティブな要素が入ったとき、人は離脱しているといえます。次項ではそのネガティブな要素について考えてみます。
離脱要素1:デバイスの変更
古くはbeatmaniaからbeatmaniaIIDXへの移行、太鼓の達人のCRTから液晶ディスプレイへの変更、といった変更によりこれまでそのゲームに最適化されていた操作方法が事実上リセットされる、ということがありました。音ゲーにおいて家庭用移植版の売れ行きが芳しくないとか、その移行の段階でアクティブユーザーを大きく減らしたとか、そういう話をよく聞くのはそのせいです。
離脱要素2:納得できないデバイスの反応
いわゆるいっこく堂現象から、ガバすぎる判定、デバイスの特性に不釣り合いな判定など、そういう正しいか間違いかの基準が不明瞭なことで、快感を得にくくなると、別にこのゲームやらなくてもいいやとなり、離脱していきます。
離脱要素3:要求される認識能力が高すぎる
表示される譜面が速すぎるとか、小さすぎるとか、重なってて認識が遅れるとか、方向が定まらないくてどこを叩けばいいのかわからない、などの理由でプレイに集中できなかったり、これをこうすれば認識できるのになぁという改善点を思いついたとしてもそれを反映できない仕様でプレイさせられる、などすることでその人はクリアできないのをゲームのせいにしてそのゲームをやらなくなります。
音ゲーを作るのは簡単か
まぁ、そういう意味では、音ゲーって作るのは簡単だけど、それを受け入れてもらえるかどうかってのは意外に高い技術力が必要なんだろうなぁと思ったりします。
なので、今続いてる音ゲーはそういう研鑽を日々怠ることなく積み上げてきたんだろうなぁと思うと、本当にスタッフさんありがとう、というしかないです。
新しく出てきた音ゲーも、消えていった音ゲーも、惜しいなぁと思うことがたくさんあるので、日々改良を続けるとか、次作に活かすとかしてほしいなぁと思いました。
サポートいただくと、生活費や取材費などの活動のために有意義に使わせていただきます。よろしくお願いします。
