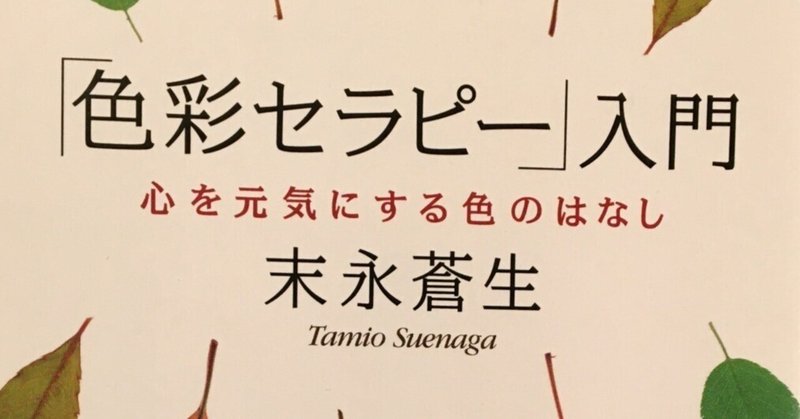
#93『色彩セラピー入門』末永蒼生
めっきり絵を描いていないが一時期は非常に熱心に描いていた。何枚も絵を買って頂いたこともある。しかし絵の勉強をしたことはなく、色についても全くの無知。
最近、何か絵というか、色に対する疼きのようなものがあった。心の奥のかなり遠い所でそれは起きていたので充分に認識するには至っていなかったが、この本を読んで「なるほど」と思う所があった――何か、心の中に表現したいものがあるのだ。
表現したいと言っても芸術的なことではなく、もっとありふれたこと。自分の思い、である。
40代になった。子を持った。離婚した。一人で暮らしていると、内側から自然と湧いてくるものがある。寂しさや悲しさではなく(その時期はもう通り過ぎた)、自由な身であるからこそ湧いてくる「俺って、何をしたいの」という自問。それがあてどもなくさまよい出ては消えて行く。そういえばそんな気配を感じながら暮らしていることに気付いた。
色と言えば、子供の頃から保守的だったに違いない。奇抜な色を選ぶような発想の自由が残されている家ではなかった。美大に後に進むことになる当時の友達にしばしば「無難だね(フッ)」と言われたりしたものだ。美術の時間などに。
色彩センスはほぼ死んでいた。35歳くらいで絵を描き始めるようになるまでは。
初めて自画像を描いた時、その顔は青だった。その時、分かった。これが絵を描くということなんだ、と。それから立て続けに描いた。コントラストの素晴らしさをしばしば褒められた。
何も狙っていない。好きな画家も見本もいない。ただ思いつくまま描いた。「ここは緑だな」とかその程度の思い付きである。しかし今見ても、良い絵の数々だと思う。発想が自由なのである。
しかし何事も最初の衝動に伴う力は強いが後に減衰していく。今では当時のような激しく力強い絵を描く必然性が自分にない。だから自分は色の世界の前でしばし立ち止まっているのだろう。その内また何か描いてみるか…などと思うが、もう少し先のことであるに違いない。
色の選択には間違いなく心の状態や願いが映し出されていると本書は言う。赤は激しく生を求める心、青は退行した意識の中で平穏を求める心。黄色は力強く、緑は調和を表し、桃色は甘美な喜びを想起させる。
子供は大人よりもはるかに柔軟に自由に色を選択する。だから子供の心理状態はそのまま色に出るそうだ。そんな変遷を辿るエピソードをいくつも紹介する本書は、人間の心に対する深く優しい洞察を投げかけている。著者の人間観察眼には卓抜したものがある。
私は今、何の色を求め、何の色をよく目に止めるだろう、と思った。一貫して私は白いシャツばかり着ている。最近服を仕立てに行ったが、やはり白である。青や緑や黄と言ったシャツを着る自分は、どうもイメージ出来ない。
白にも勿論、色々な願いや様相が込められている。古来聖職者が白に身を包んだのは潔白になるためだった。同時に、浮世の想念を持ち込まないという誓いでもある。
ピカソがゲルニカを描くのに白と黒のモノクロに終始したのは「色を使えばそこに救いが生じる」という理由だった。ゲルニカにおいて、ピカソは戦争による虐殺を見て、一切の希望をその絵に宿すことを自らに赦さなかった。それがゆえのあの絵の迫力なのである。
白と黒はある意味で、剥き出しの現実を表してしまうのかもしれない。我々人間にとって「剥き出しの現実」とはしばしば残酷極まりないものである。
しかしそこにやがて色が芽生える。子供はなんと自由に色を選び色を楽しむことか。この本を読んで、自分のこれからの様々な色との付き合いをよくよく考え感じてみたいと思うと共に、子供の心が如何なる色に惹かれながら育っていくのか見届けたいと思った。
良書である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
