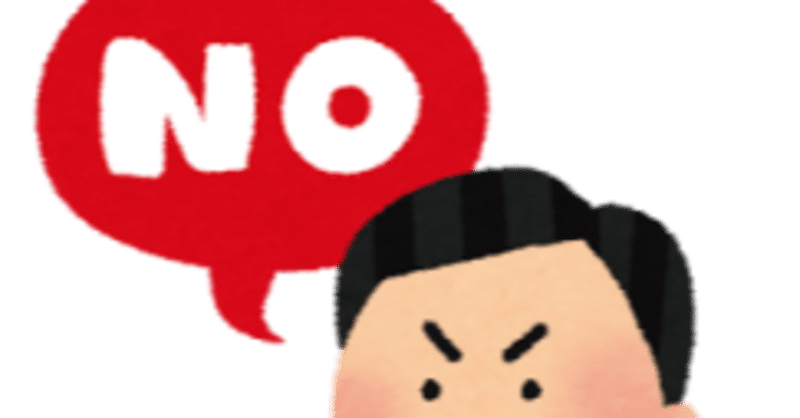
歌ってみた系で見かけた間違っている情報など
まぁタイトルのままだけど、その人たちをディスるとかじゃないのよ。ネットの情報だけを頼りにmix師とか歌い手とかで持ち上げられてしまった悲しみの結果生まれた、嘘というか間違いじゃないかなぁと。
mix師って人たちも歌い手の子供たちと同じで基本的には承認欲求。歌い手からmix師になります、って人が多いことを見ても「繋がっているどころか同じ領域」なんだと思う。仕事でやっていてそのついでにあそびでやるか、って人以外は音に関わることで承認欲求を満たしたいだけなのだ。それは物事のスタートとしては悪くない。認識できないで「肩書き通り凄くなければならない!」と考えてしまうとややこしいだけで。
だからマウント合戦も存在するし、多少の嘘混じりの背伸びもする。
プラグインの数を競ったり、機材の価格を競ったり、音楽歴やmixした数を競ったり。どれも音楽的な仕事ではなんの意味もないのに。
そう言った誰も得しないマウント合戦の結果、訳のわからない情報が一人歩きを始め、それをなぜか正しいと思ってしまった人たちの手によって拡散してしまう。
ネット上の肩書きってのは情報の正しさを担保するものではない。
例えば「音楽歴10年」とか「mix200曲」って言われても、知識を蓄えながらなのか無知なまま数をこなしてきているのかで全然意味が違う。Twitterで見る限り音楽歴って書き方する人って、胡散臭い人が多い傾向がある。
で話を戻すと情報を集める時は、どんなことでも複数人に質問してみるといい。人は間違っちゃうものだから。
「こう聞いたんですがこれってあってます?」
って他の人にも聞いてみればいいのよ。
今年一年で「スタジオでもお仕事をする人間」がツイッターやスペースで見かけた「それを初心者にいうたらあかんやろ」というのを年末(2021末)なのでまとめてみる。
わかってると思うけど、こんな人ばっかりじゃないからね。あくまでも酷いのだけピックアップしてるんだからね。こんな人もいるんだぁ・・・って笑い話にしておくぐらいでちょうどいいのです
明確に間違ってたり勘違いを生むやーつ
なんとなく項目を分けてみる。
MDR-CD900STこそ最高のヘッドフォン
これなんぞ、と言う人のためにざっくり説明するとどこのレコーディングスタジオにも置いてある、プロ標準のSONYのヘッドフォン。別名、赤帯。

スタジオに標準装備ってことはプロクオリティなんだから最高だ!
これがある種の誤解を生んでいる。
レコーディングスタジオで録音をする際にこれをつけるんだけど、何を聞いているかってと「自分で演奏した音」だったり「自分が発声している声」だったりする。あとどうしても発生してしまうノイズとかね。で、そう言う時にヘッドフォンに求めるのは「上記内容だけが聞き取りやすいこと」に他ならない。このヘッドフォンは特性として高音がよく聴こえ、低音はスカスカ。つまり、バンド系で考えるとわかりやすいのだが低音に声や演奏している音がかき消されずに聞き取りやすくなるのだ。だからお仕事の現場で使われている。
これ、録音ばっかりする人にはいいんだけど、自分で楽曲をリスニングしたり作ったり編集したりって用途だと「あまりいい選択肢ではない」と言わざるを得ない。だって高音が強く聞こえちゃうのでバランスメタメタになるわけで。
なので、用途も確認せずにMDR-CD900STをお勧めする人は、可哀想な人と思っておこう。こう言う特性をわかった上でおすすめしてくれる人は逆に素晴らしい人。ただ意味もわからず他人に勧める人は相変わらず多い。なんだって適材適所なんだよね。
宅録にはコンデンサ
宅録で使うマイクは大きく分けてダイナミックマイクとコンデンサマイクと言うものがある。一般的な意見だが、業務的には壊れにくいダイナミックマイクはライブやイベント司会でよく使われており、声仕事のレコーディングではコンデンサマイクが使われることが多い。

だったら宅録ならコンデンサマイクこそが正義じゃないか!
と言いたくなる気持ちはわからなくもない。
問題は防音環境。
コンデンサマイクはダイナミックマイクに比べると細かい音も「拾ってしまう」のだ。つまり、防音環境をそれなりに用意していないと、録音した品質で言うと殺意を抱く程度に悪くなることもしばしば。家での録音を考えると、無条件でおすすめしていいアイテムではないのだ。
一方、ダイナミックはそこまで繊細ではないので、多少防音が足りなくても問題なく録音できる。あと、壊れにくいという部分も大きい。湿度ですぐに壊れるコンデンサマイクと違って、ダイナミックマイクは基本的に出しっぱなしにしようと投げようと車に轢かれようと問題なく使えたりする程度には頑丈。それでいて人間の歌声をとる能力もちゃんと持っている。
こう言う違いを理解している人は多いと思うんだけど、特徴が違うだけでどちらが優れていると言うわけじゃないのよね。なので、防音とか住宅のことを考慮に入れることなくコンデンサマイクをお勧めする人は敵だと思っておこう。こう言う説明をした上で、好きな方選びな、がいいよね。
ダイナミックマイクはこもる
これははっきり言うと、録音知識の欠如です。
どうやってもこもるようなマイクをプロのアーティストがライブやイベントで使うでしょうか?プロの仕事を馬鹿にしてますね、これを脳死で言える人は。
そもそも声がこもって聴こえる理由ってのはほとんどがマイクの距離を間違えているからであってマイクの特性ではない。そりゃコンデンサマイクに比べれば多少録音に関してのお小言はでなくはないものの、問題があるレベルならSM58というダイナミックマイクがどこのレコーディングスタジオにも置いていることをどう説明するのかと。
というわけで、ここから先は以前ダイナミックマイクとコンデンサマイクについて説明した記事がこちらにあるので、ちょっと読んでみてください。わりと真面目に書いているので、マイクの種類で悩んでいる人は軽くでいいから読んでみて欲しい。
【宅録限定】どっちのマイクがいいの?
https://note.com/oichan_d/n/ndd01b1cbc611
音圧論争
まぁ大体のケースで音量と音圧をごっちゃにしている人が言いがちです。もちろん楽曲的に音圧調整大事!ということもあるものの、歌ってみた系列で音圧高めまくっても、聞く時にのっぺりした感じにしかならないので、ほどほどに、レベルかな。音圧って本来単位はパスカルなのよ?
と、苦言を呈していても仕方ないので過去にまとめた音圧に関しての考察の記事へのリンクを貼っておきます。音圧にこだわる人って、ぶっちゃけ同人活動だと上手い人あまりいないとは思いますぞ。トランジェントにこだわる人の方が大体上手。音量も音圧もほどほどでちゃんと聴かせられるってのが、編集する人の腕なのです。のっぺりしてるものしかないってのは、下手な証拠。
世界中で「いい音楽には隙間がある」って言われてるからねぇ。
音圧とは何か?
https://note.com/oichan_d/n/nea1477a9f5bb
個人の歌い方、個性とか
これ、難しい問題ではあるものの、歌い方とか録音方法ってのはある程度確立された技術が存在しているので、「音楽に正解はない!」とか言ってる人達はある程度バッサリ切り捨てていいレベル。技術があってそれを知っていて、その上で「正解がわからない!」って人は逆に信用していい。

歌い方については必要な技術があるからボイトレのスクールがあるし、マイクや機材には適切な使い方があるから技術者が存在しているのです。その辺りの最低限ができた上で、個人の良さ、を語るのが正解じゃないかな。
よく若い子がいう「俺は声量お化けだから本気出すと音割れするんだよね」ってのも同様で、録音の仕方知らないだけです。プロのガチ声量お化けの録音、割れてないでしょ?録音にも技術があるって証左に他ならない。
基礎的な知識を身につけるのって面倒だけど、それだけで一気に上達する可能性あるし、少しだけでも勉強してみると幸せになれる。
個性とか自分らしいって単語を逃げ道に使ってしまうと、正しい方法覚えられなくなっちゃうのよ。
声に合うマイク問題
これもなかなかヘソで茶を沸かせるレベルのコメント。
市販されているマイクで声をとることを考えるとRODE NT1ぐらい極端なもの以外は、基本的には普通に録音もできるし、ブラインドテストで当てられるのは一部の耳の状態がおかしい変態か、特定のマイクの音だけ聞き続けてなれている人のみ。
そもそも論でいうと、マイクの特性を最大限に出せるほどの発声ができるレベルの歌を歌えて、かつ、それだけの録音機材などの環境があって初めて「マイクによる個性の違い」が明確に出てくる。最低限マイクプリアンプを10万程度の安いものでもいいから持っているレベルじゃないと、語るのが難しいレベルなのです。もちろん防音も。

もちろんマイクにもマイクプリアンプにも個性や特徴があるので人によっては相性というものは存在する。ただ、それを見抜けるだけの環境を用意するって結構大変。宅録で考えると、ちゃんとした機材の組み合わせならそこまで気にしなくていいよ、と。
ただ、価格帯で能力が一気に変わったりするので、マイクもマイクプリアンプも新しくする時には同価格帯よりも、一気に価格帯を変えてしまった方が変化を楽しめる可能性は高い。
あと、面白いことにマイクって価格が性能とダイレクトに結びつかないことが多いので、これ安いけど結構いいじゃん!ってのを見つけると楽しくなってくる(沼の入り口からの声
AG03の功罪
この機材を欲しがる人ってのは何にも活動していない人疑惑がある。
というのも、これ欲しい人って基本的にループバックという単語が必要だ!とネットで見た人が多い。本当にその機能が必要かどうか理解していないにしても。
あと配信用!という実際のイメージもあり録音はダメだ!っていう人もいる。この辺りは人気商品で特殊な商品なので、色々言われるのは仕方ない。
というわけで、過去の記事を二つリンクを貼っておきたい。
AG03はなぜ録音に向いていないと言われるのか?
https://note.com/oichan_d/n/nd5ee6166c895
そのループバック機能、必要なの?
https://note.com/oichan_d/n/n9ae252e477d3
もちろん、ちゃんと理解して活用してる人はたくさんいる。ただ、なんとなくそれがいいと聞いて、の人は少しだけお勉強してからの方が満足度上がりますよ。
機材やソフトのおすすめの雑さ
ネットの情報をソースにした人に多いのがこれ。
実際に使ってみてこうだったから、まで言える人って案外少ない。
筆者、一応Cubase, Logic, FLStudio, Studio One, Ableton Live, Protoolsは所持していて、最低限は使える。その上でお勧めするならこれかな、は言える。Ableton Liveだけは使ったけどどうしても肌に合わないので語れない。

で、ほとんどのネット上の活動の人って持っていて一つ、触っていて二つが限界じゃないだろうか?
そういう人がお勧めできるってやっぱり幅が狭くなるし、持ってないものお勧めするとしたらちょっと無責任じゃないかな?
お勧めを聞くってのは難しいから無難に「体験版を片っぱしから触れ!」って方が相手のことをしっかりと考えていると言えるし正しい。今は体験版のないソフトって基本的に存在しないしね。
あと機材でも同様。
令和にもなって今の時代では完全に旧世代の遺跡になっている機材をお勧めしたり、近年登場したてで評価が定まっていないものを「初心者」にお勧めする人、結構多い。無責任極まりないし、好みで逃げられてもこまるのだ。
「あれ、よかったよ」、「この価格帯だと一番音が良かった」、「バンドルソフト考えるとこれスタートがいいよね」とかの経験者の声こそが本当に信頼すべきであり、無責任なお勧めは無視すべき。
機材の相談にポップガードとマイクスタンドを考慮しない
これはガチ。
ポップガードとマイクスタンドって高いものじゃないけど録音することを考えるつ、絶対に必要なアイテム。予算伝えての相談でこの二つ入っていなかったらマジで大問題と思ってくべき!それぐらい大事なアイテム。
あと、ポップガードは布と金属があるんだけど、金属のやつは正しい向きがあるので注意。この辺りも事前に知っておきたい!
ミックスボイスに関しての説明
これもわりと見かける。
ボイトレの先生が見てたら金属バット振り回して襲いかかってくるレベルの嘘を平気で言う人がいる。特に歌い手とmix師。どっちも歌や発声のプロじゃないんだから無理に語らなくてもいいのに、と思うレベルで間違ってる人多い。
そもそもミックスボイスが何かわかってないのにミックスボイス出せるのが正しいみたいになっているのが、わりと老人から見たら謎だったりする不思議な世界。別にプロの世界ではそれが正義とはなってないのにね。
高音とかミックスボイスとかは時に気にすることなく、発声とか滑舌にだけ意識を持っていくことこそが訓練そのものだったりする。
ピッチ補正絶対主義
それ大事?
ものすごく個人的な経験則で言うと、補正ってのはプロでも必要なことは多い。とはいえ、そこに数時間もかけたりはしない。どうしても、リテイクしても治らない数カ所をちょとっといじるだけ。
そもそも楽譜通りピッタリくっきり合わせるなら、それこそボカロに歌わせておけばいいわけで。

あと、ピッチ補正ソフトを通すことでの音質劣化の方が仕事的に言うと明確に嫌なのもあるけど、歌ってみた、はなぜにそこにこだわるのか。メロダインとか明確に通すだけで音が変化しちゃうからねぇ。なんで必須アイテムとか言う人がいるのかわからないレベル。
そもそも、ピッチ合わせは歌う人の責任なので、リテイク頑張るべきだし、それでどうしてもこことここだけなんともなりませんでした!ってところだけ直せばええんよ。ピッチ補正で何時間もかける暇があるなら声の調整、楽曲の調整に時間をかける方がクオリティ上がりますよ、と。そもそも、活動継続するなら徐々に上手くなっていっても全然いいわけでさ。つまり、何度も練習しよう。
この動画のおまけ部分を見てもらいたい。原音と補正ソフトを通しただけの音を重ねてるだけなのにこうなる。つまり、音が明確に変化・劣化しているわけだ。気にすべきはピッチよりも、音の劣化じゃないかな、と思わなくもない。ピッチ補正してくださいって言葉は、音を劣化させてください、ってことと変わらない。そんな人間が歌い手なんて名乗っていていいのだろうか?
【実験動画】ピッチ補正のソフトをいくつか使ってみる
https://note.com/oichan_d/n/nfb71a1deac3b
ディレクションできます
これ、歌ってみたというシステムじゃ基本的にほぼ無理なんだよね。
ディレクションってのは言葉を変えると「黙って俺の言う通りに歌え。責任は俺がとる!」ってことなのね。なので、仕事で言うとPとかDってのはお金を出すサイドの人が行う。それか、ディレクションのプロとして権限とお金を受け取ってるか。
歌い手がお金を払うことが一般的なことを考えると、金払う人よりも受け取る人の方が偉い、って状況になる。普通にありえないのよね。そもそも、最終的にはお金を払って発表する人間が気に入らないものにしてはいけないわけで。
こうするといいよ、とアドバイスはできると思うけどディレクションできますってのは、ちょっとディレクション未経験感あるよね。例外としてはディレクション代払うので、あなたの最高と思う方法で導いてください!って歌い手サイドがお願いする時。稀だと思うけどこれならあり得る。
マスタリングできます
これはプロの意見としてという前提で説明。
マスタリングエンジニアってのは制作の工程でわかるんだけど、やばいレベルの魔法使い。スタジオ持ってても曲作ってても「マスタリングエンジニアのやってることって意味がわからないレベルですげぇ」って誰もが思うレベルの変態。
それをたかが数千円から数万円程度の価格帯の歌ってみたの世界でやれるって人マジでいるの?という本音。
中にはそう言う変態が遊びでやっているケースもあるけど、かなり稀。つまり、マスタリングできます、って単語を口にする人ってマスタリングがそもそもわかってない可能性の方が高い。個人的にはプロと明確にわかっている人以外で言ってる人は信用しないようにしているレベルでマスタリングってのは難しい。だってミックスダウンされた曲に0.2dbだけEQかけるとかで、聞こえ方が激変するような魔法使い。日本で何人いるのってレベルなのよ。
エンジニアです
ちょっと意地悪なやつ。
mix師って単語がダサいのでやってる作業がエンジニアなのでエンジニア名乗ってますって素人の人が結構多かった。話聞いても「実は名乗ってるだけっす」がそこそこいた。なので、あまり肩書きで人を判断しなくていいかな、と。匿名のおじさんがいうことではないけどねw
これに限らず、資格の必要のない肩書きって名乗り放題なので、そんなに気にしたりしなくていいかな、と。
こう言うことは言いふらしてほしいやーつ
ここからは覚えておくといいよ!ってこと
録音知識こそが品質
歌い手もmix師も、録音知識ある人ってのは音質のレベルが高い。録音しないといけないんだから当然なんだけどね。なので、録音の相談ができる人は大事にした方がいい。我々仕事でやってる人間は歌や声を録音したものをもらって、マイクの距離があってるか、機材のレベルがあってるか、発声はどうか、程度の簡単なことはすぐに判断できる。なので、それを教えてもらえるかどうかってのは、ものすごく大事なことと思っておくべき!逆に録音について相談できないとか具体的なことを言えない人はちょっと・・・って態度でいいと思う。
どう言う人と会話してるのか
わりとツイッターって「どう言う人たちと普段やり取りしているのか」ってのが人の判断で重要。学生が学生としか話してないならそういうことだろうし、やっぱりプロとかそっち系の人たちはそう言う人たちで普段会話してる。どういう同業者と話をしているかみてると、なんとなくその人の知識レベルとかも推察できるようになるわよ、と。絶対的な指針にはなり得ないけど参考として。
自分に金と時間をかけましょう
歌い手もmix師も趣味で好き勝手やるならいいんだけど、結局は他人に見せたり聴かせたりしたいからそう言う活動をしているはずなんだよね。だとしたら、結局のところ録音知識とか発声知識は自分で身につけないといけない。
時間もお金もかかるし努力も必要
なので、そこを自分の足場としてしっかり固めていければ楽しく過ごせるんじゃないかな。
余談だけど商業プロとして音楽で飯を食っている人たちと話していたところ「ネット上で見かけるmix師って肩書き名乗ってる人間って、嘘つきか音楽的な能力なさすぎのどっちかしかいないと思うようにしてる」って複数人が言っていた。もちろん言っている人間たちも、全員がそうだとは思っていないんだけどね。そう思うような人が多い、という意味合いで。
全体が間違っているわけではないんだけど、そう思われて得することなんてないよね。多少は「襟を正さないと」って人が出てきてくれれば書いた意味もあるというもの。
教える立場なのでできる限りはワークショップなどで教えた内容を説明していこうかなと。地方の人やワークショップに事情があって参加できない人たちへのサポートが今後もやっていければと思っています。
