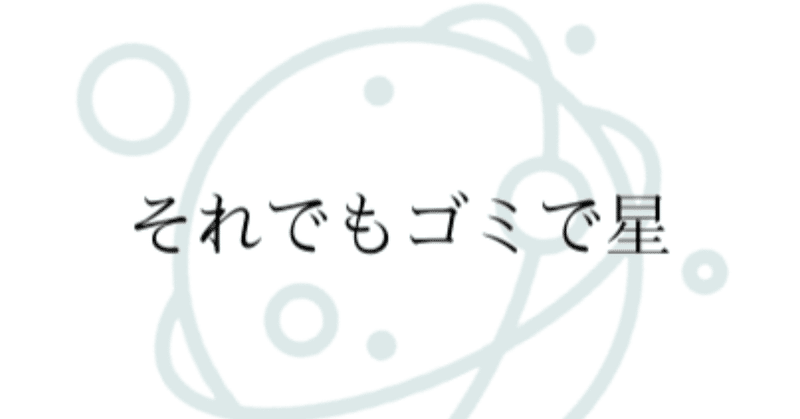
それでもゴミで星
辞表を出す。
机の上の辞表を、常務がじっと見つめる。
何度もシュミレーションしていた通り、言うぞ。辞めます。言う。言ってやる。自分に言い聞かせて口を開こうとしたとき、常務がこちらを見上げる。
ただ見上げる。右眉だけがあがる。口角は下がる。言おうとしていたすべての言葉は、喉仏に引っかかって出てこない。
何も言わない俺に、常務も何も言わず、そのまま辞表を摘まむと隣にいたヤギに食わせる。ヤギは唇で食むように辞表をくわえると何も考えていなさそうな顔でむしゃむしゃむしゃむしゃむしゃむしゃむしゃむしゃ——
返せ! 俺の辞表!
叫ぼうとして目が覚めた。
ごづん、と頭が何かにぶつかる。
天井を周回するように、空中庭園たちがゆっくりと飛んでいた。
底に埋め込まれた浮遊石が朝の光をあびてきらきら輝いている。たとえばここが家具屋のカタログに載ってる部屋だったら、最高にお洒落な朝だっただろう。でも現実は小汚いおっさんのワンルームでしかない。天井にかけたつっぱり棒には洗濯物がかけっぱなし、ベッドの上だけはなんとか死守しているものの、床はもう足の踏み場もないほど工具やら材料やらで埋め尽くされている。扱っているのが主に土と芝生なので、どれだけ掃除しても床はざらざらだ。
目覚し時計を見ると六時の十分前だった。休みの日なのに平日と同じ時間に目覚める自分が憎い。でも二度寝したらまたさっきの夢を見そうだ。
なんとか床に手をつける場所を探し、体を起こす。
先ほど頭をぶつけたのはガラスで出来た玉だった。観葉植物を入れて天井から吊るしたりするものだ。うちではこれを空中庭園の寝床として使っている。
今日から三連休。この日のために芝を植えて安定させておいた土台が十個ある。今日中に完成させて、明日には動作チェックをやって、明後日には最終調整をしてしまいたい。
ぼーっとしながら一日の予定を立てていると、いつもよりはるかに低い位置にいる空中庭園が一つ、こちらに向かってふよふよと飛んできた。一号、と呼んでいる。一号はそのままゆっくりと肩のあたりに突撃してきて、方向転換をすることもなくぐいぐいと前に進もうとする。
この部屋を飛んでいる空中庭園たちは、すべて動作確認で問題があったものたちだ。
一号は障害物をよける機能が動かない。天井付近で旋回している二つ、マチュとピチュは、自分で寝床に帰ることが出来なかった。寝床で貯めたエネルギーが尽きると、ぼて、と落ちてくる。
六時にセットした目覚しがバリバリと鳴りはじめた。まだ頭がはっきりしない。脇腹を掻いて、コーヒー、いや、切らしてたか。思い出そうとしていると、ぼて、ぼて、とマチュとピチュが落ちてきた。エネルギー切れになったのだろう。
目覚しを叩いで黙らせ、一号、マチュ、ピチュと全員つかまえ、のろのろと立ち上がる。洗濯物の隙間にぶら下がっている寝床に突っ込むと、取り付けられた充石が浮遊石と反応して、飛ぶためのエネルギーを送り始めた。
洗濯——は、あとでやろう。覚えていれば。
「さて」
腕をまくり、床を埋め尽くしている工具類を足でどけていく。作業机の前に自分の尻がおさまるスペースが出来ると、ぼきりと肩を鳴らした。
+++
ヴヴ、とスマホが震える。
無視。というかどこにあるのか不明だ。きっとスーツのポケットか鞄に入れっぱなしだがどちらも台所に放置されている。あぁスーツはクリーニングに出しにいかないと。でもとりあえず後だ、後。ヴヴ、また震える。無視。この三連休は作業に没頭すると決めているんだから。
ヴヴ、ヴヴヴ、ヴぃーーーーーー。
「クソ!」
ついに通話が鳴り始めた段階で、我慢できずに立ち上がった。キッチンに置かれていたスマホが振動でシンクに落ちてまだヴーヴー跳ねている。発信元は確認しない。どうせ掛けてくる人間なんて一人しかいないのだ。
「なんだクソ野郎」
『はよっす! 今から行きます!』
「来るな、死ね」
通話を切り、電源も落とす。よし作業再開だ、と思ったところで、
ピンポーン
と、最高に嫌な予感のする音がした。工具からハンマーでも持っていこうかと思ったが、大人気ないしそういう冗談は嫌いなのでぐっと我慢する。
ドアを開けると思った通り九野が立っていた。
「っていうか来てます!」
「ハイ殺ーす」
チェーンを外さないままグーで脇腹を殴るが、九野は笑いながら身をよじるだけだった。帰れと言ってるのだこっちは。
そういえば今日は十九日。
十九、二十、二十一の三連休だ。つまり給料日前で、九野が来ない方がおかしい。最近忙しくてすっかり忘れていた。
「寂しい先輩のためにごはん作りに来てあげましたよー。はい開けてー。チェーン外してー」
「帰って死んで二度と来ないでー」
「開ーけーてー」
「消ーえーてー」
ドア越しに押し問答するが相手が帰らないのは分かり切っていた。それでも追い返さずにはいられない。俺は、作業、するんだ。
「コーヒーそろそろ切れたでしょ」
何もかもお見通しですよみたいな顔をして、九野はぶら下げていた紙袋から中身を出した。勝ち誇った笑みを高そうなドリップパックでゆっくり隠す。
コーヒーを盾にされては敵わないので、やむなくチェーンを外した。
+++
九野は会社の後輩だ。俺が入社して三年目に入ってきて、以来ずっと同じチームにいる。真面目で仕事もできる上に性格もさっぱりしていて、まぁ、可愛いやつだ。一つだけ欠点を上げるとするなら、いつも給料を一瞬で使ってしまうところ。給料日だろうが給料日前だろうが関係なく、年中いつでも金がない金がないと言っている。二言目には「奢って、先輩」とハートマークを飛ばすようなアホだ。
俺だって頻繁に奢ってやるほどの金はなかった。あんまりうるさいから、お前が飯を作って宅呑みにするなら金を出してやらんでもない、と言ったら嬉々としてノッてきて、月末になると上がり込んでくる。
「あー……いてて」
作業がひと段落し、ぐっと上に伸びをする。ぼきぼきぼき、と肩も首も遠慮なく鳴った。ちょうどいいタイミングで九野もスマホから顔をあげる。
「終わりました?」
三連休ぜんぶ使うつもりでいた作業は、集中できたおかげで思っているよりずっと進んでいた。これだったら今日たっぷり寝ても、明後日にはサイトにアップまでいけそうだった。
「うん。今日の分は終わり」
「じゃあ食いましょ呑みましょ!」
「どうせチリワインだろ?」
「ですです。今日は白の一番安いやつ」
ビールよりもワインをボトルで買った方が酔えるし安い、という理由で、九野が買ってくるのはいつもワインだ。しかもチリ産のクソ安いやつ。
「にしても三連休なのにお前、うちしか来るとこないのかよ」
「明日も来ますし、材料だって三日分買っちゃいましたよ」
「ヒマ人だなほんと」
机は作業途中の空中庭園未満たちで埋まっているので、百均のどんぶり鉢を膝に抱えて食べる。俺は地べた、九野はベッドに胡坐をかいて手を合わせた。豚の角煮丼。まさに男の料理だ。
「だって金ないんですもん」
「それ訊きたかったんだけどさ。お前ってなんでいっつも金ないの?」
問いかけると九野は一瞬言葉に詰まり、あー、だの、うー、だの、言葉を濁しながら視線を泳がせた。が、すぐに真面目な顔を作って言う。
「デンマーク行きたいんすよ」
「デンマーク? なんでまたそんなとこ」
「幸福度世界一の国だから」
へえ、と相槌を打ちながら顔を窺うが、冗談を言っているようには見えなかった。
「ワーホリ使ってデンマーク行って、そのまま国籍とって移住できたらなって」
「移住!? 移住まで考えてんのかよ!」
「だからオランダ語教室に通って金貯めて、みたいな」
「……オランダ語? 喋れるんだ?」
「喋れますよ」
にま、と笑うと、九野はベラベラと知らない言葉を喋りはじめた。身振り手振りを交えて、やけに楽しそうだけれど、何を言っているのか全然わからない。英語だったら意味が分からなくてもなんとなく知ってる単語が聞こえてきたりするものだが、それすらなかった。九野はやがて一息ついて、
「……みたいな感じっすね!」
くすぐったそうに頭を掻いた。いや、喋ってくれなんて頼んでないし、急だし、っていうかなんて言ってたんだよ今。全然わかんねえよ。
さっきまで鬱陶しいけど可愛い後輩だったやつが、なんだか違うところに行ってしまったみたいだった。俺の中の九野は、ちゃらんぽらんで、気さくで、友達みたいで、でも会社では俺に怒られたり、俺と一緒に上司に怒られたり、そういうやつだった。デンマークに住みたいなんて思ってないし、外国語は英語もあやふや、きっと金はソシャゲとかライブとかに使ってるんだろうなと思っていた。
なんだ。お前、俺のそばにいると思ってたのに、全然遠いのかよ。
「先輩は、何かしたいことあるんですか」
「……俺?」
俺、の。
したいこと。
ふと思い出す。大学の卒展が終わった後、ゴミ捨て場に作品を捨てに行ったこと。
絵だの、立体だの、四年間かけて作り上げた作品たちが、ゴミの山になっていたこと。結局俺のいた学科から、芸術家になったやつは一人もいなかった。それでも周りはとっくに就職を決めていて、デザインをやるやつもいれば芸術に全く関係ない仕事に就いたやつもいた。
腹の内では笑っていたのだ、俺は。
芸大にきてなんで営業だの事務だのになるんだ。馬鹿ばっかだな。なんて見下していた。俺だけ現実が見えていなかった。自分に見切りをつけるのが遅くなった分、自分の行く末が分からなくなっていて、今もまだその行く末とやらは行方不明のままになっている。
「仕事やめてこっちで食ってくとか」
低空飛行を続ける一号を指でつつきながら九野が言う。そんな、そんなこと、
「……無理に決まってんだろ」
なんとかそれだけ言って、あとは飯を食うことに専念した。
+++
浮遊石を使ったミニチュア空中庭園を作り始めたのは、務めて二年半経った頃だった。
やっと仕事にも慣れてきて、休みの日に何か作ろうかな、と思ったのがはじまり。大学時代に作っていたジオラマの、もっと小さいやつなら今でもまたやれるかと思った。ついでに最近流行りのハンドメイド通販サイトで売れたら小遣い稼ぎにもなって最高。そんな考えだった。
うちは芸術家の血筋だ。遠い祖先が江戸の歌舞伎役者だったのにはじまり、やれバイオリニストだの画家だの、陶芸家だの、パティシエだの、とにかく企業に所属している人間がいない。かといってモデルやタレント方向ではないので世間一般に有名でもない。スーツを着て出勤するのはうちの父親くらいだった。役所勤めと結婚した母は親戚でもかなり浮いていた。
俺は、もちろん自分も芸術家になるのだと思っていた。
中学高校も美術部、当たり前のように芸大。
もしも地球に魔法があったら、というコンセプトで作った架空世界のジオラマはものすごく受けがよくて、一回生で開いた個展からファンがついた。取材もきた。北国から南の海辺、それこそ惑星一個分くらいの都市は四年間で作ったんじゃないだろうか。一つの作品がコタツひとつ分くらいの大きさがあったから、個展の会場はどんどん大きくなった。大きくなるほど客も増えた。このジオラマシリーズで、卒業後も食っていけると信じていた。
けど、売れなかったのだ。
一個も売れなかった。
みんな見に来てくれて、褒めてくれたが、買ってはくれなかった。
買う気になるような、小さなものを作ればいい。分かっていた。でもそれは俺の作りたいものじゃない、価値を分かってくれる人なら必ず買ってくれる、だって俺の作品はすごいんだから。本気でそう思っていた。
魔法が見つかるまでは。
人工開発された新元素レニウムは、組み合わせ次第で魔法のような効果を発揮する。飴玉ほどの大きさでもミニチュア空中庭園を浮かび上がらせるくらい簡単だ。
俺の作った魔法の世界など、あっという間に「前時代的」になってしまった。
悩みながら作ったヤギはどことなく困ったような顔をしていた。
これは『困り顔ヤギさんのいる牧場』という名前にするしかない。小指の第一関節くらいの大きさをしたヤギをピンセットでつまみ、人工芝の上にそっと置く。このヤギは別に動いたりしない。ただの置き物だ。
結局ほとんど眠れず、眠れないならいっそ作業しようと思って徹夜してしまった。
外はだいぶ明るい。通りを車が走る音が聞こえる。ベッドにもたれかかりながら思い切り伸びをしたけれども、眠気が血の代わりに全身を巡っていて指先まで重くダルかった。たぶんテレビでは戦隊ヒーローものが終わってオーケストラが始まっている頃だろう。照明の周りを、二つの空中庭園がゆっくりと移動していた。
マチュとピチュ。一号はいない。
「……一号?」
がちがちに凝っている体を無理矢理動かし、立ち上がる。部屋の隅にぶつかってもいない、どこかに落ちてもいない。ひとしきり部屋を歩き回っても見当たらなかった。脱走か? いや、窓を開けてないから出ていくわけがない。いるはずもないベッドの下なんかも探すが、やっぱりいなかった。どこだ。とりあえず外を探しに行こうか。考えを巡らせている間に、ふと、寝床を見ていないことに気付いて洗濯物の隙間をのぞく。
ガラスでできた玉の中に、一号はころんと転がっていた。
昨日の夜中に寝床に入れてやったのだ。でもそれ以降見ていなかった。
「おーい……一号……?」
生き物でもないのに呼びかけつつ、寝床から引っ張り出す。人工芝がぱらぱらと手のひらに落ちた。嫌な予感がして土台をひっくり返す。
底に嵌め込まれたレニウム鉱石が、全部黒くなっていた。
寿命だ。
空中庭園の寿命は三年に設定している。もし持ち主が飽きてしまった後、ずっと押入れの奥で飛ぼう飛ぼうとし続けるなんてあまりに可哀想だと思ったからだ。
本当は、星が作りたかった。丸い星。空中庭園みたいな土の塊が浮いてるんじゃなくて、小さな星を部屋に浮かべたかった。結局、丸い土を安定させるレニウム鉱石の配列がどうしてもうまくいかなくて、今の空中庭園を作ることにした。
一号は最初に作った空中庭園で、最初の失敗作だった。それから丸三年、毎日俺の部屋をゆっくり飛んでいた。障害物を避けられないから壁に当たっては少しずつ方向転換し、また壁にぶつかっては方向転換し、ときどき部屋から脱走してなぜか風呂場にいたりする。
ひとまわり大きかったはずの土台は、ぶつかるたびに少しずつ土を落として、ずいぶん削れてしまっていた。『何かにぶつかったときは部屋に土が落ちます』って説明書に書かないといけないな、と気付いたのも一号がいたからだった。
ぶつかってもぶつかっても前に向かって飛ぶ俺の一号が、俺の手の上で終わっている。
「小っさ……」
玄関の開く音と、九野が鼻歌をうたっているのが聞こえてきた。
「はよっす先輩、今日すげえ天気いい、って……どしたんですか、それ」
「寿命だよ。安っすい石使ってるから、壊れた」
「壊れるんですか、それ、……あぁ、石。石、替えたら直るんでしょ?」
「さあ……やったことないから」
「やりましょうよ」
いつものバカっぽさが嘘みたいに九野は言った。いや、こいつのバカっぽいのは嘘なのだ。夢に向かって頑張ってる、外国語がぺらぺら喋れるのがこいつの本当の姿だ。
「やらないよ、っていうか、……やめた」
「何が」
「こういうの全部」
床にぶちまけられている工具類を雑に押し退けて、スペースを作る。空いた床に寝転がると、落ちた砂粒のざらざらした感触が作業着越しでも分かった。このうちのどのくらいが一号だった砂なんだろう。そんなことを考えたってしょうがない。徹夜明けの体には日差しも部屋の蛍光灯も眩しくて、思わず両腕で顔を隠す。九野にも今は顔を見られたくなかった。
一号は教えてくれた。頑張って何かやっても、元からない能力が生まれるわけではない。障害物を避ける機能がないならずっとないままだ。ぶつかってぶつかってなんとか方向転換できても、最後には身が削れて終わるだけ。
「お前のやってることと違って、しょうもない小遣い稼ぎだ。夢も希望もない。はー……」
なにやってたんだろ、俺。
なにやってんだ俺。
「なに言ってんだよ、あんた」
ぽつりと、九野が呟く。その声が震えている気がして、目を開けた。
部屋と廊下の境目で立ち尽くしたまま、九野は俺を睨んでいた。見下すのではなく、真っ直ぐ俺を見る目には、はっきりと怒りがあった。
「しょうもない小遣い稼ぎってなんだよ」
「……その通りだろ」
やはり顔が見ていられなくて、床の上に丸くなる。
「っていうかお前にそんなキレられる筋合いねえよ」
「あんた……あんたサイテーだ」
「そうだよ。サイテーだよ」
サイテーサイアク、ドン底だ。
暗くなった視界の向こうで、九野が何か言おうとしていた。けれども結局何も言わず、そのまま部屋を出ていく。扉の音。あぁ、鍵をかけないと。起き上がってのろのろと歩いていくと、勢いよく扉が開き、
「カギかけろ! ベッドで寝ろ!」
勢いよく閉まった。
+++
七時。
「嘘だろ……」
昨日の朝十時くらいに寝始めたはずだから、だいたい二十一時間ほど寝たことになる。
こんなに寝たのは赤ん坊のころ以来、いや、赤ん坊のときだってこんなに寝ていなかったと思うので、母親の腹の中以来だ。思いっきり眠って思い切り爽やかな朝、目が覚めて思ったもうひとつの「嘘だろ」は、昨日の自分だ。イライラしていたのか寝不足だったのかどちらもか、理由はどうあれあんな小学生以下の八つ当たりで後輩を怒らせてしまった。いい歳をした大人が年下の友達にとる態度ではない。
「あー、まじか、うわー……」
二十一時間前の自分にドン引きする。三連休の最終日ではあるものの、昨日の様子だともう今日はこないだろう。冷蔵庫に残った食材もどうしたらいいのか分からないし、謝るにも、仲直り(仲直り! 小学生か!)にもどうしたらいいのか分からない。連絡を入れようか、いや、もしかしたらまだ寝ているかもしれない。常識的に連絡は九時半以降で、いやでも夜中の二時に連絡してくるやつもいるし……なんてことをつらつらと考えつつも、体はちっとも動かなかった。明日には仕事でまた一緒に働くことになる。会社でもほとんどペア扱いなのだ。気まずいまま仕事なんて出来っこない。でもやっぱり、動けない。
部屋は最高に汚いわ、空気はなんか変な匂いがするわ、結局スーツはクリーニングに持っていってないわ洗濯もしてないわで、生きててごめんなさいと神様あたりに意味もなく謝っておかないといけない気がする。とりあえず窓を開けて換気扇を回して、部屋の空気を入れ替えた。
久しぶりにたっぷり寝たからか、立ち上がるだけでも昨日の二倍くらい早く動けた。シャキッと立って、洗濯を回し、スーツはとりあえずハンガーにかけて、工具類をまとめていく。買ったはいいものの使っていない鍋がキッチンにあったので、殴る工具、削る工具、接着剤、と大雑把に分けていき、材料や小物の類も手あたり次第に片付けた。収納の奥底に仕舞われていたクイックルワイパーを使う。一往復もしないうちに砂粒で前に進めなくなった。どうせ消費期限切れのシートだ。大盤振る舞いすることにして、とにかく床を拭いていく。できた洗濯を突っ張り棒に干して、意味もなくベッドを整えたりした。
このテンションのまま風呂掃除までやってしまおうかとシンクに立ち寄ったところで、ふと玄関に白いものが落ちているのに気付いた。
ドアについた郵便ポストが壊れているので、よく郵便物が玄関に落ちているのだ。電気代かガス代かクレジットの支払いくらいしか届かないので別に困ることもない。今度はなんの請求だろうかと白いものに近づくと、そこには二文字、綺麗な筆文字が描かれていた。
辞 表
夢にまで見た文字に、どきりと心臓が震える。辞表。辞表だ。白い封筒に入ったそれを、おそるおそる開く。九野の字だった。
この手紙を君が読んでいるということは、俺はもうこの世にいないということなのだろう。
なんて、これ一回でいいから書いてみたかったんです。
でもこの手紙を読んでる先輩に、俺はデンマークに行くことを言えてるのかな、言えてないのかな。とにかく、先輩のおかげで金が貯まって、デンマークに行けることになりました。
本当にありがとうございます。
俺はずっと先輩のファンでした。大学のとき、同棲してた彼女にプレゼントするために先輩の空中庭園を買って、でも注文した次の日に彼女が出ていっちゃいました。彼女の物がなくなった部屋は空っぽよりもずっと寂しかった。ボー然とする俺のもとに、空中庭園が届きました。最初は部屋中ウロチョロされて最悪だとおもったけれど、気付けばなんか、いやされて、それからずっと捨てられないでいます。
先輩。俺、デンマークにいっても、幸せになれないかもしれない。
けれども俺は行こうと思います。幸せがなんなのか、俺は知りたい。
というわけでサミシイ先輩を慰めてごはんを作ってあげる係は退職します。
たまに帰ってきて飯作ってあげますから、そんときはよろしくお願いします。
「先輩」
いつの間にか扉が開いていて、九野が立っていた。その手にはミニチュアの空中庭園が握られていて、両目からはぼたぼたと涙が落ちていた。下から見上げたレニウム鉱石は、軒並み黒く変色している。
「……直して」
俺の空中庭園、直してください。
泣きながら必死で両手を突き出してくる九野を、とりあえず部屋にあげてやる。手渡された空中庭園は、俺の記憶が正しいならはじめて売り出したシリーズのものだった。まだ動物のミニチュアはない。ただの芝生に、赤い郵便ポストが一つ、ぽつんと立っている。ただそれだけの空中庭園。ひっくり返して、底に嵌っていたレニウム鉱石を取り出す。いつも新しいやつを作る通りに石を嵌めていくと、洗濯物の隙間に干されている寝床にそっと入れてやる。寝床にとりつけられた石と空中庭園に嵌められた石が反応してぼんやりと淡い光を放ち、やがてポストを乗せた空中庭園は、ふわりと浮き上がった。
「……」
九野はぽかんと口を開けたまま、再び宙を漂い出した空中庭園を眺めていた。両目からはまだぼたぼたと涙が流れている。むしろ直る前よりも多くなったかもしれない。涙腺ガバガバだ、こいつ。
「せんぱい」
ぼたぼた泣いて涙腺ガバガバのまま、九野は俺を呼んだ。俺も悠然とワンルームを飛び回る赤いポストを眺めながら、ん、と応える。
「ファンです」
「聞いたよ」
辞表なんて出しやがって。そう思うと妙に腹が立ってきて、脇腹をグーで殴った。九野は身をよじって笑うばかりだった。
マチュとピチュ、ポストと一号が飛ぶと、さすがにワンルームの天井も窮屈に感じる。下は舌で、半分残っていたチリワインと二日分の料理でちょっとしたホームパーティーみたいになっていた。まだ昼前だというのに俺と九野は大いに飲んで、一度二人してコンビニまで出向き、またアホみたいに安いチリワインをしこたま買い込んで、飲み続けた。
「おめーみたいななぁ、クソみたいな後輩は、とっととデンマークいって、幸せになっちまえ!」
「だからさぁ。せェんぱいもさぁ、幸せにさぁ、なりましょうってぇ」
そんなことを九野が言うものだから、俺の涙腺は一瞬でブッ壊れた。いわゆるガバガバだ。
思い出すのは昨日交わした会話だ。先輩はしたいこと、ないんですか。俺は即答できなかった。やりたいことは山ほどある。大学生のときから、ずっとずっと、やりたいだけのことなら、いくらでもあった。けれども、自分がやりたい上に評価も高かった作品が売れなくて、ゴミとして捨てなくてはならなかったとき、何かがぷつんと途切れたのだ。やりたいことを、やる、という普通なら繋がっているはずのものが、途切れてしまった。
「俺もう、何がしたいのかわかんない……!」
本当は星が作りたかった。小さな星をいっぱい部屋に浮かべてみたい。たとえば、触れるプラネタリウムとか。光を当てて、影として星を見るのではなく、星自体がぼんやり光ってくれるような。そんなものがやってみたい。他にもまだまだいっぱいある。レニウム鉱石の可能性は無限大だ。安定して効果が出せる配置はまだ全然見つかっていないけれど、逆に言えばそれだけ可能性に満ちているってことだから。
こうやっていろいろ思いついたとき、ぷつんと途切れる前だったら、すぐに作れた。すぐ取り掛かれた。でも今は、頭の中で声がする。「え、またゴミ作るんだ?」って。
「俺の作りたいの、だからどうしたってものばっかりだ。役に立たない、飾っておくには邪魔」
「たとえばぁ?」
胡坐の中に抱え込んだワインボトルにもたれかかるようにして、九野は訊いた。もうほとんど目が開いていなくて、呂律も回っていない。かくいう俺も白のボトルに甘えている状態だ。
「本当は、星が作りたいんだよ」
「ホシ! たーとえばぁ?」
「たとえばー……あ、USJの入り口にあるやつ。あれぐらい大きい、浮いて、回って、それで映画の一場面とかがジオラマになってるやつ」
酔った勢い、その場の思い付きだったが、なかなか自分でも面白いアイディアだった。そうだ、めちゃくちゃでかい、惑星のジオラマ。星はでっかいのに、アメリカ合衆国のそれぞれの州で一個の映画の一場面を再現するくらい細かいやつ。最高。
「作りましょうよ!」
「作ってどうすんだよ」
「貸すんですよ! USJに! 年間三億円くらいで!」
「ばっかぼったくりすぎだろ三億って。三百万くらいだよ」
「安売りはダメですよ。そゆことすると他のアーティストがもっと安く買いたたかれるんです」
せめて一千万ですよ。いや三千万かな。年間三千万。心底真面目な顔で九野は言った。いいですね。三千万ですよ。
「じゃあ、デンマークで完成報告待ってますね」
「……どーすっかなぁ。すげー小さい星から、ちょっとずつでかくするべきだよな」
なんだかその気になっている自分がいる。飯がうまい。酒がうまい。たっぷり寝た。今日もあとは寝るだけ。こんな最高な日だからかもしれない。
「じゃあ猿の惑星とかどうです?」
「見たことねえよ」
「ビデオ屋にいくらでもありますよ。借りましょ」
「あー、そーね。明日ね。今日もう眠いから。明日ね……」
言って、九野が陣取っているベッドの上にのそのそとあがる。あぁ、ベッド最高。寝具って寝るための道具だもんな。専用の道具ってのはいいもんだよ。むにゃむにゃとそんなことを言いながら、枕を引き寄せる。
「……おやすみなさい、先輩」
俺、帰りますね。
九野がそう言うので、おう、明日な、と俺は軽く返して、眠りについた。
次の日、九野は会社に来なかった。三連休のギリギリラストで辞表を提出したらしい。もう有給消化に入ってそのまま退職、というか、今日の朝イチの便でデンマークに発ったのだそうだ。
久しぶりにメールを使う。なんと送っていいのか分からなかったので「クソ野郎」と送ると、すぐに返事がかえってきた。時差とかないのか。
『星、楽しみにしてます。あと、空中庭園を買った他のお客さんたちにも、ちゃんとアフターサービスしてくださいね』
忠告に従ってメンテを請け負うページを作ると、すぐさま三つほどの依頼があった。メッセージには、どうしても今いる空中庭園がいいのに動かなくなってしまって、新しいのを買うかどうしようか迷っていたというような内容が多かった。これは新規と同じだけの需要が見込めそうだ。
続けてもう一度メールが届いた。
『あと、部屋の掃除はこまめにして、たっぷり寝てください』
結局ゴールデンウィーク中に完成させられなかった空中庭園たちもあるし、これからは星作成のための試行錯誤の日々が始まる。きっと最初は手探りで、失敗ばっかりで、やっぱりゴミをいっぱい作ってしまうだろうけれど、それできっと落ち込むんだろうけれど、そうしたら、九野に連絡しよう。デンマークの写真でも送らせて、それを見ながらクソ安いチリワインを飲むのだ。作業もほっぽりだして、とにかく掃除して、思いっきり寝る。そうしたらきっと、次の日からまた頑張れる。気がする。今だけかもしれないけど。
さぁ、まずはビデオ屋に行こう。
猿の惑星を借りなくては。
サポートされてみたいです!!!!!!!!!!!!!!!よろしくおねがいします!!!!!!!!!!!!!!!1
