
あなたはどんなキャラを演じていますか?ほんとうの自分を守るため、仮面を探し求める人々◆ゴフマン(1)芝居と仮面【ぷろおご伊予柑の大預言】
鼎談:「ぷろおご伊予柑の大預言」をアーカイブしています

大預言を読む
○大預言とは?
ぷろおごと伊予柑が古典を消化して対話をし、
『大預言』を生みだそう!という企画
伊予柑…人類補完計画を企む悪いおとな
ぷろおごとは数年の付き合いがある
今回はスペシャルゲストにトリさんをお招きしております。
こちらは動画;ぷろおご伊予柑の大預言を加筆編集したものです。
◼️今回の課題図書

芝居と仮面
あなたはいくつ仮面を持っていますか?
会社に行けばサラリーマン、家に帰れば誰かの子ども、あるいは親にだってなるかもしれない。そして旧友と会えばいつまでも変わらないお前にもなる。
人は、場にあわせて仮面をいくつか持ち合わせているようです。仮面はあなたに属性を付与し、どのようにふるまうべきか導きます。
仮面を身につけ、場にただよう特有のリズムをつまぐり、求められた役を演じれば、あなたはまるであなたでないようで、世界もほんの少し表情を変えるでしょう。
しかし、やりすぎてはいけません。役に埋没する喜びにやみつきになれば、赤い靴を履いた少女のように踊り続けることになってしまいます。
今回お送りするのは、演じずにいられない男と演じることができない男のワルツです。



伊予柑:今回の課題図書はアーウィング・ゴフマン『日常生活における自己呈示』という本です。わりと社会学のなかでも有名な本のひとつで、ぷろおごが選びました。これはなんで選んだの?
ぷろおご:課題図書どうするっていう話があって、最近演劇の話をしていたし、ちょうどよさそうだなとおもった。とりあえずこれにしますか、って箸休めみたいなかんじ

トリさん:箸休めなんだ
ぷろおご:なんでしょう。こういう本を元ネタに、みんないろんなものを作ったり書いたりするじゃないですか。今からジョジョの一部を見るみたいな話ですよね。そんなに新しい情報がなければ、そんなに重くもないのかなとおもって
伊予柑:今回、僕は6月めちゃくちゃ忙しくて読めてないのですが…

伊予柑:今日のゲストはトリさんです。お前の発見を語れの過去グランプリで、ひとことでいえばあなたは何者ですか?
トリさん:無職です
伊予柑:はい、無職の人。トリさんも演劇をやりたいみたいなことをおっしゃっていましたよね
トリさん:演劇というのはスラムで言われている演劇と、一般的な舞台芸術のほうの演劇と、どっちの意味でもですね。僕は舞台が好きで、もともと演劇をやってたんです。それに、日常のなかでも演劇をしたいですね
見えないルールが見えることと空気を読めることはおんなじか
伊予柑:ちょっと前の大預言で、演劇というのを特別な用語として定義をしました。そこでいう演劇は一般の演劇とちょっと違っていて、ルールのある遊びぐらいの意味なんですね。
【演劇】相互に加害が成立するフィールドのこと
1)場所や時間が限られている
2)日常と違うルールが明確にあり、合意されている
3)演劇をしていない観客がいる
4)審判など中止できる人がいる
5)演劇の成立が全員の目的である
サッカーや相撲は演劇。殴ったりタックルしても合法
サッカーは演劇である。なぜかというと、日常生活と違って手を使っていけないから。そこにはなんの根拠もない。こういうものは演劇だよねっていうのが僕の指摘でした。
つまり日常生活のコミュニケーションのなかで、あるキャラを演じる。「俺はボケキャラだから〜」というよりも、なんらかの見えないルールに従ってコミュニケションをとるということ。僕はそれを演劇だなあというふうに思うんです。
あるコールがあったらコールに乗らなくてはいけない、とか。上司がこう言ったらこう言わなくてはいけない、それはルールじゃないですか。俺にはよく見えないんですけどね。
トリさん:「なんでぺこぺこしてるの?」とかもそうですよね
伊予柑:そう。演劇には見えないルールがある。この本では演劇的なものはどう書かれているんですか?
ぷろおご:この本は、演じる人のことをパフォーマーっていってるんですよね。おもしろい表現だよね

実は個性なんてなくて、ただそういう役割があって演じているだけ?
ぷろおご:基本的に具体例はいろいろ書かれているんだけど、それこそ前回あたりで話した医療において医療者は「居る」ことがむずかしいみたいな話、そういうのもちょうどでてきましたよ。
治療を受ける側から見て、医者が院内をぷらぷらして歩いてるのはなにもしてないように見えるけど、すごい大事だよね。みたいなことが書いてあった。医者の姿が見えるようになってないとコミュニケーションに齟齬が生じて、患者は不安になったりする。
演劇としてパフォーマンスがなされることによって、可視化されるものがある。たとえば葬儀だったら、基本的にはなににいくら金を払っているのかわからないわけじゃないですか。だから、この棺に金を払ってんだなっていうのがわからないと満足することはむずかしくて、「オレはなにに金払ってんだ?」となってしまう。
世界は結婚式場みたいなもので、そこに参列する人たちは全員役割が決まっていて、儀式的にものごとが進んでいる。
すべてがそういう構造のなかで動いている。構造的に社会を見るみたいなものにも近いですね。
章立てでいうと、
第1章 パフォーマンス
第2章 チーム
第3章 領域とそこでの行動
第4章 見かけと食い違った役割
第5章 役柄から外れたコミュニケーション
第6章 印象管理の技法
第7章 結論
1章は世界は劇場で、人々はパフォーマンスをしてるねっていう話をしていて、2章はチームにおける演劇の話をしてる
伊予柑:役割分担だ
ぷろおご:そう、サッカーとかね。
3章は「領域とそこでの行動」、つまり場所ですね。それこそ仕事場にいるか家にいるかで人はふるまいを変えますよねっていうもので、野球スタジアムという劇場にいればそれらしいふるまいになるよという話でもある。
4章は「見かけと食い違った役割」要するに、見かけ上の役割と実際に担っている役割が異なる人のこと、サクラとかスパイとか
いろんな印象管理の技法っていうのが6章にあって、技法というのは一般的に行われている、サラリーマンはかっちりしたスーツを着て見せているよね、とか。全般的にむずかしいことは書いてないが、ただちょっと長いからあれだね。そのぶん具体例はけっこう書いてある
伊予柑:デュルケームで見たやつだ!みたいな赤ペン感がありますね。すべては儀礼であるという
ぷろおご:そういうものをもうちょっと我々の現代的な日常生活に寄せたようなかんじ
トリさん:具体的なのはめちゃくちゃありがたい。読みやすい
ぷろおご:最近扱ってきたテーマと被るし、というかもはや被らないものがないよね。いろんな角度で同じことをしゃべっている

自分で価値判断ができないと、誰かに許しを乞わねばならないか?
伊予柑:前の演劇の話だと、今SNSでは善が混乱しているという話がありました。善というのはルールと価値観のことです。
サッカーだったら手を使ってはいけない。そしてなぜかしらんが相手のネットにゴールを入れるとポイントが獲得することができるからいい。みたいなルールがありますよね。
そうした複数のルールがSNSに順番に流れてくるから、どれに従っていいのかわかんねぇ、というふうに、そのルールに自信がない人;おさなごは混乱しちゃうよねっていう議論をしてたんですけど、トリさんにこの話が響いたそうです。
トリさんはルールを勉強してちゃんと身につけられるマンな気がするんですけど、複数のルールにさらされて混乱なさってるんですか?
トリさん:そうですね。まず、自分の一番根源的なところが不安定で、俺ってここに居てもいいのか?そもそも俺って居てもいいのだろうか、っていう気持ちが社会に対してあります。それは社会というルールを前に混乱しているとも言えることができると思っていて、なんていうか、難しいな
伊予柑:あなたがいていいかは誰が決めるんですか?
トリさん:誰かによって決められてるというイメージがあるんです。本来、自分という人間は居てはいけないなんてことはないじゃないですか。居ていいんです
伊予柑:そうですね。憲法によると居ていいということになっています

トリさん:そうなんですよ。そうなんだけど、誰かに居てもいいと許しを得ないといけない気がするんです。居てもいいよって決めるのは誰かで、それがないと僕はここに居られないみたいなものが根本的なところにあるんです。
ツイッターではいろんなルールが目に入るじゃないですか。だからもうなにを信じていいのかわからない。信じるものがひとつももないから、「あ、この人はこんなことを言っていてる」「だけどぷろおごはこんなことを言っている」っていうところでわァ…ってなっちゃうんですよね。
子ども時代に受けた呪いが大人になっても、人々を苦しめるのはなぜか
伊予柑:そうするとこの国でいちばん偉い憲法よりも偉い、あなたがここに居ていいかを決める誰か、あるいはなにかを信じてるんですね
トリさん:そうですね
伊予柑:それは誰なんだろな
トリさん:家族とかですかね
伊予柑:基本的に家族は憲法より偉いですからね。少なくともおさなごにとっては憲法はまだ見たこともないので
トリさん:そうですね。だから本当におさなごという表現はめっちゃわかりやすいなあと思ってね。子どもなんですよ。僕が子どもで親が、「お前、〇〇しないとここにはいちゃいけないよ」と言っているようなもんです
伊予柑:そういうことを言うんだ
トリさん:言うというか、伝わってきますよね。父親の機嫌を損ねてはいけないというルールがあったんですよね。そのルールのもとに生活をしていた。でも、父親とずっと一緒に生きていくというわけではないから自分の軸がない。なので、生活は不安定で、不安にもなります

伊予柑:今、父親を殴ったら倒せますか?
トリさん:余裕で倒せますね。それも頭ではわかってるんです。だけど当時、僕はまだ子どもで、子どもにとって居場所を脅かされるとか放っておかれるっていうのは生命の危機につながるじゃないですか。
そのときの「放っておかれないようにしないといけない」「役に立たないといけない」っていう感覚がどこか残ってるんでしょうね。もう大人になったからべつに放っておかれても死なないっていうのは頭ではわかってるんだけど、そのときの不安がずっと続いているって感じで
これはちょっと仮面の話から離れちゃうのかな
伊予柑:いえ、その通りだとおもいます。スラムで、呪いとは不快だけど逃れられないものというふうに定義しているんですけど、まさに不快だけどなぜか逃れられない
トリさん:そうですね、恐怖がしみついているみたい
他人がいないと、自分に対して厳密に一貫性を求めてしまう
伊予柑:でも、だいぶ呪いについて自覚されていますよね。いつごろから自覚できてるんですか?
トリさん:僕、中学のときにいじめられて引きこもってたんです。そのときはやることがなかったので、ずっと自問自答したり、内省を繰り返してたんですよ。人に読ませるわけではないけど、自分の心の動きとかをずっとメモに書いたり、言語化だけは死ぬほどしてきたんです
伊予柑:なるほど
トリさん:自分がどう思ってるのかとか、なんで俺はこんなことを思うのだろうか、とかそういうことは延々と考え尽くしてきたので、頭ではわかってるはずなんです。だけど心はまだ納得してないんですよ。
自分は居てはいけないということ、お前は不安定であるべきだみたいなものを信じてるんでしょうね。ほかに信じられるような自分の軸みたいなものは見当たらなくて
伊予柑:その時の父を信じてるんですね
トリさん:そうですね、父とか兄を信じてるのかもしれないですね
伊予柑:ほかにも信じてもよさそうな気もしますけどね
トリさん:そうなんですよ。ほんとにそう思います。なんでなんですかね。ここまで言語化できてるし、わかってるつもりなんですけど怖いんです。恐怖、不安が大きい。僕の頭の中にはインナーひろゆきがいて、
伊予柑:ああ!よくお見かけします
トリさん:なにをしゃべるにも、どんな行動をするのでも、「え、でもあなたってこれですよね?」って言ってくる。それはいくつかパターンがあって、なにも自信を持ってしゃべれない。
そのモードに入っちゃうと本当になにもしゃべれなくなっちゃうから、仮面をつけて、音ゲーとしてこなすんですよ。そうすると心では思ってないようなことまでも言えるようになる
伊予柑:まだ他人がいないんでしょうね
トリさん:そうですね。見本となる、規律となるような人はいないかも
伊予柑:トリさんみたいに考えてる方はけっこう多そうですけどね
トリさん:多いと思いますね
不安は伝播する。他人の演技に気づけるのはどんな人か?
ぷろおご:(トリさんは)なんかソワソワしてますよね
トリさん:ソワソワしてますね
ぷろおご:ずっとソワソワしてる人っているよね。彼らってソワソワしてることによって、余計になにかしてないと許されなくなるんだよね。だってソワソワしてる人にはなんかさせてあげたほうが場は安定するじゃない。ソワソワしてるよりはね
トリさん:ぷろおごから見て…ってことですか?
ぷろおご:おそらく一般的に、場の物理学として。場というものを考えたときに、たとえばなんだろうな、動いていないと落ち着かない人は動かしておいたほうがいい
伊予柑:暇になると病むんですよ

ぷろおご:それは局所的なこういう場においてもそうで、居るだけで平気な人は居るだけでよくて、しゃべってもしゃべらなくてもいい。だけど、その場にソワソワしてる人がいたら、その人のケアが発生するんだよね。ソワソワする人は、しゃべらせておくとか、なにかさせておいてあげれば、まだソワソワしなくなるじゃん。
ただ、それはどんどん加速するよね。しゃべらないと居られなくなる。そういうふるまいになっちゃうんだよね。しゃべらせておいたほうがいい人になっていく。そうすると、ソワソワしていない人の過ごし方をやろうと思ってもできないというか、居るだけが求められた時に居るだけができないままだから。そのへんはまたむずかしいところですよね
伊予柑:不安障害とか愛着障害の方はなにもしないと不安がどんどん膨らんで、ぐおおお!っていうふうに落ちていってしまうことがある。なので、それを誤魔化すためにソワソワして、仕事をするっていう人はそこそこいますよね
トリさん:僕はそういうタイプですね
ぷろおご:この本だと、パフォーマンスとかって言うんですけどね。あまりにも自分が休む場所がないとバランスはとれないんでね。ワークライフバランスじゃないですけど、パフォーマンスにもいろいろあるみたいで、ソワソワしてるだけでは人間は成り立たないんでしょうね。居るだけの時間も欲しいよなあってなるよね
トリさん:そうですね

伊予柑:でも居るだけだと不安になっちゃうんでしょう?
トリさん:そうなんです。
だけどいまはそれも悪くないかもしれないと思ってます。演じてしまう自分は嫌ですよ。だって本当は居るだけで肯定してほしいし、居るだけでソワソワなんてしたくない。これまでは僕が仮面をつけまくってるのは不自然で、間違ってることだって思ってました。
だけど、あの演劇の記事を見てちょっと肩の荷がおりたところがあったんです。自分は不安でどうしようもなくてソワソワするから、入れ替わり立ち代わり仮面をつけ替えて演じてという、そういう能力が身についちゃったと思ってるんですけど、手にあまるその能力も、身についてしまったならいっそのこと使いましょうよっていうのをあの記事を読んで思ったんですよね。
つい演じてしまうというふるまいも人から羨ましいって言われることもある。そうすると、これはひとつの能力として肯定した方がいいし、活かせるだろう。だからそのままでいいと思うと、ちょっと楽になりましたね

ぷろおご:なんかあれだね、いい人選だね。ちょうどいい。ドンピシャだ。仮面をつける意識ね
トリさん:演じていいんだ、ってちゃんと思えたというか
強いられた演技で観る者を魅了することはできるか?
伊予柑:僕は演じられなくて大変なほうだった。ASD系の人は上司だろうがなんだろうがズケズケとものを言う。適切な演劇が得意ではない
トリさん:反対だなあと思いますね。そういう人にけっこう憧れるんです。なにもしないで物怖じなく言える人ってかっこいいなあって。
僕みたいに憧れる人は多いと思います。だからぷろおごはフォロワーが多いんじゃないでしょうか。僕のような人からすれば憧れの対象でしかない。こんなにズケズケと言えるの……?っていう

伊予柑:愛着障害気味の人のなかで、演技性人格障害に寄っていく人が一定数いるんですけど、それは自分のキャラクターがすごい過剰になってしまって、そのキャラクターにどんどん入れ込んでしまった結果なんですよね
トリさん:だって仕事できる人間としてふるまっていたらもう終わりですもん。3ヶ月後には、「ああ、もう休みたい…」ってなってるのに「オレ仕事できるからめっちゃ期待されてるし、実績もちょっとだけ足してきたから、もうこの役降りれないな」ってなってしまう。
僕はだいたい半年ですべての仕事を飛んでるんです。演じることに疲れてしまう。1年以上続けた仕事ってほとんどないんです。しかも連絡せずに飛んでしまう。社会的には最悪なんですけど、怖くなってどうしようもなくなる
伊予柑:話を聞いてると、なんとなく親云々というよりも期待に過剰な負担を感じてしまう人のような気がしました。僕の表現だと善に弱い人というんですけど、周りがこうだという評価軸をとてもとても過剰に受け取るタイプの人のような気がしますね
トリさん:そうですね
ぷろおご:過剰演劇ですよね
伊予柑:これはよくいるというか、悩みが多いやつ。女性の方に特に多い。めっちゃ良い子ちゃん しちゃう、みたいなもの
役者のからだに合わない配役を演技で補うことはできるか?
トリさん:僕がなぜ演じずにいられないかというと、エピソードとして無理やり親とか引っ張り出してたんですけど、シンプルに善が弱い人間だからだと思います
伊予柑:そうそう。そっちのほうが多くて、べつに理由なんてないんですよ
トリさん:そうですね。たぶん性欲が強いんでしょうね。欲望が強くて、エネルギーの量は多い。だからめっちゃ稼ぎたい、めっちゃモテたい、めっちゃなんかしたい。だけどそうなるには、こういう像でなければならないというのがあって、そういった理想像に囚われているのかもしれない。いい子というかすごい人間でなければならないとか
伊予柑:僕は逆で、欲望が弱く、実はたんに体力も弱いだけだと思います。トリさんはイケメンすらっと青年ですけど、単純にちょっと体が弱い文系の女の子と思った方がいいのでは?
月に2日ぐらい休暇しないと働けない、たんに体が弱い子とご自身のことを思ったほうがよさそう、僕はそんな気がする
トリさん:体は弱いですね。めちゃくちゃ弱いと思います
ぷろおご:体はハードウェアですからね
伊予柑:周りはすらっとした青年であることをトリさんに期待してしまうが、実際には体が弱い子なので、体が弱い子のPRをもうちょっとしたほうがいいのでは?包帯がまかれているとかわかりやすい
トリさん:僕もよくnoteで使う表現なんですけど、包帯ぐるぐるまきのミイラ男だなあって自分のことを思っていて、それが適切にアピールできたらたしかにいいですよね
演技がヘタな人に共通する癖はなにか?
ぷろおご:すごいひどいことを言うんですけど、トリさんは演劇はヘタですよ
トリさん:まじで????
伊予柑:おもしろい展開になってきた
トリさん:そんなバカな・・・
ぷろおご:ちょっとヘタ…ですよね
伊予柑:おもしろい
ぷろおご:なんていうんだろうな。場に則さない演技だとおもうんですよ
伊予柑:はいはいはい
トリさん:場に則さない・・?
ぷろおご:演技されてらっしゃるなあというのはわかるし、ちゃんとガワを整えてえらいなあとおもうんだけど、なんかジャニーズ主演の映画みたい
伊予柑:ぷろおご、サイテー!!
トリさん:くるなあ・・・

ぷろおご:ちょっと、ん?ってなるところがあるというか、空気感が、ん?ってたまになる。映画を見ていられないというほどではないけど、適度な違和感がある。それはシンプルに演技があまり上手くないから。
たぶんキャラデザがわるいとかそういうのもあるとおもうんだけど、演技がそもそもそんなに上手くないから不思議な場になるんじゃないかな。演技しすぎているってことはヘタなわけじゃん。過剰というのはさ、ちょうどよくないってことだから

トリさん:適切ではない
ぷろおご:適切な量ではない
伊予柑:カジュアルな服装でお越しくださいっていうところに、キレッキレのスーツでくるとかが過剰なわけですよね。スーツで来ることはなにも悪くはないんだけれど、
ぷろおご:そうね。そこのむずかしさというか、やっぱりシンプルにそんなに演劇のセンスがないから疲れるんだとおもうけど
芝居はヘタでも演出が上出来だったら、いい演劇になるだろうか
ぷろおご:上手な子ってするっと演技するよね。それでいて、疲れてることも自覚していない。疲れるといっても、苦手な人とも付き合えちゃうから、その結果苦手な人と一緒にいることで疲れるとかそういうのならある。
だけど、自分が演技することに疲れるっていうのは上手くなってないからだとおもうんだよね。だって、なれない役をずっとやっているってことでしょ。さすがに慣れてくるはずというか、それだけの回数をいろんな人とやっていたらその場の演技っていうのはかたまってくるわけじゃない?
たとえば、声優さんだって1~3話までは不思議な声の出し方をするけど、そこから先は安定して、同じ声を出せるじゃない。「はい、やって」って言われたらすんなりと声がだせるわけで、だんだんだんだん疲れなくなっていくはずだからさ。
ずっと演技しているのに、演技していることそのものにコストを感じるとしたら、それは演技がヘタということだとおもう
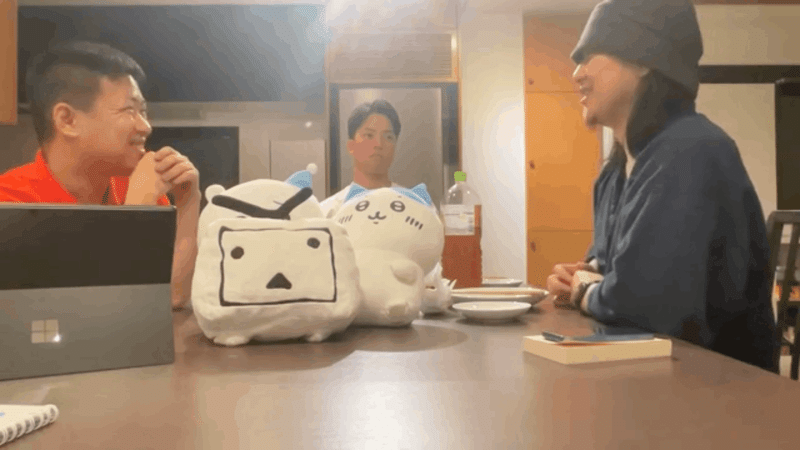
伊予柑:ちなみにぷろおごは演技がヘタすぎて、演技ができない人です。つまり常におなじぷろおごでしかいられない
ぷろおご:そう
トリさん:キムタク
伊予柑:そう、キムタク。はまるやつをまわりが整えてくれないとまったくはまらない
トリさん:そういうタイプってことなんですね
ぷろおご:キムタク映画はまずキムタクがいて、そこからキャスティングして、作品をつくっていくじゃん。そうすると、キムタクはいい役者になる
伊予柑:演技がうまい人っていうのは、どんなにクソな作品、配役であっても一定以上の点数をとってくる人のことですね
トリさん:なるほど。納得感がつよい
問題解決を人格に委ねてしまうと、生きづらくなる?
ぷろおご:仮面の枚数ってヘタだから枚数が増えちゃうんですよ。差別的な言い方だと捉えられるかもしれないんだけど、人格が分離する人っているじゃないですか。見てると、問題解決能力がない人ほど分離の量が多いんですよ。分離する人数がちがう。
人数っていうのは仮面の数のことで、ある程度、問題解決能力が長けてる人は、2、3人で済むんですよ。そんなに仮面の数を増やさなくても、それなりに2、3役があればたいていの仕事はできるじゃないですか。
だから仮面の数は社員の数みたいなものでもあって、要は頭のわるい社長がいると、社員が3人じゃ足りなくなるんですよね。仕事の割り振りが適切ではないから、必要になる社員の数がすごく増えちゃうんですよね。
たとえば、こういう男に対してはこういうふるまいをする。でもわたしはそういうふるまいができないから、Aちゃんにやってもらいましょうっていうので、自分のなかでAちゃんを自動で生成する。そうすると、問題に対応できる。だけどそれはあまりにも局所的な問題解決のために生み出された人格だから、その人格がほかにできることはとくにない。
また新たな問題に直面したら、今度はそのためのオリジナルなわたしを用意しないといけなくなるから、どんどん仮面の数は増えていって、今日はどれにしましょうって言うことになる。そうなると、それを取り出すコストがかかるじゃないですか。整理されていないから

伊予柑:料理が下手な人ってキッチンの道具を無限に増やしていくんですよね
ぷろおご:ペティナイフがあったらそれでこと足りるのに、ナイフをいっぱい持っている
伊予柑:りんご専用のやつがあって〜、みたいな
どんなに仮面が増えても、手は2本、顔はひとつ
トリさん:僕、すべてにおいてめっちゃアドリブ効かないんです
ぷろおご:それはたんに演じるキャラクターを増やしちゃったからというのと、ヘタで場が見えていないから。それからその場の新しいキャラクターをわざわざつくらないといけないという、そういうふうに見えますよね
トリさん:僕もそう思います。すげえ納得感がつよい
伊予柑:たぶん、トリさんはいま、だいぶ体力がついてきたので、単純に断捨離して、キッチンのツールを減らすといいと思うんですよ
ぷろおご:そうだね
トリさん:そう、ちょうど今それをしているんです。いまは仮面をださなくていい場所にいて、どんどん健康になって強くなってるんです
伊予柑:道具の数が多いとメンテナンスも大変だし
ぷろおご:もっとツラくなると、ほんとうに違う人間みたいになりますよね。ストレスがもっとかかってくる場面に対応しようとするとき、それをするのは別人です、人格が違いますっていう前提をとったほうが切り替えやすいから、そうなっていくんですよね
トリさん:仮面とかじゃなくてってことですか?
ぷろおご:わたしは5人いますみたいな世界になっていく
伊予柑:多重人格になっていく
トリさん:このままいってたらなってたでしょうね
ぷろおご:一般的に2、3人ですよね。それぐらいでだいたいどうにかこうにかまわして、ってイメージがありますけどね
伊予柑:僕らはナイフ一本以上持てないので、一本を研ぎ澄ますしかないんですけど
ぷろおご:それを長い時間やってるとね、ほかの人たちよりうまくやれたりする。なんていったってそれしかないからね
つづく
◾️次回記事はこちら

◼️インナーひろゆき

この対談を動画で見る、対談について語り合うには「ぷろおごマガジン」の購読が必要です。マガジン購読後、slackコミュニティ「三ツ星スラム」に入ることで最新情報や、記事についての議論を読むことができます。
◾️「三つ星スラムの」入口はこちら
こちらのアカウントへのサポートは、スラム編集部への支援となります。よろしければ感想やご要望なども頂けると嬉しいです!

