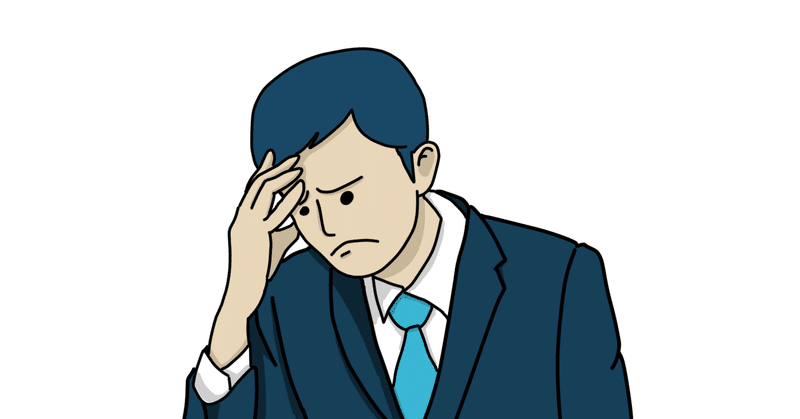
否定疑問文には要注意!
ある問診票の質問に答えているときに面食らった。
「〇〇でアレルギー反応が出たことはありませんか? はい / いいえ」とある。これまでアレルギー反応は出たことはない。そう答えたい。口頭で質問されたら、「ありません」と答えるだろう。でも「はい」か「いいえ」しか選択肢がないと、どちらを選べばいいのか大いに迷ってしまった。
「ありませんか?」の部分に反応すれば「はい」になるだろう。しかし、「アレルギー反応が出た」の部分に反応すると「いいえ」と答えたくなる。
何でこんな答えに困るような質問文にするのだろう?
ほとんどの人は覚えていると思うが、英語を習いだしてしばらくすると「否定疑問文」が出てくる。例えば、”Do you like dogs?”(犬は好き?)でも ”Don’t you like dogs?”(犬は好きでない?)とどちらで聞かれても、犬が好きだったら “Yes” と答えるし、好きでなかったら “No” と答える。当時の英語の先生は、否定疑問文では、日本語と英語では返事の仕方が逆になる、と解説していたように思う。
しかしそうだろうか?最初の例に挙げたように、日本語の「はい」や「いいえ」は英語の場合よりもかなりあいまいなような気がする。
英語では、文の形が普通の疑問文だろうが否定疑問文だろうが、“like dogs” の部分に対して答える。だから、その部分について肯定するなら “Yes” だし、否定するなら “No” になる。一方、日本語では疑問文全体について肯定するなら「はい」、否定するなら「いいえ」と答えることが多い。
「答えることが多い」と上に書いたが、日本語では、英語ほどきちっとした原則があるわけではない。冒頭の例で挙げたように、どちらで答えればよいか迷うことがよくある。
日本語では得てして丁寧に表現しようとすると、期せずして否定疑問文になってしまい、答えにくい疑問文になってしまうことがある。気を付けた方がいいと思う。
最初の問診票の質問には、散々迷った挙句、「いいえ」と答えておいた。結果的に英語の否定疑問文で聞かれたときの “No” と同じになってしまった。
あの時の英語の先生だったら、どう答えただろうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
