
失うと即アウトとなる事業資産
BCPの策定や運用で常に考えて、備えて・構えておかなければならないものがあります
事業に影響を与える脅威リスク
脅威リスクが招く事業への被害・損害の範囲と程度の予測
事業に必須な重要業務と事業資産
BCPの策定や見直しの際に、これらを見誤る・不十分であると非常時に大変な目に遭うこととなります
特に、事業継続に必要な資産を失ってしまうと、事業の存続を脅かすこととなります
そんな事業継続に必要な資産とは、 "人・モノ・お金・情報" といわれます
さて、昨今の数々の事案では、事業継続に必要な資産が上記のものだけではないことがうかがえます
と言うよりも、 "人・モノ・お金・情報" を間違って捉えていることで、事業の存続が危うくなっています
今回は、「失うと即アウトとなる事業資産」について、再確認する機会になればと思ってお話いたします
■ 信用・信頼を失うと即アウト
ズバリ、失うと即アウトとなる事業資産とは、"信用と信頼" です
では、信用と信頼とは、どういうことでしょう
辞書に載っている解説が、信用と信頼の本当の意味なのでしょうか
① 信用と信頼をするのは人
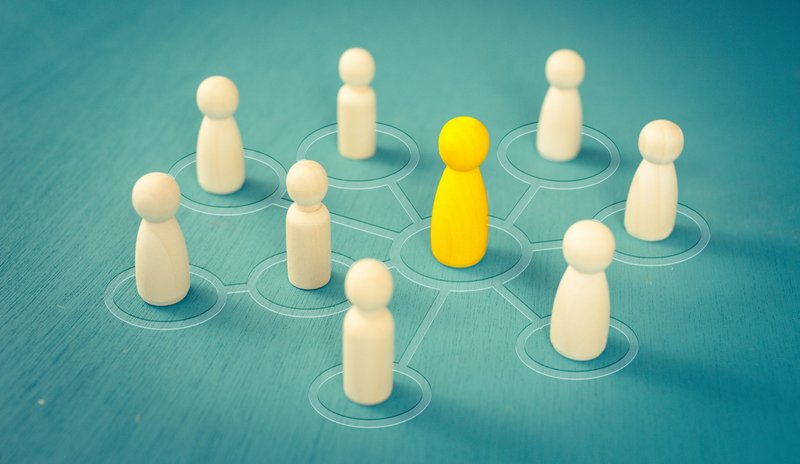
"信用と信頼をするのは人" です
"社会的な信用や信頼" という言い方であっても、人が信用・信頼することに変わりはありません
そして、人々からの信用・信頼がなければ事業は成り立ちません
事業継続に必要な資産としての "人" は、その存在だけでなく、人の内面の感情・心象が重要です
「怪しくて、あの店では買いたくな~い」
「あそこの会社の人たち、頼りないよね~」
こう思われてしまうと、お客さんという人々が離れてしまいます
また、事業内部にいる人々からの信用・信頼も絶対必要です
「上の者は、何を考えているのか分からない・・・」
「ボスの言うことをきかなかったら、ひどい目に遭うかも・・・」
事業内部の人間関係、上司と部下、同僚同士などの間で信用・信頼がなければ事業は弱くなります
弱くなった事業に、お客さんや取引先、銀行などは敏感です
ややもすると、内部分裂や不祥事などが発生して事業が存続できなくなることもあります
② 信用と信頼は情報
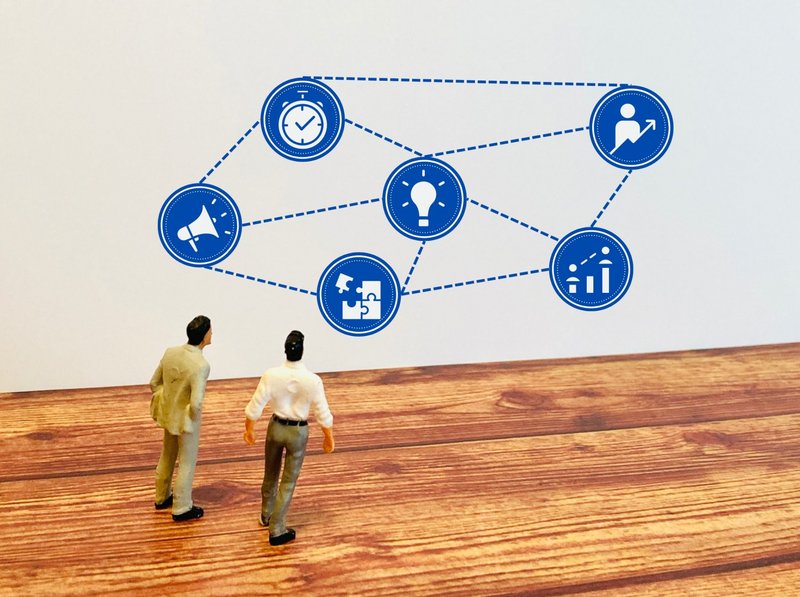
"信用・信頼は情報" とも言えます
信用と信頼という評価は、一人だけに留まることはありません
信用と信頼は、その人・その事業の情報として伝わり・広がります
時には、文字として永遠に記録され続けることもあります
情報の伝わり・広がりは、時として恐ろしい事象・結果を引き起こします
現代における情報は、簡単・安価・短時間・広範囲に伝わるという特性があります
情報は、人伝えのほか、ネットの口コミやSNSの書き込み、一般報道を媒体に伝わります
情報の受け側は、容易に情報収集することが可能で、選択することも可能です
結果として、好ましい情報も好ましくない情報も混在する中で、受け側次第の情報が届くことがあります
好意的に受け入れられているモノ・コトは、良い評価として流れ、"ファン" や "推し層" という人が現れます
反面、好意が持てない・受け入れられない場合は、悪い評価として流れ、"ヘイター" や "オキラ層" が増えてきます
昨今の世間・社会を揺るがすような事案・不祥事が発覚した企業などを思い浮かべてください
かつては人気があり、支持されていた企業が事件や不祥事を起こした場合などです
会見で誰が何を言おうと信じられず、組織体質を疑われ、説明責任を果たしていないと言われます
事案の検証、改善策や賠償などの方針を表明しても、"何も変わっていない・甘い" と評価されることがあります
人からの信用・信頼を失った後に、回復することは非常に大変なことです
更に、拡散した情報で失った信用・信頼の回復は、極めて難しく、相当の努力と時間を要します
信用・信頼を回復するまでの間、事業を存続させ続けることは可能でしょうか
③ 信用と信頼は一体的

信用と信頼をそれぞれ独立して考えてはなりません
信用とは、人や事業が発信・提供するコトやモノが "公明正大で、相手方が安心して信じている" ことです
信頼とは、人や事業が発信・提供するコトやモノが "安全・安定的で、相手方の頼りになる・利益となる" ことです
信用と信頼は、両方が適正な状態で備わってなければなりません
なぜなら、どちらかが欠けている場合、結果として両方を失っていることになるからです
昨今話題の芸能プロダクションであるJ事務所の事案を例に考えてみます
この事案は人権侵害が原因となっているため、極めて深刻な社会問題となっています
Jが抱えるタレントさんらは、芸能面の評価が高く、起用することで利益を生んできた
⇒ 商品・商材としての価値があり、実績からも確実に信頼できる今までの、また、今後のJ事務所内部の体質・気風に疑念や嫌悪感を持つ人々が多い
⇒ 賠償や組織改革などを表明しても、知られていない事実や今後の事業経営に対する不信感が増しているJと契約・提携していた企業は、自社保護を理由に取引を控えつつある
⇒ 自社事業やブランドイメージに対する世論からの信用と信頼を保護しようとする傾向にある
また、人権侵害を許していた取引先との関係を断ちたいとの感情も持つタレントさんらも自身の処遇や将来に不安・不信感が募る
⇒ 内部改革と外部対応ばかりで、内部不信の増大を引き起こしかねない上記のような報道などで、絶対的ファン層も離れがちとなる
⇒ 一度広まった不振や疑念は、長期にわたって影響し続ける
いかがでしょうか
提供するサービスや商品が優秀であっても、事業の経営や組織体質に問題があると、それらが打ち消されてしまいます
サービスや商品を受ける・購入する側にとっては、品質だけでなく、事業の理念や体質なども総合して評価・判断する時代です
信用だけがあってもダメ、信頼だけあってもダメ、両者が備わってなければ無いに等しいと言えるでしょう
また、提供側と受け側の二者関係だけでなく、関係者や世論などの第三者も絡むことで、信用・信頼の関係は複雑になります
第三者的な立場にある企業などは、事案の "とばっちり" を受けないように危機管理機能が働きます
第三者企業なども、自分らの信用と信頼の両方を保護しなければなりませんので、当然の行動でしょう
そんな第三者企業などの対応も、やりすぎると世論からの不満やバッシングを受けるかもしれません
"他の企業もやっているから、自分らもやる" といった短絡的な対応は、世論は敏感に察知するものです
結果として、そんな第三者企業も信用と信頼を失うことにもなるかもしれません
自分ら個人と自分らの事業にとって築くべき・守るべき信用と信頼とは何か
これを明確にし、堅く示し・守ることが、これからの事業継続には絶対必要なことです
なお、不祥事などで信用・信頼を失った事業に対して、あえて後ろから支援する人や企業が現れることがあります
信用などを回復した後、その事業に協力したという実績が支援した人や企業の信用と信頼を強くするという効果があります
それはそれで、自分らが築くべき信用と信頼が明確で、その先の将来が見えているので、行動できるのだと考えられます
"信用と信頼は、一体的であり、絶対死守しなければならない事業資産" ということは肝に銘じておくべきことです
■ 信用・信頼を失わないために
信用と信頼は、築くのも守るのも自分らです
そして、信用と信頼の評価は、商品やサービスの受け側や世論などの第三者です
"自分らの想いや言動" と "受け側や第三者の心証や評価" に隔たりがあると、信用・信頼が低下します
"創業〇〇年、信頼と実績があります" と自ら宣伝しても
"老舗を装う怪しい企業" とか、 "実績と言っても、トラブルも多いみたい" と思われたらアウトです
なぜ、隔たりが生じてしまうのでしょうか
いくつかの原因があります
正確な情報を正しく伝えていない・伝わっていない、そもそも正確ではない
現在は安心・安全・安定でも、将来は確実ではない・不安要素がある
守られるべき一般的なモラルや倫理、法律から逸脱している・逸脱が疑われる
これらの原因を防ぐ・回避するためには何をすべきでしょう
カギは、やはり人です
① 人の内面を養成・教育する

これらの原因を生じさせるのは人です
組織として生じさせたとしても、組織を構成している人が必ず関与しています
国や行政機関でも、その構成員である政治家や公務員という個人が関与しています
信用・信頼を失わないためには、人がどのように関与するかが重要です
提供するサービスや情報が相手に対して正当であり、誠実に対応している
自分らの言動がモラル・倫理・法律から逸脱していない
逸脱している・その疑いがあるとき、速やかに修正できる
逸脱を防止するための人の活動が有効に機能している
組織内の意志統一のほか、倫理観や遵法心が全員に浸透されている
要は、人の内にある知識と心のあり方、それに基づいて活動・行動されることが重要なのです
これは、人がどのように育てられたかにもよりますが、その後の "養成・教育" でかなり左右されます
自分らの事業を優先し、お客さんや世間を後回しにする事業のほとんどは、役員・従業員の養成と教育を誤っています
お客さんや世間のための行っていた事業が、養成と教育を間違った方向に進めることで信用・信頼を失う例が多々あります
中古車販売で有名なBM社は、社員の指導・教育を間違った方向で行った結果、事業全体の信用・信頼が失墜しました
真面目に必死になって頑張った社員もろとも信用・信頼を失っています
人が原因であれば、それを防ぐのも人です・・・人でしかできません
どんな規模の事業でも、モラルや倫理、コンプライアンスが正しく具現されていることが肝要です
日常的な朝礼や従業員を集めた研修など、養成・教育する機会を作って行うことは非常に重要です
たとえ一人事業者でも、勉強と情報収集を継続し、公明正大にあり続けなければなりません
② 他者の思いを量る
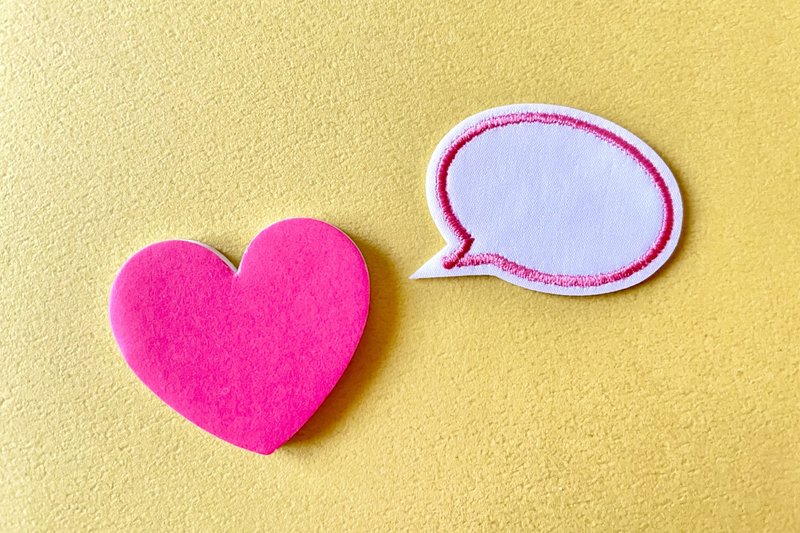
初めて会う人や初来店のお店などは、当初は信用・信頼が低いところから始まります
初めての人とは、遠慮気味・警戒しながら話を始めますが、次第に気が楽になって話を続けることがあるでしょう
また、初めて入ったお店でサービスを受け、良かったと思うと次は気楽に行くようになることもあります
いずれも、当初の緊張感や警戒心が薄くなり、"慣れてきたから" と思うことでしょう
実はこれ、"慣れ" ではなく、信用・信頼度が増したからなのです
会話から相手のことが分かり始め、店員の対応やサービスの質が心地良かったという心証が信用・信頼につながります
気が楽になる・心地良いと相手に感じるためには、こちら側の対応・言動がどうなのかによります
事業運営においても、顧客や取引先から "あそこに頼めば安心だ" と思わせる事業でなければなりません
相手にそう感じてもらうために、自分らはどうすべきかを思い量って行動しなければなりません
相手を思い量ることは、結果として世論や第三者を思い量ることにもなります
事業を続けるためには、事業に携わる人々が知識と心をもって、思い量ることが非常に大切です
なお、先ほどの養成と教育、他者を思い量る活動は、達成度を数字などで評価することができません
従って、人の養成と教育、思い量る啓発は、日頃から行い続ける必要があります
■ 失った信用・信頼は回復できるか
失ってしまった信用と信頼を回復した例はあります
それは "信じるに値する・頼るだけの実態" が認められた場合に限られます
① 認められるケース
信じられる・頼れると認めるのは、商品やサービスの提供を受ける相手と世論などの第三者です
信じるに値する・頼れる存在だと相手に伝わり、そのとおりだと思われることです
そして、信用信頼の回復を信じて応援してくれる人々が現れることです
業績不振であったが、経営の見直しを図ることで事業体力が改善された
財務諸表などのデータとして、誰が見ても明らかに経営状態が良くなったと認められたケース万が一の場合でも事業を継続できる事業体質へと改善できた
災害等が発生しても確実に受注品が納入できる事業運営が確立できたケース不信感を払しょくするような組織体質の改善
不祥事が発生したが、従業員等の対応姿勢から、企業内部の気風が良くなったと感じられたケース改善された状態やその過程で支持層が事業を支えた
回復に向けた姿勢や努力が認められ、かつてのファンや新たなファンが口コミで良い評価をしているケース
これらは、現実にあった信用・信頼の回復事例ですが、これ以外の事例もたくさんあります
共通するのは、"自他ともに認められる存在になったこと" です
信じて認められる実績や成果が見えること、伝わることで信用と信頼を回復することができます
② 回復するまで頑張れるのか

信用・信頼を失う事態の発生直後は、認められる実績や成果を伝えることは非常に困難です
事態の原因や発生過程、以後の補償や改善策を打ちててても信じてもらうことは稀ででしょう
政府や行政、大企業ですら、誰からも認めてもらうのは至難の業です
この記事を書いている頃は、マイナンバー制度やマイナンバーカードに関する不信感はかなりのものになっています
信頼回復のための政府施策も疑いの目で見られ、何をやっても非難されるという状況です
失った信用・信頼はいずれは回復できます
問題は、回復するまで "努力を続けられるのか" と "それをどのように発信するか" です
努力を続ける間も失ったお客さんや取引先なしで事業を運営・経営する体力があるのか
従業員らの処遇や給与が担保され、積み重なる業務を行う意志が従業員にあるのか
改善のための努力を、どのように・誰に対して発信・公表するのか
信用と信頼の回復のための道筋ができても、それを継続する財力と従業員らの意志がなければ達成することはできません
ここでも事業資産のうちの "人" である従業員らの存在と頑張る意志のあり方が重要になります
また、運営資金などの "お金" という資産、努力の経過や実績などの "情報" という資産も必要となります
③ BCPの存在

信用・信頼を失うような事態が発生したとき、直後の対処と回復施策を並行して・的確に行うことができるでしょうか
事前の対策や準備、いざという時の構えがなければ、非常に難しいのが現実です
そのようなことを事前に考えて詰めておくのが "事業継続戦略" であり、それを形としたものが ”事業継続計画(BCP)" です
BCPは、災害や感染症に特化した計画ではなく、事業の信用と信頼を維持し、失ったときの回復戦略・計画でもあります
例えば、以下のような活動が必要となります(これらだけとは限りません)
信用・信頼を失わず、維持向上させるために日々行う活動や着意すべき事項
信用・信頼が失われるような事態が発生した場合の顧客や取引先などの保護・救済
利害関係のない第三者からなる対策員会の立ち上げ
事実や原因を究明しつつ、事業全体をミクロ・マクロの視点で見直す
それらの結果を受けて、人の再教育、内部組織や業務の改革変更の計画策定
顧客や取引先などに対する謝罪・説明・賠償
以上全てを行いつつ、事業を運営するための方針や戦略決定
非常に多くのことを短時間・短期間で行うこととなります
そこで、BCPでは、時間の経過ごと(時系列的)に "対策" と "対処" の戦略と計画を示します
事前対策:事案防止、被害の回避・極限のための戦略・計画
危機管理:事態発生直後の実動対処のための戦略・計画
事後処置:事態下の事業の存続・継続のための戦略・計画
・・・という流れの中で行うべきことをあらかじめ定めておくことです
いざという時、慌てる・混乱する・迷う中で可能な限り的確に行動するための方向性を示しておくことが重要です
このようなBCPが備わっていれば、事態発生当初の信用と信頼を失っても回復する道筋が見えてくることでしょう
その道筋があれば、事業に携わる従業員も信じて頑張れることでしょう
信用と信頼は、失わないようにすることも、回復することも可能です
ただ、それに向けた戦略と継続した努力が絶対に必要です
それらがなければ、"即アウト” は必至でしょう
■ まとめ

不祥事だけでなく日頃の事業運営の姿からでも、人からの信用・信頼は薄らぎ・無くなってしまいます
失わないために何をすべきか、どのようにすべきか、いざとなったら誰が・どうすべきかを考え抜くことです
その活動は特別なものではなく、日頃の事業運営・業務の一部であることを理解していただきたいと思います
失うと即アウトとなる事業資産とは "人からの信用・信頼"
信用と信頼をするのは "人" という事業資産 、信用と信頼は "情報" という事業資産
信用と信頼は一体的であり、絶対死守しなければならない事業資産
失わないために人の内面を養成・教育し、他者を思い量る
失った信用・信頼は回復できるが、自他ともに認められる存在になる継続した努力が必要
信用・信頼の回復には、存続するための事業資産と事業継続戦略・BCPが絶対に必要
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
