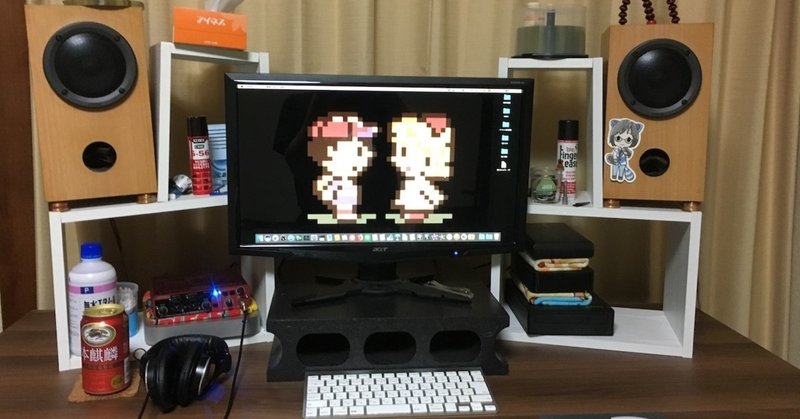
【楽曲制作】 音を重ねる、ということ。
5月になりましたね。
時代が平成から令和に変わって、もう1年が経ちました。
超絶ハードモードの2020年、それでも時は進み、
ぼくらは生きていかねばならない。
前記事まで、万貴音のアルバムのセルフライナーノーツ、
全11曲分を解説していきました。
需要があるのかとても心配だったんですが、
思ったよりは好評だったのかなあ。
とかく、書ききれたのはとても良かったです。
これから何を書こうかな、と考えていってるんだけど、
基本は音楽の話をしていきたい。
料理の話とかレシピとか、もしたいとこなんだけど、
それはきっと不定期になると思います。
なにぶん素人なもんで。笑
楽曲解説はまた要望があればしたいと思うんだけど、
もっと根本のテーマを書いていこうかな、と思ってまして。
となると、自分が書けるのは楽曲制作についてと、
楽曲アレンジについて。ですかね。
今後どっちをメインに据えるか考えたんだけど、
決断しきれなかったので、今回はそれの両方に関わる、
「音を重ねる」ということについて、書こうと思います。
需要があればいいなあ。笑
・歌だけでも音楽、楽器を重ねても音楽。
それこそ「アカペラで歌う」とか、
ギターをポロンと爪弾いてみるとか、
それでも十分に音楽なんですね。
「弾き語り」という形式では、
多くの場合「ギター+歌」「ピアノ+歌」
といった形で奏でられたりします。
弾き語りの例。これはアコースティックギターとボーカル二人。
「バンド」の例。一般的な例だと、
ドラム、ベース、ギター、キーボードを主として、
数種類の生演奏にボーカルが乗っかる形です。
打ち込みなんかを含めたものの例。こちらは主にCDとか配信とか。
ボーカルや楽器の生演奏に加えて、PCやシンセサイザー等の
プログラムされた音を含めたりして、曲が構成されたりもします。
音楽の三要素は、「リズム・メロディ・ハーモニー」です。
どれも一人で出来はするんだけど、とりわけハーモニーは、
複数(多種)の楽器で作られることも多いです。
(ハーモニー:音程のある音が二つ以上重なること。ざっくり)
今回はそういう要素で「音を重ねる」ことについて、
書いてみますね。サンプル音源付きで。
・サンプル音源「Tower of Tones」。
めちゃくちゃ昔の音源で恐縮なんですけども、(MTR時代だ…)
昔の広島ローカル音楽番組「The Street Fighters」で
特集してもらった時に作った音源です。
ボーカルなし、所謂「インスト曲」ってやつですね。
この楽曲は、短いイントロの後、
リズミックな前半部分とメロディックな後半部分、
それが2回繰り返される短い曲。とてもシンプルな構造です。
これをパートごとに分解して、重ねていきます。
曲名は超有名ファンクバンド「Tower of Power」を捩ったもの。
あんまり詳しくはないけど、超かっこいいよ、このバンド。
・屋台骨はドラムとベース。
楽曲の屋台骨を作るのは、ドラムとエレキベース。
ドラムは明確な音程を持たないので、もっぱらリズム要因。
生演奏の時、ドラムが不安定だと最高に演奏しづらいです。笑
逆を言うと、みんながドラムを基準に音を出す、重要な役割。
ベースは多くの場合、音程のある楽器の一番低音部を担う楽器。
ドラムと一緒にリズムを安定させつつ、ここから上に重なる
音程楽器の土台となります。
・ピアノを入れてみよう。
ピアノを追加しました。
実家のグランドピアノに、マイク一本突っ込んで録音したものです。
ピアノといえば美しいハーモニー、さらにソロもお任せ!
みたいな万能楽器ですね。しかもどの楽器よりも音域が広い。
なんだけど、この曲のピアノは結構リズムを出した演奏が特徴。
ファンクっぽい曲なんで、こういう弾き方です。
・バッキングギターを追加していく。
ステレオスピーカー、もしくはイヤフォン・ヘッドフォンでどうぞ。
やや左から聴こえるのが「アコースティックギター」、
やや右から聴こえるのが「エレキギター」です。
楽曲が少しずつカラフルになってきました。
アコースティックギターはイントロとかのキメを補強しつつ、
コードをアルペジオ(分散和音)で弾いて横の流れを。
エレキギターは前の記事でも書いた「ワウペダル」を使って、
アコギとはまた別のアプローチ。
特徴的な「チャカポコ音」はファンクの代名詞みたいなサウンド。
・ブラスをプラス。
ブラス=管楽器。本来は「金管楽器」を表す言葉なんですが、
ポップスの場合、トランペット/トロンボーン/サックス
なんかをまとめて「ブラス」と言う場合が多いです。
(ちなみにサックスは「木管楽器」ですね)
この曲ではトランペットが2本。自分の生演奏。
同族の楽器が複数ある場合は「セクション」と言われます。
この曲での役割は「アクセント」、もしくは「キャラ付け」。
ボーカルやソロ楽器がある場合、主役はもちろんそれらですが、
楽曲のカラーや方向性を含む、いわば「強い音」というか。
舞台や漫画で言うなら、「名脇役」になるのかな。
主人公は同じでも、ストーリーがラブロマンスになるのか、
ラブコメディになるのか、みたいな役割。あくまで一例ですが。笑
・ソロギターを入れて完成。
Epiphoneのレスポールタイプのエレキギターに、
BOSSのブルースドライバーをかけて、VOXのミニアンプをマイク録り。
って形でレコーディングしたんじゃなかったかな、これ。
ソロギター、なので一応この曲の主役です。
メインメロディ担当、「こんなストーリーだよ」を伝える役。
イントロのキメは複数の楽器でなぞる。
「でれれれってってー」のとこですね。
1回し目の前半はほぼサボってます。というか、オカズ役。
スペースを空けると、ピアノのリズミックなやつが
メインっぽく聴こえてきます。
1回し目の後半からはずっとメロディを弾いてます。
ようやく明確に、主役として機能してますね。
メロディの隙間には、各楽器のオカズが出てくる。
どの楽器も出るとこは出て、引っ込むとこは引っ込む。
主人公だけ輝くのが音楽ではなくて、
みんな役割があって、一つの音楽を作ってます。
・アンサンブルというハーモニー。
そんなこんなで、「Tower of Tones」という楽曲を、
音を足していきながら解説していったんですが、
短い文章で説明するのがなんと難しいことか。笑
あんまり長々書いてもね、と思ったので、
今回はこのぐらいの分量で書いてみました。
ちょっとでも伝わってたら嬉しいです。
それこそアカペラだったり、ソロ演奏だったり、
それでも十分素敵な音楽はあるし、作れる。
なんだけど、音を重ねるのって面白いよ、
っていうのを伝えたかったんです。
二人以上で同時に演奏することを「アンサンブル」と言います。
この曲は全部自分が演奏して作ったんだけど、
色んな楽器を演奏して重ねて、一つの音楽を作る。
それは自分にとって、とてもワクワクすること。
料理も似てますよね。
色んな材料を使って、一つの料理を作ること。
また、ハーモニーは日本語では「調和」と言います。
複数の音が、または自分と他の人が、
一つの素敵な音楽を作っていく。
ライブの場では、音楽を届けるお客さんも一緒に、
素敵な音の鳴る時間を一緒に作っていく。
全部、大きなハーモニーなんだと思ってます。
ライブがしたいなあ。
次回以降は、楽曲制作についてのお話をしようかな、
と思ってます。
出来るだけ分かりやすく書こうと思うので、
どうぞお付き合いください。
俺、こんなことばっかりやって生きてきたので、ね。
料理の話もいいかなと思ったけど、それはまた考えよう。笑
*この記事は「投げ銭制」にしていますが、
「本文」は全文無料で公開しています。
記事購入後は現在、お礼の文章と「プラスアルファ」を公開しています。
読んでもらえるだけでも、心から感謝です。
ここから先は
¥ 100
よろしければサポートをお願いいたします。いただいたサポートは、自分とその周りに関わる音楽活動費として役立てさせていただきます。全力で頑張ります!
